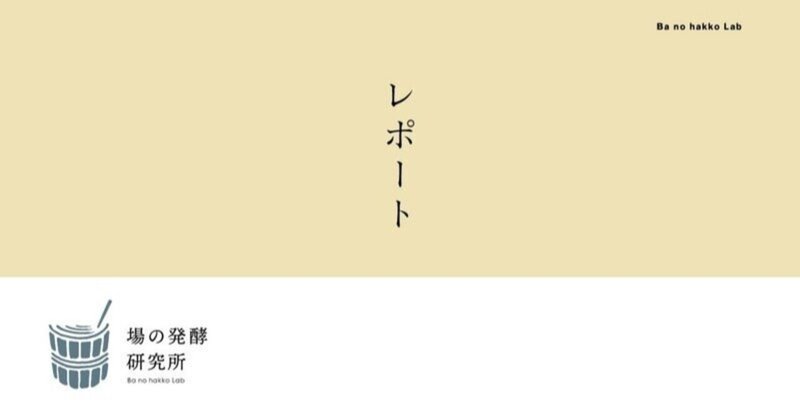
【レポート】場の発酵研究所:第1期#11 [ゲスト]寺田優さん
こんにちは、事務局の渡辺(わったん)です。
11月9日(火)、場の発酵研究所・第11回でした。第7回以降は研究員と共に話し合って決定したゲストです。今回は、自然酒蔵元『寺田本家』24代目当主の寺田優さん。研究所ではこれまで、様々な意味を込めて「発酵」という言葉を使ってきましたが、元々はお酒の発酵から着想を得ています。研究員を「杜氏(とうじ)」と呼んでいますが、これもお酒をつくる職人を表現する言葉です。今回はついに、本物の杜氏をお招きすることができました。
第11回ゲスト:寺田優さん

1973年大阪府生まれ。自然酒醸造元「寺田本家」24代目当主。千葉県神崎町の「神崎発酵の里協議会」の代表世話人。横浜国立大学在学中から世界各地を旅し、卒業後、動物カメラマンに。聡美と出会い、食の力に目覚める。31歳で寺田本家に婿入りしてから、先代当主・寺田啓佐のもと、無農薬の米作り、酒造りを修行。以来、“本物の自然酒”にこだわり酒を造り続ける。稲刈りイベントや、小学校で大豆の豆まきから始める未噌作り授業を行うなど、地元を中心に“発酵”を身近に感じてもらえるような活動を展開。
創業340年の寺田本家がある神崎町には、利根川が流れていて、酒を運ぶのが便利で醸造業が集まっているそうです。米大豆麦の栽培も盛ん。寺田本家は滋賀県近江で酒造りを始めましたが、大消費地であった江戸に近づくため、約340年前に千葉に引っ越しました。
寺田本家では代々、婿が入って当主を継いできたそうです。代表作「五人娘」の由来でもあります。優さんもまた、2003年に婿入りを機に酒造りを始めました。そして2013年には著書も出されています。
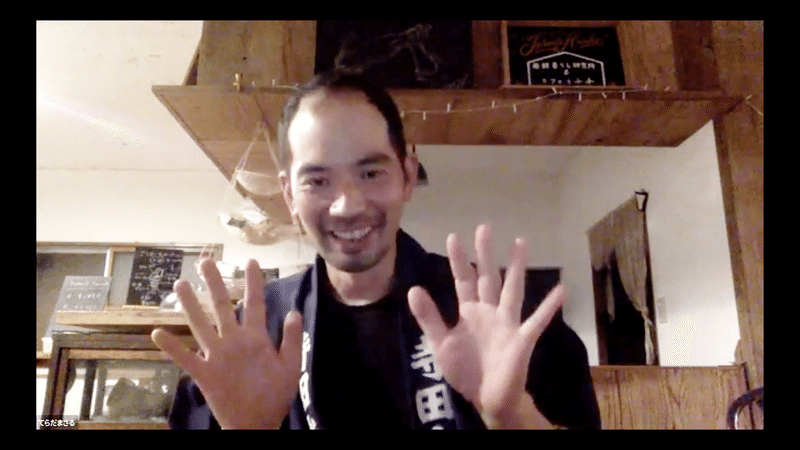
寺田本家の「発酵」
米に触れながら、温度、柔らかさ、体全体を使って酒造りに関わる優さん。見えない微生物がどういう気持ちでいるか、五感で感じたい。大量生産よりもおもしろい酒造りをしたいと思い、少しずつ機械を止めていったそうです。
「fermentation(発酵)」。お酒を通して発酵の楽しさを伝えたい。微生物はどんなところにいて、微生物を介してコミュニケーションをとっているといっても過言ではないと、優さんは言います。
優さん:
お米、お水、微生物が一つになっていく。日本酒づくりって、これだけなんです。
添加物を入れると計画通りに安定してお酒をつくることができますが、それだとおもしろいくないなあ、と思うのです。
蔵にいる菌が、なんだか楽しいなあとか、発酵したいなあと思ったら、ぶくぶくと泡立って発酵が始まります。
ある程度の設計図はありますが、基本的には微生物まかせです。うまくいかないこともありますが、自分の想像を超えることもあるんじゃないかと思っています。安定して高い品質をつくるよりも、その時に現れる微生物の働きを楽しんでもらえるようなお酒をつくりたいです。
お米
寺田本家では米づくりから取り組んでいます。自分たちの田んぼと、近所にある15件ほどの農家にも栽培してもらっていて、お米は全部で2,000俵(約120トン)ほど使うそうです。
水
寺田本家の蔵の裏山には神崎神社があり、原生林が守られているそうです。そのおかげで今も井戸水が湧いています。周りの自然環境が整えられてること全てが、味となって表れると優さんは言います。また樹木同士がエネルギーを交換しているなど、まだわかっていない微生物の働きもたくさなり、それらも酒づくりに関係しているのだろうと。
菌
お酒づくりにはいくつか菌がいます。麹菌、乳酸菌、酵母菌。他のお酒と日本酒の違うところは、日本酒はいろんな菌が同時並行で発酵すること(並行複醗酵)。
優さん:
一種類だけが繁殖するわけではなく、一つの菌の発酵が終わったら次の菌が現れ、違う役割を果たします。そうしてバトンタッチしていきます。
いろんな菌がタッグを組みながら、自分の仕事を終えたら場所を明け渡していく。
謙虚に見えるところがおもしろいですよ。

お酒づくりの過程
米を蒸す
大きな蒸し器を使います。食卓だとお米は炊きますが、日本酒の場合はお米を蒸します。水が多すぎると柔らかくなりすぎるので、水分量が大事です。
掘り起こす
蒸したお米を掘り起こします。以前は機械を使っていましたが、なるべく手作業で掘り起こします。なるべくお米に触れながら、体を使ってつくります。最近、フランス人の方が蔵人としてやってきて、きちんと理由を知ろうとするので、説明しないといけない状況になったそう。その時に、ふわっと共有していたことを言葉にすることで自分たちの理解も深まったそうですが・・・
優さん:
一方で、言葉にしてしまうと、ど真ん中ではない感覚もあるんです。
身体を使って見えてくるもの、感じられるものは、言葉にしづらいなあと感じます。
麹(こうじ)を作る
麹菌の胞子を胞子を蒸したお米に種付けします。麹はお米のデンプンを分解して、ブドウ糖にします。小さな箱に小分けして混ぜながら、3日かけて麹を作ります。
優さん:
お米を使うお酒は世界中にたくさんありますが、麹を使うのは日本酒くらいなんです。
日本人は昔から麹を生活の中に取り入れていて、味噌や醤油にも使われています。
麹は日本の食文化を形づくってくれた菌だなあと思っています。
もと摺り
桶の中にお米と麹と水を入れて、数人で棒を使ってゴリゴリとすりつぶしていきます。「もと摺り」というスタイルで、江戸時代からの方法です。機械から手作業に戻していく過程で、はじめは黙ってやっていたそうですが、昔の人たちにならって歌いながら作業することにしたそう。
優さん:
昔からある「酒づくり歌」を練習して歌うようになると、蔵人の心が一つになりやすいと感じています。
仮にわだかまりのような雰囲気があったとしても、歌っていると「まあいいか」という感じになる。そんな雰囲気づくりは、微生物にも影響している気もします。
醪(もろみ)
酒造りの最終行程で、大きな桶にいれてお米と麹と水を混ぜ合わせていきます。この時も歌うそうです。ここから先はあまり人の手が入れられず、微生物の発酵にまかせる、お祈りする、という感じで30日かけて発酵させるそうです。
優さん:
泡がぼこぼこと出てきて、それで微生物のご機嫌を見ます。
泡の形、泡の盛り上がり具合などを毎日観察しながら、いま元気だなあとか、いま落ち着いてきたなあとか、発酵の時期が終わって香りを作っていく時期だなあと、判断します。
毎日観察することが大切なんですが、それを言葉で表すのが難しいところです。
こうして2〜3ヶ月かけて、1本の酒ができあがります。
瓶詰めしてすぐに出荷するお酒もあれば、熟成させるお酒もあるそうで、半年から1年、長いと10年以上かけるそうです。
優さん:
美味しく飲めるまでは長い時間がかかりますが、時間をかけることで、いろんな微生物たちの関わり合う関わりしろができるんじゃないかと思います。
その関わる入り口を開けて待っているのが自分たちの仕事です。
酒づくりのプロセスは、寺田本家のHPでも紹介されています。
雑菌大歓迎、地域に開いていく「発酵」
寺田本家では、酒蔵見学も歓迎しています。人は雑菌をたくさん持ち込むので、酒蔵にはあまり人をいれない方がいいという考えもあるかもしれませんが、寺田本家では「雑菌大歓迎」という考え方。酒蔵見学はもちろん、様々な取り組みを通じて「発酵」を地域に開いています。
優さん:
いろんな菌がいた方が、お酒づくりの菌も元気になるんじゃないか、と。
森の中のように、お互いに共存していると、どれか1つが急に増えることはなく、不要な菌は淘汰されていき、自然とバランスが取られます。
自分たちの判断で「汚い」や「綺麗」を分けず、とりあえず受け入れてみます。
蔵開きのお祭り「発酵祭り」
お酒づくりが終わる3月に開催しているお祭りですが、商店街の人たちを巻き込んで、まち全体の「発酵祭り」となっているそうです。実行委員長が町長で、役場の人たちも協力して開催。人口5000人ほどの神崎町を「なんとか元気にしていきたい」「発酵のまちにしよう!」ということで、賛同者や移住者が増えてきたそうです。
https://chiicomi.com/press/3518/
酒蔵祭りを紹介する記事
まち全体で「発酵推し」:カフェや道の駅
寺田本家では、酒粕や麹を使った発酵食を提供する「カフェうふふ」も運営しています。町内には他にも発酵食を味わえる店があるそう。道の駅の名前も「発酵の里こうざき」。地域の産品というよりは、とにかく「発酵推し」なのだそうです。
https://www.teradahonke.co.jp/ufufu/
「カフェうふふ」のページ
子どもたちと発酵を学ぶ
神崎町にある2つの小学校では、畑に大豆を撒くところから体験できる味噌づくりの時間があります。神崎町の小学校に通うと、みんな手前味噌が作れるようになる。子どもたちは家で発酵の話をするので、家庭にも発酵が広がる。大人になると神崎町を離れる子もいますが、発酵を思い出してくれたら、という気持ちで取り組んでいるそうです。
地域のマーケット
地域のお母さんたちとマーケットも開催しているそうです。まちの遊休施設を使って、週1回。高齢の方から子どもまで集まる場となっているそう。
優さん:
自分たちがお酒づくりを続けていくことができるのは、農家さんたちが地域でお米を元気に作りつづけてくれているおかげ。ただ農家さんが田んぼを続けるには、土地や機械があればいいというわけではなく、コミュニティが必要だと感じています。
なので、地域に関わる活動にも積極的に取り組むようにしています。
酒づくりの方向転換、その背景
ここからは、場の発酵研究所の藤本と坂本を交えて話が進みます。
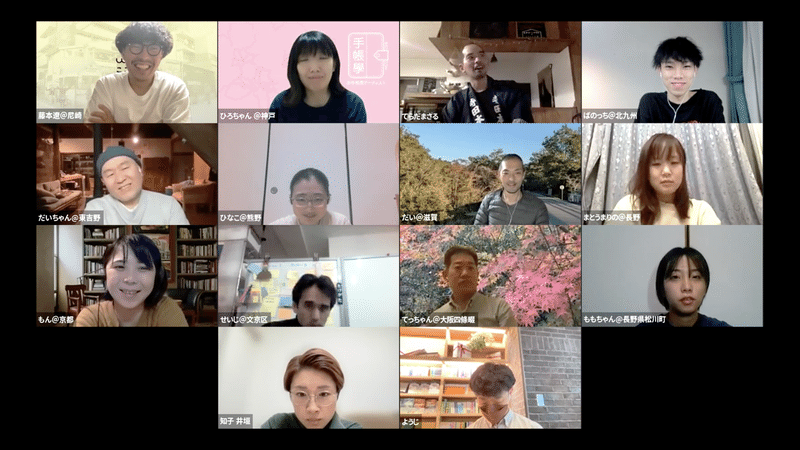
優さんがお酒づくりを始めた2003年には、蔵人が杜氏を連れて冬だけ蔵に来て酒をつくる、という杜氏の仕組みが崩壊しつつあったそうです。出稼ぎではなくて、酒づくりをやりたいひとが集まってくる。そうすると「おもしろくしたい!」と思う人が集まってくる。根本的には、そのような変化があったそうです。
そうして、手づくりでやっていこう、無添加でやってみようなど、1つずつ実験しながらやっていくと、「おもしろい」が連続するようになったと。この先に、現在の寺田本家があります。
一方で、340年の歴史をもつ寺田本家。新しいことを実験していく時には、周囲や社内からの反発はなかったのでしょうか。
優さん:
もちろんありました。銀行からも。しかし、従来の方法を続けていても限界がある、ということもありました。小さな酒蔵なのに、大手と同じような手法でお酒を作っていても、おもしろくない。
最初の切り替えは、先代の頃、1985年頃でした。少しずつ自然の方法に、ゆっくりと変えていった。
お客さんが一気に離れたこともありました。例えば無添加の酵母菌に変えて酸っぱくなった時や、お酒を透明に近づける濾過をやめた時。
しかし一部のマニアックなファンが支持してくれました。マーケットが移り変わったのだとも負います。
元々は先代の寺田啓佐さんが、自身の病を機に方向転換されたことから、自然的な方法への回帰が始まりました。経営難を乗り越えるべく効率化を図りましたが、うまくいかず、ご自身も倒れてしまったそうです。そこから始まった「発酵道」、ぜひ啓佐さんの書籍も読んでみてください。
目に見えないものとの関わり
寺田本家の裏山には神社があるという話がありましたが、そこでは原生林が守られているなど、神社の存在が自然環境を守っているという考え方もできます。神社や神様と酒づくりは、どのような関係性があるのでしょうか。
優さん:
どちらも、目に見えないものを相手にしている、と常々思っています。
実は昔の人たちのほうが、目に見えない何かへの想いは強かったのではないかと思います。
昔の人たちは科学的な根拠を今ほど知らなかったので、発酵の良し悪しの原因もわからない。
だからこそ、祈るような気持ちが強かったでしょうし、自然に対して謙虚になる気持ちがあったのではないかと。
一方、知れば知るほど謙虚にならざるを得ないとも思います。酵母菌が気持ちよく働いてくれるためには、そこに想いをよせるしかありません。
だからこそ、お酒は神事に近いところにあるのかもしれません。
実際、寺田本家の日本酒も地鎮祭などに使われます。
目に見えないものを相手にする、発酵が始まると祈る気持ちで菌にまかせる…。そうしてお酒が作られる過程を観察しながら、たとえ酸っぱくなったとしても、その時だからこその味として受け入れる。味の変化でお客さんが離れる時は、微生物がそのように調整していて、酒づくりが自分たちの手の届く範囲から離れすぎないように働いているのかもしれない。優さんは視点をもちながら、発酵する微生物たちを日々観察していると言います。
最後に坂本から、「場づくりではなく場の発酵」という表現があっていると確信した、という一言。
今回はお酒づくりという「物理的な発酵」の話ではありましたが、目に見えない微生物や、言葉にならない何かを共有し、その感覚をみんなで味わいつつ、何を感じ取るかは参加者に委ねるような、まさに発酵的な場となっていたのかもしれません。
いつもご覧いただきありがとうございます。一緒に場を醸し、たのしい対話を生み出していきましょう。
