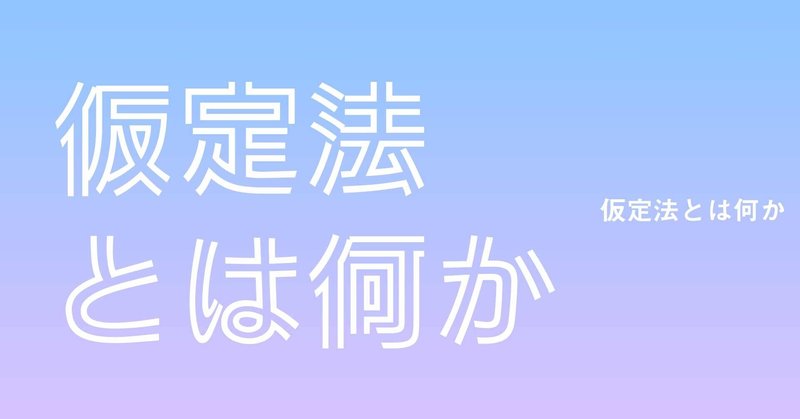
1-4 言語学と論理学と哲学のあいだ 英語における直説法(1)
0. 前口上
前回の更新日は10月15日でした。その後くらいからですかね、貯金が尽きてき始め、デリバリーをやってもほとんど鳴らず(仕事が来ず)、「こりゃやばいぞ」となって11月は就活していました。結果、12月からフルタイムで働き始めたのですが、職場が何というか、詳述は控えますがアレなところでですね、私と同時入社した人が2週間で辞め、私も2か月で辞めることになりました。この辺の運には本当に恵まれません私は。もはや肉体労働バイトくらいしかすることがないのですが、あいにく先月自転車で事故ってしまい肘の骨にヒビが入っておりまして、始めるにせよ早くて3月からにした方がいいだろうと思い、2月は家で過ごしておりました。その中で自分と向き合うわけですが、やっぱりこの原稿を放置してはおかれますまいというふうに、何というかリアライズしたわけです。その結果が、これです。
この1-4からは直説法について述べていくわけですが、英語における直説法というのは酸素みたいなもんで、なかなか普通に勉強していく限りではその存在を意識することがないものです。命令法を動詞の原形を用いる「命令形」としてくくって除外してしまえば、英語における法というのは直説法か仮定法かのふたつということになります。そして、学校で英語を教わる場合では、仮定法というものを習うときになって、初めて「法」というものが英文法のカテゴリーとして存在することを知り、同時に仮定法を習う前に接していた文のほとんどの動詞が直説法と言われることも併せて知ることになるわけです。直説法とはいわば、仮定法でないものとして導入されるわけでして、直接──奇しくもダジャレになってしまいましたが──「直説法とは何か」と定義しようとすると、これが一筋縄ではいかないのです。そんなわけで直説法について述べるこの1-4と次回の1-5はこれまでで最大の文字数となりました。
1. 英文法における直説法の位置
1-4で、古英語に基づく英語の動詞の活用表を紹介し、直説法 Indicative Mood との対比をしつつ仮定法を紹介しました。しかし、直説法などと急に言われてもピンとこなかったのではないでしょうか。学校文法でも、動詞の活用といえば、〈do - did – done〉のように、〈原形 - 過去形 - 過去分詞形〉を覚えてしまえば、十分とされています。実際のところ、英語の場合、動詞の活用が極めて単純化されており、法の形の上での区別(形態上の区別)を事実上失っているので、法についても意識する必要性がなくなっています。例外的なケースを除いては、すべて直説法だとみなしてもそれほど支障が出ないため、わざわざ直説法の動詞を直説法と呼ぶ必要すらなくなっています(英語以外の西欧の言語を学習したことのある人であれば、このことの不思議さに既に思い至っていることと思います)。
まず、おおざっぱに言ってしまえば、直説法と仮定法の最大の違いとは、「事実」との関わり方にあります。直説法で表すか、仮定法で表すかによって、話者が「事実」とどのような関係にあるのかが違ってくるのです。ここで、『現代英文法講義』で述べられている直説法の定義を確認してみましょう。日本語の英文法書で直説法について単独で定義されることは稀なため、これは貴重な資料と言えます。なお、この文法書では、直説法(Indicative Mood)に対して「叙実法」という訳語が採用されていますが、訳語の違いに過ぎないので「直説法」について言われているものと理解してください。
叙実法(indicative mood):事柄を「事実として」(as a fact)述べる叙法で(※1)、「直説法」とも言うが、本書では、細江(1933)に従い、より適切な名称として叙実法(fact-mood)を用いる。大半の文は、この叙法で書かれる。
※1:事実を述べるのではなく、事実として述べるのである。例えば、Two and two makes five.(2足す2は5)は、数学的な事実ではないが、叙実法で書かれた文法的な文である。
2. 事実「を」述べることvs事実「として」述べること
2.1 事実「を」述べること
この引用文中の、「事実を述べるのではなく、事実として述べる」ということはどういうことか、という視点から検討していきましょう。まず注意すべきは、引用中でも書かれているように、直説法は「事実を」述べるのではなく、「事実として」何かを述べるのです。インターネット上の解説などでは、この重要な区別がなされていないものが散見されますが、そうした説明は誤りです。また、この直説法の説明を裏返した仮定法の説明として「仮定法は事実でないことを述べるもの」という説明がありますが、それも正しくはありません。こうした説明は、書籍として出版されているレベルのものでも見かけることがあり、ことほどさように仮定法の説明というのは、不正確なままになされているのです。
では、どうして「事実を」述べる、というのが誤りで、「事実として」述べるのが正しいと言えるのでしょうか。ここでは、ひとまず「事実」という言葉の日常的な使われ方に着目して考えていくことにします。日常的な意味においては、「事実」とはしばしば「本当のこと」「真であること」の意味を持っています。そのため、「事実を述べる」と言うとき、「本当のことを言う」や「真であることを言う」という意味に等しいと言えます。例えば、ある人が「ちゃんと事実を言ってください」と言うとき、それは「ちゃんと本当のことを話してください」と言っているに等しいし、政治家などが「いまご指摘いただいたこと、そのような事実はありません」と言えば、「あなたの言っていることは間違っている」と言っているに等しいのです。
直説法で述べることがそのまま「事実を述べる」になるのなら、私たちは「真である」ことしか言えないことになります。ですが、そんなことはあり得ません。私たちは、事実と異なった認識を持つときには、確信を持って事実でないことを口にする(間違ったことを言う)ことがありますし、事実に沿った考えを持っていたとしても、嘘をつくこともよくあるからです。直説法で述べることがそのまま「事実を述べること」になるというのは、原理的にあり得ないのです。別の角度から説明すれば、「“事実”が述べられたか否か」というのは、結果としてそう判断されるのであって、誰かが何かを言う(発話する)段階で判断できるものではないのです。
2.2 事実「として」述べること
一方で、ではなぜ「事実として述べる」という説明が許容されるのかと言えば、この場合、述べられていることが実際にそうであるか否かはカッコに入れられている(棚上げされている)からです。「事実として述べる」ということを話者の観点に立って次のように言い換えても良いでしょう。
自分が述べることがらが実際のところそうであるか、すなわち真か偽どちらなのかはわからない。だが、自分はいちおう実際にそうである(真である)とした上でこのように述べる。
人は事実を述べようとして述べることはできません。人が「事実を述べる」ことはありますが、それは、誰かがあることを事実として述べ、それが実際に事実であることが確かめられた結果、その人は「事実を述べた」ことになるのです。
3. 事実の定義を変更する
3.1 事実はただ事実である
これまでに私は「実際のところそうであるか」とか、「実際に事実であることが確かめられた結果」というような表現を用いてきました。「実際」という言葉を使っているところがポイントです。「真である」かどうかは、発話において述べられた文が「実際のところどうなの?」というフィルターにかけられて判断されます。つまり、「事実を述べる」という表現が、「述べられたこと」と「真偽(真か偽のいずれか)」という2つの要素しか検討していないのに対して、「事実として述べる」においては、「実際のところ」と「述べられたこと」と「真偽」という3つの要素が考慮されています。
ここから重要な手続きを踏みます。これまで使用してきた「事実」という用語に対する定義に変更を加えます。この文章では日常的な用法に触れつつ「事実である」ことと「真である」ことはイコールである(等しい)と見なしてきました。しかしここで、このふたつを引き剥がすことにします。そして、ひとつ前の段落で「「実際のところどうなの?」というフィルター」と述べるのに使った「実際」と言う言葉に対して「事実」という用語を当てます。この整理の仕方は『論理的原子論の哲学』のバートランド・ラッセルに倣ったものです。
事実には明らかに真偽の二極性がありません。ただ事実があるのみです。事実はすべて真であるとするのは、言うまでもなく間違っています。なぜなら真と偽は互いに相手を必要としているのであって、偽でありうるものだけが「これは真である」と言われうるからです。事実は真でも偽でもありえません。そういうわけで、言明や命題あるいは判断という、いずれも真偽の二極性を持つものが問題になります。
この内容を噛み砕いていえば、事実はただ事実としてあり、人間は言語によってそれを文として言い表そうとします。いわば事実は人間にとって外在的なものとしてあります。言語によって言い表された事実は、もはや単なる事実ではなく、事実についての「言明や命題あるいは判断」(文)となり、この段階において「真偽の二極性を持つ」ようになります。
この用語の使い方の変更に伴って、先に述べた「「事実として述べる」における3つの要素」の用語も改めると、次のようになります(図1)。
〈「事実として述べる」における3つの要素〉
変更前
述べられたこと — 実際のところ — 真偽
変更後
文— 事実 — 真偽
先ほどの例を使って考えてみましょう。「2足す2は5だ」という文を見て、私たちが「正しくない(=偽である)」と判断するのは、その文を認識した瞬間に自動的に数学的な事実(2 + 2 = 4)に照らし合わせているからでしょう。図1に当てはめれば次のようになります(図2)。
文:「2足す2は5だ」
事実:2 + 2 = 4
真偽:偽
3.2 事実であることと本当のこと
さて、ここでちょっとした問題が起きています。「事実として」述べるというときに使われる「事実」と、その「「事実として述べる」における3つの要素」ひとつである「事実」の意味合いに齟齬が生じています。事実は述べられた段階でもはや単なる事実でなく事実についての「言明や命題あるいは判断」(文)になるのでした。よって、事実について「事実として」述べるということは不可能なはずです。というか、事実について事実として述べるとか、何言ってんだって思いますよね。
私たちはこれまでのところで事実は人間にとって外在的なものであるというように定義を変更したばかりです。なので、ラッセルを引用して定義した方の「事実」(「文」「事実」「真偽」のうちの「事実」)はそのまま扱うことにします。そうすると、解釈の変更を加えるべきは、「事実として述べる」の「事実」の方だとわかります。それでは、「事実として述べる」というときの「事実」とは何なのでしょうか。それが「事実を述べる」のところで着目した、「事実」イコール「本当のこと」あるいは「真であること」と言いたいのですが、この「本当のこと」「真であること」というのがクセモノでして、こう言ってしまうと、事実がそのまま真偽の問題になってしまい、再び「事実(実際のところ)」と「真偽」がくっついてしまうことになるのです。
ここは大変ややこしいところです。ですが、1-4と1-5の全体を通して理解できるようになっていますのでご安心ください。ここであなたがわからないと思ったところは、やがて回収される伏線だと思ってください。ひとまず私は、「事実として述べる」の方の「事実」について、これは「本当のこと」という意味を当てたいと思います。そして、真偽の問題になってしまうのを避けるために、「本当のこと」と「真であること」を同義と見做すことをやめます。私は上で次のように述べました。
「ちゃんと事実を言ってください」と言うとき、それは「ちゃんと本当のことを話してください」と言っているに等しい[...]
ここで「本当のこと」というとき、それは事実に照らして真であることを相手が言うことを希求していると同時に、相手が本心から、隠し立てなく率直に、相手自身にとって信じられている事柄を言うことも期待していると言えるでしょう。直説法の定義として使われる「事実として述べる」という言葉には、この後者のニュアンスが重要となります。
4. 文・命題・直説法
4.1 直説法と命題
上の3.では、事実をただの事実として扱い、真偽から引き剥がすということをしました。真偽は文として表される「言明や命題あるいは判断」において宿ります。以下では「事実」からは少し離れて、命題を中心に考えていくことにします。なお、ラッセルは「言明や命題あるいは判断」と並列して述べているところですが、ここでは「言明や命題あるいは判断」を一括して命題として考えます。言明も判断も、命題に付随することがらで、命題の方がより高次の概念だからです。
命題は、主に論理学で使われる用語で、真か偽かを必ず明らかにすることができます。
[…]その文が事実を述べようとしたものである場合、それが事実の通りなら「真」と言い、事実の通りでないならば「偽」と言います。そして、真偽が言える文のことを「命題」と呼びます。
論理学上の目的にとっては、真偽の二極性の典型的な担い手を命題に絞るのが自然です。命題とは直説法の文のこと、問いを発したり命令したり願望を表現するのではなく、何かを主張する文のことだと言えます。
ふたつほど引用しました。ひとつは論理学の入門書からの命題の説明で、もうひとつは先に引用したラッセルの『論理的原子論の哲学』の別の箇所です。このラッセルの引用(20頁)で興味深いのは、彼が命題について説明する際に、直説法に関連させてその説明を行なっていることです。命題は直説法の文で述べられる。これは正しいです。論理学も高度になれば記号によって記述されますが、そうした記号も文に変換することは可能で、その際は直説法によって記述がなされます。また、「問いを発したり命令したり願望を表現するのではなく」とも言っています。これは、問いを発するのは疑問文、命令するのは命令文(命令法)、願望を表現するのは祈願文であるというわけですが、疑問文において使われる動詞を直説法の動詞であると見なすこともできるので、ここでは、ラッセルの命題の定義を拡張して、命題は直説法が用いられる平叙文(直説法平叙文)で述べられると言うことにします。
4.2 命題と文の意味
ここで重要なのは、命題は文の形を持ちますが、私たちがふだん発話する文がそのまま命題として扱えるのではないということです。私たちが口にしたり、書いたりする文には、大概の場合、命題以上の「意味」を持っています。何度も使用しているあの足し算の例を引けば、Two and two makes five.(2足す2は5だ)という文は直説法の文ですが、ここからわたしたちは「2 + 2 = 5」という命題を取り出した上で、それについて計算したり、検討したりして、真とか偽とか言うわけです。というかそもそも、人間が「2足す2は5だ」というような台詞だけを単純に吐くということは稀なはずで、より具体的な場面を想定し、たとえばあなたが算数の教師だとして、目の前の児童に足し算のクイズを出しているという状況を考えてみてください。相手の児童は、「2足す2は?」という質問に対する応答として、——残念ながらその子が5という答えを導いてしまったとして——「2足す2は5……かなぁ。」「2足す2は5だと思うよ、たぶん……。」「10の半分でしょ」「4の次の数かも」などのような様々な形が考えられますが、「児童が2足す2という問題について5と答えた」ということには変わりありません。命題は、この元の発話された文から、ある程度の意味が捨象された段階において見出され、真偽というのはこの段階で導出されるのです。図2で示した内容をより現実に即せば、次のようにアップデートできます。
文:「2足す2は5です!!」(児童が自信たっぷりに)
事実:2 + 2 = 4
命題:児童の回答「2 + 2 = 5」
→ 真偽:偽
別の例を挙げます。使い古された例ですがコップの中に半分水が入っているとします。これを「コップの中にまだ水が半分もある」と言うか、「コップの中にもう水が半分しかない」と言うかでは、意味が異なります。しかし、命題的な価値としての意味、「コップの中に水が半分まで入っている」という点については変わりません。ここで重要なのは、同じ事実について言及しているとはいえ、異なる表現を話者が用いている以上、そこには異なる意味合いが生じるということです。すなわち、命題的には等しいが、文全体としては意味的に異なるというケースがこの世には往々にして存在するのです。八木沢敬氏に倣って言えば、「ひとつの命題がいくつもの文によって言い表されることはありうる」のであり、「命題は文そのものではない」のです。

命題もまた文の形を持つのでややこしい。本稿では命題を文(発話文)から導かれるものとして扱います。
なお、文が命題と価値を等しくするときがあり、その場合には黒の円と赤の円が重なり合います。
4.3 逆は真ならず
4.1では、命題とは、直説法が用いられる平叙文(直説法平叙文)で述べられる文であるとしました。これを論理学の条件文で言い換えれば、「命題であるのなら、直説法平叙文で述べられている」となります(これもまたひとつの命題であることに気づいていただければと思います)。この命題の定義が受け身の文でなされていることに注意してください。命題は文から見出される(措定される)ものとしてこの文章では扱っています。発話された文があって、その後に、命題は認識されたり文として表現されたりするのです。この観点からいえば、いま述べたばかりの、命題を定義したときの命題「命題であるのなら、直説法平叙文で述べられている」の「逆」が必ずしも真ではないことがわかります。すなわち、「直説法平叙文で述べられているのであれば、それは命題である」という命題(元の命題の逆)は「偽」なのです。それは次のような文を反証として認めることができます。
直説法平叙文で述べられていても命題にならない例
(1)このパスタはうまい! (主観的な表現)
(2)四月は最も残酷な月(詩の一部)
(3)お前、人間のクズだな。(罵倒・主観的な表現)
(4)私はこの船を「クイーン・エリザベス号」と命名する。—— 船首に瓶を叩きつけながら発話されたものとして(遂行体)
(5)君のひとみは10000ボルト(メタファー)
解説するのも野暮かもしれませんが、ひとつひとつ見ていきますと、(1)あるパスタが美味しいのか美味しくないのかということについては、そのパスタをどれだけ検証しようが無駄で、結局はパスタを食べる個々人の主観に因ります。(2)「四月は最も残酷な月」かどうかを4月について調べたりアンケートを取ったりしても無駄です。(3)のような捨て台詞は、相手にメッセージを伝えるというよりも、言葉を相手に吐き捨てるように投げつけることで、自分をすっきりさせることを目的としているでしょう。たとえ、本当に相手に「お前はクズである」というメッセージを伝えようとしていたとしても、ある人がクズかどうかは、やっぱりそう言ってしまう人にとって相手はクズなのかもしれませんが、クズと言われた人も家に帰れば良いお父さんだったりするものです。船に名前を与える儀式において、(4)のように宣言することは、「[...]と命名する」と言うまさにその瞬間に命名するという行為を遂げたことになるので、発話その瞬間自動的に真に確定すると言えます。よって、命題として真偽を問うことが無意味になります。(5)「君のひとみは10000ボルト」と述べられたからといって、眼球に電圧を測るテスターをかまそうとするでしょうか。万が一、電圧を測ったとしても、実際は0ボルトでしょう。では、その結果を受けて、「君のひとみは10000ボルト」は偽だったと見なしますか? 確かに、真偽でいえば偽でしょうが、このセリフを吐いた当人からすれば、「いや、伝えたかったことはそこにない……」と思うでしょう。
以上のような例から、直説法で述べられている文——それは、英語を使用する場合の多くの場合の文のかたちです——であるからといって、それが命題である(真か偽かを問うことができる)とは限らないこと(「直説法平叙文で述べられているのであれば、それは命題である」は偽であること)がわかりました。
*
それにしても、私たちはここまでで一体何をしてきているのでしょうか? 否、「私たち」ではないですね。単にこれは私が単独でやらかしていることに他なりません。なぜ、普通の参考書や語学書であれば「直説法とは事実を述べるもの」あるいは「直説法とは事実として述べるもの」というようなたった一文の説明で済ませてしまうところを、延々と書き綴ってきているのでしょうか。
ここまでの理解で可能になっていることは、文と命題の切り離しです。
直説法とは事実について述べようとするときの動詞の形で、事実について述べられたことは文としての形を持ち、それは言明文としてすなわち真偽を問える命題として扱われる……というような理解においては、文と命題が一緒くたにされています。しかし、私たちはこれまでそれが正しいとは言えないことを確かめてきました。直説法の動詞で述べることがそのまま命題になるのではなく、正確には、命題というものが見出され文の形をとるときに、それが直説法平叙文で述べられているのです。また、直説法の平叙文を述べたからといって、命題に還元され得ないような文があるのです。
4.4 生き生きとした文のほうへ
ここからは、話者(話し手、言葉を発する主体)の視点を中心に考察を進めていきます。これはなにも、最近の「発信型英語」重視の流れに寄り添おうとしているわけではなく、話者をベースにして考えなければ蔑ろにされてしまうような観点が言語を語るときには存在するからです。
直説法平叙文で述べることを命題と直接に結びつけてしまう観点からは、扱える文が非常に限られたものとなってしまいます。「2足す2は5」のような数学的な事実に関する記述は、その最たるものです。これに加えて、科学的な事柄に関する記述、次いで歴史上の事柄に関する記述が、真偽を問い易いとされるために、言語学では命題的な文の例文として好まれる傾向にあります。
科学的事実というのは、パラダイムが変わらない限りという留保付きではありますが、時間を超越しているものです。実験で水が100度で沸騰することを確かめた次の日に「昨日はそうだったとしても、今日も水が100度で沸騰するかはわからない」と言って、毎日水を沸騰させる科学者はいないでしょう(*「いや、そうとも限らんぞ?」というのが真に科学的な立場とも言えるのですが、ここでは話を複雑にしないために、触れないでおきます)。科学的事実も「2 + 2 = 5」のような数学的事実と同様に真偽を問いやすいのです。なお、蛇足になりますが、学校文法で現在形をならうときに「普遍の真理」については現在形を使う、ということを習います。これもいま述べたことと多少関係しています。しかし、ここでは指摘するにとどめておきましょう。第2部以降で現象学的な言語把握を試みる際に詳しく述べる予定でいます。
「江戸時代は1603年に始まった」「鎌倉幕府第3代将軍は源実朝である」のような歴史上の事柄に関する言明文であれば、明らかに過去に起きたことであるがゆえに、こうしたものも命題的な文(真偽を問うことのできる文)として扱われます。とは言え、歴史上の事実については、数学や科学についての事実のように一筋縄ではないことに注意が必要です。例えば、鎌倉幕府の開幕については、「良い国(1192年)つくろう鎌倉幕府」ではもはやなく、現在、学校では1185年で教えられます。ただ、これとて1185年であることが実証的に明らかになったわけでなく、鎌倉幕府成立年については依然「諸説あり」という状況です。1185年が正しいとされているのは、検定教科書の記述がそうなっており、入学試験を含むテストの解答として1185年でなければバツとなる、というようなコンセンサスのようなものが出来上がっているからに過ぎません。こうしたことは、戦争責任が絡むことについては更に事情が複雑となることは指摘するまでもないでしょう。
数学的、科学的、歴史的な事実は特に真偽を問いやすい(命題として扱いやすい)ということをいま述べてきました。こうした文というのは、例文などではよくお目にかかる種類の文です。しかしながら、こうしたカテゴリーの文は、私たちの日常を取り囲む様々な文(発話)の中では、限られた範囲の文なのです。私たちの日常の言葉は、真偽が明白な文よりも、はるかに多くの別の何気ない事柄について費やされているのです。
文法について述べた論考というのは、都合よく主張を補佐する例文をひとつかふたつ持ちだしてくれば、それなりに真っ当そうな説明になってしまう傾向があります。「地球は太陽の周りを回る」とか「2は素数でありかつ偶数である唯一の自然数」のような文だけを対象にして、文というものは命題について述べたものだと言い切ってしまうこともできます。そうしておけば、この直説法について述べている文章ももっと短く済んだことでしょう。しかし、私はお茶を濁すような真似はしたくありません。「地球は太陽の周りを回る」のような命題と不可分になってしまっている例文は、私にはガラスケースに入れられた剥製の標本のように見えます。形はあるが、生きてはいないのです。言葉たちをそこから現実へと連れ出して来なければ仮定法はわかりません。ウィトゲンシュタインに倣って言えば、ツルツルでなくザラザラ。前に進むためには摩擦が必要です。だから私は、これからの論を進めるにあたって、次のような何気ない現実的な場面における文をダシにして考えてみたいのです。
A「ねえ、昨日また駐車場のところの猫にエサやったでしょ?」
B「うん。あげた。」
A「もお。今日も来たらどうすんの?」
B「まあいいじゃん。かわいいし。」
A「かわいいしって、どうすんの? 手術させなきゃいけないとかあるんだよ?」
同居しているふたりの喧嘩が始まりそうな場面ですが、ここでの論点を先取りして申し上げれば、実に身も蓋もない「事実」ですが、それはこういうことです。
私たちが何か言葉を発するとき、たいがいの場合は自分の発話が命題としてもちうる内容のことなどは考えてはいない。
この例文(スキット)では、Bの「うん。あげた。」という発話に着目してみます。Aに問いかけられて、それに対して「うん。」というBがいます。この「うん。」という応答は、「Bが昨日駐車場のところに現れた猫に対してエサをあげた」という命題に還元されうるものですが、それだからといってBが発話の際に命題との関わりのなかで文を発していると見なすのは、どうも直観には沿わないように思います。質問されて、自分(B)が本当だと思うことをとりあえず述べた。だから単に「うん。」と言う。命題に還元するというのは、言語を観察的に検討した場合に可能になりますが、生きた言語を産出する当の人間にとって、それは意識化されません。発する人のみならず、同じ場にいる会話の受け手にも意識化されてはいないはずです。発話の際に人間の脳の中で命題が意識化されているか、というのはfMRIなどを使っても科学的には明らかになりはしないでしょう。それゆえ私は「意識化されていないはずです」とか多少自信なさげに言ったり、一方で断定的に「考えてはいない」とあえて述べたりしていますが、ここではそういうものとして話を進めたいと思います。
さらにこの会話においては、—— 別の新しい、しかし例文というものを考えるのに欠かせない論点として—— もうひとつ検討しなければならない点があります。ここでBが「うん。あげた。」ということで、私たちは読み手として「Bは昨日駐車場のところに現れた猫に対してエサをやった」という命題に対して「真である」のだろうと判断するわけですが、その根拠はと言えば、「Bがそう言っているから」でしかないわけです。私も思わず「質問されて、自分(B)が本当だと思うことをとりあえず述べた」と書いてしまいました。しかし、Bが虚偽を言っていないという保証はどこにあるのでしょうか? とはいえ、文を受け取るにあたっては、私たちは会話文中の話者であるBのことを信じている、というかひとまず信じざるを得ないわけです。これは文を読むことにおいて無批判に前提とされる慣習の一つで、これがあるからこそ「信用できない語り手」という小説における手法も実用性を持つというわけです。
上のスキットの例文は私が先ほど即興でこしらえたもので、フィクションといえばフィクションなのですが、次のように仮定してみましょう。AとBは確かにこの世界——これを読んでいるあなたと私もいるこの世界——に存在していて、私はそのAとBの会話のやりとりを横で聞いていて、その聞き取った内容を書きつけたものが先の会話文であると。すると、Bはこの現実の人間であるわけですから、Bが実際にエサをやったかやっらなかったかのどちらかであることは事実なわけです。「Bがエサをやった」という事実に対して、今のところは「Bがそう言っているから」という根拠しかなかったわけですが、駐車場の監視カメラにBが猫にエサをやっている瞬間が写っていたとか、あるいはBが猫にエサをあげているところを見かけた人がいたとか、そうしたことによって、「Bがそう言っているから」という以外の、客観的な証拠によって事実が保証されるわけです。しかし、ここまでくればほとんど裁判のプロセスになってしまいます。何気ない会話において、そこまでして真偽を突き止めようとするでしょうか? もちろん、万が一、Bがエサをあげたのが実は野良猫ではなく2軒先に住むNさんの飼い猫で、Bがやったエサを食べたことで死んでしまい、Nさんが犯人を突きとめるべく動き出した、とでもなれば事実検証プロセスは進んでいくでしょうが……。日常的な場面における発話を命題に還元して事実検証をしようとすることはこれほどに厄介なのだということを理解していただけたでしょうか。
私たちが普段、言葉を使ってコミュニケーションをするなかで、命題のことは意識していない。命題を念頭にして話すことなどはない。けれども、コミュニケーションをする中では、相手の言うことをとりあえず「そうなんだろうな」と思って受け取り、その相手の発言を踏まえて今度は自分が相手に言葉を返す。このような状況において、何か命題における「真」以外の「真」があるのではないかという直観を持つことは可能だと思います。それを3-2ではとりあえず「本当のこと」と言ってみたのでした。
続く1-5では、ひとまず「本当のこと」と呼ぶにとどめたこの点についてつぶさに検討していくことになります。
5. まとめ
「事実を述べる」ことはできない。たとえ結果としてそれが「事実だ」と言われるのであっても。
「事実として述べる」と言われるときには、「真であるものとして述べる」という意味と、「“本当のこと”として述べる」という意味の2つの意味合いを含んでいる(後者については詳しくは1-5で述べられる)。
事実は単に事実であって、人間にとって外在的なものである。事実について述べたものは、もはや事実ではなく、命題的な文となる。その文が事実に照らされ、真か偽と判断される。
直説法で述べることが命題的な文になるとは限らない。話者はいつも真偽値にコミットしているのではない。そもそも文を述べるにあたっては、いちち命題のことなんて気にしていない。
発話文は常に命題に還元されるわけではない。少なくとも日常の言葉のやりとりでは、命題に還元されないことの方が多いと言える。コミュニケーションの場で、命題のことなんて考えない。
次回予告
続きである1-5 にいく前に、間奏曲的に1つか2つ、短めの文章を掲載する可能性が高いです。今月中に公開できればと思っております。
(以上35枚/ここまでの合計89枚)
参考文献
安藤貞雄『現代英文法講義』開拓社、2005年
オースティン, J. L.『言語と行為』飯野勝己訳、講談社学術文庫、2019年
ジャッケンドフ, レイ『思考と意味の取扱いガイド』大堀壽夫・貝森有祐・山泉実 訳、岩波書店、2019年
勢力尚雅・古田徹也『経験論から言語哲学へ』放送大学教材、2016年・・・ウィトゲンシュタイン云々のところはここで引用されている『哲学探究』107節から。
野矢茂樹『まったくゼロからの論理学』岩波書店、2020年
野矢茂樹『論理学』東京大学出版会、1994年・・・4.の補足でのコップが半分に関する議論はこの26ページの改変。野矢は「財布の中の1万円」を例に使っている。
ラッセル, バートランド『論理的原子論の哲学』髙村夏輝訳、ちくま学芸文庫、2007年
ロッジ, デイヴィッド『小説の技巧』柴田元幸・斎藤兆史訳、白水社、1997年
八木沢敬『分析哲学入門』講談社選書メチエ、2011年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
