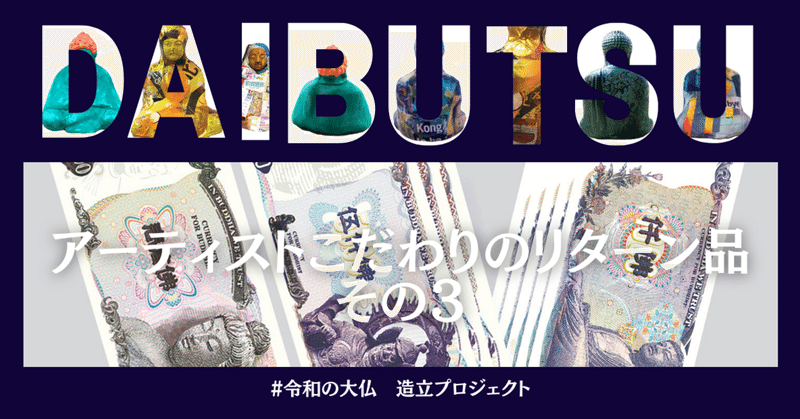
緊急対談「#令和の大仏」造立プロジェクト! Vol.19 アーティストこだわりのリターン品その3
先が見えない中、前向きにみんなの力を未来へ向け、願うための対象として大仏を作るプロジェクト。より多くの人に参加してもらいたいという思いを込めて、連夜対談をライブ配信しています。
今こそ大仏を!プロジェクトの発起人の風間天心と前田真治。Vol19では、アーティストたちがこだわったクラウドファンディングのリターン品について迫りました。その3です。
対談まとめ
今日の作品アーティスト 太湯雅晴とは?
日本の美術家。紙幣を模した平面作品やそれを用いたパフォーマンス、他に日常空間に介入するプロジェクトで知られる。German Suplex Airlinesのメンバー。

太湯銀行券 無限円とは?

Prototype for the Private Currency, Self-portrait (2005)
(太湯)この作品はアートワーク(芸術作品)として作っているんですけども、なぜ額面を無限円にしたかというと、市場経済に於いてはアートワークは無価値にもなり得るし、とんでもない価値にもなりえると思うからです。これを作ったのは10年以上前になりますが、その当時は価値がなくても、ギャラリーを通す等して市場に出回ることでどんな金額でもなりうると考えました。10年前であれば1円2円だったかもしれない。だけど、何かのきっかけで100万円、500万円、1000万円になりうる可能性もあるという意味で、無限円という文字でこの作品を作りました。そこに自身の作品の証明として、私の名前である「太湯」を冠し、太湯銀行券としました。これはそういう作品であります。これはただ作るだけではなくて、市場に出回らせました。私がこの作品、つまりお金を持っていろんなところに行って、お店の人にこのお札で商品を買いたいんですけどと交渉をするんですね。そこでお店の人とのやりとりが成立すれば物が買える、何かのサービスが受けられる。「いや、こんなんじゃだめですよ」と断られたら、その交渉はそこでおしまいという関係なんですけれども。
ユーモアによる価値
通貨とは、「利用者自身がその流通圏内に属している事を意識させるために在る」ということに気がついた。以来 既存通貨とは異なる、任意に定めた共同体内の人々を繋ぐためのメディウム=オリジナルの紙幣をつくりたいと考えるようになった。
出典
(太湯)よく言われる話なんですけど、お金というのは、現在の考え方でいうと信用、信頼で成立していわけですよね。決して、紙切れや硬貨に何かしらの価値があるわけではなく、それを価値あるものだと信じることでそこに価値が生まれるわけです。それを保証するのは通常は国家であったりとか造幣局だったりするわけですけども、私が作る作品、貨幣は、その信頼を担保するものは何もないわけですよ。ただそこに価値があるんじゃなかろうかと利用者が思い込むことによって価値が生まれる。唯一、私の紙幣作品の価値を担保するのは芸術家としての私自身。それを私は「ユーモア」という言葉で代替したつもりです。
私たちを取り巻く社会は、規制や因習、マナーといった約束事を重層化して形成している。
約束事とは、所謂生きる知恵だったり共同体をまとめる為の制度だったりするわけだが、それらは歴史を加味しながら大きなシステムを成し、システムの破綻を招くような因子は予め排除されるように編集される。
出典
私たちを取り巻く社会は、規制や因習、マナーといった約束事を重層化して形成している。
(太湯)社会というのは、皆んながその存在価値を認めること、信じることでそれが成立しますね。信頼に価するものとして成立すると思うんですよね。そしてその信頼は規制や過去から積み重ねられた習慣、マナーといったものを皆んなが共有することで生まれます。
約束事とは、所謂生きる知恵だったり共同体をまとめる為の制度だったりするわけだが、それらは歴史を加味しながら大きなシステムを成し、システムの破綻を招くような因子は予め排除されるように編集される。
(太湯)そしてそこに所属する人たちは、お互いのことを思いやったりとか、約束事を作りそれを守ることで社会を安全に運用することができると思うんです。この文章の中では社会の仕組みのことを「システム」という単語で表していますが、システムの破綻招くような要素、行為は排除されます。ここで言う「システムの破綻招くような要素、行為」について明記はしていませんが、システムの維持に協力的でない人、例えばホームレス、反社、犯罪者等の存在または彼らの言動を指しています。他人の迷惑を顧みず好き勝手に行動するような人は強制的に弾き出されます。常識を覆すという意味ではアーティストもシステムの破綻招く要素になり得ますが、他者がいなければその存在が成り立たないという点に於いて前者とは異なります。
私はテロ的な行為を起こそうと考えているわけではないんだけども、その約束事っていうのを相対化させるような行為を持ち込むことで、社会の成り立ちに違和感を生じさせたいと考えています。それが先ほど紹介した紙幣の作品に繋がっています。
Buddyという作品を作ったときに考えたこと

(太湯)私の個人的な宗教観ですが、仏教に限らずどんな宗教でも空想の産物だと思うんです。そこに何かに救いを求める対象として、何かしらの概念をみんなが欲しがるわけです。そこにたまたま神様という存在が想定されます。そしてそれを具現化したものとして仏像であったりとか、キリスト教であれば十字架があるんだと思うんですよね。それを僕なりに表現した物が今回のBuddyというお札、作品になるんです。それをより物語として重層化するために、この図柄の中にいろんなモチーフとか要素を持ち込んだというのが今回の作品のあらましです。
Buddyのデザインと印刷について
(太湯)日本では特にそうなんだけれども、お札って画面の右側に肖像画といった物が入ってくるんですね。 これはなんでなんだろうなと私なりに考えてみた結果、上手下手(カミテシモテ)の概念を持ち込むとわかりやすいんではないかなと思ったんですよね。舞台とか映画でよくある考え方なんですけども、画面の右側に偉い人などが来て、左側にお客さんというか地位の低い人たちが配置されることが多いなと考えているんです。吉本新喜劇でも、画面左手に玄関があって、右側にお家のや店の主人とかがいるんですよね。今回のBuddyであれば、大仏であったりとか四天王であったりとかブッダの像が配置されているんですね。それに対して左側に弱い立場の人というのは変だけれどもそういうものを配置することによって、画面として一つのレイアウトができるのではないかなと思ったんです。図像的にはデザイン的なZ字レイアウト、F字レイアウト等、日本漫画の文脈で言えば逆Z字のレイアウト等ありますので、上手下手の概念もあくまで一例と考えて貰ればと思います。
また表面上部に「IN BUDDHA WE TRUST」という文言を描き入れています。元ネタは米ドル紙幣裏面に書かれている「IN GOD WE TRUST」です。我等は神を信じる者也という意味です。我々が神を信じている限り神は存在する、神が居るのであれば我々、つまり我々のいる社会は神に祝福されている、従ってこの貨幣は価値がある。一神教的且つ記号論的な論法ですが、私はこの文言をこのように理解をしています。
今回はコロナが一つのテーマになっていると考えたので実はBuddyの地紋のところにコロナのアイコンが配置されていたりとかそういう細かい芸がちらほらあるのも個人的には見てもらいたいところかなと考えています。色味に関しては理屈で考えたかったが、感性の部分が大きくなりました。
印刷についてですが、実際のお札の印刷では一色ごとに版を作っています。ブルーであればブルーだけの版、イエローであれはイエローだけの版を作ります。それを明度の高い色、明るい色から順番に濃い色を印刷していくんですよね。一番下に淡い色、薄い色を印刷します、その上にちょっと濃い色、彩度の高い色等を印刷、その上にはさらに色味の強い色、という順番で印刷しています。現在の日本銀行券では、肖像画部分の濃い藍色や茶色を一番最後、一番上に印刷します。色の配色方法に関してBuddyはその方法を参照してます。高精度インクジェットで図柄を印刷し、透かしの部分には質感の違いを出すためにシルクスクリーンという印刷方法を試みています。
Buddyの始まり

写真:全国キャラバン中(左)風間天心(右)前田真治
(風間)そもそもBuddyというのを考え始めたのは、大仏を同じように僕と前田さんでいろいろ話しているうちに出来上がっていったコンセプトなんですけども、特に日本の仏教とかお寺って、お金に関わることをどうしても揶揄されがちだと思うんですね。だけどお金っていうのは、あくまでも一つの価値として存在してるだけであって、昔であれば僕が生まれたお寺だと檀家さんがお米を持ってくることがあったりだとか、カンボジアだと食べ物を持ってその場でお坊さんたちが食べるという形がある通り、それがお金に替わったというだけであって、元々のお布施という性質には変わりがないと思うんですよね。お金と仏教の関係を考えたいなと思って、まず始めたものです。
Buddyで善意の循環を
(風間)最終的にどういうものかというと、太湯さんも作品に対していろいろコンセプトがある通り、僕らもこれがどういう形で使われて、どういうものになっていくかを深くシミュレーションをしたんですけども、今回はそこまでいうと逆に難しくなってしまうのと、クラウドファンティングで使う上で、実際の金券ではない、これを日本銀行券と替えたりできるものではないとちゃんとわかるように明記するように言われたのがあって、作ったときの本来のコンセプトとは変容しているところはあるんですけども、簡単にいうと善意の循環というのでしょうか。
返しきれない恩をBuddyで表現
(風間)僕も40年生きてきて、今回のクラウドファンディングもそうなんですけども、どうしても自分では返しきれない恩ってありますよね。特に若いうちはそうなんですけども、金銭面でもそうですし、すごく助けてもらった。だけど、自分が持っているものでは返しきれないと思った機会は必ずあると思うんですね。その時にこれを使って欲しいというイメージなんですよね。それはさっき太湯さんが言ってくれた通り、お互いにそれが共有できていないと難しい部分だと思うんですけども、何かの善意を受けた時に感謝を表明するためにこれを渡すというイメージです。今回も、見た目もお金っぽいんですけども、あくまでもクラウドファンディングで支援していただいた気持ちをこういう形でお渡しする。もらった人も、ただもらったわけではなくて、ある形で協力し、支援したという形のある種の証明というか、そういうものとして機能して欲しいというのがあって作りました。
お金にある「性質」
(風間)お金って、例えば最近は、この会社の商品を買わないとか、結局お金がどう巡っているかというのをイメージした時にそれぞれの思想が反映されたりすると思うんですけども、善意という物がBuddyに乗って伝わっていくという。そもそもの日本銀行券に特別な性質があるのではないですけども、せっかくならある種の性質が乗った物があってもいいんじゃないかなと思って作った物です。Buddyは第一回目のクラウドファンディングでほぼ全てのリターン品に入れたんですけど、おすすめのリターンです。太湯さんが作ったものを実際に見みると、実際にみなさんが思っている以上に精巧にできているものです。
紙幣と信頼、そして共同体
(太湯)紙幣というとさっきも言ったように、そこに信頼さえ乗っければなんでもいいと思うんですよ。ペンでもいいですし、なんだったらトイレットペーパーだって通貨の代わりになると思うんですよ。ただ、現存の紙幣というのは、偽造防止というのもあるんだろうけど、共同体の力、国の力を示すため、うちの国ではこれだけのことができるんですよということを示すために精巧に作っているというところもあると思います。私はそのあたりを意識して頑張って作っているので、絵の美しさ、精巧さに関しては自信を持ってお見せできます。
日本人のお金に対する信仰
(風間)元々僕たちが普段使っているお金も、誰かが実際に描いているある意味で版画というか作品とも捉えられるような性質のものなので、だからこそみんな大事にできると思うんですよね。現代はお金に対してのある意味の信仰みたいなものもあるとも思いますし、日本人は、例えば、神社とかに行ったら五円玉入れる方が多いんですけど、ご縁って日本人の独特な捉え方が五円玉にあったりすると思うんですけど。資本主義とかとは別にお金に対してのある種の敬いっていうのも含まれているので、そう言ったこともいろいろと考えたりしてできています。
Buddyは誰に選ばれるのか?
(風間)Buddyは話せることが実はいっぱいあるんですよね。最初に考えたコンセプトに一応触れておくと、今は仮想通貨とかなんとかペイみたいな電子マネーが山ほどあると思うんですけど、それを選択するときの理由って多分ポイントがつくとかそういう理由だと思うんですよね。だけど、いっぱいある通貨の中で、これを選ぶというのが、例えば仏教徒はこれを選ぶというような通貨があったら興味深いなというところから始まっているんですよね。流通するとどうかというのもあるんですけど、実際どういう人たちの中で使われていくのかっていうのは、Buddyを考えた時にイメージしたことです。
Buddyが国境を超えるとき
(太湯)私がかつて作品として作っていた時もそうだし、今回のBuddyに関してもそうなんだけど、日本円は主に日本だけで使われる通貨。ドルは基軸通貨ではあるけれど主にアメリカで使われる紙幣です。一方私の太湯銀行券にしろBuddyにしろ、それを信頼する人たちであれば世界各地どこでも使うことができる、流通させることができると思うんですよね。そうすると特定の国境とかで区切られたものではなくて、また別の共同体というか、別のフレームが浮かび上がってきたりすると思うんですよね。そういう意味でもBuddyをプロジェクトの一つとして捉えると、先々面白い展開が見込めるのではないかなと個人的には考えています。
モノだからこそある意味
(風間)世代によって伝わらないと思うんですけど、北の国からというドラマで、吾郎さんが泥のついたお札を持っていたシーンがありましたが、それはお札のものの価値とはやっぱりまた別な意味を持ってくるんです。たとえでいうとああいうイメージになると思うんですよね。同じように交換できるものであるけれども、その一枚に込められた想いっていうのは、やっぱりものである限り、ものだからこそ生じることなのかなと思うんですね。電子マネーだと起こり得ないことなのではないかなと思います。Buddyは大仏プロジェクトとは他に僕たちが進めたいプロジェクトではあって、それくらい話始めるといろいろと出てきてしまうことがあるんです。
「Buddyコース」について
■ [仟Buddy、伍仟Buddy、壱萬Buddy]
「仟 Buddy」札を5枚、「伍仟 Buddy」札を3枚、「壱萬 Buddy」札を1枚、郵送します。(Buddyは善意の性格をもった貨幣作品であり、日本銀行券などと換金できる金券ではありません。)

■ [支援者として大仏横にお名前を明記]

支援していただいた方のお名前、場合によってはその会社名だとか自分が書いて欲しい名前を大仏の構造体の中に書く予定になっています。
Buddyコースはこちら
第二回目 大仏造立クラウドファンディングに挑戦中
大仏造立の物語にもっと近くで参加できるクローズドコミュニティ
こちらのクローズドコミュニティ(非公開コミュニティ)では、このプロジェクトにご関心のある方向けに情報発信し、コミュニティ内でつながっていけるようにいたします。ご入会はクラウドファンディングへのご支援、または1000円以上のご支援をいただいた方はどなたでもご参加いただけます。コミュニティはFacebookを利用します。お申し込みはこちらのフォームにてお願いいたします。令和の大仏造立の物語に、一緒に関わってみませんか? なお、いただいた申込金は、大仏造立資金に活用させていただきます。
いただいたサポート金は、大仏造立資金に活用させていただきます。


