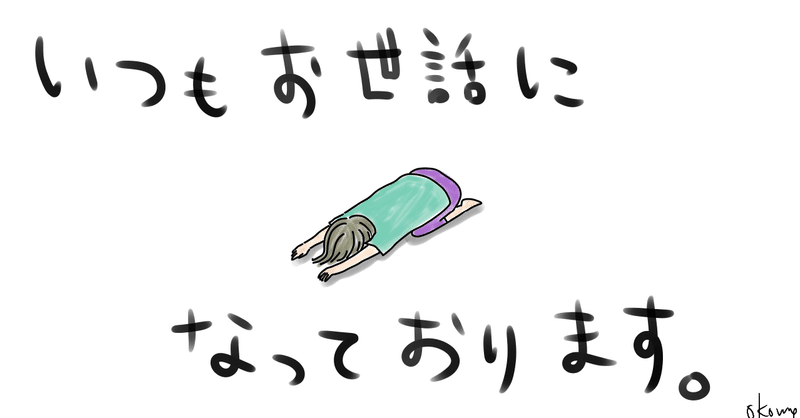
感性盛りがこわい
独特の感性、というものが苦手だ。むろん、小説を読むたのしみの主たるものとして「独特の感性」に触れることはあるんだけれど、年々じぶんにしろ他人にしろ「感性」というものを信頼できなくなっている。一般的に「かわいい」と見做されないものを「かわいい」といったり、多くに共感されないだろうことを熱心に話したりすることに「ハイいま感性盛りましたよね???」っておもってしまう。
しかしこうした態度はおそらく表現に関わる人間にとって望ましくない。個人の認識、それを自認する術としての言語(ないし美的)感覚は他者と共有されるのを前提に生まれてきたわけじゃない。持ち主の望む/望まざるに限らず存在してしまった感性についての接しかたであり、理解しようと歩み寄る行為としておそらく「表現」というものがあるから。それをわかりつつ、そしてそれを積極的に自作のなかにとりこみつつも、他人に「独特の感性」を突きつけられるとウッ!としんどくなる。
というのも、ぼくはじぶんの感性に自信がない。これについてはじぶんの育ちが深く関わっていて、先ほどから書こうとしても簡単に説明できるものじゃなかったので、いずれ機会があれば詳しく書きたいのだけど、まあこれまでの人生でぼくは「感性が腐っている」「絶望的にセンスがない」みたいなことを言われ続けてきたのだった。
そのせいか、ぼくはハイセンスな友だちと街をぶらぶら歩くのがとてもこわい。ハイセンスな友だちは街を歩けばすぐに「さっきの◯◯、××っぽいよね」みたいなことを言い出すのだけれど、だいたいぼくはそれにまったく共感できず、「お前と俺の感性はこれだけちがうんだぜ……!」と見せつけられているような気がする。共感しない場合のコミュニケーションとして思いつくのは、「なんでやねん。そんなわけあるかい」的なものなんだけど、こうしたイジりは令和以降あんまり好まれない傾向にあるし、感性のマイノリティ的側面を蹂躙してしまう可能性すらあるから、対応が難しい。
どんなに気心しれた間柄でも、街を歩いていてなにも起こらない時間が五分十分と続くと「これはおれがおもんないからなんや……」とすごく落ち込んでしまうんだけど、一昨日に義妹の夫が「ロバート秋山が市民プールで泳いだあとひメシを食う番組」を教えてくれた。すこし元気になった。
頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。
