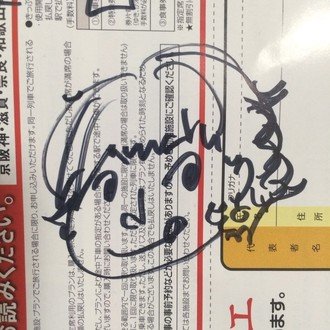【第5回】「良い本」とはなにか──Richard Powers ”To the Measures Fall”冒頭
リチャード・パワーズは現代アメリカ文学でたぶんとてつもなく重要な作家のひとりだとおもうのだけど、とうぜんながらアメリカのほうが日本よりも作家数は多いとおもわれるので、見聞きしたものから推測してこういうに留めるくらいしかぼくにはできない。こうした「大きなこと」をいうのは「適当」か「願望」かのどちらかにあたるものなのだけど、ぼくがパワーズに寄せるおもいは後者だ。パワーズという作家さえ読まなければ、文章を仕事にしようだなんておもわなかったにちがいないし、パワーズさえ読まなければ、小説を書くことがコスパの良い趣味程度になっていたはずだから。
今回とりあげるThe New Yorker に掲載された短編『To The Measures Fall』はまさにそうした内容の物語だ。留学中の大学3年生の「あなた」がElton Wentworthによる小説『To the Measures Fall(メジャーズ滝へ)』と出会い、その本による執着と読者である「あなた」の人生が描かれているわけだが、「本」というものの価値を「読書」という行為を参照しながら問い続けている。小説で用いられている二人称は、この問いの気配を読者に与え続けるために導入されていると読める。
この翻訳研究で課題を抽出するとなれば「現実を参照する」ということになるだろう。そもそもぼくはあらゆる解釈には「翻訳」的な性質が不可避的に内包されていると考えている。「読む」であれ「書く」であれ、言語活動のすべては「表象と参照」により構築されたネットワークのうえに成り立っている。「目の前の記号」と「その記号が参照する対象」の中間経路を整備し、構築することが翻訳であり解釈と呼ばれるもので、固有名詞や現実の事件や歴史が大量に埋め込まれている作品群はそれに強い自覚がある。パワーズがデビュー以降やりつづけている小説の技術的なアプローチは、「表象と参照」の経路を「物語」と名付ける行為だろう。
リチャード・パワーズという作家
パワーズは1985年に『舞踏会へ向かう三人の農夫』によりデビューしたが、それ以前の経歴がかれの小説を知るうえで重要な要素が多く、パワーズ自身も自伝的小説『ガラテイア2.2』にて小説と自身の半生についての内省を行なっている。学者を志しイリノイ大学で物理学を専攻するものの、深く狭い専門領域内のみで思考を完結させることに違和感を感じ、修士課程では文学専攻に鞍替えする。しかし、文学という領域でもまた同様の閉塞感に抗いきることができず、修了後に専門とはまったく関係のない職(プログラマ)に就いた。その後、ボストン美術館でアウグスト・ザンダーが撮影した写真を見て小説を書くことを決心し、写真を見てから48時間以内に会社を退職、それから2年間かけて書き上げた小説が『舞踏会へ向かう三人の農夫』だといわれている。
パワーズの小説の大きな特徴はスケールの大きさだ。自然科学や文学、音楽、歴史といった雑多な知識がふんだんに用いられ、複数の物語が並行して進みながら、やがてそれぞれの物語が運命としかいいようのない不思議な力学で引き寄せられ、絡み合いながら、ひとつの場所へと収束していく。
狭く深い専門の縦糸と、「物語」という横糸。
これはパワーズの以降の小説でも作品の主たる骨格をなすものとして使用されつづけていて、これはかれが学生時代に抱いていた専門性にとらわれることによる閉塞への対抗にもなっている。この世に起こるほとんどの問題は極めて複雑で、だからこそ大きな問題に対しては一般に要素分解がまず行われる。要素分解された小さな問題に対する合理的解決法を提示し、それぞれの要素の解決の線形和として大きな問題の解決が与えられるという発想が、社会では広く信じられているようにおもう。しかしそれはちがう。物事が複雑である理由は、多くの要素を含んでいるがゆえに生じているだけではなく、複数の要素が非線形に絡み合っているからで、それに対して小さな解答を単に足し合わせただけでは説明などできやしない。
「世の中で起こる問題のほとんどのことに正解などない」
このようなことがよくわれていて、そしてこのことばは理系出身者への揶揄として用いられやすい傾向にあるのだけれど、ぼくからすれば「自然科学に深い理解をみなしている人間ほど、物事の複雑さの仕組みを理解している」とおもう。正解がない、という現象はそれじたいよりももっと前段階に思考されるべき構造を持っていて、そこにいかなる非線形性がひそんでいるかを検討されなければならない。
パワーズの小説がおこなっているのはまさにそれだ。ほんらいなら交わることのない雑多な事象を小説という技巧のなかで交錯させ、現実に不可解さいをもたらしている非線形性をテクストに引きずり出す──自然科学と文学を、現実とフィクションを区別する壁をその強大な筆力によってパワーズは破壊する。
短編小説『To the Measures Fall』もまた、断片的にだが本の内側と外側のふたつの世界が描かれている。今回は本作の冒頭の翻訳を通して、いかに読み、いかに書くかということを考えたい。
また『To the Measures Fall』は日本語訳が未だ発表されていない作品のため、今回はぼくによる翻訳のみを掲載する。
(課題文)
First read-through: you are biking through the Cotswold when you come across the thing. Spring of ’63. Twenty-one years old, in your junior year abroad at the University of York, after a spring term green with Chaucer, Milton, Byron, and Swinburne. (Remember Swinburne?) Year One of a life newly devoted to words. Your recent change, of course, has crushed your father. He long hoped that you would follow through on that Kennedy-inspired dream of community service. You, who might have become a first-rate social worker. You, who might haves done good things for the species, or at least for the old neighborhood. But life will be books for you, from here on. Nothing has ever felt more preordained.
(引用:Richard Powers, "To the Measures Fall", The New Yorker, 2010)
頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。