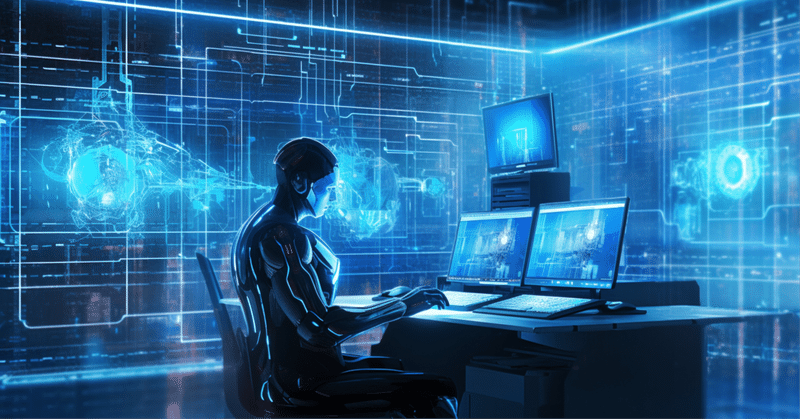
読了『仕事に役立つ新・必修科目「情報Ⅰ」』
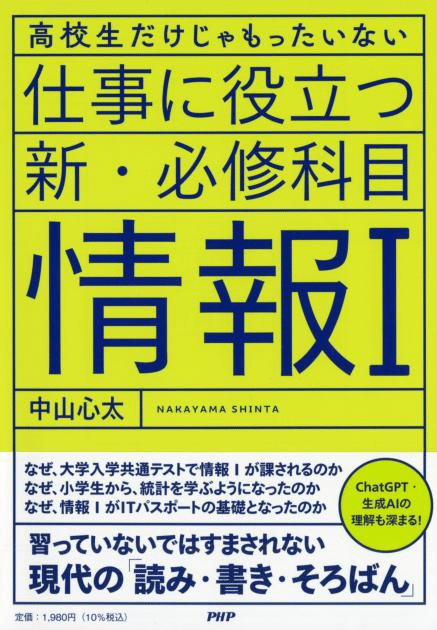
ITに対する世の中の状況(温度感?)みたいのを感じたくて読んでみました。
学校教育におけるIT
高校の「情報Ⅰ」では、ITパスポートの内容のざっくり半分ほどを学習することになるようです。私が高校生の時はITはもちろん統計やデータ分析も扱っていなかったので「いまの高校生はこんなことを学ぶのか・・・」と驚くと同時に専門家として身が引き締まる思いです。私が学習したのはITパスポートがまだ初級システムアドミニストレータと呼ばれていた頃だったので、改めて試験範囲を学習するのが良いかもしれないと考えています。
全ての人がこれらの知識を持って社会に出てくるとは限らないのでしょうが、「IT技術者と話すための知識」を持った人は増えていくのでしょうね。
プログラミングとは「群盲像を評す」の逆
プログラミング初学者の質問に回答していて「プログラミングをする際に必要となる考え方は何か」を考えることがあるのですが、「普段意識しない部分を意識して言語化していく」ということが必要なのですよね。コンピュータは空気を読めないので。人間にとって自明なところを意識して深堀りし、解像度を上げ、そして小さな問題へ分解していく。そうすることでようやくプログラミング言語に置き換えられるようになってくる。技術的な知識と合わせて、こうした感覚が理解できるかどうかがプログラミングに必要だと思います。
まとめ
まずITの普及により日本企業のアジリティの源泉が変化し、デジタル技術によるアジリティの獲得が必要になったという背景があるのですね(労働人口の減少もあるのかもしれない)。そのために統計やデータ分析、IT技術者と対話するための基礎知識としての「情報Ⅰ」、という理解です。
IT技術者もこうした世の中の流れを踏まえてキャッチアップしていかないといけないですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
