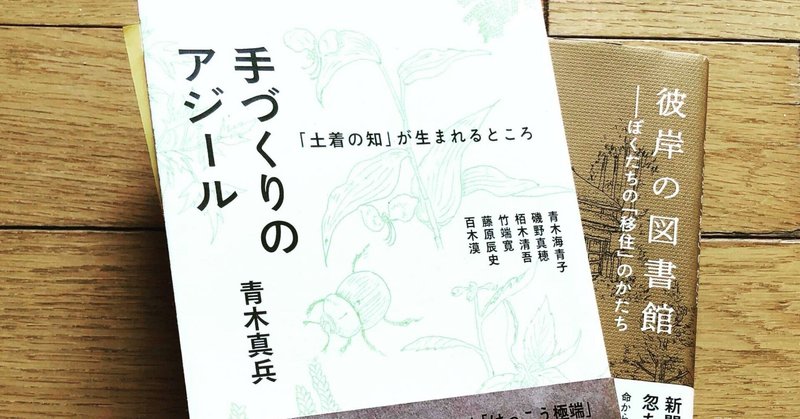
『手づくりのアジール 「土着の知」が生まれるところ』 青木真兵著 読む#1
たまたま知り合いが撮影した本棚に写っていたことからこの本の存在を知ったのだが、「手づくりのアジール」というタイトルがすごく印象に残っていた。というのも、私のいる共働学舎はアジールのような場所になるのが理想と思っていたからで、そこに手づくりという枕詞がつくのだから興味をそそられる。
*アジールは世俗の力の及ばない聖域、外の社会の迫害から身を守ってくれるところであり、誰もが利用できる駆け込み寺的な機能を持つ。
読んでみると予想通りに、いや予想以上に面白い。体調を崩して都会の生活を命からがら逃げ出した青木夫妻(真兵さん、海青子さん)が奈良県の東吉野村に辿り着いて、そこで古民家の自宅を図書館として開くという生き方を始めたのである。対談をメインとする構成になっているのだが、前著の「彼岸の図書館ー僕たちの移住のかたち」(2019年)の発展版という形式になっており、そちらも早速購入してしまった。
自分が共働学舎に参加するようになったのも、私的には違和感が多く感じていた都会の生活に疲れてしまい、農的な生活を求める中で出会ったのであり、同じように都会の生活を逃げ出したのだ。彼らの方がより具体的で切実な事情がある。真兵さんも持病持ちの上に体力的に厳しい状態が続き、大きく体調を崩して休職せざるをえなかった海青子さんは仕事のできなくなった自分に意味を見出だせなくなり、自死を試みるというところまで追い詰められた。そうした経緯があった上での移住であり、新しい生き方を始めたということである。(農的な世界に入ってから都市生活に違和感を抱く人に多く出会うことができたが、潜在的にそう思っている人はかなり多いだろう)
自分達の直感に従ってまず移住を決めて、山村に住み、自宅を開き、図書館活動を行うという3つ活動を始めたが、全て社会の外部である自然への「回路をつなぎ直す試み」という点で共通している。真兵さんは古代地中海史の研究者であり、海青子さんは司書として図書館に勤務していた経験から、二人は慣れ親しんでいる人文知というアプローチで暮らし方や働き方を見直して、社会に発信することを始めたのである。自分たちの暮らしからの気付きをまとめた本の出版や手づくりの冊子、そして毎週水曜日にはインターネットラジオ「オムライスラジオ」(二人での話やゲストを呼んでの対談)を配信している。
本の副題にもなっているが、彼の考えのベースには「土着」という思想がある。それはどんなものだろうか。土着について書いている部分を拾ってみる。
(今の時代には)まず今いる場所が自分に合っているかどうかを確かめることが大切、自分の中の生き物としての部分に自覚的である必要があり、それが「土着の知」です。この知には優劣はなく、誰もが持っている知だが、社会的に評価されたり、他人よりも一歩先んじられるとか、そういうたぐいのものではない。
人は(イリイチのいう)離床によって地縁、血縁などの「しがらみ」から解き放たれました。自身が商品と化すことでどこでも働くことが可能となり、対価を得ることで欲しいものが買えるという自由を得ました。(中略)商品を買うことで享受できる世界の方が、そうでない世界よりもフェアだと思います。(中略)しかし、(オルダス・ハクスリーのディストピア小説)「すばらしい新世界」のように離床がさらに進んだスマート化された社会をまるごと受入れたくはありません。なぜかというと、人は合理的な部分だけで成り立っているわけではないからです。(中略)だからぼくはこの離床の流れに反して、個別性や身体性を取り戻す「土着」を目指しています。
(ぼくは障害福祉の仕事をしていますが)彼らが自分の「土着」を抑え込んで社会に適応する術を身に着けていくことよりも、せっかく持っている土着的な部分を大事にできるような、ゆるやかな社会を作って行くことの方が大切だと思っています。
健常者社会は、少しでも逸脱している人に「障害者」のラベルを貼りますが、土着の秩序にあまりに反した働き方をさせられた時に疾患が出てしまうのは健全なことですよね。
土着という考えは、オリジナルなものではなく人類学者のジェームズ・C・スコット「実践日々のアナキズムー世界に抗う土着の秩序の作り方」で、土着の秩序と公的秩序が対比されていることも紹介されている。土着な秩序は土地に自生し気候や風土に合った季節による柔らかな変化があるが、公的秩序は乗り物が時刻表から遅れないような規則性だという。土着の論理はまた内在的合理性、公的秩序は外在的合理性と言い換えることもできる。生物は外在的合理性ばかりが押し付けられると生きる力は弱くなってしまう。
これは都会にいるとよく感じることではないだろうか。僕は都会にいると自分が社会の歯車の1つになってしまったような感覚を強く持つ。一方で自然豊かな場所や田舎にいる時には自分の存在を強く感じることができるのだ。だから田舎暮しをするようになってからは、ときどき都会に出るのは楽しいのだが、ずっと都会にいるとエネルギーが消耗するような感覚があり、田舎に戻るとホッとするようになった。しかし、都会の近くで生まれ育ち、通学や通勤では満員電車という環境では、それを受け入れるのが当たり前でありおかしさに気がつけないのだ。まあ、僕の場合はそういう感覚が他の人より強いのだと思う。だから、都会で暮らしている時は週末になるとよく山に通っていたわけである。
もちろん、都会の生活が合っていて、田舎の生活など考えられないという人も少なくないと思う。田舎で1年間の住み込み農業研修をした時には田舎ならでの縛りというものがいろいろとあり、どこか共同体的な感じでどこに行ってもプライベートがないような感覚も知ることができた。また共働学舎に入ってからは長野や北海道のかなり雪深い地域に住んでるので、基本的に生産性のない除雪作業の大変さというのも知った。だから田舎から都会に出たい人が多いのだということにも大いに納得できる。
しかし、都会で生活するためにまずお金が必要であり、お金が無ければなにもできないような行き過ぎた消費社会というのはやはりおかしいのだと思う。(内在的論理が外在的論理に押しつぶされてしまう状況)資本主義は全てを商品化しようとするため、そこに生活する私たち自身も商品としてシステムの中に組み込まれてしまう。そして、一度組み込まれてしまえばそこから出ることは難しいほどに大きな力が働いている。(日本で高度な資本主義が当たり前になったのはそれほど昔のことでないけれど、1980年以降に都会で生まれ育った人はほぼ資本主義のシステムしか知らないのではないだろうか。つまり生まれた時から資本主義というシステムに組み込まれてしまっている)
資本主義自体が行き詰まってきているところから、ポスト資本主義ということがいわれるようになって久しい。齋藤幸平さんのように脱資本主義が必要という人もいれば、資本主義の制度を改善して使い延ばしていくという考え方もある。(資本主義はこれまでもさまざまな状況の中で変化しながらサバイバルしてきて、世界を覆い尽くすようになったのである意味で恐ろしいのだけど)青木さんたちの資本主義から距離をとるためのアイディアは2つの原理の間を行き来するということである。
「現代社会のさまざまなシステムを「当たり前」だと思っているぼくたちは、社会の外側を想像することができません、社会の内側で生きていくことしかないと思っているからこそ、その原理を回しているお金の力に抗うことができない。このような社会を「此岸」としたとき、ぼくたちはお金とはかかわりのない世界として「彼岸」を構想しました。彼岸を設定することによって社会の内部を相対化し、内と外を行ったり来たりすることができる。ここではないどこかへ「逃げ場」があると思うだけで、言動や思考の自由度は上がります。ぼくのいう「土着」とは、内部と外部、都市と農村、自分と他人といった二つの原理を対立させるのではなく、両者を行ったり来たりすることによって「なんとなく」のグレーゾーンを生み出していく行為なのです。」
青木さんは里で生きるのに必要なのは「お金を稼ぐ能力」であり、山で生きるのに必要なのは「お金がなくても生きていける力」ともいっている。北海道に来てからTVドラマの「北の国から」をレンタルビデオで見なおしたのだが、父親である黒板五郎(田中邦衛)の言葉を思い出した。北海道の片田舎に引っ越して電気もない、水も川からひいてくるような生活を始めた時に息子の純はいろいろなものをお金で買うべきだと不満をぶつける。五郎は「お金があったら苦労しませんよ。お金を使わずに何とかしてはじめて、男の仕事っていえるンじゃないですか」と返すのである。資本主義的な世界観からは、ありえない世界ではないだろうか。お金がなくても生きていける力というのはようするに使用価値オンリーの世界である。資本主義から脱した生き方ともいえる。しかし、経済が今のように発展する前までは、これが当たり前の感覚だったのだと思う。
思想家である内山節さんの「里という思想」から、次のような言葉も引用されている。「山上がり、昔は山にさえ上がれば一銭もなくたって1年や2年生きていけるという気楽さがあった。」昔は山林がアジールの1つであったわけだが、それが可能であったのは雨をしのぎ、火を焚き、食べることができる山菜や木の実を見分け、魚や獣を捕るという膨大な生活技術を身に着けていたからである。ずっと都会に暮らしてきた現代人には、お金を使わずに山で生き延びることはまず不可能だろう。自給自足的な生活を良しとする共働学舎でも根本にはそうした価値観につながる精神がある。一般社会からの資本主義的な考え方の圧力を受けて、だいぶやせ細ってしまってはいるけれども。
二つの原理が必要だというのも、伝統社会ではそれが当たり前だったのである。そして異人やアウトサイダーがその二つの世界を繋ぐ存在であった。今の時代には二つの原理を対立させるのではなく、有限の生態系の中で自由を手にするために、地に足をつけつつ各人が主体的にさまざまな二項対立を行き来するということを意識的にやらなければいけないのだと思う。簡単なことではないけれど、僕もまたそうすることで新しい展開や風景が見えてくるような気がしている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
