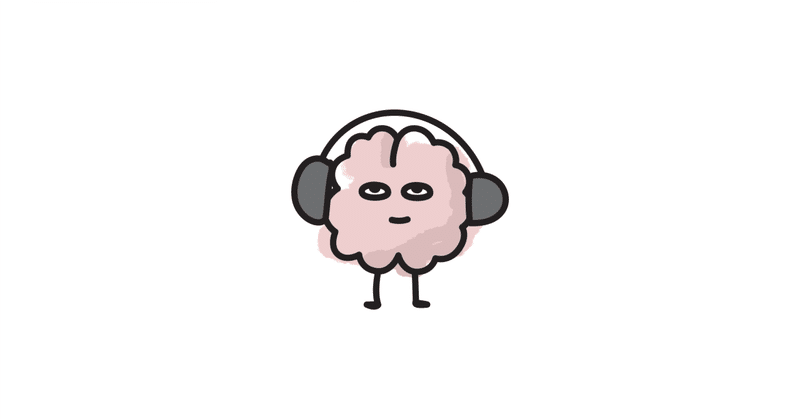
アメリカの特別支援学校の避難訓練、サイレンの音量は普通に大きい
明けましておめでとうございます、とお祝いしたいところですが、日本は大きな地震に見舞われて心が痛みます。皆さまの安全をお祈りします。
さて、アメリカでは一月二日から仕事も学校も始まるところが多いです。お正月ムードも何もなく淡々と新年が過ぎ、意外とあっさりしています。
地震に関連した記事を書こうかなと思ったのですが、私の住む地域では地震がありません。なので近いところで、「アメリカの特別支援学校、避難訓練はどんな感じ?」で書いてみます。ただしこれもあくまでも私の学校の場合でございます。災害は地域によってタイプもかなり変わるのでご了承を!
私の勤める特別支援学校はアメリカ北東の都市部にあり、12階建ての建物に入っています。地震やトルネードのような災害はほぼなく、ストームや洪水がありがちなシナリオです。あとは火災。
2022年に今の学校に転職する前、私は通常学級とインクルーシブ学級で10年近く働いていました。ですので学校の避難訓練はそれまで何度も経験していましたが、特別支援学校は初。
「大きな音に敏感な子供たちが多くいるし、特別支援学校内のサイレンはさすがにコントロールされた音量だよね」と当初は思っていましたが、見事にはずれました。
アメリカの避難のサイレン、馬鹿デカイです。
サイレンと共にパチっパチッとフラッシュも見えます。
これは避難したくなります。苦笑
サイレンが鳴ったら生徒を連れて階段で下がります。私の教室は8階です。経験前は「これは難しいだろうな」と思っていたのですが、意外や意外、ほぼほぼみんなスムーズに地上まで移動するんです。これは驚きました。
私の学校には校庭がないので外に出ると即ストリートです。車も通るので外に出ても安心できません。生徒が飛び出さないように常に気をつけます。
また裸足で外に出る生徒も多いので、そんな生徒には非常用の簡易スリッパを出入り口でもらい、履かせます。マラソン選手が使うあのギラギラブランケットも冬場には用意されています。
そんな感じで学校のあるブロックは生徒とスタッフで埋め尽くされるのですが、生徒の数を確認した後で訓練は終了し、みな教室へを戻ります。
もちろんパニックになる生徒もいるのですが、その辺はさすがのスタッフ、慣れています。小さいタイヤのついたオフィスチェアだとか、使えるツールを駆使して生徒を外に移動。あれをみた時は感激しました。プロです。
それにしてもどうやってあそこまでスムーズにこなせるのか。パッと思いつくそれらしき理由が2つあります。
一つ目は生徒とスタッフの比率。生徒2〜3人に対して先生が一人います。学校にはそれ以外にもセラピストなどのスタッフが大勢おり、避難訓練のサインが鳴り響くとどこからともなくスタッフが教室に入ってきて、ほぼ1:1の状態で避難できます。多くても2人。これは助かります。
二つ目は避難訓練の回数。めっちゃ避難の練習をします。少なくても月一回はしているんじゃないかな。だから比較的慣れてるというのはあるかも。
これは余談なんですが、去年の避難訓練の話を。
生徒を連れてストリートまで出て、校長からの「教室に戻っていいよ」のサインを待っていました。その時UPSの配達のおじさんが近寄りスタッフに「君たちの仕事には感謝をしているよ、本当にありがとう。僕にも子どもがいるからわかるんだ」と。多分発達障害児のお父さんだったんだと思います。ちなみに私も発達障害児の母なんですが、これにはグッと来ました。いい声かけだ。私も真似しようっと・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
