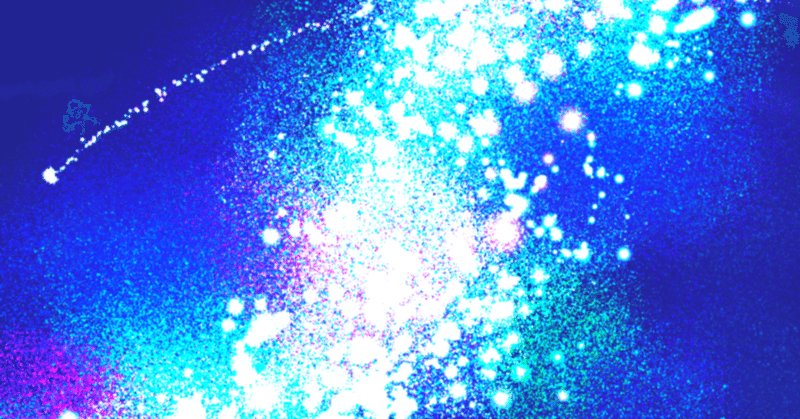
サドンデス 第一章第一話
第一話
「僕、今度、五十崎将衛を書いてみたいと思ってるんです」
縄暖簾でも掛かっていそうな、渋い店構えのカウンター席。
佐紀雄太は、隣の男性に持ちかけた。
「五十崎将衛ですか?」
案の定、早乙女は、渋面を浮かべて押し黙る。
ライトノベル作家の佐紀の、新しい担当編集者だ。メールや電話で、引き継ぎは済んでいる。
十代後半で単行本デビューした佐紀のキャリアは十年近い。
数冊連作しているヒット作もあり、新作も定期的に出している。
売れ行きはといえば、可もなく不可もなくといったところだ。
それでも昨日までは中高生だった彼等が次から次へと作家になり、先生と呼ばれるご時世で、本を出してもらえるだけでも、ありがたいと思っている。
「それは……、こう。なんて言うのか。ライト文芸的な感じに、ですか?」
早乙女は口元に手をやり、言葉を選び、こちらに探りを入れている。
顔つきといい語調といい、それは困ると語っていた。
通常よほどの大御所でもない限り、作家と編集者はメールか電話でしか話をしない。プロットの打ち合わせもそうだった。
初稿を上げてからの改稿の相談も。
佐紀は言外に面倒くさいと嫌がる早乙女に懇願し、今日という日を設けてもらった。
初顔合わせの印象は、思っていたより優しげで中性的だ。
年齢は三十三歳。七歳年上という事か。
夜の十九時三十分。
待ち合わせた場所で名刺を交わし、手土産を交わし合う。初対面の儀礼も終えている。
早乙女は陰鬱に黙り込み、手酌で冷酒を御猪口に注いだ。
「あっ、すみません。気が利かなくて」
「いえ、いいんです。先生はお酒、お強いですか?」
「そうですね。強いです」
「わりと、はっきり言うんですね」
黒縁の細い眼鏡の向こうで早乙女が、ようやく目元を和らげた。
早乙女はといえば、あまり強くはなさそうだ。御猪口を二杯空けただけで、耳が赤くなっている。
徳利を持った早乙女に促され、佐紀は空になった御猪口を差し出した。
初夏らしいストレッチ素材の白いジャケット。黒いストライプのシャツ。黒のボタン。ストレートのブラックジーンズ。ブラックのスニーカー。
中肉中背の体型と、さらさらした黒髪によくマッチしていて似合っている。
すっきりとした顔立ちで、カジュアルな服装だからなのか、二十代に見えなくもない。
眼鏡と時計をコレクションしていそうなタイプだと、想像する。
「先生の場合、主に十代が読者層ですからね。漢字だらけの歴史ものというと、転生や召喚ファンタジーで書いても、なかなかですね。食いつきが……」
カウンターに頬杖をつき、空の御猪口を手慰みにいじりながら、ひとりごとめいた口調で説得にかかっている。
佐紀は今、なるほどなぁと気がついた。
店選びは彼に任せていたのだが、男が横並びに並んでも、酔っぱらっても気にせずいられる店だった。
佐紀も早乙女と毎回会おうなどとは、思っていない。
前の担当者とは長いつきあいだったのだが、一度も会った事はない。
ただ、早乙女の次回作についての尖ったメールの文面や、ビジネスライク全開の電話対応。毎回毎回気に食わない。
どんな奴だと顔が知りたくなったのだ。
「五十崎将衛は、もう書き尽くされた感もありますし。先生のファン層は十代前半の女の子達ですからね。……なかなか、ちょっと」
じりじりと、ボツ方向に追い込みをかける早乙女が薄く笑う。
「……っていうか、ラノベは卒業して、純文学に転向とかですか?」
早乙女はメールでも電話でも高圧的。上からものを言われている。
そんな気分にさせるダメ出しと、電話の声音。どんな奴かと思ったら、こんな奴。
だが、既に初稿は書き上げた。
早乙女の承諾が得られれば、すぐにでも打ち合わせができるように準備した。なぜだか無性に気が急いた。冒頭の一文は、『将衛様はキツネ憑き』。
将衛様はキツネ憑き。
お気の毒にも御人変わりなされたと、居城の大塚城では誠しかやに囁かれている。
重臣のみならず城に出入りする業者にまで、噂はさざ波のように広がった。
将衛は晋国藩主を父に持ち、正妻腹の第一子として生まれた男児だ。
跡継ぎに向けられた父の期待は尋常ではなく、幼少期から帝王教育がなされていた。
養育したのは兵学は基より、和歌や茶道に通じた粋人、平井雅也。
五十崎一族は美貌で知られた家系だが、瓜実顔の将衛も、ほっそりとして秀麗な面立ちだ。
深く切れ込んだ眦と、少年らしい一文字の眉。
教養と礼節に裏づけられた輝きを放つ漆黒の瞳。鼻筋の通った高い鼻梁。
紅をさしているような、薄く紅い唇が織りなす容姿は、どんな美女より美しいと称賛され、男女を問わず魅了した。
今はそれが、かつての話になりつつある。
杉の大木が天を覆い、幹の根元に熊笹が生い茂る山奥へ、華奢な体つきの少年は、林道を逸れて分け入った。
両袖を取り外した単衣の着物に半袴。
剥き出しの手足には、鋭い笹の切り傷が増えていく。
ざんばらの前髪の隙間からのぞく双眸は、恐いような切れ長だ。
閃かせている眼光は、餓え乾いた獣のように昏かった。
総髪の後頭部を、黄色の派手な組み紐で高々と括り立てている。
左肩に小弓を乗せ、足元の熊笹を右手の鎌でを払いつつ、彼は山の中をさまよった。
すると、その時。
左手にある林道に、一頭の鹿が跳ね出てきた。
鹿を見るなり、膝下まで覆う熊笹を刈っていた鎌を投げ捨てる。
鹿を狙って向きを変え、斜めに背負った矢筒から素早く抜いて番えると、胸を開いて竹弓の弦を大きく引き切った。
解き放たれて唸りを上げ、幹の間を飛び去る矢羽根のその行方。
少年は、それを身じろぎもせずに凝視した。
山の麓の畑に来た百姓の女房が、腰が抜けたように座り込む。古びた単衣に前垂れをつけ、網代笠を被っている。
「母ちゃん、どうした?」
「……また、やられた」
ナカは日焼けして真っ黒になった顔を手で覆い、声を詰まらせ息子に答える。獣に踏み荒らされた畑の畝、食い散らされた作物の苗が、無残な姿をさらしていた。
「しょうがねえだろ。泣いたって」
十三になった息子の明宏は、大人びた口調で言い捨てた。
明宏は小さな顔には釣り合わないほど目が大きい。
鼻梁は高くもなく低くもなく、先端がややツンと上を向いている。唇は上下ともに厚ぼったくて艶やかだ。
ぎょろりとした目と、血色のいい赤ら顔が猿のようだと揶揄されるのだが、明宏は文字通り顔を猿のように赤くした。
「こんなことで泣いてたら、この土地で百姓なんかやれねえよ。諦めろって言ってるだろ」
ぐずぐずと泣き崩れている母の姿に、無力な自分が重なった。
明宏はそんな母を見ているだけで気が滅入り、畑の方に目をやった。畝に残された足跡は、鹿か猪のものだろう。
苗を植え、程よく育った頃合いを見計らっているように、奴等は我が物顔で食い荒らしていく。
毎年だ。
そのくり返しだとわかっているのに、自分達の田畑がこの山麓にある限り、受け入れるより他にない。春夏秋冬、同じ事で同じように憤り、なす術もなく泣きをみる。
十三歳になったこれまでも、それを。
そして、これからも死ぬまでそれを続けるしかない己の因果。
抗いようがないのだと、自分自身に言い聞かせ、明弘は枝の折れた大豆の苗を次々引き抜き、投げ捨てた。
国の中央部の集落は藩の直臣ではなく、小高い山の北麓に屋敷を構えた豪族が統括している。
国主が何代変わろうと、土着の豪族は、代々手持ちの集落を受け継いだ。中には高い塀や火の見櫓、広い濠で、護りを固めているほどに、財を成した豪族もいる。
そんな屋敷を取り囲む水濠にかかる石橋を、一人の百姓が駆け渡る。
長槍で門を警護する門番は、槍を十字に掛け合って、取り乱す百姓を押し留めた。
「 深作様……、深作の旦那様に、至急お取り次ぎ下さいませ」
百姓からの、息も絶え絶えの主訴を耳にするなり、二人の門番も顔色を豹変させた。
裏門の脇戸を開けて中に入り、百姓共々母屋を目指して疾走する。門番は母屋の縁側をひた走り、主の側近に報告した。
「何事だ」
書卓に向かって居住まいを正し、写経をしていた深作は、居室に飛び込んできた側近を睨みつけ、静かに筆を硯に置いた。
しかし、耳打ちされた深作は、瞠目をして息を呑む。
「……誠か? それは」
「はい。たった今、小百姓が訴えに……」
門番は肩で激しく息をした。深作は、眉根を僅かにひそめたきりで、決然として立ち上がる。
「誰か居るか!」
老いた農夫の見間違いではないのなら、集落を預かる身として由々しき事態だ。声を張り上げ、側近達を呼びつける。
と同時に、床の間の具足びつを下男に命じて開けさせた。
深作は着物を脱ぎ捨て、筒状の袖の下着に着替えたのち、戦に赴く作法に従い、左足から袴を履いた。
脛当てと籠手も下男につけさせ、刀と脇差を腰に帯びる。
同じように武装を済ませ、弓と槍をたずさえた 剛の者に、前後左右を囲めさせ、険しい顔で板葺きの正門を後にした。
糸杉の大木が両脇にそそり立つ林道で、鹿が横倒れに倒れている。
両袖を外した単衣の着物に、膝丈までの半袴姿の少年は、鹿の首を貫いた矢を引き抜いた。
その矢を背負った矢筒に入れ、仕留めた鹿を放置したまま、踵を返した時だった。
「捨てるの? それ」
背後から、凛とした男児の声に問われて思わず振り返る。
見知らぬ子供が熊笹を掻き分けながら林道まで出て、置き去りにした屍と、撃ち取った少年の顔を交互に見た。
「いらないのなら、もらうけど」
「……やってもいいが、穢れだぞ?」
少年は、穢れの語気だけ強くした。
痩せた男児は七、八歳といったところか。
着古した単衣姿で、埃まみれの乱れ髪を、麻縄で無造作に束ねている。
男児は見ず知らずの相手にも、声をかける度量がある。
また、男児の側には、放ち髪の童もいた。
こちらの童は、四つか五つ。
肩の長さの放ち髪は、灰でも被ったかのように、汚れて白くなっている。
丸々と肥えた鹿の前にしゃがみ込み、童は無邪気に突ついていた。
男児と童は吊り上った目尻といい、品よく通った鼻筋や、鷹のくちばしにも似た上唇など、よく似通った面立ちだ。おそらく兄弟に違いない。
ただ、年少の童子の右目が、腐った魚の目のように銀色に鈍く濁っていた。
生まれつきなのか、怪我か病で潰れたか。
ただ、その童の左目の澄んだ瞳の輝きと、右目の曇った瞳の対比が不思議と脳裏に焼きついた。少年は、あらためて周囲を見渡した。
けれども森閑とした林道には、親らしき者の姿はない。
何はともあれ、この山で狩った鹿を欲しているのだ。自国の者とは思えない。おそらく親を亡くした他国の子供が、二人で流れて来たのだろう。
「売るなり食うなり、好きにしろ」
少年は、兄らしき男児に言い捨てた。
北麓に居を構える山を含め、一帯の集落を治める深作平兵衛は、報せに来た百姓に先導させつつ、山の林道を上り出す。
深作の周りは、弓と槍も装備した側近達が固めている。
全員顔を強ばらせて、件の輩の正体と目的を探るべく、慎重に歩を進めていた。
すると、深作の脇から小柄な男が前に出て、道の真ん中で屈み込む。
「どうした? 市松」
「ご覧下さい。やはり血です。人のものか獣のものかは、わかりませんが」
市松が指した場所には、真新しい血溜まりの跡がある。
しかし、肝心の死骸が見当たらない。
これでは獣が他の獣に食われただけかもしれないと、深作は無言で眉をしかめたが、憶測だけでは決めかねる。
「……で、ですが、わしは、この目でちゃんと見たんです。この一帯では禁忌のはずが、狩りをしている小僧がいて……」
たばかったのではないのだと、案内役の百姓が必死の形相で言い募り、釈明しようとした時だ。血溜りを囲む深作達の頭上をかすめ、一本の矢が唸るように、空を飛んで横切った。
「な……っ!」
一同は顔をめぐらせ、矢の方向を見送った。
直後に、大木の枝葉が重なりから甲高い鳥の奇声が上がり、彼らの足元に落ちてきた。
「……ひえっ!」
市松が、声を発して飛び退いた。
林道に落下したのは、胴を矢で射抜かれたキジだった。
そのキジの死骸をおずおずと深作達が取り囲み、畏れ慄き絶句した。
これで、ようやく見間違いではなかったことが明かされた。
百姓が見た少年は、確かに山の中にいる。
単独なのか、集団なのかは分からない。
だが、その穢れには深作でさえ躊躇して、どうすることもできずにいた。
さらに林道脇から下草を、掻き分けるような葉音が徐々に大きく近づいて、深作達は身構える。
サドンデス -Sudden Death- | 記事編集 | note
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
