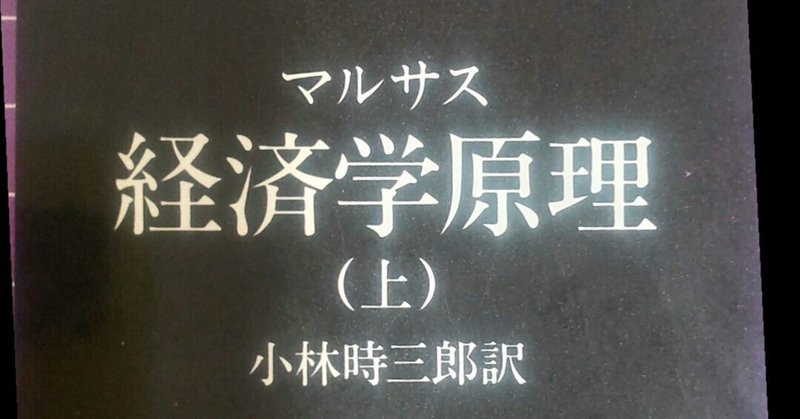
労働価値説と交換価値の一尺度①〜経済学原理第二章第四節〜
商品の価値は人間の労働によって決めれるという労働価値説は、初めて体系化されたのは15世紀で、ウィリアム・ペティ(1623年5月26日〜1687年12月16日、イギリスの医師、測量家、経済学者)の租税貢納論に記されている。アダム・スミスはその後輩といえるのだが、マルサスはスミスの研究に対する批判も加えて、商品の価値を測るその尺度について論じている。スミスは商品の価値は人間の労働量によって決められ、交換においては支配する労働量(購入できる労働量)に決まると論じた。しかし、この2つは本質的には別物であるとマルサスは考え、前者よりも後者の方が、正確で実用的な価値の尺度と主張した。しかしここでは一見すると、奇妙な理論をマルサスが展開していく。彼は、「ある一つの商品に多くの労働量が投じられた場合は、それに交換される別の商品も多くの労働量が投じられるのだから、ある一つの商品の交換価値は、それに投じられた労働量に比例しない」と述べている。正直いってこれをはじめて読んだときは困惑した。普通に考えれば、労働量が多ければ多いほど価値が上がったと考えるのが妥当だし、リカードもそのように反論している。
マルサスはおそらく、市場での商品取引が同等の労働量が交換されるだけなら、いくら労働量が追加されても、商品の価値が変動したとはいえないと考えたのであろう。それと、実際に行われる商品の交換は、労働量が同等でない事例が頻繁であるとも考えたようにも見える。その次のページでマルサスは、産業らしい産業が、まだ存在していない古い時代(おそらく旧石器時代の初期)の商品交換のことを例に挙げている。そのころの人類における各商品の交換は、投じられた労働量とはほとんど無関係であり、さらにその段階は極めて短期間だったとマルサスは述べている。つまり、資本(道具などの生産の元手)がある程度集まった経済活動がない状態だと、生産された商品の労働量と交換価値が不均衡が著しいもので、その時代(道具がない時代)は短く終わったとマルサスは考えた。ちなみにこれは私の見解だが、人類の知能の発達に伴って、「この品を得るためにこれほどの労力がかかったのだから、それに見合ったものと交換して欲しい」という思考が、強まっていったのではないかと思う。もっとも、マルサスが述べた「その古い時代における商品交換は、投じられた労働量とはほとんど無関係」というのはあくまでも、現在(マルサスが生きていた時代)と比較してのことである。マルサスは自分が生きている時代においても、商品の労働量と交換価値の不均衡はそれなりに存在すると主張している。だが、道具の生産がある程度発展してきた頃には、商品作りの労力を、上記のように鑑みる思考がかなり高まったと私は考える。
もう一つの大事な点は、作った商品によって収益が得られる速さにはそれぞれの差があることだ。遅くなるほど交換価値が高まる傾向があったとされている。マルサスは古代人における丸太舟作りと鹿狩りの比較を例に挙げて、そのことについて説明している。当時の人間が作る丸太舟の値段は、同じ日数をかけて仕留めた鹿の倍の交換価値になるとマルサスはいう。鹿の場合は、狩りをするために働いた数日以内にその分の利益が得られるが、丸太舟の場合は1年以上はかかる。これは丸太舟作りが鹿狩りに比べて、労働量が遥かに多いというワケではないらしい。問題は、古代人が丸太舟を作るのにどれくらいの時間がかかるのかだ。縄文時代を研究している大工の雨宮国広氏の丸太舟作りから、大まかな予測をしてみると恐らくは、一人で作るのなら20日間はかかる。4人で作ったのであれば5日になる。4人で鹿を一頭仕留めるのに同じくらいの日数がかかり、それにも関わらず丸太舟は鹿の二頭分の交換価値になる。
だがどうして労働量が同じなのに、後者に比べて前者は利益の回収がそこまで遅くなるだろうか?それは当時の古代人たちが、狩猟採集を中心とした生活をしており、農耕がまだ未発達で、丸太舟作り自体も珍しい仕事だったからだと思われる。さらに、鹿のような大型の動物を狩る数日間において、片手間に食用となる動植物を採集することはできても、丸太舟作りの場合は難しかった可能性が高い。従って後者の方が、1日に行える作業量自体は遥かに少ないだろう(もちろん両者ともに、売れる商品が出来上がるための労働量自体は最終的には同じになる)。ということは、丸太舟が市場に出回るのが遅くなり、その数量が比較的に少ないことを意味する。これが、労働量が実質的に同じであっても、丸太舟の方が値段が高くなる理由であろう。

