
そしてヨザルは恋を知った
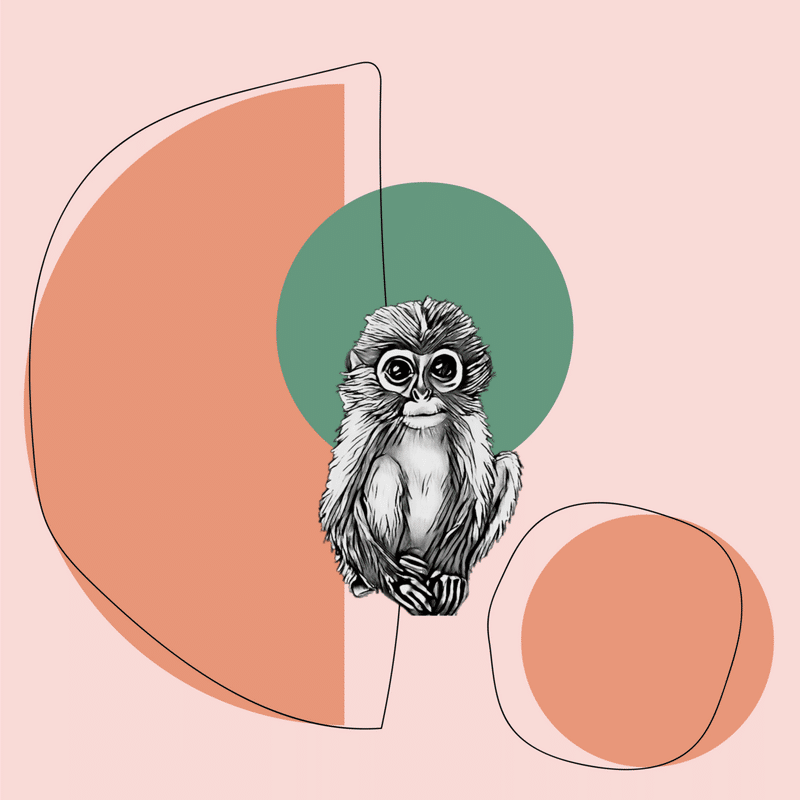
僕とヨザルの出会いは平凡なものだった。
その頃の僕はなぜか自分を追い込みたくて、過度なダイエットの為に毎日キャベツだけを食べていて塞ぎ込んでもいた。ようは蒼くさかった。
時間はたっぷりあったので、先天的な孤独というものについて煎じ詰めて考えていたりした。
何かひとつ答えを見つけるごとに世界が狭まっていくことに気づけるくらいに自分が蒼くさいということに気がついた時には、
僕の部屋はキャベツの芯ほどの固い孤独に覆われていた。
一方、ヨザルはその頃、場末のペットショップの片隅で怯え続けていた。
店員さんに怯え、気まぐれな来店客に怯え、そして何より醤油くさいこの国の風土に怯えていた。
──風のない9月のある夜
そのペットショップで僕らは出会った。
繁華な街のきらめきを逃れて入ったのがそこだった。
物情騒然たる毎日において、僕はやはりひとりだった。深い意味で。
元オマキザル科、現ヨザル科。
そんなヨザルを僕はその時初めて知った。
実は僕とこのオスのヨザルには共通点があった。
それは互いに円形脱毛症ができているという点だった。
ヨザルは背中に1つ、僕は頭に2つだ。
しばらく展示ケージの中の彼を見ていたけど一度も目が合わなかった。
『心のケア』なんて弾みで言い出す大人が僕はずっと怖かった。
このヨザルの何かが、人ごとに思えなかった。
だからなのか、生後半年のオスのヨザルを飼うことに決めた。とても高額だった。
その日のうちにヨザルを連れて帰った。勝手な使命感があった。
道中ずっとヨザルはケージの中から食い入るように夜を見ていた。
その日から僕とヨザルの暮らしが始まった。
◆ ◆ ◆ ◆
ヨザルはもともと樹木の上で生活しているせいか、部屋の中でも高いところを好んだ。
本棚の上や冷蔵庫の上、カーテンにしがみついていることもよくあった。
僕とヨザルは互いに尊重し合い、適度な距離を保ったまま生活した。
だいたい毎日僕らはキャベツを食べ続け、ロックンロールを聴いた。
ヨザルはロックンロールを聴くと、体を揺らしてリズムに乗った。僕はそんなヨザルを見るのが好きだった。
踊っているヨザルを見ているとやなことは全部忘れた。
◆ ◆ ◆ ◆
──半年が経ち、春がきた。
不思議とヨザルは春に無関心なように見えた。
この頃になるとヨザルは高いところではなくて、床に近いところで大きな目を無機的なまでに凝固させて、物思いに耽っているようなことがしばしばあった。
また、ときどきは、窓の開いた隙間から外へ出てしまい数時間後に魂を抜かれてしまったかのような状態で帰ってきたときは、何も口にせずに細長い自分の指先を見つめているようなことも……。
僕は心配になった。
そして僕は、このての心配に不慣れだった。
ヨザルはこの家を出たがっているのではないだろうか……。
自然と僕はそう考えるようになった。
僕の目にはヨザルは、デンキショックのような刺激的な生活を求めているように映った。
──そんなある夜、その日はやってきた。
ついにというべきか、とうとうというべきか、ヨザルは家を出たまま帰ってこなくなった。
町中がジューサーの中に落とし込まれたかのような嵐の夜だった。
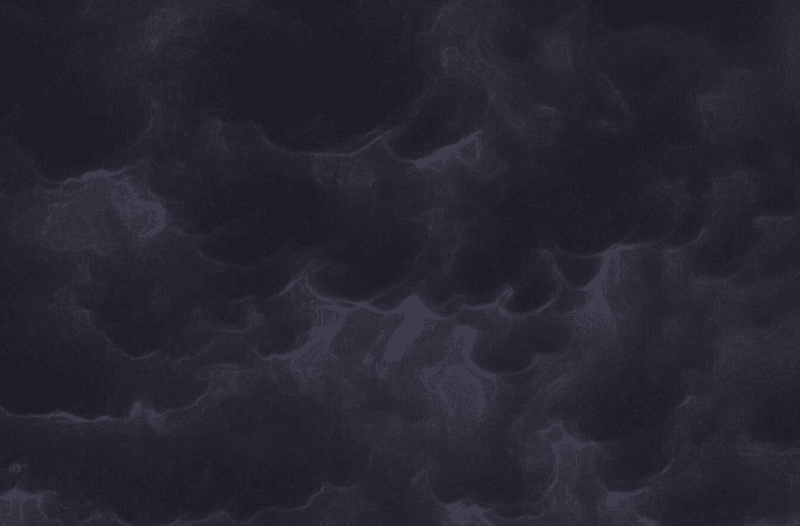
◆ ◆ ◆ ◆
僕はまたひとりになった。
ヨザルがいなくなった部屋の中は、どこを見まわしてもヨザル一匹分切り取られて見えた。
毎日ため息をつくようになった。ため息をつかなかった日を数えたことはなかった。
いったい、ひとりになってしまう人間と決してひとりになることのない人間の発するものの波長にどれほどの差があるんだろうか……。
──とにかくヨザルはもういない。
僕はビールを飲み、そしてキャベツをかじりながらロックンロールを聴いた。
毛穴という毛穴にずしずしと土足で入り込んでくるようなロックンロールをだ。
例えば子供の頃にできていたらよかったなと思うことは寂しさを紛らわすことだと今思う。
引き換えにする何かがあってはじめて引き換えにできる。それはあとから思う。
もしも今ここでヨザルがひょっこり顔を出してくれたら、僕はもう何もいらない。でも、そんなことは起こらないということはロックンロールがいちばんよく教えてくれる。
それでも、念のため僕は、ヨザルがいつどんな状態で戻ってきてもいいように、木の実に、昆虫に、風邪薬、胃腸薬、消毒薬、シャンプーにリンスも用意しておいた。……念の ために。
さらに3日が過ぎ、1週間が過ぎたが、ヨザルが戻ってくることはなかった。
いったいどこで何をしているのか、その行方は杳として知れなかった。
無事でいてくれればいいけど……。
僕はヨザルが車に轢かれてしまった光景やカラスにさらわれてしまう光景を想像して首を振った。
この世は危険に満ちているのだ。
さらに10日が過ぎ、1ヶ月が過ぎた。
僕はようやくひとりきりの空間をうまく体に馴染ませられるようになっていた。
会社は辞めた。もともと好きな仕事じゃなかった。
とくに慰留されなかった。
守秘義務に関する誓約書を書かされているときもずっとヨザルのことを考えていた。
あきらめかけていたそんなある朝、思いもかけないことが起こった。
なんと、ヨザルが帰ってきたのだ。
まだ日も昇りきらない明け方、眠っている僕の鼻の頭をヨザルは手で弱々しくつかんで、覗き込むようにこちらを見ていた。
「また、この家に厄介になるけど、いいかい?」
ヨザルは静かな声でそう言った。
その声はどこか気の抜けたサイダーのようだ。
僕は起き上がって、「もちろんだよ」と頷いた。
久しぶりに見るヨザルの体は一まわりも二まわりも大きくなったように見えた。
◆ ◆ ◆ ◆
僕とヨザルはリビングにあるテーブルに向かい合わせになった。
僕は椅子に深く腰掛け、ヨザルはテーブルの上に腰をおろした。
少し疲れの見えるヨザルを窓から差し込む朝陽がいたわるように優しく包んだ。
僕は冷蔵庫からリンゴジュースを取り出し、コップになみなみ注いでヨザルの前に出した。
ヨザルがストローをくれと言ったので、カクテル用のステアリングストローを1本差してあげた。
「そういえば のど 渇いてたんだ……、ずっと……」ヨザルはつぶやくようにそう言うと、手足でコップを抱えるようにして、ストローで器用にリンゴジュースを飲みはじめた。
「上手だね。どこで覚えたんだい?そんな飲み方を」僕がからかい半分で尋ねるとヨザルは寄っていた目を僕のほうに向けた。
「デートでさ」
──デートでさ
それは通り雨くらいさりげない言い方だった。
僕は軽く頷きを返してから、一度席を立ちアイスカフェオレをつくって戻り、飲んだ。
しばらくの間、沈黙が僕らを包み込んだ。交互にストローで音を少し立てた。
居心地のいい沈黙だった。
朝陽が沈黙を運んできたのか、沈黙が朝陽を呼んだのか、そもそも沈黙それ自体が朝なのか……。
とにかくヨザルは帰ってきたのだ。
まるでハビタブルゾーンそのもののような沈黙のなかで僕は改めて安心していた。
でもそれは、まだ僕がヨザルときちんと向き合う前だから得られたものだということを、このあと知ることになった。
「おいらがいったいどこでなにをしていたのかを話すべきだろうね」
ヨザルは空っぽになったコップの中でストローを遊ばせながらそう言った。
「話してくれるのなら、もちろん僕は知りたいけど……。でも、キミが帰ってきてくれただけで僕はものすごくうれしかったんだ」と、僕が素直な気持ちを伝えると、ヨザルは難しい顔になった。ヨザルにしてはかなり難しい顔だと思う。
◆ ◆ ◆ ◆
「おいらはこの家に帰ってきた。だからあんたには知る権利がある。ちがうかい?もしも、おいらが帰ってこなかったとしたら、あんたは知るすべもないという特権を得ていたんだ。ちがうかい?『知らない』ってことは最強の鎧なんだ、自分のど真ん中を守るためのね。そうは思わないかい?」
「権利だなんてそんな大袈裟に言わなくてもいいんじゃないかな。たしかに知らないほうがいいことってあるとは思うけど……」
僕は困惑した。たぶん声にもあらわれていたに違いない。ヨザルは間違いなく背負いきれないほどの感傷を持ち込んでいた。明らかに過積載だ。
「大丈夫、おいら、頭をなんか打っちゃいないよ
。心は……、そう、心は多少うたれたかもしれないけどね」
ヨザルは何かを探し求めるかのように胸のあたりを掻きむしった。
◆ ◆ ◆ ◆
「あの嵐の夜、おいらはある娘に出会ったんだ……」と、ヨザルは語り部のように話し始めた。
「出会った瞬間にこの娘しかいないって直感的に思うことは人間にもあることなのかい?世界中のあらゆる賛美歌に乗って、おいらの想いは駆け巡ったのさ。おいらは運命に感謝した。それまで運命なんてダイレクトメール広告くらいの軽薄なささやきにすぎなかったのさ。なあ……、あんた知ってるかい?パンダは百年に一度大量死するんだ。それは、竹の花が百年に一度花を咲かせちまうからなんだ。笹がなくなっちまうのさ。そんなパンダが例えば、運命になんか感謝すると思うかい?」
ヨザルは息継ぎの仕方を忘れてしまったかのように連綿と話した。
「ようするに、キミは恋をしたんだね」と僕は言った。
「そうなんだ、おいらは恋をしたんだ」
ヨザルはそこでやっと大きく息をした。
そのあとで、特に意味もなくヨザルと僕はニ、三度頷き合った。
「あんたに質問があるんだが……」と言ってヨザルはお尻としっぽを浮かせてからまた落ち着かせた。
「ブシツケな質問だが、あんたは恋をしたことがあるかい?」
「うう……ん、あるといえばあるし、ないといえばないよ」僕はヨザルの考える恋の重さをはかりかねた。
「ふうん、そうかい、あんたらしい答えさ。でもいいかい、あんたにだけは勘違いされたくないんだが、おいらの言う『恋』ってのはけっして動物的なものなんかじゃない。もちろん人間的なものでもない。もっともっと壮麗さや静謐さを兼ね備えた美しいものなんだ。わかるかい?」
「つまり、プラトニックなものなんだね」
「いいや、違う、ちがうんだ!」ヨザルは少し興奮気味にテーブルの上を手で叩いた。
「あんた、恋ってのはそもそも溺れるものかい?落ちるものかい?それとも彩られるものかい?」
「さあ……、あらためて考えてみたことはないけど……、どれも当てはまるんじゃないかな」
僕のいまいち煮えきらないその答えにヨザルは「ノン、ノン」と言って指を立てて振った。
これもデートで覚えた仕草なんだろうか……。
◆ ◆ ◆ ◆
「なんにもわかっちゃいない」
ヨザルは失望の絞り汁のような口角泡を飛ばした。
「恋はあんたの、そして人間の道具じゃない。おいらもあんたもそれ以外もみんな恋に選ばれてるのさ。恋がじっくり吟味してこいつに今日から恋をくれてやると決めたとき、はじめてそいつは恋を授かるんだ。そこを勘違いしてはいけないし、思い上がってもいけない」
ヨザルは毛で覆われた体を少し丸め、腕を組んだ。
「そういう考え方ってもちろんあっていいと思うよ」
僕は肯定も否定もしなかった。
この世の中において思想は常に自由であるべきなのだ。
それがたとえ、一匹のヨザルの感傷味溢れる恋愛論だとしても……。
「世の中は恋で溢れかえってるじゃないかってあんたは言いたいんだろ?町中どこを見たって三度のメシよりも恋が好きそうなやつらがうろうろしてるじゃないかって、そしてそいつらがなんなく恋を拾い集めてるじゃないかって、そう言いたいんだろ?」
ヨザルは自分の顔を手で荒々しく何度か拭いながらそう言った。
「たしかにそういう風に見える時もあるかもしれない」と僕は答えた。
──たしかにそういう風に見えているかもしれない。
僕は空っぽになっていたヨザルのコップにリンゴジュースを注いだ。

◆ ◆ ◆ ◆
僕が注いだリンゴジュースをヨザルは一口だけ飲むと横へとずらして体をその前に出した。
「あんたはキャベツだけ食ってダイエットしていたから分かると思うが、空腹感なんてものは信用ならない。空腹感は本当にこれ以上食べないと餓死してしまうポイントの何歩も手前の段階で脳が警告として発する信号に過ぎない。つまり、実際はそれほどの空腹ではないわけだ。脳ってやつは、当たり前かもしれないがおそろしく保守的で、甘い。恋についてもそうなんだ。本当の恋の何メートルも手前でみんな脳の甘い誘惑に負けるわけだ」
ヨザルの声はときどき裏返った。それは切実さの裏返しのように聞こえた。
そろそろ核心に触れる必要がありそうだった。
「キミは本当の恋を知ったんだね」
「ああ、そうさ、おいらは本当の恋を知っちまったのさ……」
ヨザルは頷きながらそう言ったあと、大きなため息をひとつそこに加えた。
ヨザルは本当の恋を失ったのだと僕はそこで確信した。
「月並みかもしれないけど……、これ一度きりとは限らないじゃないか」
僕はできるだけ控えめな声でそう言った。ただ、余計なことだったかなとも思った。
「なあ、あんた、本当の恋が二度もあったらそれは本当の恋だと言えるかい?言えるわきゃあない。だってホンモノの恋は替えはきかないんだ、1点ものなんだよ」
ヨザルは大袈裟に首を振ってみせた。
その表情は、まるでおもちゃ箱の一番奥から這い出してきたかのようにくたびれて見える。
僕は丁寧に何度も頷いたあと、ヨザルのかわりにリンゴジュースを一口飲んだ。
「ペンペン草一本残らない……。すべては終わったんだ。残ったのは虚無感だけだったよ。なあ、あんた、恋なんて覚悟なしにするもんじゃあないね」
「でも、たとえ一時にせよキミは夢中になれたんだろ?」と僕。
「ああ」
………………ああ
ヨザルは背中を丸めたまま視線を落とした。
「別に刹那的な生き方を擁護するわけではないけど、物事なんて区切り方ひとつで変わるんじゃないかな。例えば、恋の前、恋の最中、恋の後を別々に考えて……」
僕は言いながら、慰めようとできているのか自信がなかった。ヨザルの尊厳を傷つけてやしないかとさえ思った……。
するとヨザルが視線を上げて、「なあ、あんた」と、僕の話を遮った。
「わかったようなこと言わないでくれ」とつづくのかと思ったけどそうではなかった。
──「なあ、あんた、この話はもうやめにしないかい?」
ヨザルは朝に小さなピリオドをうった。
「わかったよ、この話はもう終わりにしよう」
そう
ヨザルは
この家に帰ってきてくれたのだ。
「ロックンロールでも聴くかい?」僕はそう言って指を鳴らした。
「ああ、ロックンロールを聴こう」
ロックンロールには答えがあったし、ロックンロールにないものは結局は答えではないのだから……。
僕らは、できるだけ澄み切ったこの朝にそぐわないものを選んだ聴いた。
それは、朝に対する僕らなりのささやかな抵抗だった。

終
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

