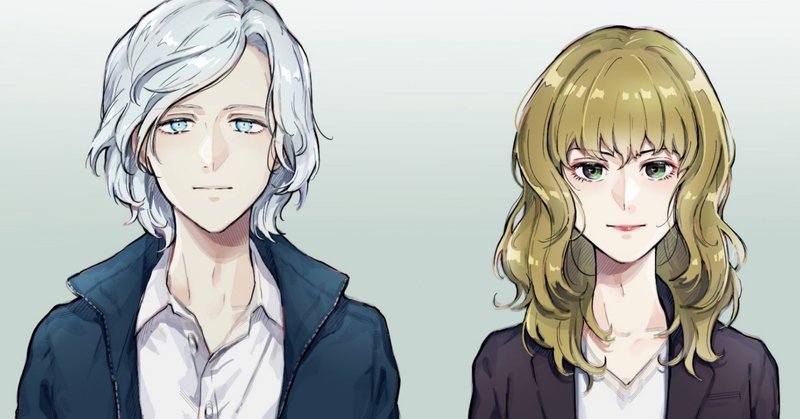
ふたのなりひら
1-3
家に帰る道すがら、森に恵のことを尋ねると、森は照れたように何も言わない。さては、彼(彼女)に初めての恋心でも芽生えたのだろうかと、相馬におかしかったが、しかし、森は男でもあり、女でもある。この場合、森が恋心を頂いた場合、それは正しいのか、正しくないのか。しかし、同性婚が全体の三割を超える現在、些細なことだと感じられる。昨今は、AIとの結婚、異種婚礼も増加しているが、周囲の理解が得られれば、それほど問題にはならない。しかし、フタナリヒラという存在が世に出ることによって、新たな問題が浮上してきている。恋愛の相関も、網目状に増え続けている。相馬は、自分がその渦中に入り込むなど、もちろん想像すらしていなかったわけではあるが……。
自分の城に戻ると、途端に現実が押し寄せてくる。荒ら屋のようで、気が滅入った。先程までいた山の手とは違う、汚れた下町である。そうして見ると、鳩の穿った糞までも視界に明るくなる。
締めていた扉を開き、店を開ける。森を二階へと連れて行くと、階段の途中、ついぞ最近は嗅いだことのない甘い匂いが鼻を掠めた。
「どうしたの?」
「何か甘ったるいな。」
「先生だよ。」
「先生か。先生を連れてきたんだな。」
先生、という言葉に、低めの声が聞こえてくるようだった。そうして、この日のために彼(彼女)に着せたブレザーにシャツ、半ズボンを脱がすと、彼(彼女)は動きやすいように、いつも着ている濃紺のチェックシャツに、柴犬の刺繍が施された長ズボンに履き替えた。
「明日から、いつもあの先生のところだ。」
「お勉強?」
相馬は頷いた。森は、声はまだ軽く柔らかいが、しかし、恵のように、フタナリヒラの声というものは、低く、男女の交じりを含んだものに変わるのだろうか。そうして、森の背後に、自分がこれまでの間に蒐め続けてきた、さまざまな標本が目に映る。とりどりの蝶々がいた。その中に、あの白昼夢で見かけた、ウスキシロチョウがいた。異常種である。その、異常のモザイク斑を見つめながら、相馬はゆっくりと、森を抱き寄せた。抱きしめていると、相馬は安心した。
「痛いよ。」
「ああ、悪かった。」
慌てて森から身体を離して、相馬は立ち上がると、
「お部屋で遊んでなさい。」
相馬の言葉に、森は頷いた。そうしてそのまま、部屋に置かれた本を手にとって、ぱらぱらと捲る。
森は、それほど蝶々には興味がないようだ。自分の子供だからとはいえ、自分と趣味が似通うことなどままないことだとは理解できるが、少しでも蝶々に興味を持てばと、それならばどれほど嬉しいものか知れない。しかし、森は昆虫には別段興味もなく、玉虫色の相馬の部屋に、一寸の有難みも感じてはいないようだ。
相馬は、森を残して、階下へと降りた。そうすると、あの匂いも、蝶々の香りも消えて、目の前に、古ぼけたパラフィン紙が香った。同じパラフィン紙でも、蝶々を包むものと、古本を包むものは、匂いまでも変容する。それが、相馬には不思議でならなかった。それは、相馬が蝶々への偏愛を抱いていて、自分の鼻腔にまで影響しているのが理由かとも思えたが、ふと森にどう思うか聞いてみたところ、森も同じように言うのである。蝶々は、甘い匂いがする。
相馬はカウンターに座ると、新聞を開いた。近頃の新聞は、日本語も、英語も、韓国語も、中国語も、全てが同一の紙面に並んでいる。相馬は辛うじて英語の意味は理解できるが、金のことの以外は、まるで理解できない。
フタナリヒラのニュースがないのか探すのが、相馬の日課である。フタナリヒラは、この世に顕れてからまだ半世紀も歴史がないから、最長年齢でも三十後半だという。自分と大して変わらない年齢だと思うと、自分が幼い時分が、この世の変容の潮目だったのかとも思う。近頃は一世紀以上世界大戦など起きてもいないが、近頃はまたきな臭い動きが大陸で起きているようだった。そうすると、美術品の値段にも影響があって、高騰するものもあれば、下落するものもある。あらゆる不快な出来事は新聞の中だけで構わないが、しかし、相馬には五月雨のごとくに、些事の全て、生きていくことの全てが、近頃は曇るようだ。
BOYARDを一本取り出して、咥えた。カウンター越しに見える車は全て自動運転で、貧乏人か物好きしか手動運転を行わない。もちろん、相馬はその範疇内だが、新しい車を買うのにも、大金が必要だった。
(あれは助成金だろうか。)
フタナリヒラには、国から補助金が出ていた。一人につき、年間で七百万ほどであるから、加えて働いていれば裕福な暮らしが出来るだろう。無論、森にも助成金が出る運びだが、それは成人してからの話で、あと十三年、彼(彼女)は普通の少年少女である。
ベルが鳴って、ドアが開くと、白髪を逆立てた老人が一人、店内へと入ってきた。常連の古村だった。相馬は何もいうことはなく、ただ片手をあげると、古村は何も言わずに、壁に架けられた絵を物色し始める。
医者であり、物好きな男だった。変わった絵が好きで、その点では相馬と趣味が重なっていたから、彼の接客をするのは相馬にとっては好きな仕事だった。しかし、絵は一人で観ている時間が大事だから、彼が絵を観終わるまでは、何も言わない。画商は、口うるさく薦めてくる人間が多すぎる。商売だから仕方がないが、自分が買う分には余計なプレッシャーを感じるものだと、若い頃の相馬はそう思っていた。同じ絵が好きな者同士、商売が絡むと、目が曇る。だから、彼は距離を置いて、客に話しかけないこともある。そうして、古村はこのギャラリーが仕入れた新しい絵を隈無く観ていて、相馬はその間、煙草を吹かすだけである。
「煙草は止めろと言っただろ。絵が汚れる。」
相馬を見もせずに、刺すようにそう言うと、古村はしゃがみ込んで、床に鎮座している猫のテラコッタを見つめた。
「いい品でしょう。木内克の作品だ。」
「木内克ね。お高いだろうな。」
「四百五十万円。」
「それは手が出ないなぁ。」
古村は眉を顰めながら、木内克の土色の猫を眺めた。
「ローンを組みましょうか?六〇回払い。金利が五%で月々七万八千七百五拾円。」
「こんな高い物ばかり売りつけているのに、店は汚いままだな。」
相馬は煙草を歯噛みして、
「幼い子供がいますから。」
「やもめ暮らしの哀しいところだ。」
古村はそう言うと、きょろきょろと、店内を見回した。
「森ちゃんは?」
「上で遊んでる。」
古村は頷いて、そうして、視線を金子國義の絵に向けた。
「新しいな。」
「お目が高い。院内に飾られたらどうです?ぐるぐると回る犬が、輪廻転生のようだ。」
「タイトルは?」
「『詩的なループ』。」
「御代はいかほど?」
「七百万。」
そう言うと、古村は腕を組んだ。出せない額ではないのだろうが、金持ちでも難儀する額だろう。
「まぁ、しばらくは売れませんよ。ですから、ゆっくりお考えになるといい。」
「六百なら?」
「僕に旨味が無くなる。」
古村は絵を見つめながら、
「森ちゃんの先生はどうだった?」
「とてもきれいでしたよ。フタナリヒラに、きれいというのが正しいのか、美しいというのが正しいのか……。」
そうして、森のことを、森くんや、森ちゃんと、どちらかで呼ばれてくると、頭の中にいる森の洋服が、ころころと変わる。それも、いまだけの遊びかもしれない。
「きちんと教えてくれそうか?」
「おそらくね。まぁ、僕も成人したフタナリヒラに、そう何度も会うこともありませんから、信じるしかないんでしょうが。」
「それならよかった。」
古村はほほを緩めて、またしゃがみ込んだ。今度は、小さなブロンズ像を見つめている。
古村は、森を取り上げた産科医だった。今まで、八人ほど、フタナリヒラを取り上げたことがあるようで、森は四人目だった。
「山の手のね、金を持ってそうな家に住んでました。」
「ああ、フタナリヒラは金には困らんだろうな。」
「僕は困りそうです。」
「店を畳めばいい。そうすれば、一括で何千万かになるだろう。」
「手元にいくら残るか。」
「子育ての方が楽しいぞ。」
「普通の子供ならね。」
「普通の子供なんておらんさ。」
「性別の話ですよ。」
相馬はそう言うと、自分を見下ろす金子國義の絵を見つめた。そうして、金子國義の、デカダンの極みとも言える、絵の数々を思い出した。かの作家は、そのように過剰なデコレート、過剰な装飾で、耽美とも言える世界を作っていて、屋敷までもが、その作品のようだったのを、本か何かで目にしたことがある。白い蘭の花が、橙の灯りの下に煌めいていた。二十代の頃、金子の絵に惹かれて、自分の住まいも店もそのように、様々な芸術で埋め尽くした。それが、文明文化の香りを産み出すと、信念めいて見えたものだ。それがせいで、一階の店内にはがらくたと芸術の山、二階の書斎には、埋め尽くす程の標本である。あれも、金子のものと同様に、過剰とも言える量で、いつか天井が抜けるでのはないかと思える。
「最近も虫採りは続けているのか?」
古村は疲れたように、カウンターにもたれ掛かった。相馬はかぶりを振って、
「全然。結婚してからこっち、一度も行ってませんよ。ガキが出来てからは、ネットで輸入するだけです。」
「それでも蒐集は続けているのか。」
古村は呆れたように笑って、
「集めて、蒐めてね、そうしないと、不安になるんですよ。何故かわかりませんがね。」
「根っからの蒐集家だからだろう。コレクターはさ、頭がイカれてんだ。まぁ、博打打ちと変わらんわな。」
「その言葉はご自分に返ってきますよ。」
相馬が笑うと、古村は頷いて、
「お前さんも、いい加減に二階の標本は捨てるか、焼くかでもしたらどうだ。そうすれば、森ちゃん一本で、何の迷いも衒いもないだろう。」
それだけ言って、もちろん、何かを買うこともせず、古村は帰っていった。出来れば、森に会いたかったのだろう。森を、孫のように見ている節がある。相馬は、親とは疎遠だから、森にとって、古村はほんとうの祖父のようだろう。しかし、殊更に会おうとはせず、ただ偶然会えば、そのときの話す程度である。古村にとって、森がどのような存在かまでは、相馬にはわかりかねたが、医者である以上は、気になるサンプルなのかもしれなかった。
相馬は、古村が帰って、急に虚ろだった。山のような骨董に囲まれていると、自分の卑しさが迫るようだった。そうして、彼が言った、標本を焼くという、そのような考えが、妙な空想を伴って、脳裡に浮かんだものだ。
焼いてみるのもいいかもしれない。
標本のひとつひとつを、灼いてみる。
そうすれば、無惨に召された命が、またどこかに宿されるのかもしれない。
雌雄モザイクの、あのウスキシロチョウ。
三角紙に包まれた、てふてふ宿した、ふたのなりひら。
余白を抱えた、青い魂。
これはなんという美しい病気。
男女が交わり、男女が消える。
そうして、低い声が、森の名前を呼んでいる。相馬のことを、見ている。
リビングに佇んでいた恵の顔が浮かんで、相馬は目を開けた。しばらく眠っていたようで、彼は欠伸を一つすると、腕時計を見つめた。長い間心にある、この屋敷を畳むことも、もう現実的な気がしていた。骨董など、儲かる商売ではない。借金も、返さなければいけない。このような、宝の山に埋もれていても、誰も識らないのだ、過去の芸術家、名も知らぬ芸術家など。
そうして、恵の家にあった、李禹煥の版画を思い出した。石と紙だけの静かな家。あのような、静かな生活をこそ、森には必要なのかもしれない。そうして、森のことを思い出すと、相馬は彼(彼女)がどのように恵から授業を受けるのか、それを見ておきたいと、急に感じられた。
「参観日というやつだ。参観日。」
独りごちながら、参観日という言葉を口ずさんでいると、彼は、急に自分が父親になったような気がしていた。
そうして、翌日の初めての授業の日、相馬は森を送りがてら、そのまま、授業を見学してもよいかと、彼女(彼)に尋ねた。恵は、黒いワンピースを着ていたが、先日と変わらぬ涼しげな様子で、それは別にかまわないと、そう一言言うと、森の手を握って、リビングへと案内した。
ちょうど、リビングには白い月があった。その白い月が、庭におかれた石と照応をなしている。恵は、小さなノートを取り出して、そこに立て膝をついて座った。向かい合わせに、森が正座させられる。
「じゃあ、はじめましょうか、森。まずは、私たちのなりたちから、お話します。」
低い声だけが、リビングに響いた。リビングにおかれたソファに腰を下ろして、相馬はその授業を見守るわけである。
「私たちは、フタナリヒラと呼ばれています。人間には男と、女がいます。そのどちらも抱えているのが、フタナリヒラ。フタナリヒラには、ペニスもあるし、ヴァギナもあります。そうして、男の心も、女の心もあります。どちらもあるから、両性具有と呼ばれています。それは識っているね?
私たちは、産まれながらに、どちらの性も持っていて、識っているけれど、子供を作ることはできません。私たちは、産まれてきて、成長して、そうして、一人で死んでいきます。まずは、それを識って欲しいの。あなたも、わたしも、どちらも、その子孫を残すことは出来ません。だから、自分たちの子を手の中に抱いて、ミルクをあげることもできません。私たちはミルクで大きくなったのに、それを繰り返すことはできないの。
そうして、私たちは、色々な人から必要とされます。それは、善い人であったり、悪い人であったり、様々だけれど、私たちには、寄る辺がない。だから、あなたには、一人で生きていくことと、フタナリヒラとして生きていくこと、そうして、美しいものとを色々と、これから教えていこうと、思っています。」
恵は、森を見つめながら、延々と、あの低い声で話しかけた。ただ、話すだけである。しかし、途中、足の震えに我慢の限界が来た森を引き寄せると、そのまま、後ろから抱きかかえて、また話し続ける。本当に、ただ彼女は言葉を、話し続けた。
「あなたの身体はまだ子供だから、わからないとは思うけれど、ほら、私には胸があるでしょう。そうして、もちろん、ペニスもあります。あなたにも、ペニスとヴァギナがある。それは、やっぱり、大人になるにつれて成長していきます。どちらもあるということは、普通の男女にはないことです。だから、私たちは特別な存在だと言われています。私たちのことを、神話の人と呼ぶ人もいる。でも、心は他の人と変わりませんから、ひどい言葉で傷つくし、優しい言葉で温かくなる。人を愛することもあります。フタナリヒラは、フタナリヒラ同士で恋人になることが多いと言われています。それは、今まで生きてきた二人の道が、交わりやすいからでしょうね。もちろん、男性を好きになっても、女性を愛しても、構いません。けれど、彼らや彼女たちと私たちは、決定的に違う。それは身体の部分についてであって、受け入れられる人もいれば、そうでない人もいる。だから森、まずは、あなたはあなたの身体の好きな部分を作るようにしましょう。私は、こののど仏が好き。こののど仏は、男のものよりも幾分も円いの。こういう可愛らしい仏さまは、私にしかない。女は平でしょう。フタナリヒラにしかないものです。あなたはきれいな顔立ちをしていますから、大人になれば、きっと素敵な人に育つでしょうね。そのときに、あなたはフタナリヒラとして、自分を誇れる部分を持っていることで、誰とでも対等になれる。これから、それも探していくことになります。」
相馬は、しばらくの間、彼女(彼)が彼(彼女)に囁くように話し続けるのを聞くだけだったが、しかし、その言葉が彼の耳に染みいってくる。心に含まれていく。そうして、リビングに飾られた白磁の茶碗の曲線が、人型のようで、相馬に美しいと思えた。
恵の話は小一時間ほどで、話し終わると、森は少し疲れたように、目を閉じた。恵は立ち上がると、
「少し休憩だね。」
そうとだけ呟いて、リビングから出て行ってしまった。相馬は、先程の話に、自分も引き込まれるものを感じていたが、仕事に戻ろうと、後ほど迎えに来ると森に囁いて、リビングから出た。
先日初めて訪れた時には気付かなかったが、部屋にはいくつかの版画が架けられている。その全てが、一つの作家、一人の作家で、全てが李禹煥のものだ。
(いくらかかっているんだろう。)
職業病か、相馬にはそのような、下世話な考えが頭に浮かぶ。彼の版画ならば、リトグラフでも数十万、モノタイプならば、数百万はくだらない。そうして、その算盤は、恵の住むこのモダンな邸宅にも及んでいく。ただのフタナリヒラならば、これほどの物件に住むのは、そうそうないだろう。ほとんどのフタナリヒラは、金には困ることはないとはいえど、一般の人々よりもわずかに上流と言えるほどであろうが、恵はというと、はるかにとも言えるだろう。それは、彼女(彼)の出自に関係しているのかもしれないが、削いだようにものが少ないこの邸宅は、彼女(彼)を見たときに感じる余白にも通じている気が、相馬にしていた。
玄関までへの道を進んでいくと、ミネラルウォーターが入ったペットボトルを持った恵が目の前に顕れた。驚いて、相馬は間の抜けたように、惚けた顔になる。
「授業参観は終わりですか?」
そう言うと、恵は水を口に含んだ。女めいた顔に円いのど仏が隆起した。
「仕事です。また、お迎えに上がります。四時半に。」
「お仕事は骨董屋でしたよね?」
「ええ。絵画や、古書、アンティーク……。大抵の美術品は扱っています。」
「李禹煥も?」
「ああ、いえ。彼の版画はないな。版画は少ないかもしれない。タブローが好きなんですよ。油絵が特に。厚塗りのね。質感が好きなのかな。だから、結局は自分の趣味みたいなもんで、自分の好きな絵ばかり置いています。」
「好きな画家は?」
「金子國義が。」
「ああ。『花咲く乙女たち』ね。置いているの?」
「いくつか。」
「今度観に行こうかな。」
「是非。似合いのものを見繕って差し上げます。お安くしておきますよ。」
恵は幽かに眦をさげた。そうして、そのまま背を向けると、森のもとへと向かっていった。
キャラクターイラストレーション ©しんいし 智歩
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
