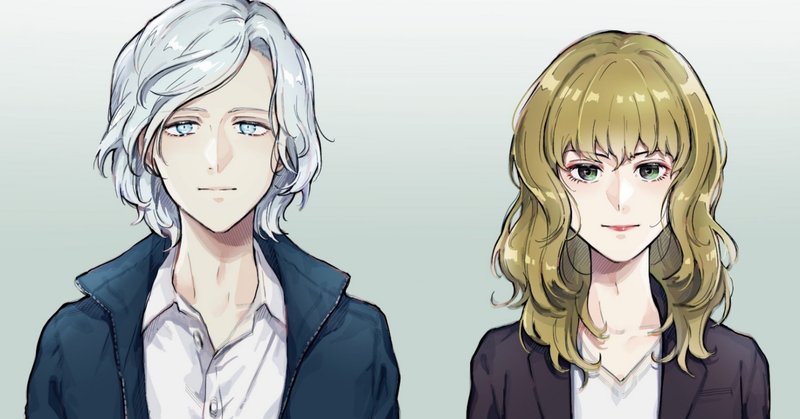
ふたのなりひら
1-4
改めて、金子國義の絵画を整理する。ギャラリーにはいくつかの絵があって、どれも、少女か、男性が描かれている。美しく無表情な人物が、鑑賞者を見つめている。それらの絵には、全て、女性器も露わに描かれているが、いやらしさはない。それは、描き手の目線によるものだろうか、興味によるものだろうか、相馬にはわからなかったが、なぜ自分がこの絵に惹かれるのか、それもまたときどき、わからなくもなる。幼い頃に、嵐山にあるオルゴール館に連れて行かれて、そこで見たデカダンスの香りを放つオートマタたちに、趣向がねじ曲げられたのかもしれない。そして、そのように自分の好きな絵を手に入れて、一通り愛でると売り捌くのは、画商の宿痾であって、所詮は金儲けに囚われている自分に、絵の価値などわかるものかと自嘲する。
彼女(彼)は、この絵を買うだけの財力がありそうだと、本気で勧めてみるのもいいかもしれないと、相馬は思った。売れれば、数十万の金になるし、数ヶ月は食うに困らない。しかし、彼女(彼)は息子(娘)の先生であり、恩人になる人かもしれない。そう考えると、このように高い絵を売りつけるのは、気が引けた。どこまでも、露悪的なまでに、人を欺ける人間が画商に向いているが、しかし、相馬はどこまでも甘いのかもしれない。だから、儲からないのである。
その日も、客は二人しか来ず、三件ほどのネットでの問い合わせ、一件の注文が入っていただけだった。それは、無名画家のリトグラフで、二万円ほどで売れたが、相馬に入る金は五千円にも満たない。相馬は、注文者に丁寧にメールで返信すると、時計を見て、もう四時を回っているのに気付いて、慌てて車に乗り込んだ。
恵の邸宅に着いたのは、五時半を回っていた。いきなり遅刻をするとは馬鹿な親だと、相馬は青ざめながら、チャイムを鳴らす。しかし、返事がなかった。相馬は、訝しく、何事かあったのではないかと不安が心に寄ってきて、恐る恐る、木目の扉を開けると、鍵はかかっていない。随分と不用心なものだと、そのまま侵入者よろしく、邸宅の廊下を進んでいった。
やはり、邸宅の中も、廊下も、音がないのだ。相馬は、息を呑んだ。まるで、蝶々を追うように、そうして、蝶々を捕まえるように、音を殺して、リビングを覗いた。
朝の白い月はもう黄色くなっていて、そうして、朝のままに、フタナリヒラが二人、そこにいた。恵の膝の上に乗せられて、森はすやすやと寝息を立てている。眠る森は、人形めいて、少年と少女が息を吐くたびに入れ替わる。
恵が相馬を見て、しっと人差し指を立てた。相馬は会釈をして、そのまま、ソファに座った。
「すみません。遅れてしまって……。」
「お仕事がお忙しかったんでしょう。」
相馬は言葉もなく、頷いた。森は、起きる気配もない。
「森くんは、とても良い子ですね。良い子だけど、余白が多いです。」
余白、という言葉に、相馬は自分の心が覗かれたように思えた。
「フタナリヒラで、御母様がいらっしゃらないのなら、気をつけないと。」
「面目ない。」
「お父さんのことを、あなたのことをよく話していましたよ。そのうちに、疲れてしまって、眠ってしまいました。」
「眠ると、どちらかわからなくなる。」
「性別?」
「どちらでもあるのはわかっています。でも、どちらにも振れそうで、怖くなります。」
「あら、怖くなる必要はないでしょう。怖くなるのは、森くんでしょう。」
「そうです。一番怖いのは森です。でも、僕も怖くなります。」
「一人親ならそうなるでしょうね。誰にも話せないのは辛いでしょうね。」
恵はそう言うと、森の髪の毛を撫でた。母のようにも父のようにも思えた。
「森くんが言っていました。蝶々の採集がご趣味だとか。」
「ああ、そんなことまで。」
「家にも標本があるとか。」
「山のようにね。」
相馬は自嘲したようにそう言うと、脳裡にぱっと、蝶々たちの姿が浮かび上がった。
「楽しい趣味でした。ガキの頃から、ずっと、蝶々を追ってね。きれいなものが、美しいものが好きなんですよ。」
「今のお仕事と変わらないのね。」
「ああ、その延長なのかもしれない。」
相馬は、ぼうっと、幼い時分を思い出して、そうして、虫採り網を持って走る様を、思い描いていた。大人になっても、変わらないのである。同じように、森や山に分け入り、蝶々を探す。そうして、貴重な眩い蝶々の数々を何度も何度も捕らえてきた。
そうして、あの日が来た。あの日に、都会の喧噪で、街の中で、人の形をした蝶々を捕らえて、そうして心臓を潰した。
妙な間があった。恵は、糸のような眦をこちらに向けていた。
「楽しいのね。」
「ええ。ガキの頃から、さんざん蝶々を捕まえましたよ。目的は標本です。まぁ、コレクションですね。子供の頃から、顕示欲が強かったんでしょう。しょっちゅう、採集に行っていました。蝶の水飲み場を見つけるたびに、お袋に報告してね。得意でした。たくさんの蝶々をね、標本にしたんです。」
「美術品として?」
「さぁ……。戦利品みたいなものかもしれない。たくさんの蝶々を、殺しては、三角紙に包んで、ピンを刺して、部屋に飾った。」
「なるほど。それならば、狩猟のようなものですね。」
「変わった種類が好きでね。色々な種類。特に、異常のあるやつが好きだった。」
「異常?」
「羽根の色がおかしかったり、模様がおかしかったり。」
「ああ。」
「一番、僕が嬉しかったのは……特段変わった……、雌雄モザイクのね、ああ、雄と雌の、それぞれの遺伝子を持った、特異なやつですー、そういう羽根の、ウスキシロチョウっていう蝶々を、ある日見つけた時です。とても美しかった。片方の羽根は黄色くて、もう片方が茶色がかった黄色なんです。きれいに二つに分かれていて。二つは違うのに、翅脈は同じように細いんです。僕は興奮して、何が何でも捕まえると、そう思ったんです。そうしてね、捕まえたんです。蝶々はね、標本にするために捕まえたときに、心臓を潰すんですよ。指と指で圧死させる。そうすれば、儚く死んでしまいます。その、雌雄モザイクも、俺はすぐに殺したんです。簡単に。」
「何が言いたいんですか?」
「俺が殺した雌雄モザイクは、森なのかもしれない。森は、俺が殺した命の生まれ変わりなのかもしれない。」
相馬は、自分が何を言っているのか、悪酔いでもしているのではないかと思えた。恵は、何も言わずに、ただ森の額に手を当てて、その温かいのを掌で感じていた。
「俺の妻は、蝶々みたいな女でしたから。てふてふだと、自分のことを言っていましたから。」
「奥様が、蝶々の化身で、森くんは雌雄モザイクの蝶々。とても綺麗な物語ですけど、クソ喰らえです。」
恵は、低い声で、そう言うと、今度は森の手を、自分の手で包んだ。
「私も雌雄モザイクですよ。なら私も蝶々?私は人間です。森くんもね。」
相馬は何も言えなかった。急に、二人がこうして月の下でいる姿に、胸が溢れたのは何故だろうかと、なぜ斯様なことを口にしたのだろうかと、自分に不思議だった。
「失礼しました。妙なことを言って……。」
「輪廻転生のお話は好きですよ。神話や、空想としてね。ただ、私も森くんも、ただ一人の人間ですわ。」
竹林が風に揺られていた。まだ、森は起きる様子はなかった。
「病魔や、災厄を、業や罰のように言う文化は好きじゃありません。そのようなことを言う人は、信じてはいけませんよと、ついさっき森くんにお話したばかりです。」
相馬は窘められたようで、俯いた。森が産まれて、陽菜子と隔ててから、心のうちに抱いていた思いを、人に初めて吐露したわけだが、しかし、やはりばかげた空想に過ぎない。しかし、それを初めて人に伝えたことは、相馬に、妙な感慨があった。
恵は、森をゆっくりと床に横たわらせると、立ち上がり、相馬を見た。相馬は、恵を月の下で、改めて見た。
雌雄モザイクは、身体の紋様が見事に雌雄で別れている。しかし、恵はどうだろうか。恵は、女寄りのフタナリヒラであって、女性の特徴が多く出ているように思う。しかし、のど仏は男性よりも低いものの円く顕れていて、肩幅はかすかに広い。乳房は女性のそれであり、手も固く大きいように見える。端からは、女にしか見えないが、どこか歪であるのは、雌雄モザイクと同様だった。
そうして、恵は着ていたワンピースを脱ぐと、その裸身を相馬に見せた。相馬は驚いて、目を瞑ったが、しかし、恵は何も言わずに、森は眠ったままだ。相馬が目を開けると、恵は月明かりの下に、佇んだままだった。余白という言葉が、思い浮かんだ。女の余白に男の性が一滴落ちたようだ。そうして、その裸身は、ギリシャ彫刻の、眠れるへルマフロディトスを思わせるほどに白磁めいていて、それは相馬が男性だからだろうか、美しい曲線は扇情的でもある。女性が見たのならば、女性にとっての扇情的な印象になるのだろうか。
「あなたの言う、雌雄モザイクと、フタナリヒラとは違うでしょう。」
相馬は頷いた。そうして、一度脱いだワンピースを、恵はまたするすると身に付ける。
「おそらく、森くんも、このような身体になります。彼は、男寄りのようですから、男性性に傾くと思うけれど。」
「先程は、失礼しました。」
相馬は改めて、恵に謝った。恵は首を振って、
「森くんが幼いころには良い寝物語だと思いますよ。あなたの御母様は蝶々の化身だと。」
恵はそう言うと、リモコンで部屋の灯りをつけた。ぱっと、ライトが灯って、部屋が灯りに包まれる、森が目をきつく瞑って、目を覚ました。恵は静かに、森の肩を抱いて、頭を撫でてやる。
「随分寝ていたね。今日は初めてだから構わないけれど、明日からはお家に帰るんだよ。」
「はい、李先生。」
森は静かに頷いて、そのまま相馬に気がつくと、ばつの悪そうに、顔を背けた。
「帰るか。」
相馬は明るくそう言うと、
「李先生、今日はありがとうございました。また、明日もよろしくお願いします。」
恵は幽かにほほ笑んで頷いた。そうして、森に小さく手を振った。
大谷石の道を下りながら、邸宅を振り向くと、やはり、この邸宅に一人で住む恵の神秘性が、相馬に不思議だった。しかし、同時に、自分の幻の共有者であるということが、たまらなく嬉しいものに思えた。
助手席の森は、冴えた目をしていて、遠ざかる山の手の光を見つめていた。
「李先生はどうだった?」
「すごく好きだよ。優しい先生。たまに口が悪いんだ。」
そうして、先程の恵の言葉を思い出して、相馬は思わず口元が緩んだ。
「悪い言葉は真似するなよ。ああいうのはな、大事な時に、ふっと出ちゃうからな。」
「でも、うちに来るお客さん、みんな言葉が悪いよ。」
「確かにな。だから、みんなうだつが上がらないんだよ。」
「うだつって?」
「貧しいってことさ。」
「先生はお金持ち?」
「ああ。パパなんかとは偉い違いだ。」
そうして、また森は外を見た。だんだんと、普段の町並みに戻ってくる。
「先生のお家、きれいな絵がいっぱいあったね。うちにある怖い絵とは違って、寂しい絵。」
「怖い絵じゃない。うちにあるのは幻想絵画だ。きれいな絵なんだぞ。」
そして、そう言いながら、森もまた、蝶々に興味はなくても、絵には興味があるのかと、相馬に嬉しい思いだった。しかし、森は、相馬が蒐めたり、売っているものを、やはり怖い絵だと認識しているようで、少し複雑な思いでもある。
「ねぇ、先生はスモモなんだって。」
「スモモ?」
「先生の名字はね、スモモって意味なんだって。かわいいでしょうって言ってた。」
李とは、スモモの意味があるのか、そうして、かわいいでしょうと、そう聞く娘めいた恵の低い声が、相馬の耳に再生された。そのうちに、下町の自分の家が、だんだんとその姿を現してきた。
キャラクターイラストレーション ©しんいし 智歩
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
