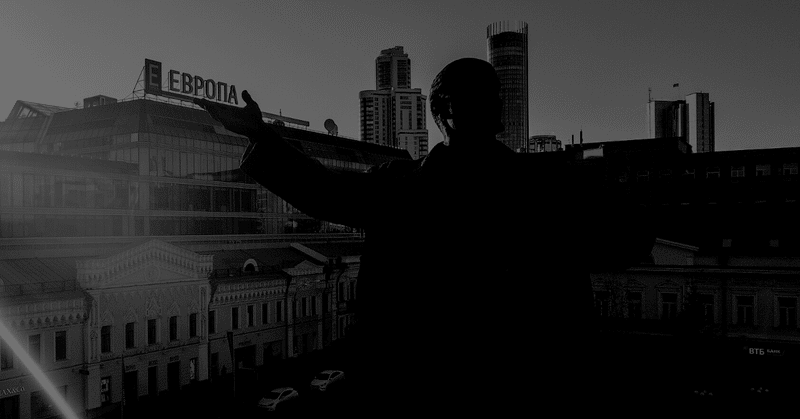
渡辺健一郎×小峰ひずみ 往復書簡(第二回)
忠誠なくして反逆なし 小峰ひずみ
渡辺健一郎様
Ⅰ
私は大阪平野の最北端にある五月山の麓に住んでいます。家を出て、南を向けば梅田の蜃気楼が白く汚れて透け見え、北を向けば新緑がざわざわと風に揺れているのが見えるのです。南は一年を通して一向に変化がありませんが、北の景色はむろん流転します。この木々の流転に合わせて「桜が咲き始めました……」とお返事を書きたかったのですがダメでした。出版社の編集者や選挙管理委員会の役人がカレンダーで動いているのに、自分だけは五月山と呼吸を合わせて、というわけにはいきません。結局、四月末の原稿の〆切を終わらせて、この往復書簡に向かっています。
遅くなりました。往復書簡の依頼に私を選んでいただいて非常に光栄です。ありがとうございます。
今年の一月末に「指導者について、書くことについて」と題された渡辺さんからの書簡をいただいたとき、この返信を書くことの難しさに当惑しつつ微笑したことを記しておきます。渡辺さんの対談などを見させていただいても思うのですが、その螺旋のようにぐるぐると回りつつ反省を重ねていく弁証法的(?)な思考のあり方には、「渡辺健一郎」という固有名が刻まれているように思います。いわゆる、渡辺節、というやつです。にもかかわらず、渡辺さんの著書『自由が上演される』は拙著『平成転向論』に比べて明快なように思える。私の思考そのものは将棋盤の隅にいる香車のように単線的なのに、文章そのものが隠喩で占められていて、読者を選びます。渡辺さんが「狂信者」であり「演説家」である私に対して、「しかし、小峰の言う「エッセイスト」とは何なのか」と執拗に問うのも、私の文章のわかりにくさゆえでしょう。君はいったいどんな主体論を持っているのか? と問われているように思います。
しかし、主体論と言えば、まずはあなたの業績にふれないわけにはいきません。『自由が上演される』であなたが提示した「俳優」という概念は主体論のゼロポイントを示す画期的なものです。つまり、「俳優」は何者でもないがゆえに何者をも模倣することができる。「俳優」は模倣する存在であるがゆえに、「偽物」として長く政治家や哲学者によって糾弾されてきました。その汚名を返上することが、主体論を大幅に書き換えることになった。あなたの業績は決して思想界に受け入れられているとは申せません。私も渡辺さんの論を的確に受容しえたとは言い難い。ただ、あなたの業績がパスカルのそれに類似するものであったと考えています。ポール・ド・マンは「パスカルの説得のアレゴリー」で「ゼロ」と「1」の関係について次のように述べています。
ゼロがなければ1もありえないのだが、しかしゼロというのはつねに1[one]の外観をとって、つまり(何らかの)事物の外観をとって現われる。名前とはゼロの譬喩である。ゼロが実際には名前をもたないのだとしても、ゼロというのはつねに「名づけられない」もの[one]と呼ばれることになるわけだ。(傍点著者)(注1)
私の解釈では、俳優は本物と一体です。ド・マンをパラフレーズすれば「俳優がなければ本物もありえないのだが、しかし俳優というのはつねに本物の外観をとって、つまり(何らかの)事物の外観をとって現れる」というわけです。俳優があるから本物があるとも言える。というより、本物とは非・俳優としか言えないのではないかと思います。古代ギリシャ以来、哲学の主体論でこの「ゼロ」=「俳優」が貶められていた。ニーチェもしばしば「あいつらは俳優だ!」と他者を執拗に攻撃しています。そうすることでしか本物を表象しえないからではないか。自らの共同体から「俳優」(プラトンの言う詩人)を排除するというある哲学者の野望は、決して叶えることができません。「俳優」がなければ、本物の政治家も本物の哲学者も、何もないわけです。
では、わが「エッセイスト」はどうなのか。もともとの意味を踏まえて、「試みる人」と曖昧に規定してしまいましたが、これは悪手でした。エッセイストは「詩人」との関係で捉えられねばなりません。ここで言う「詩人」とは俳優のことではありません。むしろ、政治的な概念です。私は『平成転向論』でSEALDsを念頭に置きつつ次のように述べました。民主主義や革命を「信じえない状況に置かれながら、信じようとするとき、私たちは政治と日常を「凝縮」させる詩を生む。それがSEALDsに、〈戦中〉としての平成が求めたスタイルである。しかし、その「凝縮」を成り立たせていた詩的状況が消えると、政治と日常をつなぐ糸はぷつんと切れる。詩人は日常生活へ帰る」(注2)。エッセイストは、言ってしまえば、大勢が国会前に集まっていた状況でなくなり、日常生活に戻ってなお、政治的=詩的であろうとする主体を捉えた概念です。
最近、このエッセイストに非常に近い言葉を見つけました。ゲリラ、です。一九六八年の学生運動が退潮期に入り、ユートピアを求める街頭での実力闘争が機動隊の力で挫かれたあと、新左翼に同伴した知識人たちはチェ・ゲバラや毛沢東を引用しつつ、日常生活においてなお闘争を継続するための「ゲリラ戦」の可能性を模索し始めます。それは全共闘のイデオローグだった津村喬の「反差別闘争」や「日常生活批判」に結実します。あるいは、田中美津たちが率いたウーマンリブもゲリラ戦的発想を引き継いでいます。
にもかかわらず、東アジア反日武装戦線が三菱重工本社ビルを爆破した一九七四年あたりで、その「ゲリラ」という言葉はタブーとなった。実は、彼/女らの出したパンフレットは『腹腹時計 都市ゲリラ兵士の読本vol.1』と題されていたのです。「人民は海、兵隊は魚」という毛沢東のテーゼに則り、日常生活をいかに怪しまれずに「演技」(笠井潔)して、つまり人民を装う「俳優」として生きていくかが書かれたのが、このパンフレットです。家族とはつかず離れず、友人関係は浅く狭く、同志での飲み会は禁止、大家には愛想よく……。この台本は「俳優」たちに己が「俳優」であることを忘れないよう釘を打つために書かれたように思います。終わらない上演。唯一、爆弾闘争をしているときにのみ、彼/女らは楽屋に戻ることができたのでしょう。
私は彼/女らの爆弾闘争が正しかったとは思えません。また、笠井潔は日常生活を「演技」して生きていくという彼/女らの戦術を、「俳優」嫌いの哲学者らしく「生活憎悪」「民衆憎悪」の現れであるとして退けていますが、この規定も正しいと思います(注3)。しかし、「ゲリラ」という主体のあり方をタブーにし模索しなくなったのは運動論にとって致命的です。ゲリラという発想の根幹にあるのは、「軍隊とは制服を着た人民である」というテーゼです。つまり、あなたの言葉を用いれば、キューバ軍や紅軍などのゲリラは「俳優」たちの軍隊だったと言えるかもしれない。カール・シュミットよろしく、パルチザンは戦闘におけるゼロ(俳優=人民)と1(本物=兵隊)の区別を攪乱します。市民軍では誰も彼もが兵士を真似ます。
どうでもいいですが、れいわ新選組の地元の選挙を手伝いました(大阪で唯一当選した「れいわ」の候補です)。れいわ新選組の運動員はみんな仕事が終ってから来るボランティアです。自民党・大阪維新の会や民主党系の運動員などは青年商工会議所や労働組合を抑えていますから、職場の命令で運動員にさせられています。極端に言えば、前者はゲリラ軍で、後者は正規軍といった感じです。だから、士気が全く違います。そして、私なども維新の会のビラ配りの仕方や演説の仕方を真似ました。見よう見真似です。
Ⅱ
ただ、渡辺さんの見立てへの違和感もあります。『自由が上演される』では二極の間で宙づりにされている点が、この往復書簡では一極にふれているのです。少し思い出話をしましょう。私たちが最初にお会いした日に、大阪駅前ビルの地下の居酒屋に入りましたね。そこで私は「こいつは自分とは違うタイプの活動家だ」(「活動家」という言葉を渡辺さんは嫌がるでしょうが)と思う人にしかしない質問を渡辺さんにぶつけたことがあります。私はいままで二人の師匠を含めて幾人かにしかこの質問をしたことがありませんでした。
「何が世界を変えますか?」
という質問です。すると、あなたはこうおっしゃいました。
「教育が世界を変える」
ここから先は
【定期購読】文学+WEB版【全作読放題】
過去作読み放題。前衛的にして終末的な文学とその周辺の批評を毎月4本前後アップしています。文学に限らず批評・創作に関心のある稀有な皆さま、毎…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
