
光明【総集編】
第一章
突然変異
突然変異?、新しい人類?の可能性がある・・・らしい。
カチンスキのもとへ届いた情報である。
国立人類学研究所、カチンスキが研究に没頭する場所である。
科学の驚異的進歩、特にAIに関しては、いずれ人類を凌駕するのではないか、
既にコントロールする側のはずの人間とAIの立場は主客転倒しているかのようである。
それに対してあたかも警鐘を鳴らすかのように、ハリウッド映画などでは一つのジャンルになって久しい。
今こそ、人類は原点回帰すべきではないか・・・カチンスキはそう考えた。
人類とは、そもそも何なのか?直立二足歩行を始めて約七百万年、現生人類が誕生して
約二十万年という気の遠くなるような時間が経過している。
それが僅か二千年(西暦)の間に、有り得ないような進歩を成し遂げ、食物連鎖の頂点に君臨するに至った。
しかし、自ら作り出したAIの能力に頼り、高度な知能活動を安易にAIに委ねようとしている。つまり、人類のさらなる進化を放棄しようとしているのではないか。
そうゆう安易さ、傲慢さが、現在地球上に発生している諸問題の根本的原因なのではないか。
いつからかは分からないが、人類は間違った方向へ向かうようになったに違いない。
それを確かめ、対処するべく、人類というものを見詰め直す。
それは、自分自身に与えられた神の意志なのだ、そう考える至った。
カチンスキの両親は敬虔なクリスチャンであったが、自身は無神論者であった。
にもかかわらず、見えない力を感じたのである。
それ以来カチンスキは、ありとあらゆる手段を使った。
そして遂に、
「大統領が、話を聴きたいと言われている」
その結果が、世界中から人材を求め密かに作られた現研究所である。
そのカチンスキのもとへ届いたのが先の情報である。
その情報
「生後6歳になる女児。
脳容量1400㏄、消費エネルギー50%前後と推測される」
「何、50% ?!」
※通常、脳の消費エネルギーは20~25%前後、心臓、肝臓などと同程度だと云われている。因みにその重さは全体重の2%程に過ぎない。
「そんな馬鹿な、何かの間違いだろ」
しかし、目は次の情報を追っている。
現在、食事のみでは体力を維持することが出来ないため、常時点滴を要す。
能力 現在調査中であるが・・・
学習した言語、現代数学、物理学、生物学etc.を、極めて短時間(およそ一ヶ月)
で理解する。
「そ、そんな馬鹿な・・・」
人間の脳の活動領域
「人間の脳はその10~15%前後しか使用されていない」という神話が存在するが、それは単なる都市伝説でしかないと言われて久しい。しかし、脳活動の不可思議さはその殆どがいまだに謎につつまれて、解明されていない。

第二章
エミリ
「ママ、行ってくるわね」
「気を付けるのよ。最近は交通事故が多いし、エミリはとばすから・・・」
母、鞠子が言い終わらないうちにドアを閉める音がする。
「全く、あの子ときたら誰に似たのかしら」
郊外の比較的高級な部類に入る住宅地に、エミリは母と二人で住んでいる。
エミリが幼い頃、
「ママ、うちにはどうしてパパがいないの?」
「パパはね、天国で神様のお手伝いをしながら、エミリのことをお空から見てるのよ」
それ以来、エミリは父親のことに触れない。賢い子だと思う。
鞠子としても父親の分まで頑張らなければとわき目もふらず働き、大学まで卒業させた。
しかし、一抹の寂しさのようなものは、母子ともに心の底に沈殿しているのである。
エミリは車を走らせながら、研究室で眉間に皺を寄せ論文を読みふけるカチンスキの顔を思い浮かべる。とにかく笑わない男である。
必然的に研究員達からは敬遠される。真面目過ぎるのである。
しかし、そんなカチンスキを嫌いではない。自分も似たような者だからだ。
ハーバード大学医学部を卒業後、脳科学研究一筋の人生を歩み、三十六歳になる今でも独身のままである。
食事を共にし、一夜を共にする相手はいるが、向こうも研究者、幸せな家庭生活などに全く興味を示さない。研究者というものは変わり者が多いのである。
「エミリさん、おはようございます」
研究所入り口の守衛室から声がかかる。
「おはようジョン」
顔パスで通過する。

第三章
タンザニア
ルルルル・・・
「はい、エミリです」
「おはよう、悪いがすぐに来てくれ」
と、カチンスキの声。
「分かりました、すぐに伺います」
慌ただしくドアをノックする音。
「エミリです」
「入りたまえ」
「何かありましたか?」
「まっ、これに目を通してみてくれ」
読み進むうちに、エミリは目を見開く。
「先生、こ、これは・・・」
「うむ、見ての通りだ」
「また、アフリカですか。しかもタンザニア・・・」
「そうだ、タンザニアの出身のようだ」
タンザニア
アフリカ大陸東部に位置する国である。
人類の最初期、約三百八十万年前の二足歩行足跡化石(アウストラロピテクス・アファレンシス)が発見されており、人類誕生の地の一つとして有名である。
人類の進化過程の全てはアフリカで起こっている。ある時期まで、多地域進化説(北京原人が進化して中国人に、ジャワ原人が進化して東南アジア人に、ネアンデルタール人が進化してヨーロッパ人にと云った具合に進化する)が信じられていたが、現在ではDNA解析により否定されている。
但し、現生人類のDNAの一部にネアンデルタール人、デニソワ人の痕跡があるのは、同時期に存在し交雑していたことが窺える。
またミトコンドリアイブ説によれば、全ての現生人類の母は約十七~二十万年前アフリカに生存していた一人の女性に行き着く。アフリカ単一起源説を支持する有力な証拠の一つであるらしい。尚、この説には詳細な説明を必要とするが、ここでは割愛する。
「ミランダ・・・素敵な名前ですね」
「そうだな、この上ルーシーだとか言われたら情報そのものを疑ってしまうよ」
「でも、ルーシーはエチオピアですよ先生」
「そうだったね」
エミリは、カチンスキの顔が僅かに微笑んだような気がした。
「エミリ、君を呼んだのは他でもない。ミランダに関する全ての資料を取り寄せてくれ」
「特にMRIは詳細にな」
「承知しました」
ルーシー
やはりアウストラロピテクス・アファレンシス、三百十八万年前の化石人骨とされ、全体の四十%にあたる骨がまとまって発見され資料上の貴重さから広く知られている。
発見当時、調査隊がビートルズの「ルーシーインザスカイウィズダイヤモンズ」を聴いていた為、この名前が付けられたという。
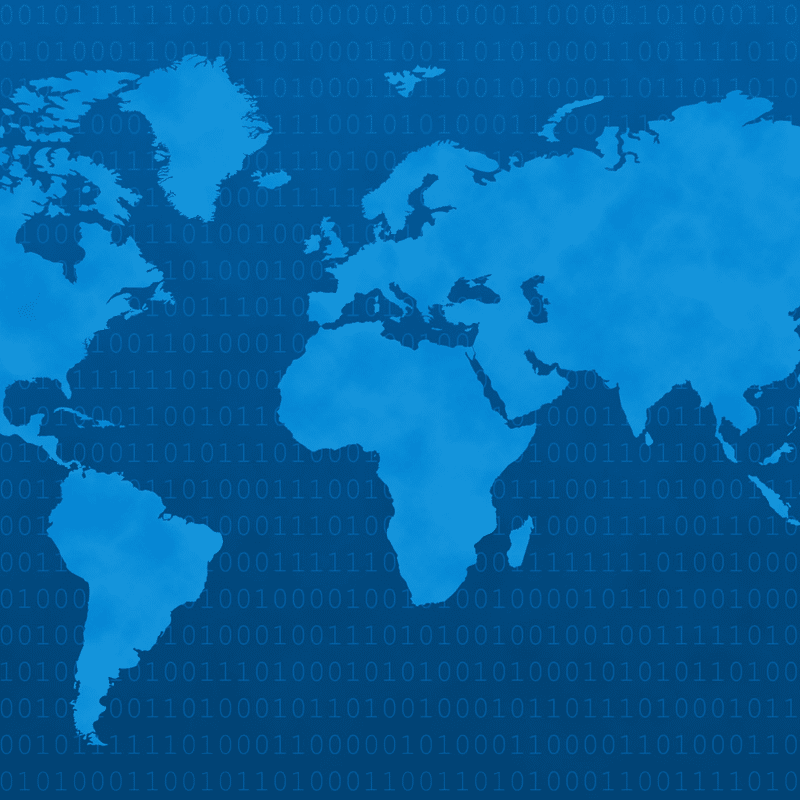
第四章
驚愕
「エミリ、どうかねミッシェルの分析の方は」
「先生、今回はビートルズとは何の関係もありません。ミランダですよ」
エミリは今日のカチンスキは、いつもと違うと思った。
「先生、何かいいことでもあったのですか?」
「うむ、ミランダの点滴が外れたらしい」
「えっ、脳活動が普通になったのですか?」
「それが、さしたるエネルギーを消費せずに、驚異的な能力を発揮しているらしい」
「順応?・・・安定したということですか?」
「その可能性は高い」
「やっぱり・・・」
「ん?どういうことかな?」
「実は、ミランダの脳のMRI解析中に見かけない影を見つけたんです」
「マシンの不具合じゃないのかね」
「勿論、私もそう思いました」
「誰もが見過ごすような影なのですが、私には見過ごすことが出来ませんでした」
「で、それがどうかしたのかね」
「はい、私には超微細なウィルスに思えるんです」
「ミランダが脳症にでもかかっているのかね」
「先生、極めて突飛な推測を言ってもよろしいですか?」
「脳科学を極めた君の推理だ。聞こうじゃないか」
「ありがとうございます」
「私は、このウィルスが人間の脳活動を制御していたある物質を死滅させたのではないかと・・・」
「・・・・・」
「そうすると君は、人間が生存するため脳の消費エネルギーを抑える必要に迫られ、脳活動を制御していた何らかの物質が存在し、尚且つ、それをウィルスが食ったとでも言うのかね」
「おっしゃる通りです」
「君、そんなこと言ってたら、のべつ突然変異が起こってるじゃないか」
「そのウィルスが数十万年に一定時期存在するものだったとしたらどうでしょうか?」
「・・・・・」
「人類の進化のスウィッチだと言いたいのかね」
「その影は、採取できるのかね」
「できません。脳の最深部です」
「そうか、もちろん今も活動中なんだね?」
「いえ、死滅していると思われます」
「そうすると、そのウィルスは人類の進化のトリガーとしての役割のみで数十万年に一度存在するということなのだね」
「そうとしか思えません」
二人とも押し黙ったまま口を開こうとしない。
重苦しい沈黙の時間が流れる。
カチンスキは絞り出すように
「エミリ、私はこれまでの研究人生で、これほどの驚きを覚えたことはないよ。
人類進化の何らかのトリガーの存在を考えてはいたが、口に出すことは憚られた。
君の考えがそこに至ったことは、感無量だよ。
しかし、まだまだ可能性の段階だ。
エミリ、これからも宜しく頼むよ」
「はい!」

第五章
拒絶
エミリにMRIの画像解析を入念にさせたことは、やはり正解だった。
予測していた結果とは言え、カチンスキは狼狽していた。
この先のさらなる予測はカチンスキにとって、できれば外れてほしいと思うような内容だった。
コンコンコンコン・・・いつもながら慌ただしいエミリノックである。
「入りたまえ」
「失礼します」
「エミリ、ノックは二回で十分だよ」
エミリ、そんなことはすでに聞いてない。
「先生、大変です!」
「何かあったのかね」
「何かあったどころの話ではありません」
ミランダは、その後、学習することを悉く理解し、さらに応用し留まることを知らない。
そのうちに、既成の事実、常識とされていることを次々にひっくり返す。
ミランダにしてみれば、当然のことであり何でもないことなのである。
最初のうちは、世界中の研究者の間でも
「やはり、そうか!」
「よくぞ証明してくれた!」
賞賛のあらしだったのだが・・・
次第に、それが既得権益、既成のヒエラルキーに影響を及ぼすに至っては、ガラリとその評価が変わる。
悪魔、共産主義者・・・ありとあらゆる誹謗中傷を浴びせられるようになった。
AIを凌ぐ勢いで成長しているミランダにとって、そういう人間の意志構造を理解するのにさしたる時間を必要としなかった。
わずか、六歳なのにである。
エミリは、そういった情報を涙ながらに報告した。
「先生、何とかなりませんか!」
カチンスキは言葉が無かった。
何もかもが、予測通り展開して行く。
「やはり早すぎるのだ」
ミランダの成長スピードがである。
いや、そうではない。
人類は頭脳の進化に関して決して寛容ではない。歴史がそれを物語っている。
ガリレオ、ダーウィンの例を引くまでもなく、新たな歴史を切り開く者の出現はいつであろうが歓迎されない宿命にあるのだ。
歴史に学ぶことを知れば、いまだに繰り返されるジェノサイドが起こることは無いはずである。
それゆえ、何の罪もない純真無垢なミランダはキリストのような宿命を背負っているのではないか。繰り返すが、わずか六歳である。
カチンスキは、言いようのない虚無感に囚われるのである。
「先生、先生!」
エミリの悲痛な叫びに、我に返った。
「先生、ミランダは生まれ故郷のタンザニアに帰りたがっているそうです。
何とかなりませんか」
「ミランダは、オックスフォード大学にいるんだったな」

第六章
邂逅
カチンスキは、その恐るべき行動力と、国家の力押しでミランダを保護した。
やはり、「帰りたい・・・」とミランダは言う。
「エミリ、この子を連れてタンザニアに行くことにしよう」
「はい、母にはもう了解をもらっています」
カチンスキは、喜び勇んで旅行の手配をするエミリの横顔をぼんやりと眺めている。
この子は研究一辺倒の学者ではないんだ・・・
ふと、エミリが髪をかきあげた時、首筋に目が行く・・・ホクロ。
「先生、手配出来ました。出発は三日後です!」
「そうか、わかった」
「ところでエミリ、お母さんの名前はなんていったかな」
「どうしたんですか先生、急に・・・」
「マリコ、鞠子ですけど・・・」
カチンスキ、思わす息をのむ。
「君のお父さんは?」
「先生、私の履歴者を精査してハンティングして頂いたんじゃないですか?」
「私のパパは天国で神様のお手伝いをしているそうです」
と言って明るく笑う。
鞠子から妊娠したという話は全く聞いていなかった。
「あなたは、研究一筋に生きてください」
そう言い残して、カチンスキの前から姿を消した。
それから、三十数年が経ち、この邂逅である。
エミリ、ミランダ、カチンスキは何か見えない力の存在を意識せざるを得ないのである。

第七章
キリマンジャロ
キリマンジャロ国際空港に降り立つ。
空気が澄み渡り、空は雲一つなくどこまでも青い。宇宙から地球を俯瞰した時の色はかくありきかと思わせるほどである。
乗降客は思った以上に多い。近くにはキリマンジャロ国立公園、人類発祥の地として名高いオルドバイ峡谷等々観光地が多いせいであろう。
オルドバイ峡谷
タンザニア北部にある谷幅数百メートル、全長四十キロにも及ぶ巨大な峡谷で、アウストラロピテクス・ボイセイの化石人骨と最も原始的な石器を世界で初めて同一地点同一文化層から発見され一躍注目を集めた。さらにその後もホモ・ハビリスの化石が発見されている。
出迎えてくれたダルエスサラーム大学の研究員ハルムの案内で、まずはアルーシャに向かう。車はベンツの新車であり、乗り心地は極めてよい。大学の所有であろう。
「博士、長旅お疲れさまでした」
「うむ、皆元気にしているかな?」
「はい、おかげさまで元気すぎるほどです。皆、博士に会えることを楽しみにしています」
カチンスキとエミリは、一週間後にダルエスサラーム大学に立ち寄る予定にしている。
アルーシャのホテルは数年前に開業したらしく、高級感にあふれ、とても今アフリカにいるとは思えないほどである。
ミランダが物珍しそうに玄関ホールを走り回っている。やはりまだ子供なのである。
「では博士、明日またお迎えに参ります」
「うむ、よろしく」
「エミリ、今日は疲れただろうから、食事を済ませたら早めに休むことにしよう」
「はい、先生」
翌朝、ハルムは時間通りに磨き上げられたベンツを玄関に横付けした。
「博士、昨夜はゆっくりお休みになれましたか?」
「立派なホテルを手配してくれたので快適だったよ」
「食事も最高に美味しかったわ、ねえミランダ」
「うん、今まで食べた中で一番美味しかったよ」
「それはよかった。私も嬉しいです」
アルーシャからオルドバイ峡谷方面へ車を走らせること約一時間、目的地の小さな山村に着く。
車が完全に停車するのももどかしく、ミランダはドアを開け一人の老人めがけて一目散に駆けて行く。
「連絡しておいたので、待っていたのでしょう」
「今ではミランダにとって、たった一人の身内です」
一通りの挨拶を済ませ、一行は目的地の温泉が湧出するという泉へ向かう。
「ここだね、ミランダ」
「そうだよ、ここで水遊びしてたの」
エミリ、あたりを見渡し感動したように
「ここかぁ、木立に囲まれて何かとても神秘的ですね」
温泉といっても比較的温度は低い。
「では、手筈通り二人は採取してくれたまえ」とカチンスキ。
エミリとハルムは手際よく、予定されたポイントで温泉水、土壌、植物etc.採取していく。
小一時間後には撮影も含めて予定の作業を終える。
その間、ミランダはずっと泉の中へ入り、潜ったり泳いだりしていた。
「うーむ、産湯のころからここで・・・」
カチンスキ、目を閉じて考え込む。
「ミランダ、帰るわよー」
と、浅瀬からミランダが立ち上がった瞬間。
一同は目を見張った。
しばらくは、呼吸することすら忘れたようである。
「せ、せ・ん・せ・い あ、あれ・・・」
カチンスキは言葉を発することが出来なかった。
エミリ
「お、オーラ?・・・光ってるよ先生」
古来、聖人を描いた絵画、彫刻等には光背が表現される。一般的には後光がさすと言われる。
「こ、こんなことが現実にあるのか!」

第八章
ミランダ
カチンスキはミランダの祖父をアルーシャのホテルに招き、ミランダの生い立ちを聴くことにした。
ミランダは、コーカサス・アラブ・アフリカ系の血が入っているようであり、顔立ちは美形である。祖父の話によると父親はトルコ人らしく、ミランダの母が妊娠すると突然いなくなり、消息は不明らしい。
母親はミランダを生んだ後、まるで役目を終えたかのように亡くなったという。
「なんて可哀そうな子なんだ・・・」
カチンスキは嘆息し、エミリは涙をぬぐった。。
その後、ミランダは祖父の手によって育てられた。
まともな教育を受けたことのない祖父に、教えられることなどあろうはずはなく、どこからか手に入れてきた本や玩具、はては新聞・雑誌などを与えていたらしい。
驚いたことに、幼児期は別として、玩具の類にはほとんど目もくれず、雑誌・新聞等で独学したものか書籍類などはその殆どを理解し、次々と新しい書籍を欲しがったとのこと。
さすがに祖父も尋常ではないと、村長に相談したらしい。
およそ一か月後、タンザニア政府から連絡があり、ミランダをダルエスサラーム大学へ預けることになったという。
ひとあたりミランダの生い立ちを話した祖父は、ミランダのことをくれぐれも宜しくとカチンスキの手を強く握り涙ながらに頭を下げた。
その後、ハルムに送られて村へ帰って行った。
村から戻ったミランダは何かまた一段と成長したしたように見うけられる。
容姿ではない。まとっている雰囲気がである。もちろんあの光背は無い。

第九章
カチンスキ
カチンスキ一行はダルエスサラーム大学の研究室にいる。
「ふーん、結構広くて立派なんだ・・・」
その一角に額縁写真がずらりと飾られている。
エミリは順に見て行く。
皆それなりに老人なのだが、一枚だけ若者の写真がある。
「これ、だれですか?」
側にいる年配の研究員に尋ねてみると
「まっ、この子ったら・・・」と笑う。
「カチンスキ博士ですよ」
「へーっ・・・変われば変わるもんだ」
数年前、カチンスキはエミリに聞いたことがある。
「エミリ、私は鶏に似てるかね?」
「えっ、どうしてですか?」
「今朝、車で信号待ちをしている時、隣に車の窓から子供が、
「あっ、ケンタッキーチキンのお爺さんだ!」と言われたんだ。
エミリはゲラゲラと笑った。
確かに似ている。白い髭をたくわえ太っている。おまけに眼鏡まで掛けているのである。
「博士は、この写真とは全く別人、なんといってもスマート過ぎるわ」
エミリは笑いながら次の写真を見ようとした瞬間、突然思い出した。
「ママぁ、このペンダントロケットの写真は誰なの?」
「これは、エミリのパパよ。ハンサムでしょ」笑顔の写真だった。
今、目の前にあるカチンスキの写真は笑ってない。が、間違いない。
母に見せられた写真と同一人物である。何よりもエミリの直感がそう言っている。
年配の研究員は懐かしそうに・・・
「博士の若い時は、それはもうハンサムでユーモアもあったわぁ」
「実はねえ、私も口説かれるのを待ってたの。
ところがねえ、今のぐうたらのばか亭主と間違いを起こしちゃって・・・」
と延々早口で喋り続けるが、エミリはすでに聴いてない。
「雲の上のパパ・・・」
ダルエスサラーム大学で、ミランダは毎日、自発的に講義を聴き、あらゆるゼミナールに参加している。
「エミリ、結果は出たかね?」
「はい、先生の予測通りです」
「ウィルスは検出されたんだね」
「はい、同種のものだと思われます」
つまり、こうである。
数十万年に一定期間、泉の温度がウィルス生存の最適温度になり、それが奇跡的に人体に取り込まれる。
そしてそれは人類の進化に考えられないような影響を及ぼす。しかも、そのウィルスにとって、その事のみが与えられた使命としか思えないのである。
人類(ホモ サピエンス)には未だに解明されていない進化の過程がある。
何故、四足歩行を止め、安全なジャングルを出たのか?
直立二足歩行は走るのが遅く、草原では肉食獣に捕捉される危険性が高い。
何故、近縁種(ネアンデルタール人・デニソワ人等)は全て絶滅しホモサピエンスのみが生き残ったのか?
何故、最も後発のホモサピエンスはアフリカで誕生し、肉食動物を凌駕し食物連鎖の頂点に立つ事が出来たのか?
何十万年も前からアフリカにしか存在しないウィルス・・・そのウィルスが人類の進化を促し、脳活動の劇的進化を助長した・・・そう考えれば納得が出来る。
全ての自然条件がアフリカでしか揃わなかった・・・そこまで考えた時、
「パパ!」
その言葉にカチンスキは我に返った。エミリだった。
「気付いていたのか?」
「太り過ぎて分からなかったわ・・・」
エミリは涙ぐんでいる。
「すまなかった・・・」
カチンスキは、言葉が見つからず、涙が溢れるばかりだった。

第十章
発信
「ねえ、ミランダ、地球温暖化についてどう思う?」と、エミリ。
「うーん、今から約四十億年前地球上に生命体が誕生して以来、あらゆる天変地異を経て、寒冷期(氷河期)、温暖期を繰り返しているの。地磁気も今分かっているだけでも十数回逆転しているのよ。地球環境に大きな影響を及ぼす可能性があるわ。
温暖化のみを考えていては何の解決にもつながらないわ。おそらく地球は温暖期に入ろうとしてるのだと思う。
ただ、今、人類がやっていることは大いに地球環境を悪化させていることは事実ね・・・
私も何とかしようと思っているわ」
「聞いた私が馬鹿だった」
ミランダは「私も何とかしようと思っているわ」と言う。
エミリは、その言葉を笑えなかった。ミランダの眼は本気なのである。
ミランダはインターネット上に驚異的なスピードで発信し始めた。
最初は、老若男女、誰を対象にしているのか判然としないものだったが、一度読むと、どういう訳かすらすらと読むことができ、驚き、感心し、感動し、最後は涙するような内容になっている。
そして、その文章は
「アイ ラブ ユー ミランダ」で終わる。
それが、やがて読み手を意識したものになる。
男性、女性、さらに、老、若、政治家、学者、医者、軍人、農、工業従事者・・・留まることを知らない。特別にタイトルに、それを掲げているわけではない。読者も、それを微塵も感じることは無いであろう。しかし、それぞれの立場で心にせまってくる衝撃が違うのである。
カチンスキは最初から感ずるところがあり、それを体系的に整理し、いつでも書籍として出版できるよう指示している。中間報告で、既に数千ページになっているらしい。
ミランダは英語で発信しているが、カチンスキは地球上で使用されている言葉のほとんどに翻訳させ発信させた。
こういった思想的なものについては、各国当局の監視対象になり、ネット上から抹消されるのが普通であるが、不思議とそうはならなかった。
時間が経過するにつれ、各国メディアがそろって取り上げ、出版依頼が殺到した。
カチンスキはミランダと話し合い、余計な解説、解釈等々を加えないことを条件に、厳重な契約書を作成し許可した。
独占契約ではないので、各出版社は装丁などを凝らし出版した。
一巻を千ページ程度になるよう設定し、既に十巻を越えている。
何と発売即完売といった有様である。
その内容は、まさに筆舌に尽くしがたい、読む人の魂の琴線にふれ、心が洗われ、いつまでも余韻が残るのである。説教じみたところは微塵もなく、ただひたすら心の内に入って来るというものである。
「奇跡の書」
「未来に向けて人類の大いなる遺産」
「聖書以来の奇跡」・・・
各国メディアの見出しである。
それに歩調を合わせるように、各国政府は、その解釈をめぐって研究機関を設ける・・・
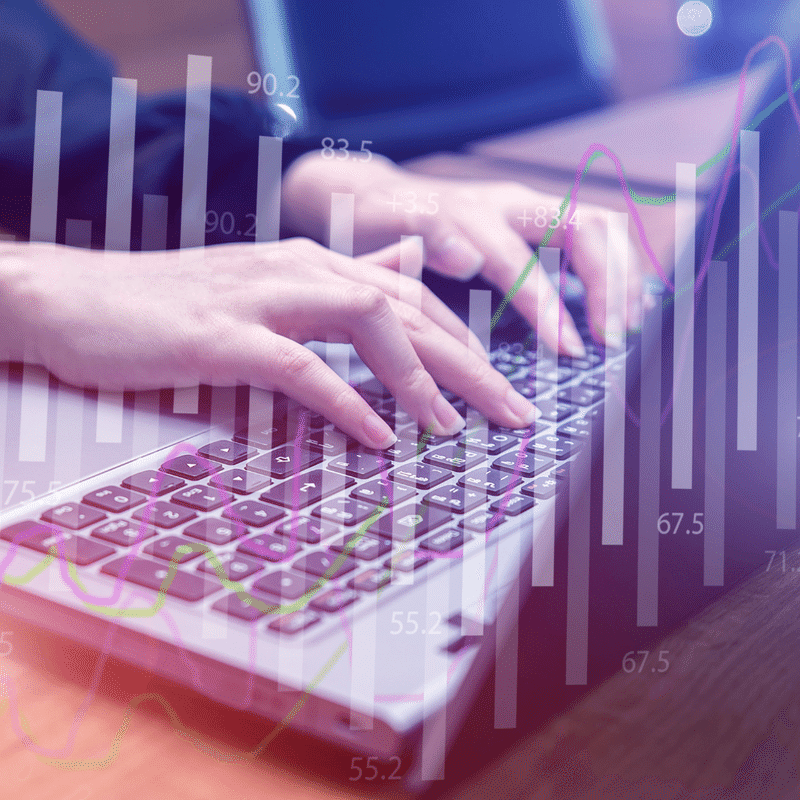
第十一章
覚醒
ミランダの発信により、世界各地で予想だにしなかった現象が起こり始めた。
宗教色の強い国での服装、礼拝といったものが極めてゆるやかになり、社会主義傾向の強い国はより民主的に、行き過ぎた保守的傾向のつよい国は徐々にその流れが変わってきたのである。
もともと国家統制の重要なツールとしての意味合いが強い宗教観は、既に現代人にとってかなり形骸化していた。
ミランダの発信は、単にそういった動きのきっかけになっただけなのかもしれないが、そのような端緒はそうあるものではない。
不思議なことに、原理主義者から反発的ムーブメントは起きていない。
文明というものが世界に誕生して以来五千年。この間、神、預言者と云われる聖人が数名登場している。ミランダは現代における預言者(神の声を代弁する者)になるのではないか。
カチンスキは、そう信じている。
一神教世界において、その宗教観は、もはや日本における多神教のそれとそう変わらない寛容さを示すようになってきている。
民族意識についてもしかりであるが、国家施政の瑕疵を覆い隠すための民族意識発揚には、少なからず辟易している者は多い。
確実に世界は変わりつつある・・・
カチンスキは数千年に一度あるかどうかというこの時期に、自分が生きていることに対して、震えるような思いを禁じ得ないのである。
民族、宗教への迫害、それに伴うジェノサイド。異常気象による災害、飢饉・・・
地球を覆うこのような現状をミランダの発信は大規模な森林火災を霧で消すかのように静かに、確実に浸透していくのである。
大国による威圧的外交姿勢も、カチンスキには変化の兆しが感じられる。
「人類の覚醒?・・・」
カチンスキは備忘録の隅に、そう書いてペンを置いた。

第十二章
光明
「先生!」とエミリ。やはり研究所で「パパ」は憚られる。
「ミランダは大丈夫かしら」
「相変わらずなのか?」
「睡眠と食事、それに僅かばかりの散歩は私が強制的にとらせているけど・・・」
「定期診断の結果は異常ないかね」
「幸い、それは異常ありません」
「なら、このまま様子を見よう」
ミランダの執筆、否、発信作業は当に寝食を忘れるという状態である。
時の経過と共に、世の中の劇的といってもよい変化を各メディアが連日のように伝える。
宗教指導者による国家支配が終わり、政権が人民に移行する。それも革命ではなく極めて自然にである。同じようにイデオロギーによる一党独裁政権も終焉を迎える。
実は各国における軍隊は対外的なもの、つまり自国民を守るべきものであるはずだが、その実態は往々にして自国民の統制のための暴力装置としての性格をも有する。
ミランダの発信により、いつの間にか各国の軍部が国家維持のための暴力装置ではなくなったのである。こうなると独裁政権は維持できない。実はあっけないくらい脆いものなのである。
人類は間違いなく進化しようとしている。
カチンスキは確信した。
やっと、AIの進歩に人類が追いつき始めた。
後世、この変化は人類史の上でも特筆されるであろう。
直立二足歩行
道具(石器)の使用
火の使用
言語の使用
文字の使用・・・等々のように・・・
しかし、これらの進化過程の後ろには常に戦争が付きまとっている。
その破滅的大量殺戮(ジェノサイド)の歴史は、まるでその時々の食糧調達能力と総人口のバランスをとっているかのように見える。事実、そういう学説すら存在していたらしい。
ミランダの発信は、戦争と共に歴史を刻んできた人類の大きなターニングポイントになるのではないか。
いや、そうあって欲しいととカチンスキは願わずにいられない。
この変化に人類の未来に一筋の光明を見い出す思いなのである。
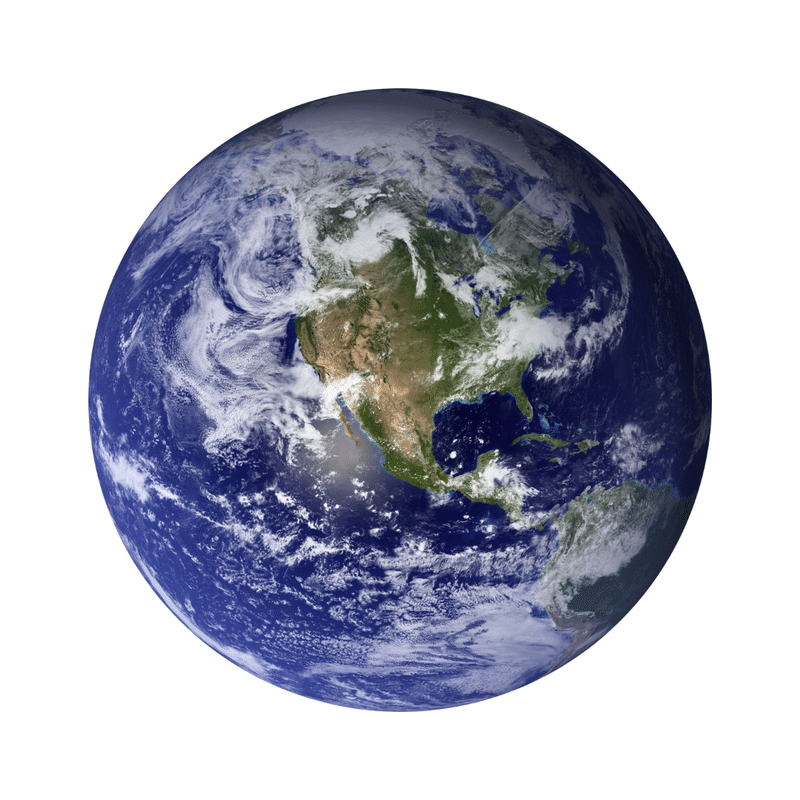
最終章
未来へ
ミランダの発信ペースが尋常ではなくなっている。何かに追い立てられているようですらある。
「先生、ミランダが一日に一回食事をとるだけになりました。散歩もしません」
という報告をカチンスキは何度か受けている。
エミリはミランダに諭すように、散歩、食事をきちんと摂るように言うのだが、その都度ミランダは微笑み「私は大丈夫」と応えるらしい。
エミリはミランダの身が心配で堪らないのだが、あの澄み切った目で見つめらると、そんな心配が自分自身の心の安寧の為ではないのかと自問せずにはいられない。
既にミランダの発信は書籍にして、一巻約千ページ、二十巻にも及んでいる。
ミランダは時折、カチンスキ、エミリをはじめ研究所の所員を集めて発信内容の補足説明をするのだが、その容姿は回を重ねるごとに衰えていく。
しかし、そのことを忘れさせるほどの神々しさがある。
ある者は両手で胸を抱き、またある者は合掌する。
世界中の知識人が集められたこの研究所で、真の意味で神の存在を信じている者は、ほぼ居ない。
にも拘らず、ミランダに神めいたものを肌で感ずるのである。
人間は自分の能力では理解できないことに接したときに畏怖する。
ミランダの七歳の誕生日に、研究所をあげて、お祝いをしょうということになった。
メインホールに集まった多くの研究者を前にミランダは演壇に立った。
全員が、ミランダの発言に固唾を飲み注視する。
しかし、ミランダは何も喋らなかった。ただ微笑むのみなのである。
どれくらいの時間そのようにしていただろうか・・・
ミランダの姿が霞んでくる。参加者全員に何かこみ上げてくるものがあり、涙が溢れ出て止まらないのである。
その時、ミランダの周りに光背が現れる。初めはうっすらと・・・
やがて、それが眩いほどになった時、ミランダは崩れ落ちそうになった・・・
側にいたカチンスキがかろうじて支える。
その顔は少し微笑みをを浮かべている・・・が、呼吸はしていない。
カチンスキは反射的に手首の脈を診るが、首を横に振る。
エミリは、堰を切ったようにこみ上げてくる感情をどうすることも出来なかった。
辺りを憚ることなく号泣した。
この子は父母の顔を知ることなく、その愛情も知らず、甘えることすら知らず、
わずか七歳で生涯を終えようとしている。
人類を混迷から救うためだけに生まれてきたのかと思うと、胸を締め付けられるような思いにかられるのである。
カチンスキも溢れ出る涙を拭おうともしなかった。
そして、ミランダ、エミリを抱きしめ・・・
「ミランダありがとう。もうゆっくり休んでいいんだよ。
エミリ、これは終わりじゃないんだ。アフリカで飢餓と貧困の為に亡くなっている多くの子供たちが、ミランダのおかげで救われる。
その中にミランダのような子供がまた出てくるだろう・・・
私たち親子にはまだまだすべきことがあるんだ・・・」
と、言いたかったが言葉にならなかった。
完

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
