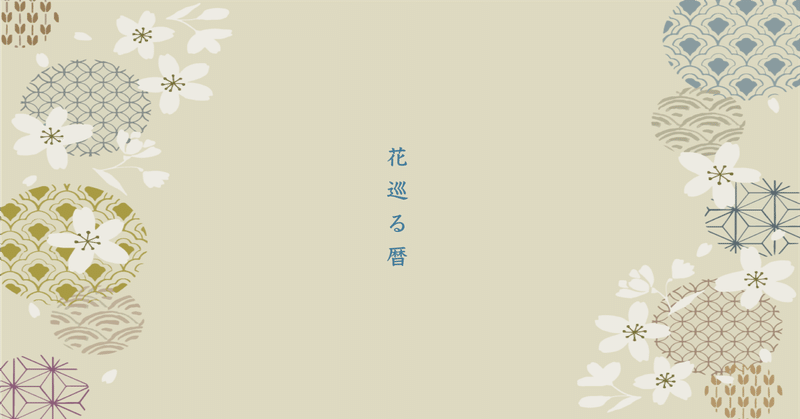
第二話 鹿肉蔦木喰 ―もみじつたきばむ― (四)
<全十三話> <一> <二> <三> <四> <五> <六> <七> <八> <九> <十> <十一> <十二> <十三>
<四>
一夜が明け、咲保は身体をゆすられる感触に目を覚ました。障子紙を透ける光はすでに明るい。
「お嬢さま、朝です。いい加減、お起きになって下さい」
「まるお? おはよう……雨戸、開けてくれたのね」
寝坊をしてしまったようだ。
「はい。数日、慣れないことをなさったせいでしょう。真夜中に、呆け狐の訪いもあったみたいですしね」
「……まるお、口が悪い」
「奥様も、今朝はゆっくりでいいとおっしゃってましたが、寝すぎですよ。みなさん、すでに朝餉も済ませておいでです」
「ああ、もうそんな時間……」
鐘の音も聞こえなかった。上半身を起こし、大きな欠伸は手で隠した。背中側が強張っている割に、全身にふわふわした感じがあって、どこか頼りない気分だ。
「お布団を干しますから、起きてお着替えなすって下さいまし。朝餉もお持ちしましたので、こちらでお召し上がりを」
「……ありがとう」
「それと、栗が揃いましたのでお持ちしました。今年は、昨年に比べてやや小振りですが、味は悪くないと思います」
「ありがとう。助かるわ。どこにあるの? 見てみたいわ」
「厨にございますが、こちらにお持ちしますか?」
「いいわ。後で見に行くから。今日は水に浸けて、甘露煮にするのは明日でいいかしらね」
「悪いものは、予め避けてありますよ」
「そうだろうけれど、中に虫がいるかもしれないでしょ」
それに、とどこかそわそわとした雰囲気のまるおを見上げて言った。
「早めに作ってしまうと、みんながつまみ食いして、また足りなくなっちゃうわ」
咲保が姉の知流耶から引き継いで、本格的に亥の子餅の下拵えを担当するようになったのは、ここ三年ばかりのことだが、一昨年にそういうことがあった。弟妹たちが食べたがっただけでなく、全員が味見と称して、一つ、二つと、保存していた容器から咲保の知らぬ間にくすねていった。そして、当日の朝には、半分ほどの量に減っていたのには驚いた。幸い、栗は大きめであったから、餅には丸ごとひとつ入れていたものを半分に割って使うことで間に合わせた、という事があったのだ。それを踏まえて、昨年は量を多くしたのだが、やはり、半分までとはならなかったが、四分の一ほどがいつの間にか減っていた。木栖家の者は概して甘党だが、甘さの基準も厳しいため、喜んでいいやら悲しんでいいやらだ。
「お嬢さまが、あまりにお上手でらっしゃるから」
「あら、ありがと」
しゅんとして答えるまるおに、咲保は笑った。
「誰でもひとつぐらいは取り柄があるものよね。でも、今年は前日に作ることにするわ。日持ちするものだから、今日、出来た方が楽で良いのだけれど」
小豆餡も作らねばならない。とにかく量が多いし、他の豆ほどではないが、下茹でなどに時間がかかる。食事用の鍋や釜との兼ね合いもあって、邪魔にならない前日の、夕食の片付けを終えた後に作るのが常だ。夏と違って、すぐに駄目になることはないが、なるべく食べる時に近い時間で作った方がいい。
(でも、どうしようかしら……)
美味しい旬のものを食べたい気持ちはわかるし、当然だ。できれば、つまみ食いなどでなく、ちゃんとした料理として家族に食べてもらいたい。
(別で買ってきて、おやつ用に別で作った方がいいのかしら? 栗ご飯とかもいいわね……)
ふむ、と考えながら、咲保は支度を済ませると、まるおが運んできた朝食に向かう。ご飯とお味噌汁と卵焼き。お漬物と昨夜の煮物の残りだ。少し冷めてはいるが、いつも通りの母の味だ。
(今日と明日、いつ何をするかを決めないとね……そうだ、茉莉花さんにお渡しする分もあったわ)
まずは、栗をどうするか、だ。咲保は急いで朝食を食べ切ると、片付けついでに厨房に向かった。
(確かに小振りだけれど、包むにはちょうど良さそう。艶々していて美味しそうだわ……いくつあるのかしら?)
咲保は、竹製の背負籠いっぱいに入った栗を眺めながら考える。確実に百個以上はありそうだが、見ただけで足りるかどうかは判断がつかなかった。多い分には構わないが、少ないのは困る。縁起物だけに、食べ損なう者がいるのは、かえって良くない。とりあえず、数えながら水に浸けていこうと思う。
まずは洗い物を終え、片付けてから、桶をふたつ用意して、その中に数えながら栗を放り込んでいく。
(二、四、六、八……)
途中、じゃれついてきたみぃに邪魔をされて数え直しがあったが、栗は全部で百五十六個あった。
(微妙な数ね……)
餅の数には足りるが、煮崩れしたりつまみ食いの数を想定すると、やや足りない気がする。皮を剥いてみて、はじめて痛んでいることに気付くものもある。来るモノの数も、年々違っている。やはり、おやつ分は別に買い足した方が良さそうだ。
(もう一度、他の材料が足りるか確認してから、買いに行きましょう)
二つの桶に水をたっぷりと入れて栗を沈めると、日常の午前の仕事をするために離れに戻った。
咲保が近所に買い物に出ている間、頼んであった桐眞の新しい火鉢が届いたそうだ。まるおの薦めにしたがって選んだ、ありきたりのよくある角火鉢だが、それを見た磐雄が、「僕もあんなのが良かった」とまた騒ぎ始めて母を怒らせた、と帰ってくるなり瑞波から告げ口があった。
「磐雄には困ったもんどす。人の花が赤う見えて仕方ない年頃なんやろけど、かないませんわ」
ひとしきり磐雄を叱って疲れたのか、母はため息を溢した。叱られた磐雄は、部屋に閉じこもったきり、夕食の時間になっても出てこない。せっかく栗ご飯を作ったのに、食べてもらえないのは寂しい。ほかの家族も、「美味しい」と言いつつも、あまり美味しそうに食べているようには見えない。がっかりだ。
「反抗期というやつでしょう。何年かすれば、他人の持っている物を羨んでも、何の意味もないことに気づきますよ」
珍しく、桐眞がそんな慰めを口にした。
「せやかて、あんたも知流耶もやけど、そういうことはなかった思いますけれどな」
「まあ、僕らはそれどころじゃなかったですから。けれど、普通にありましたよ。磐雄とは出方がちがっていただけで」
「そうでした?」
「稽古が厳しかったせいで、そっちで発散していた分が大きかったかな。知流耶姉さんもそうでしょう」
「ああ、あんたたちのことは、お祖父はんたちに、随分とお世話になったもんなぁ」
二人の会話に、咲保は黙って俯くしかなかった。咲保の世話だけで両親は手一杯だったため、兄と姉は子どもの頃、輝陽にいる祖父母に預けられていた時期があった。学校が始まりこちらに戻ったその後も、毎日、往復をしていたものだ。一人、瑞波だけが、わからないという顔をしている。
「桐眞兄さまと知流耶姉さまは、お祖父さまとお祖母さまにお稽古をつけて貰ったの?」
「そうどす。尋常小学校から中学校までは、こっちと行ったり来たりやったんえ」
「えぇ、いいなぁ。わたしも行きたい」
「おまえが行っても、一日で泣いて帰ってくるのがおちだ」
「そんなことない。お祖父さまは、お祖母さまも、瑞波にすごく優しいもん!」
「そりゃあ、普段はな。一旦、稽古となると鬼だぞ、鬼」
「えー」
「それに、毎日『あわいの道』を使ての往復や。瑞波は『あわいの道』の一人で通うんはまだ早いし、嫌いおますやろ」
「や。『あわいの道』は怖いもの。物の怪に会ったら、連れて行かれちゃうんでしょ。陸蒸気ではだめなの?」
「ほんなん行くだけで、一日かかりますえ。行って帰って、最低でも三日かかりますわ。切符代が高うて、とてもやないけど毎日は無理ですわ」
「陸蒸気に乗ってみたいのに……」
咲保は、祖父母に稽古をつけて貰ったことなどなく、実際のところ、祖父母が厳しかったのは、跡取りと外に出す娘だからというだけでなく、二人の才を見込んでのことだったのだろうと、咲保は思う。
