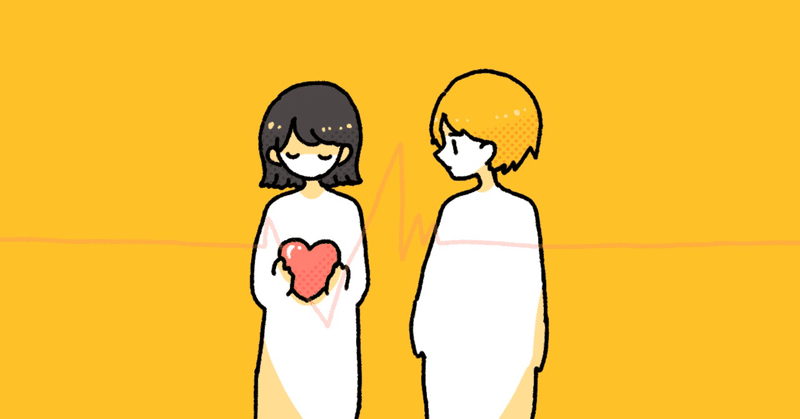
藤本タツキ「ファイアパンチ」 生きる意味を外部にしか持てないなら
あなたは生きる意味を必要とする人でしょうか?
この記事は、藤本タツキ「ファイアパンチ」3巻までの内容を含みます。3巻までは序章ですし、この漫画はネタバレが重要な作品ではないと思いますが、ネタバレが嫌いな方はご注意ください。
また序章までしか触れていないので、読んだことのない方や途中でやめてしまった方が読む機会になってくれたら嬉しく思います。
少し長い前置き
私はある時期から、生きていくために、自分の生を肯定する何かを必要とするようになりました。その "何か" はきっと人によって違っていて、恋人や家族などの人間関係であったり、目標の実現や課題の解決であったり、生き方そのものであったりいろいろだと思います。あるいは上橋菜穂子さんの小説のような(?)、あらゆる生命はただ受動的に "生まれ" てくるだけであり、生きる理由などは存在しない、けれどこの世は美しく、生きていたいと思う、といった形の、生きる意味を否定したところから出発する生の肯定もあると思います。
様々な角度からの生きる理由を持っていた方が個人として強いのでしょう。生きる理由を他者に委ねることが不安定であると知りつつ、私は生きる理由を他者にしか求められない人間でした。どんなに他の部分で人生を充実させても誰かを愛していたい、愛されていたい。だから金原ひとみさん、モラヴィアやアゴタ・クリストフ、中村文則といった小説家たちの文章に救われてきたのだと思います。喪失や別離の深い悲しみに接してなお一切の救済を拒否する、この世界には一生かけても立ち直れない悲しみが存在するのだと、だから立ち直らずに傷を引きずりながら死んだように一生を生きていったっていいじゃないかと全身で主張しているような登場人物たちに。
単なる復讐劇ではない
藤本タツキの「ファイアパンチ」という漫画は、一見すると故郷と大切な人を理不尽に焼かれ、唯一生き残った主人公が仇に復習するという王道の復讐劇として幕を開ける。一方で、わたしの長い前置きのせいで誤解してほしくないのだが、私はこの漫画の主人公の、悲しみを克服できずにどうしようもなく復讐に走るさまに共感、、、したわけではない。そもそも ”一見” 王道の復讐劇、と書いたように、この漫画はそういう話として描かれていない。私の長い前置きが活きてくる(と願っている…)のは記事の後半になるので、まずは序章(1~3巻/全8巻)のみの展開について語ってみたい。
小気味のいいテンポと見事な構成
序章で印象的なのが、漫画の中で自称映画監督を名乗るトガタが主人公アグニを主人公として映画を撮っている点だ。これにより、シリアスな復讐劇になるはずが、その展開そのものを横で撮影している人がいるせいで読者は一歩引いた図を見せられることになる。加えてこのトガタがいちいち展開にメタ的な茶々を入れるので、どうしようもなく展開が芯からの復讐劇にならない。例えば敵の兵士が戦闘の構えに入って仇討ちを誓っているのに、対するトガタが「いつまでその恰好してんの」「さっき戦ったやつと同じ能力かよ!被ってるよ~ダメダメ」「見てる人が退屈するでしょーが!」などと好き放題言う。果てはカット!といってコマがブラックアウトし、次のコマでは相手がボロボロにやられている。藤本タツキ独特の小気味よい展開の進行とせりふ回しが本当に気持ちいい部分である。
一方で撮影を嫌がる主人公に映画の演技として「あいつに復讐するためならなんでもする!」といったセリフを言わせて撮影するため、常に復讐という選択肢そのものが相対化される。つまり純粋な復讐劇の体を纏っていた初期では復讐は生きる意味(妹)を失った主人公にとっての新たな生きる意味なのだが、映画撮影の演出が入るその後の進行によって、主人公の生きる意味が徐々に「彼の選択による任意のもの」「演じられたもの」という要素を纏ってくる。
同時にこうした演技性、すなわち復讐のために生きているのではなく生きるために復讐しているのだという倒錯が、主人公の潜在意識にも自覚されていることを示唆する描写もはさんでいく。
極めつけには復讐劇に必須の悪役がすでに牙が抜け、仇を討つに足らなくなっているという事実も展開の早期から主人公と読者に見せることで、単純な「悪に対する(ダーク)ヒーロー」という復讐劇の図式が成り立たなくなっていることも早くに開示する。ちなみに次なる仇の候補としては世界を氷で埋めた氷の女王がいるのだが、これは帝国が民衆支配のために用意した仮想敵であったことが明かされるし、では民衆を欺いた支配者はというと、こちらも国を背負う重責に耐えきれず死にたがっており、やはり敵たりえない。
序章の、一歩引いた構図を作るもの
以上のように、
「生きる目的」の相対化(任意性、演技性)
主人公自身による欺瞞の自覚
「正義 vs 悪」の構造の破壊
という3点が見事に同時進行しつつ、非常に心地よいテンポでストーリーは進んでいく。そして王道の復讐劇から一歩引き、対立構造も崩れてしまっているために半ば浮遊したような浮動感(作者の作風の魅力でもあり、フワフワしていてわかりにくいと批判されるゆえんでもあろうか)が続く一方で、ずっと展開に茶々を入れていたトガタが展開の盛り上がりにつれ、映画の演出から手を引く。そして演出がないほうが面白くなりそうだと言い、どうやら冷やかし気味の序章が終わって本編が動き出しそうな予感を与えるのである。
序章のおわり、そして新章へ
3巻の終わり、ついにアグニは帝国の支配者と対峙する。といってもこいつも死にたがってるし、アンチテーゼを欠いたままのヒーローものはこの先どうなるんだろう、、、と思っていた矢先、唐突にフードを被った第三者が現れて支配者の首を落とし、自分は存在しないはずの氷の女王だと名乗る。
おおお、やっと戦うべき敵登場!ようやくここで本流の(二項対立的な)ダークヒーローアクションがはじまるのか...!?というところで序章が終了し、新章開幕となる。文章だけでは伝わりにくいのだが、なかなか熱い展開である。
まとめ
序章についてまとめておくと、
アグニが持ち得た唯一の生きる意味は妹の幸福だけであり、その妹に死なれた彼にもはや生きる意味は持ちようがなかった
しかしその妹に、死に際に「生きて」と言われたアグニは自己を欺いてでも生きねばならず、そのために復讐という「生きる目的」を選択した
彼の欺瞞とは、本当は "生きるために" 復讐をしているのに、復讐のために生きているという演技をしていることである。
復讐を誓った主人公の仇が相対化され敵たり得なくなること、復讐という目的は倒錯・自己韜晦に過ぎなかったことなど、いずれにカタルシスを置いてもよさそうだが、作者はそうしない。むしろ積極的にそれらを事前に開示して反復することで、とうに生きる目的を喪失している主人公に、お前はどうやって生きるんだと執拗に問い続ける。それはいわば自分の外部にしか生きる目的を持てなかった人間に対する試練であり問いである。
以上で序章までのお話は終わる。生きる目的は任意のものだ、という考え方は自分がいつからか持つようになった考え方だ。(大岡昇平「野火」、カミュ「異邦人」あたりの影響があるかもしれない。)何としてもまず人は生きなくてはいけなくて、だからそのために必要なら人は生きる目的をひねり出さなくてはならない。一方で同じ時期に、それでも自分は人を愛することの中にしかそれを見つけられないことにも気づかされていった。どうしようもなく自分の外部にしか生きる理由を見出せないなら?それでも生きねばならないとしたら?そうやって読むとアグニの苦しみを一段上の層から見ることができるのではないだろうか。
多くの読みどころ
新章では自覚的に欺瞞を続けるアグニに、作者は徹底的に敵を与えて "あげない" ことで彼に生きる意味の探求を強い続けます。生きることそのものが究極的な目的であるゆえに、「生きる理由」「~のために生きる」という言葉が本質的に持つ欺瞞、それゆえおそらく誰もが持つことになる人生における演技性。そのほかこの記事では触れなかった、容姿が自己定義や他者に与える影響、信仰による生きる目的の外部化とその危うさ、その一方での宗教のもつ秩序の形成や救い、道徳に反してでも生きるべきかという問いと一つのアプローチ、教養と想像力など、多くの読みどころがあります。
藤本タツキといえばチェンソーマンが有名ですが、私はチェンソーマンがあまり刺さらなかった人間でした。一方、ファイヤパンチは記事を書かずにはいられなかったくらい、自分に何かを訴えかける作品でした。
賛否が別れている作品のようですが、私はすごく好きです。この記事を読んで興味を持っていただけた方がいたら嬉しく思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
