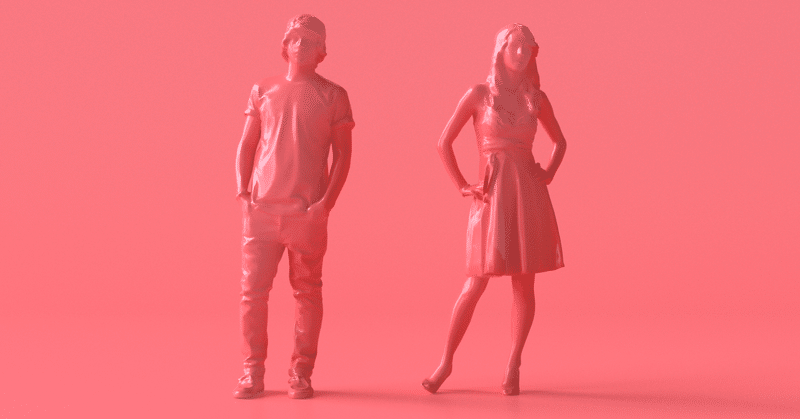
保守からみたフェミニズムの問題点〜『フェミニズムの害毒』を読んで〜
男性の中には、「フェミニズムなんて少数のヒステリー女性のもので、たいした影響力はないよ」と思っている者もかなりいるようである。しかし、それは現実を知らない楽天主義である。今の若い女性たちは、母親から、女性教師から、友達から、「働け」イデオロギーをはじめとするフェミニズムをシャワーのごとく浴びせられて育っているのである。そしてマスコミと地方自治体の多くの部署はすでにフェミニストに占領されてしまっている。それも間違った公式に毒されたフェミニストによって。
林道義著「フェミニズムの害毒」ですが、今(令和6年)から20年以上前に書かれた本です。しかし、全く古い感じがせずに、現在にも通じるフェミニズムに対する問題提起をしていると感じたので、紹介したいと思います。
この記事は全文無料で読めます。
著者の林道義氏について
著者である林道義氏は経済学者・心理学研究者(ユング心理学)です。大学在学中は学生運動に参加するなど左派的な考えを持っていましたが、その後、保守的な考えに変わったそうです。『フェミニズムの害毒』も保守側の観点から書かれたものです。
本の表紙そでにも“世のタブーを破って、フェミニズムの害毒を果敢に暴き出す問題の書!”と書かれています。初版が発行されたのが1999年ですから、まさにフェミニズムが世を席巻している時にこのような本は御法度であったのでしょう。
事実、本書の中で林氏はこう述べています。
今の論壇でフェミニズムを批判する事はご法度である。それは猫の首に鈴をつけに行くようなもので、誰もそんな怖いことに手を出すそうとはしない。私と対談したある政治家は言った。「先生、ぜひフェミニズム批判をしてください。私ら政治家はできないんです。女性票を失ったら、すぐ落選ですから」。女性に媚びるエッセイストや評論家が新聞や雑誌で幅を聞かせる世の中である。「女性の味方」のような顔をする時代である。
以上のように、政治家ですらフェミニズムに批判的なことは表立って発言できない状況であったそうです。
本書では、保守の立場から家族を破壊し専業主婦を毀損し母性を否定するフェミニズムやフェミニストを手厳しく批判しています。以下に要約していきたいと思います。
家族を破壊するフェミニズム
林氏は、フェミニズムの重大な害毒の一つが、健全な家族を否定し、不健全な個人主義を振りまくことであるとしています。
近代家族を否定するフェミニズム
フェミニズム系統の家族論は、そのほとんどが、「近代家族」批判であると林氏は主張します。
「近代家族批判」が、絶対的なものではなく、歴史の中の相対的なものに過ぎないことなど、歴史的な見方をするものにとっては当たり前のことであり、いまさらこと新しく騒ぎ立てるほどのことではない。それを鬼の首でも取ったように言いたてるのは、「近代家族」が女性を抑圧するものだと言う認識に基づいている。だから「近代家族」を相対化することでその価値を低下させ、そうすることで「近代家族」を解体することがフェミニストたちの目標となるのである。
林氏は、「近代家族」はかならずしも女性を差別したり、抑圧しているわけではないと主張します。現に『朝日新聞』の特集の「主婦の憂うつ」という特集においても、「専業主婦で幸せだ」という投書が(朝日新聞側の思惑に反して)殺到したそうですし、林氏が講演会において既婚の女性たちに質問すると「専業主婦でよかった」が半数なのに比べて、「悪かった」が少数だったそうです。
さらに林氏は、フェミニズムの唱える「多様な家族」論を批判します。同性愛者のカップル、事実婚のカップル、子供が大人になっても家にいる大人家族、父親のいないシングル・マザーの家族などをフェミニスト達は「新しい家族」として称揚します。しかし、林氏はフェミニストがもちだすそれらの「新しい家族」はすべて「近代家族」の変種にすぎないと断言します。
「近代家族」が父母子を中核にして、その愛情的な絆によって成り立つものと定義すれば、離婚家族もシングル・マザーも大人家族も、「近代家族」のいずれかの要素(父か母か子)が欠けた変種であることがわかる。またゲイや事実婚のカップルは、「愛情によって結ばれる平等なカップル」と言う原理を純粋に追求した結果であり、「近代家族」の理念の一側面を具象化したものに過ぎない。
「近代家族」に期待されている機能とは、子供を愛情を持って健全に育てるという機能であると林氏は述べます。もちろん、子供の教育は家族にだけ委ねられているのではありません。子供の教育は、家族、親族、地域共同体、学校、社会全体などの多くの同心円の重なりによってなされることが期待はされていると林氏は補足します。しかし、家族はその多くの同心円の中の中核である事は確かです。子供の人格の基礎は、家族の中での父と母と子の協力により、理屈を超えた感覚的な次元の感化よって基本的に決定されるのです。
フェミニスト達は「近代家族」を批判したいがためにやたらと上で述べたような「新しい家族」を称揚します。しかし、そこには子供に対する配慮が欠けているのではないか?と林氏は問うのです。そして、「新しい家族」が「近代家族」の変種でしかなく、さらにそこに家族として大切な要素(父母子)のいずれかが欠けているのであれば、社会を持続させるための重要な要素である「人間の再生産」に重大な支障をきたすのではないか?と危惧するのです。
「働け」イデオロギー
フェミニズムがなぜ「近代家族」を批判するのか?それはフェミニズムが「働けイデオロギー」に毒されているからだと林氏は述べます。
現在のフェミニズムは単線化し、一つの公式にはまっている。すなわち男女平等を妨げているのは女性に経済力がないからだ、したがって女性は働いて経済力をつけなければならない。こうして女性の「働く」ことが何にもまして価値があるという観念が支配することになった。私が命名した「働け」イデオロギーの成立である。
林氏によれば、フェミニズムの「働け」イデオロギーにより、そのために邪魔なものはすべて価値を落とされて捨てられていったそうです。「母親には母性本能がある」「三歳までは母の手で」などは、「母性神話」や「三歳児神話」などの迷信にすぎないとされ、かわりに「社会が育てればよい」と言われるようになった、と林氏は述べます。
フェミニズムはすべてのことを相対化しようとするが、「女性が働く」ことだけは絶対に相対化しようとしないし、専業主婦の価値観だけは認めたがらない、それはなぜか?
フェミニストは実のところ「家族」そのものを否定したいからなのである、と林氏は続けます。
シングル・マザー賞賛はアナーキズム
林氏は本書において、シングル・マザー賞賛はアナーキズムに繋がるとして、精神科医の斎藤学氏のシングル・マザー礼賛を例にとり批判しています。斎藤氏は「家族とは権力機構である」「女と男の関係を愛や性ではなく、権力で言い換えたことがフェミニズムのすごいところ」などと発言していたそうです。
以下に「毎日新聞」のコラムに書かれた、斎藤氏のシングル・マザー礼賛を要約します。
・日本の社会はシングルマザーに過酷すぎる。イギリスやフランス程度の、新生児の母の30%前後がシングルマザーということになれば、現在(平成11年)のような少子化は免れるはず。
・スウェーデンの場合、シングルマザーは性的パートナーを欠いているとは限らない。そして、そのパートナーはこの養育と成長に深い関心を示す男性がほとんどである。
・こうした家族形態が不安定とは限らない。日本では子供は「制度としての家族」を維持するための道具とされてしまう。一方、産みたくて産む母親は、どんな子であれその子の存在を受け入れるはずである。そしてその母のパートナーは、愛する女性の大切な子の「父親」役を喜んで果たすはずである。
これを林氏は、ごまかしレトリックであると一刀両断します。ごまかしの第一は、前者の悪い点、後者のよい点だけを挙げて、後者の方がよいという点で、このような比較をすれば、どんなことでも後者が「よい」ことになってしまいます。
第二のごまかしは、言葉の意味をすりかえてしまうというやり方です。シングル・マザーと聞けば、普通の人々は母親が一人で子供を育てるものだと考えるものですが、斎藤氏は「母親には結婚はしていないがパートナーはいる」、「『制度としての家族制度』を維持するために子供が道具になるよりも、そのようなパートナーがいる方がよい」と言葉の意味をすり替えています。これを聞かされた者は、「事実上の父親(パートナー)も込みでシングル・マザーなのだ」と言いくるめられてしまうのです。
林氏は、シングル・マザーの現実はバラ色ではないと主張します。その生活は孤独であり、経済的に苦しくなにより一人で子育てをしなくてはならない身体的な疲労が苦労があります。さらに、母親のパートナーは、たまに家に訪れるだけで同居しているわけではありません。そんなパートナーに父親役を果たせるだろうか?と林氏は疑問を呈します。
林氏は、シングル・マザーの一番のマイナス点として、父性の欠如を挙げています。シングル・マザーの家庭環境においては子供に秩序感覚やルール感覚が欠けてしまい、人間関係における適切な距離感を身につけられない可能性が高いというのです。
斎藤氏は、一見すると「戸籍上の婚姻にはこだわらないで男女が愛情で結ばれる携帯がよく、そこに血のつながりはなくてもよい」ととれるようなことを書いていますが、これはごまかしであると林氏は主張します。斎藤氏は形式主義を批判しているように見せかけて、実のところ形式そのもの(戸籍制度)を破壊しているのです。その証拠に斎藤氏は次のような発言をしているそうです。
戸籍が幅をきかせているうちは、家族形態の多様化など望むべくもなく、したがって少子化の勢いは止まらない
これはひどいごまかしであると林氏は述べます。「戸籍制度をなくせば、シングル・マザーが子を産み少子化が止まる」というのは、無茶苦茶な論理であり、戸籍制度を「悪」であると強引に結論したいだけであるとします。
斎藤氏のシングル・マザー礼賛の背後には、健全な家族の形式を破壊したいというアナーキーな動機が隠されていると林氏は述べます。シングル・マザーの増大は、制度としての家族を破壊する危険性をはらんでおり、それを礼賛することは一種のアナーキズムであることを適格に見抜いていかなければいけないと警鐘を鳴らすのです。
「フェ理屈」からみるフェミニズム
林氏は、本書において、「フェ理屈」という造語を使い、フェミニストの詭弁を批判します。
フェミニストたちの議論には、すりかえ、屁理屈、詭弁、ごまかしが目立つ。フェミニストが使う屁理屈を私は「フェ理屈」と名づけた。フェ理屈がどの主題に集中しているかを見れば、彼女(彼)らがなにをごまかそうとしているかが明らかになる。フェ理屈は圧倒的に母性問題に集中しているのである。
林氏の提唱する「フェ理屈」を一つ一つ、まとめていきたいと思います。
詭弁を弄する体質
「フェ理屈」の典型的な例として、香山リカ氏の論評を取り上げます。
その論文(本書の一章「理想を失ったフェミニズム」)は、簡単にまとめると以下のような内容でした。
・フェミニズムは「働け」イデオロギーに毒されている
・フェミニストの専業主婦いじめが酷い
・母性は子供にとって大切である
香山氏は毎日新聞にて、この林氏の論文を取り上げてこう述べたそうです。
・社会進出という呪縛から離れることにより主婦たちが「救われる」のか。
・「母性」によりつらい立場に追い込まれる女性、たとえば全人口の10%といわれる不妊症の人々がいるのである。
・「子どもをもつのが当たり前である」という人たちから、不妊症の人たちは今まで不当な扱いを受けてきたのだ。
これに対して、林氏は本書にてこう反論します。
・香山氏は「母性を持つのは当たり前」ということと「子供をもつのが当たり前」ということを簡単にすり替えてしまう。
・不妊症の人は、母性を持っていないわけではなく、ただ子供ができないだけである。不妊症と母性のあるなしとは何の関係もない。
・香山氏は母性を唱えることに反発したい。しかし正面から反論する論拠が見つからない。そこで母性を唱えるとかわいそうな人が出てくると言う言い方で、母性重視に対して間接的にケチをつけている。
・彼女は「母性を持つ」ことと、「子供を持つ」ことを、無理に同一視する。
そして林氏は、「子供をかわいいと思えない母親は、母性信仰によって傷つく。だから、母性神話は良くない」という言い方が、日本中でフェミニストによって繰り返されていることを指摘します。しかし、これもフェ理屈の一種であると断じます。
「子供をかわいいと思えない母親」がいたら、どうしてかわいいと思えなくなったかを調べ研究して、対策を考えるのが正しい対応の仕方である。それを短絡的に「母性を持っているのが当たり前と考えるから傷つくのであって、母性を持っていなくてもいいよと言ってあげればその母親は救われる」と考えるのがフェミニストである。
母性が足りない母親に対して、「母性を持っていなくてもいいよ」と言ってあげれば、その母親は当面気が楽にはなるが、それでは本質的に、母も救われないし、母性不足による子供への被害もなくならない、というのが林氏の主張です。
悪質なフェ理屈の一例
朝日新聞の学芸部記者の杉原里美氏は、東京大学の山崎喜比古助教授らの調査を引き合いに出して、次のように書いたそうです。
・子供と離れる時間をもっている「働く母親」よりも「専業主婦」の方が育児によるストレス値が高く、子供と接するときの心のゆとりがない。
・山崎助教授は「心の健康の上では、育児期にも働いたほうがいい・・・」と指摘する。
林氏は、上記の文章がひどい詭弁であり、そしてどこが詭弁であるかを見抜ける人は少ない、と指摘します。杉原氏の主張をまとめると以下のようになります。
大前提「ストレスは多いほど悪い、少ないほどよい」
小前提「育児によるストレスは、働く母親より専業主婦の方が多い」
結論「よって母親は育児期にも働いた方がいい」
林氏によれば、この中に2カ所、ごまかしが入っているそうです。
まず、最初のごまかしは大前提の中にある、「ストレスは少ないほどよい」です。林氏は適度なストレスならば、全くないよりはあったほうが、その人の向上につながったり、やる気を起こさせる作用をする場合もあると述べます。つまり、この大前提そのものが間違っているのです。
次に小前提です。この命題自体は、大げさな調査をしてみなくても、子供と接する時間が圧倒的に少ない「働く母親」の方がストレスの総量が少ないことぐらい、当たり前のことです。しかし、「働く母親」と「専業主婦」の育児を比較するのならば、なぜストレスの多少だけを比較するのであろうか?と林氏は述べます。
例えば「働く母親」と「専業主婦の母親」とでは、育児による喜びではどちらが上であろうか。子供に対する影響はどうであろうか。こういったいろいろな比較をした上でなければ、育児に対してどちらがよいかを決断することはできないはずである。
(中略)
しかも、結論の中にある「心の健康」とは何かよくわからない。それも「母親の心の健康」しか考えていないで、子供の心については考えられていない。
以上のように、杉原里美氏の論理は、ごまかしを積み重ねることによって、一方的な結論に導く、巧妙に仕組まれた詭弁である、と林氏は述べるのです。
専業主婦は贅沢品?
林氏によれば、フェ理屈は圧倒的に「母性」「主婦」問題について使われている、と述べます。
フェミニストの落合恵美子氏は「今や専業主婦は贅沢品である」と言ったそうです。こう言われると、なんとなく専業主婦と言うものは、時代遅れで不要なものと言う気にさせられてしまうが、この「贅沢品」という言葉は意味不明である、と林氏は述べます。
夫や家族にとって贅沢だと言う意味でなら、それは間違っている。贅沢とは、あまり必要もないのに、いらざることに多大の労力や金品を使うという意味である。家族の命や健康を守り、家計をやりくりし、子供を大切に育てるために、時間や労力を使うことのどこが贅沢なのであろうか。もしそれを贅沢と言うのであれば、それは大変に望ましい贅沢と言うべきである。皆が持つようになるといいなと思える「余裕」と言いかえるべきであろう。
林氏は、フェミニストが「専業主婦は贅沢である」という言い方の中には、「女性が外に出て働くのはたいへんだ」という意味と、「家にいること」への羨ましさが滲み出ている、と述べます。
そして、そんなに羨ましいのであれば、自分が専業主婦になればよい。働くこと、つまり自分が望んだ生き方を選んだのならば、なぜ、他の選択をした人を「贅沢」呼ばわりするのか?それは、弁解のないほどの差別的行為である、と続けます。
「反母性主義」の心理的背景
林氏は、フェ理屈は「母性」問題に集中しているのは、フェミニストにとって「母性」問題がアキレス腱、つまりそこを突かれると一番困る問題であることを示している、と述べます。「母性」は、働く女性にとってもっともふられたくない問題であるそうなのです。
フェミニストたちは、1970年以降のフェミニズムを「第二波フェミニズム」と呼んでいる。それまでの「第一波フェミニズム」が「自然的な母性」(母性本能)を強調する傾向を持っていたのに対して、「母性」が社会的に規定された(作られた)ものであることを強調するのが「第二波フェミニズム」の特徴である。
「第二波フェミニズム」と呼ばれているものは、全共闘運動の中から生まれた思想である。全共闘の女性活動家の中から、全共闘の男性には男女差別があると批判することによって、反体制的なラジカル・フェミニズムが生まれた。彼女らは、全共闘の男性を批判したように見えるけれども、実は根本的なところで、全共闘的な発想を受けついでいる。すなわち、全共闘が東大に代表される学問の階級性を告発し、大学を否定し、大学解体を叫び、あげくのはてに学問そのものを否定したのと同じように、ラジカル・フェミニズムは母性本能が権力に利用されるからといって、母性本能そのものまでも否定するのである
反権力的な視点から見ると、母性を称揚する事は「国家権力の戦争政策に利用された」と見えるらしい、と林氏は述べます。彼女たちにとって母性本能を強調する事は、支配階級の思うつぼになるとのことです。
つまり、全共闘的な「全否定」の発想に従って、母性をとことん否定してき、母親特有の温かさを強調する事は、女性を「母親役割」に閉じ込める支配階級の陰謀とするまでに至ったのが第二波フェミニズムである、と林氏は述べます。
子供にとって母性が大切だということは、誰にとって利用されるとか、誰にとって得かということとは別の問題である。母性を強調すると「さまざな問題を覆い隠す」と言うけれども、母性本能を否定する者たちもまた、母性不足や母性の歪みからくる子供たちの犯罪や心の病と言う問題を「覆い隠」しているのである。
そして林氏は、母性を否定するフェミニストたちは子育てが嫌いで、その営みから逃れたいと思っている、すでに母性が壊れてしまっているものであるとバッサリと切り捨てます。
林氏の唱える「母性本能」
林氏は、フェミニストは「母性本能」について誤解していると説きます。
フェミニストたちの母性本能否定説がなぜ破綻しているかというと、彼女らは「本能でない」と言うときの「本能」を、すべて素朴にも昆虫の本能のものと考えているからである。人間の母性本能は、昆虫の本能のように、いかなる条件の下でも自動的に発動するというものではない。つまり子供が生まれたらいかなる条件のもとでも自動的にかわいいと思うようになり、世話をしたくなる、というものではないのである。
そもそも、本能とは、本能行動を解き放つための条件がととのった時に発現するのであって、人間のように複雑な生き物であれば、その解放条件が複雑になり、またそのための要件や、それを妨害する要件も増えてくると林氏は述べます。
そして、母性本能があることを誰もが疑わない哺乳動物ですら、狭い檻に閉じ込めれば子育てをしなくなる、しかしそれをもってして「母性本能がない」とは言えません。だからこそ、子供を産んでかわいいと思えない母親がいるからといって、「母性は人間の本能ではない」と結論づけるのは、あまりにも短絡的であると林氏は主張します。
「母親に限らずに赤ちゃんと触れ合った経験のある人ほど赤ちゃんに愛情を持ちやすい」ことなど、何も「最新の研究」とやらを持ち出なくても、昔から分かり切ったことであるし、そのことからどうして「母性は本能ではない」という飛躍した結論が出てくるのでしょうか?それはおそらく「学習」と「本能」は対立するものであるという間違った認識があるからだと林氏は述べます。
高等動物の本能の発現は、むしろ学習に支えられているのである。そういうことも考えずに、ともかく、無理矢理にでも母性は本能でないと言いはるのがフェミニストの特徴である。
また、フェミニスト達は「母の愛や献身が全てだと言う社会が子供への虐待と言う悲劇を生む」「良い母親を演じることに疲れた時、虐待が始まる」「母親だけではなく、たくさんの人たちと交流し、豊かな人間関係の中で育っていくことが赤ちゃんにとっても母親にとっても必要なことなのだ」などの主張をしますが、それを林氏は否定します。
まるで「幼児にとって母親が大切」と言うことが、幼児虐待の原因であり、母親よりも多くの人に接することが大切だと言わんばかりである。「愛と献身が母親のあり方だ」ということが、幼児虐待の原因などでは断じてない。またたくさんの人との交わりが幼児にとってプラスの作用をするのは、その前に母親との心の絆がしっかりと結ばれ、そのことによって、人間一般に対する安定した関係が築けるようになっている場合だけである。それを抜きにして、いきなり大勢の人と交われなどと言うのは、幼児の心を知らない暴論というものである。
幼児虐待や育児ノイローゼの根本の原因は母性の喪失であると林氏は述べます。父親の関与がないとか、母親だけが四六時中一緒にいると言う事はそのきっかけにはなりますが、決して根本の原因ではないのです。「幼児虐待の原因をすり替え、母性本能を否定する女性たちは、実は既に母性本能が壊れてしまっている者たちなのであり、子供を育てることや家事が嫌でたまらないと言う感覚を正当化するために、母性本能を否定するのである」と林氏は主張するのです。
恨みつらみのはけ口としてのフェミニズム
林氏は、フェミニストになっている女性の多くが個人的な恨みつらみをもっていると分析しています。その対象は主に父か夫であり、それが一般化すると、男性中心社会に対する恨みつらみになるとしています。
幼少から「お前は可愛くない」と言われ続け、それが「男の視点」だということにきづいてフェミニストになったと公表している田嶋陽子氏を例にあげて、個人的体験と一般論とを区別できないフェミニストたちを林氏は批判します。
個人的体験から出発することが悪いと言っているのではない。個人的体験を通っていない思想は、浮き上がった浅薄なものになる可能性が高い。個人的な体験は貴重な栄養になりうる。しかし出発は個人的体験でも、それをどこまで一般化しうるかによって、その思想の質が決まるのである。
フェミニストたちの圧倒的多数が、個人的体験と一般論とを区別しえていない。一般論であるべき思想を、個人的体験から直接的に導き出している。
(中略)
彼女らは、自分が身近で体験した「悪い」男性を男性一般と思い込み、それを一般化して「男は悪い」「男は敵だ」と言う思想を作り上げる。そのようなやり方こそ、「個人的体験の直接的一般化」という誤った方法なのである。
思想を恨みつらみのはけ口にしてはいけない。思想や理想の名を借りて、恨みつらみの垂れ流しをするのはみっともないし、卑怯である。
“女性の批判”では無いし男性を完全に擁護するものでも無い
さて、ここまで林氏のフェミニズム批判を紹介していきましたが、誤解のないように補足しておくと、林氏は女性そのものを批判しているわけではありません。また、「フェミニズムは本来の理想を失ってしまった」という趣旨の文章もあるため、本来のフェミニズムはもっとよいものであったはずだ、という思いがあるのでしょう(これに関しては私自身は懐疑的ですか)。
フェミニストから専業主婦を守れ
林氏は、健全な社会の基礎である健全な家庭の維持にとって、主婦のあり方は決定的ともいえる影響力をもっているとしています。だからこそフェミニストが主婦の不安を煽り洗脳していくことに危機感をもっているのです。その手口は宗教的カルトの手口に似ているとのことです。
フェミニストである田中喜美子氏が、とある私立公民館にて講演会を開いたそうです。その講演は音声記録が残っていたそうですが、それを聞いた林氏は「支離滅裂でなにを言いたいかまったくわからないが、感情に訴える手法で確実にあるメッセージを伝えている」としています。それは「専業主婦などはつまらないから、専業主婦をやめて他の生きがいのある生き方をしなさい」というものです。
一番驚くべきことは、この講演会にて田中氏がサクラを隠そうともせずに使っていることです。田中氏は講演中に「専業主婦でよかったと思っている方は手をあげてください」と質問します。すると、半分近くの女性が手を上げました。今度は「いやだと思っている方は?」と質問します。すると一人しか手を上げませんでした。この結果に田中氏は困った様子でしたが、一人だけ手をあげたその女性を「あなたの意見は希少価値だから」と壇上にあげて、その女性に「いかに専業主婦が嫌か」を発表させます。
実はこの女性は、田中氏が編集長をつとめる主婦の投稿誌「わいふ」の会員であり、サクラなのです。そして田中氏も「あなたは『わいふ』の会員でしょ」と、サクラであることを隠そうともせずに公表して、以後の講演は田中氏と会員の女性とのやりとり(専業主婦批判)を軸に進行していったそうです。
驚くべき公私混同であり、依怙贔屓である。露骨な依怙贔屓をして『わいふ』の会員はこんなに私に可愛がってもらえるのよ、ということを誇示しているかのようだ。
こうして「専業主婦はこんなにも抑圧されているのだ」という雰囲気を会場内に作り出し、他の聴衆たちからも専業主婦であることの不満を(無理やり)聞き出していくというのが田中氏のやり方であるそうです。
現実を捏造して、不満を煽るこの方法はカルトの手口とまったく同じであり、だからこそ林氏はフェミニズムから専業主婦を守らなくてはいけないと主張するのです。
さらに本書においては、男性に対しても苦言を呈しています。
家父長主義的男性への批判
林氏は家父長主義的男性、つまり力や権威をもってして威張りちらす男性についても、厳しく批判しています。
誤解のないように断っておくが、私はフェミニストだけに反省せよと言うつもりはないし、女性だけが反省すべきだとは思っていない。むしろ最も反省すべきは、家父長主義的な意識をもった男性たちである。彼らは「俺が働いて食わせてやっているのだ」と言う論理で家族を支配しようとする。「働いて」稼ぐことが最も価値のあることであり、したがって「働いて」いるものが支配していいと考えている。
このように、力、とくに経済的な力によって支配しようとする男性は、私が『父性の復権』(中公新書)で述べたように「権威主義的な父」のタイプであり、そうした父の子どもも同様に権威主義的な「力」を信奉する人間になりやすい。子供だけではなく、妻もそれに対抗するために「力」の信奉者になりやすい。
すなわちこの種の男性を夫に持つ妻は、夫の「稼いでいる者がえらい」という論理に対抗しようとして、「では私も働いて自立しよう」となる。フェミニズムの中心思想である「働け」イデオロギーはこうして生まれるのである。つまり悪しきフェミニズムを絶えず再生産しているのは、家父長主義的な男性なのである。
以上のように、「働くこと」をもって家族を支配しようとする男性がいる家庭では、母や子も「働くことが至上」であることを内面化してしまい、結果としてそれがフェミニズムの原動力になってしまう、と林氏は主張しています。
上の引用内にある林氏の別書である『父性の復権』ですが、現代社会における父性の消失に警鐘を鳴らし、父性の再定義とその復権を促す本です。興味深いのは、こちらの本の中で林氏は「『男らしさ』は必ずしも『父性』とイコールではない」としていることです。少し話がずれますが、紹介していこうと思います。
よく見られるのが、父性と男性性の混同である。男らしい人が父性がある人だと思われている場合が非常に多い。しかしこれはたいへんに危険な誤解である。単に男らしくても、父性のない人がいるからである。男らしいというのは自分だけで持ちうる性質であるが、父性というのは家族に対する関係や態度である。家族に対する関係性を欠いて自分だけで男らしくても、父性があるとは言えないのである。
(中略)
男らしいだけでは父性があるとは言えない。つまり「背中を見せて」一生懸命生きている姿を見せるだけでは、十分ではないということである。もちろん自分が懸命に、あるいは立派に生きている姿を見せることも必要である。そのことが不必要だと言うのではない。しかし、子どもに背中を見せているだけではなく、子どものほうを向くということも必要なのである。「子どもは親の背中を見て育つ」というのは、一種の逃げであり、怠惰の言い訳の匂いがする。この言葉が流行ったのは、忙しくて子どもの相手ができない日本の父親に都合のいい言葉だったからである。しかし父親は自分だけ立派に生きていればいいというのではなく、子どものほうを向いて、子どもに働きかける存在でなければならない。
林氏は、父親はただ働く姿(男らしいさ)をみせればよいというものではないとしています。子供と向き合い話をする重要性を説いています。注意しなくてはいけないのは、「向き合い話をする」ことは「対話」ではないということです。「対話」は対等なもの同士の間で成り立つものであり、父と子はそもそも対等ではないのだから、一方的な語りでもよいといいうのが林氏の主張です。「子どもの気持ちを聞いてやる」というのは、母性原理の仕事であり、父親には別の仕事があるのです。
父本来の仕事は、理念を、ポリシーを、メッセージを伝えることである。ある意味では一方的な押しつけでいい。押しつけるといっても、父の考えを強制して、子どもにその考えを人生の中で実行させるという意味ではない。その意味で、「押しつける」と言うと誤解を生ずるのなら、一方的な「語り」でいいのである。父の考えを一方的に示す。子どもは黙って聞いていて、賛成と思う場合もあれば、反対だと思うこともあろう。たとえ反対だと思っても、父の意見は必ず参考になるはずである。少なくとも、そういう価値観を持っている人がいるのだということが、頭に入る。それだけでも貴重な人生経験になるはずである。
(中略)
意見は一方的に言うが、それに対する判断は子ども自身にまかせるのがよい。 子どもの拒否反応の中でいちばん多いのが、「そんな古くさい話は聞きたくもない!」という反応であろう。そういう子どもに対して、父親は断固として「新しいからよいというものじゃない!」と言って、流行を批判することのできる見識を持たなければならない。 とにかく父親は自分の意見をドンと出すべきである。アクが強くてよい。強烈な印象を与えるくらいで、ちょうどよいのである。父親が死んでから、家族に強烈な思い出が残るような父親が、よい父親である。家族になんの印象も残さないような父親の死は父親としての役割を果たしていなかった証拠である。
父親が理念を「語る」ことにより、それを聞く子は自分とは別の価値観をもった人(他者)がこの世にいることを学ぶことができます。それだけでも、その子どもが社会性を身につける下準備になると林氏は述べます。
林氏は、人間社会を持続させるために大切なものは「公正さと秩序」であり、それを子どもたちが学ぶためには「父性」が重要であるとしています。そしてその「父性」は男性が身につけなければいけないものとしています。
林氏は男女には明確な差があるとしており、社会を成り立たせる為には、男女で異なる役割を果たす必要があるとする立場です。だからこそ、男性はただ男らしくしていればよいのではなく、公正さや秩序を身につけた「大人」にならなければならないのです。権力を笠に着て威張り散らすだけの男はフェミニズムを増長させるだけの、まさに「害毒」なのです。
終わりに
いかがでしたでしょうか?20年以上も前から、フェミニズムに対して警鐘を鳴らしていた林道義氏はさすがだな、としか思えないというのが正直な感想です。
しかし…。
林氏はあくまでも立場としては「保守」であり、社会の持続性という観点からフェミニズムの害を指摘しています。
女性と関わらず生きていくMGTOWのような、社会の持続に貢献しない男性にも批判的であろうことは容易に想像できます。また、過去の個人的体験から女性全般を批判するような男性も、林氏はフェミニストと同じだとして批判するでしょう。
さらにネットではしばしば、フェミニストと(主に男性の)オタクの対立が見られます。ここで林氏の別書である『父性の復権』に書かれている一文を見ていきます。
大人になってもマンガを手離せないのが団塊世代であった。いい大人になっても、電車の中でマンガを読んでいるのは、団塊の世代から始まった現象である。それは「マンガを読んでなぜ悪い」という開き直った態度の現れでもあった。権威そのものを否定し、大人の価値を否定し、イニシエーションすなわち大人への移行を否定する価値観から出た、確信犯的な行動だったのである。
『父性の復権』の第5章、「現代社会と父性」において、林氏は「現代社会は極端に父性が不足しており、そのための病的現象がいろいろな形で噴出している」例として、上記のように大人になってもマンガを読んでいる人々(ここでは団塊の世代)を挙げています。
「マンガを読む大人」が大人になることを拒否した存在であるのならば、いわゆる「オタク」と言われる成人男性も、林氏からすれば好ましくない存在ではないかなと思います。
林氏のような保守の立場からすれば、フェミニストもオタクも「大人になれない」という意味では同じ穴の狢であり、ネット上でよく繰り広げられる「萌え絵論争」などは、どんぐりの背比べにしか見えないのではないでしょうか。
もしも保守の立場から、社会の持続性のためを思ってフェミニズムを批判をするのであれば、批判する側もオタクを卒業しなければ、つまり林氏のいうところの「大人」にならなければいけないのではないか?と思う次第です。
ただし、「フェ理屈」のようなフェミニスト達の使う論理のすり替えや詭弁などの手法、さらにカルトに似た仲間を増やす手口などは、思想を問わず(フェミニズムに批判的であるならば)知っておくべきだなとも感じました。
最後までお読みいただきありがとうございます。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
