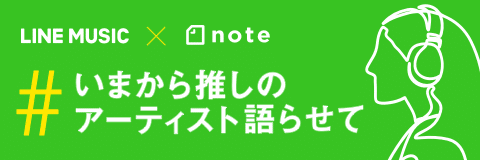スピッツが身を挺して守り抜く自陣~あらゆる生き物へ届けられる光~
スピッツは不思議なバンドだ。
出世作に「ロビンソン」という、いい加減な題が付いている点からして、風変りだと思う。
草野氏は、旅行時に知った「ロビンソン百貨店」という響きが心に残ったがゆえに、その題を付けたそうだけど、これほどの名曲の題に深いメッセージが隠されていないはずがないと、邪推した僕は随分と粘ってみた。
結果、40年も前に刊行された(とんでもなく古い)昭文社外来語辞典に「ロビンソン:シュートを防ぐためにゴールキーパーが身を投げ出すこと」という記述を見つけることができた。
これだ、と思った。スピッツが(特に作詞者の草野氏が)つづけてきたのは、まさに「身を投げ出して自陣を守る」表現活動なのではないだろうか。はかないもの、小さなもの、少しばかり汚れてさえいるもの。それらを慈しみ、磨き上げようと努めてきたのが、スピッツというバンドなのではないか。
もちろん以上は、いちファンの勝手な妄想に過ぎない。草野氏はもったいぶったり、不要なウソをついたりするような人ではないと思うので、恐らくは本当に、適当に題を付けたのだろう。そして題や歌詞を取り上げることは、本レポートの主眼ではない。草野氏の歌詞を文学的に論じるライターは多いだろうし、自分がその方々より良質な記事を書けるとは思えない。できるだけ「音」にフォーカスするようにして、スピッツの不思議さを探求したいと思う。
***
あらためて書くけど、スピッツは不思議なバンドだ。
鈴の音のように繊細な草野氏の声は、メンバーに「守られて」はいない。CDなどの音源は当然、かなり慎重に録ってあるはずであり、フィーチャーされているのは草野氏の歌だ。メンバーは一歩、後ろに下がり、その「鈴の音」をかき消さないよう心を配って、そっと音を重ねているように感じられる。それは一般的な「スピッツ観」と、そう大きくズレていないのではないだろうか。
ただ、一度でもスピッツの曲をカバーしたことのあるバンドマンになら(あるいはライブに足を運んだことがあったり、メガヒットナンバー以外も買っていたりする熱心なファンになら)ご賛同いただけると思うのだけど、演奏のアクは実のところ、相当に強い。もちろん粗野だと言いたいわけではないし、顕示欲があると断じたくもない。ただ「草野氏に遠慮などはしていない」ことは明らかだと思う。アルペジオの名手である三輪氏は、時として牙を剥くように爆音を轟かし、飄々とリズムを刻む崎山氏は、ここぞという場面では豪快なフィルインを披露する。こわれものを紙で包むような穏やかなバンドではないのだ。
それでもなお、そういう凄まじい音圧のなかにあっても、草野氏の「鈴の音」は、決して埋もれることがない。むしろ光線のように、直進して聴き手の心を照らす。21thシングル「ホタル」などが好例だと思う。今にも割れそうな草野氏の声は、バンドアンサンブルの凄まじさに(むしろ)引き立てられるように、あるいは削られて尖りでもしたかのように、リスナーに刺さる。
そういう奇跡をコピーバンドが再現することは、本当に難しい。ずいぶん若いころ、愚かにも「要は透き通ったハイトーンを出せる人がいればいいんだろう」と考え、スタジオに女性ボーカルを招いたことがあるのだけど、すぐに分かったのは「そんな単純な問題ではない」という事実だった。時として敷居が低そうにも聴こえるスピッツの楽曲群は、凡百の市民ミュージシャンを容易に寄せ付けはしない。
あるいはスピッツは、数十年に渡る活動のなかで、こういう「奇跡的なバランス」を、研究によって勝ち得たのかもしれない。草野氏の声を殺さないギリギリのラインを探りつづけた結果が、つまり努力によってもたらされたのが、スピッツの音楽なのかもしれない。でも僕は個人的には、そういった計算高さのようなものを、演奏から読み取ることができない。メンバーは各々の「やりたいこと」に従い、その結果として、鈴が引きたてられているように感じられるのだ。草野氏とメンバーの間にあるのは、もちろん信頼関係なのだろうけど、同時に緊張関係でもあると思う。豪胆なのかデリケートなのか、なんだかよく分からないのがスピッツというバンドだ。少なくとも僕は、そんな風に思う。
***
ここまで、あえて田村氏の名前を出さなかった。僕がスピッツを愛聴している理由のひとつは、自分が(もちろん下手ではあるけど)ベース弾きであり、田村氏の披露するベースラインから多くのことを学べるからである。先に「豪胆なのかデリケートなのか」と書いたけど、それが最も読みづらいのが、ベーシスト・田村氏のあり方だと思う。ライブで(時に)アンプに飛び乗り、ベースを振り回しさえする田村氏は、パフォーマーとして掴みどころがないし、アレンジャーとしても得体の知れない存在だ。
スピッツのヒット曲には「チェリー」のような「歌さえ聞こえればそれでいい」というようなものも、たしかにある。この曲をカラオケのレパートリーにしている方は、きっと非常に多いだろうけど、恐らく「ベースがゴリゴリと鳴って邪魔だなあ」などと感じることは、まず有り得ないのではないだろうか。でも傾聴してみると、そういう「歌もの」を奏でる時でさえ、田村氏の指先は楽しげに踊っているのだ。突如としてハイフレットに跳び、何ごともなかったかのように「真顔に戻る」様は、聴き込めば聴き込むほどに愉快だ。「歌うベース」という表現を聴いたことがあるけど、田村氏のは言うなれば「遊ぶベース」といったところだろうか。
その「遊び」は時として、フォークやポップスという緑化地区を飛び出す。特に編曲者として石田小吉(石田ショーキチ)氏を招いていた頃は、ベースがバンドを牽引するという、かなり特殊なアンサンブルを聴くことができた。
不勉強な僕は、それまで石田氏について多くを知らなかったのだけど、一度だけスクーデリアエレクトロのライブを観たことがあり、無骨な爆音と幻想的な装飾音を併用する(スピッツとは少し違った意味あいで)奇妙なミュージシャンだという印象をもっていた。
ところが石田氏と田村氏の出会いは、幻想的という表現は似つかわしくない、極めて攻撃的なベースラインを産み出したのである。「放浪カモメはどこまでも」のイントロに圧倒された人は、きっと沢山いるだろうと想像する。かき鳴らされるエレキギターさえも背景に押しやり、重低音の主線がオートバイのように驀進する。ベーシストは黒子だと考えていた僕は、それが固定観念であったと思い知らされた。今に至っても、ベース弾きは寡黙であるべきだと(頑愚に)思い続けてはいるけど、世に様々な「ベースのありよう」があることを、この曲から学べたことは確かだ。
また、穏やかなコードストロークから始まる「稲穂」は、そのままフォークギター1本に乗せて弾き語りにしても「牧歌」として映えるはずの佳作だけど、突如、ベースのグリッサンドが響く瞬間、牧歌とは程遠いものになる。田村氏は気ままに遊ぶことで、草野氏ならではの穏やかなメロディラインを、思いもよらない方向へと引っ張っていく。そして引っ張られる草野氏が「まいったな」とでも言いたげに、楽しそうに歌う様が目に浮かぶようでさえある。調和と称するのでは足りない。でも、もちろん対立でもない。そういう奇抜で心地よいアンサンブルに乗って、草野氏の声は活き活きと響く。まるでカモメが放浪するように、稲穂が揺れるように。
***
歌詞について述べることは控えたいと最初に書いたけど、スピッツは、まさに「醒めない」バンドなのだと思う。草野氏はリスナーに
《切なくて楽しい時をあげたい》
と心から願い、取るに足らない薄汚れた事物を抱きあげて、珠玉の歌に変える。そして、そんな創作活動を、単なる「優しさ」にとどめることをよしとせず、メンバーが遊び心を持ち寄る。身を投げ出して自陣を守ろうとするスピッツは、はてしなく優しくありながら、聴き手に油断を許しはしない。「見っけ出した」単語を、フレーズを、アレンジを、時にさりげなく、そして時に誇らしげに、僕らに見せつけてくれる。慣れあうことのないスピッツの演奏は、いつ聴いても刺激的だ。
ただ「醒めない」でいること、長期に渡って鋭くあろうと努めること、つまり長い夢を見るように日々を暮らすことが、人を(とりわけ草野氏のように細やかな歌を紡ぎだす表現者を)どれほど細らせるのかは、凡人の僕にも何となく察しがつく。東日本大震災の折に、草野氏が深く病んだことは広く知られている。「小さな生き物」の呼吸さえ聞き逃すまいと努めてきた草野氏が、未曽有の惨劇を前に「鈴を鳴らせなくなってしまった」のは至極、自然なことのように思える。醒めずに生きることで書ける曲があるわけだけど、それは大きな代償を求めもするのだ。
私的な話になって恐縮だが、僕は青春の数年間、長い夢を見ることを自らに課した。教育実習を母校でおこなうこと、その日々を善きものにすることを、絶えず願いながら時を過ごした。もちろん(たとえば教材研究だとか)具体的な努力もしたけど、善き日々に辿りつくための具体的な行動というものが今ひとつ分からなかったので、ある種の「心の持ちよう」を貫いたとしか、他人様に向けては説明することができない。22歳の初夏、願った以上の数週間を過ごせたあとで(最後の授業を終えて他教科の実習生たちと語り明かしたあとで)朝もやのなか家路を辿った時のことを、今でも鮮明に思い出すことができる。教師にならなかった(なれなかった)僕にとって、それはまさに夢から醒めた、もっと言うなら解放された瞬間だったと思う。
草野氏は「ある種の心の持ちよう」を、途切れることなく守ってきた創作者なのではないかと、ごく個人的な経験から推察する。誰にも真似することのできない歌声は、先天的に授けられたものであるのかもしれないけど、それが単に「美しい」だけであったとしたら、紙に包まれて手渡されたとしたら、恐らく聴き手には空々しく響くだろう。激情を宿しているようには見えづらい草野氏の痩躯は、熾火のような熱を秘めている。醒めることを自らに禁じて歩んできた結果が、星々のように輝く傑作の完成であり、数多のリスナーの獲得であり、そして自身の発病でもあったのではないだろうか。長きにわたって作品を、特にメロディーを生み出せるのは、誰かの(何かの)微細な傷さえも察知できるほどまでに細く、己の心を尖らせたがゆえではないかと僕は思う。草野氏は尖った色鉛筆(それが何色に見えるかはファンそれぞれに違うだろう)を手に取り、折れるリスクさえも覚悟した筆圧で、音符を描き出す。教師になること、つまり優しく生きることを果たさなかった自分に、これを言う資格があるとは思えないけど、人は優しさを持つがゆえに傷つく。どんな舞台(学校や職場や各種コミュニティ)にあっても、深いダメージを負いやすいのは「醒めない」人だ。きっと。
***
あらためてバイオグラフィを辿ってみると、大震災の後、スピッツが世に放った最初のシングルは「さらさら/僕はきっと旅に出る」である。「僕はきっと旅に出る」というタイトルから、再出発への意志を読み取るのは、それほど的外れなことではないだろう。地震を直接に取り上げた曲ではない(と思う)けど、自分が傷んでいることを吐露するような思い切った詞だ。そして何より、それを歌う草野氏の背後で、メンバーがこれまで通りに、あるいはそれ以上に「遊んで」いることが、バンドの再生を雄弁に物語る。かさぶたに触れるように、そっと鳴り始めるピアノの音に、剽軽なドラムが重なる。ギターが鋭くタイトな音を刻み始める。そしてベースはルートを実直になぞりつつ、息つぎや跳ね具合で存在感を示す。夜明けのように始まる本曲は、気が付いた時には疾走している。スピッツは再び、長い夢のなかへと旅立ち、その世界に聴き手をいざなう。
スピッツが、いつまで「醒めない」でいてくれるのかは、きっと当人たちにも知りようがないことだろう。ゴールマウスを死守するキーパーが、力尽きて立ち上がれなくなる日が来ることを、想像するのは辛いことだ。弾丸のようなシュートが日々、僕たちを襲う。それは地震や台風であったり、他者からの無理解や偏見であったり、悔いや自己嫌悪であったりもする。誰の試合にも失点はある。オウンゴールが生まれるのも異常なことではない。零封を目標に掲げることが、ピッチに立つ者の義務であるのだとしても、それを自分ひとりで目指せるほどに、僕たちは強くない。最後方で体を張り、鼓舞してくれるスピッツがいるからこそ、こと切れないでいる生き物がリスナーだ。星の見えない夜にも、スピッツの放つ光は届く。たとえば僕が本文を綴る貧乏くさい部屋にも、その光線は差し込んでくる。
※《》内はスピッツ「醒めない」の歌詞より引用