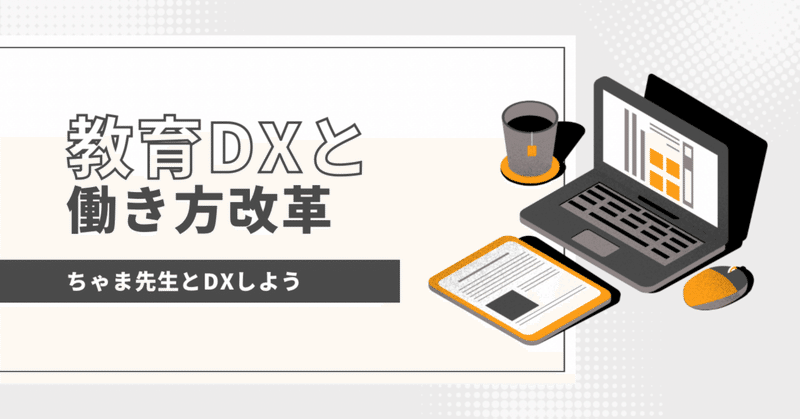
なぜ先生にもDXが必要なのか
DXってなんですか?っていうレベルの先生も多いみたい。
なんで必要なのか?をちゃんと理解してほしいですね。
自己紹介
こんにちは。ちゃま先生です。
11年間、公立の学校で働いていました。
2024年の3月に退職し、現在はOLをやっています。
先生やっていた頃は、政治・経済を教えたり、水泳部の顧問をしたりしていました。
このnoteでは、日々の愚痴も含めてちゃま先生が日々感じでいたことをつらつらと投稿しています。過去の記事もありますが、そのままにしてあります。
現在は、ホームページ(https://chama-dx.com/)にて、先生たちの業務削減のためのナレッジや、公民科に関する情報を発信中。
少しでも皆さんの負担が軽くなり、先生たちと子どもたちの笑顔いっぱいの教育界になりますように。
そもそもDXとはなにか
世の中にはDXという言葉が溢れています。
ですが、お恥ずかしいことに教育界、否、「学校の先生」たちの間では未だ、なにそれ?はじめて聞いた!というリアクションをされることも多いです。
恐ろしいことに教員を辞めて起業しようとしている、いわゆる「意識高い系」の人たちでさえ…
日本の教育界は大丈夫なのでしょうか。
ちょっとここで、本業らしく、DXについて皆様にもご説明しようと思います。読み飛ばしていただいて構いません、もちろん。
DXとは「デジタルトランスフォーメーション」(digital transformation)のこと。
transにはacrossと同じような意味、つまり「交差」の意味があるので、十字路になぞらえて"X"が略語表記に用いられます。
DXは、2004年にスウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によって提唱された概念で、彼はデジタル技術(IT技術)の浸透が我々の生活のあらゆる側面でプラスの方向に働くことを示唆しています。
最近ではDXはビジネスサイドで使われることが多いので、なんとなく教育界には関係のなさそうなワードに聞こえますが、ビジネスに限らず私たちのあらゆる生活に作用する考え方です。
DXは先生たちにもできるのか
よく「IT化とDX化は別物だ」といわれます。
まあ正直、学校ではIT化も進んでいません。
もちろん全てがデジタル化、IT化することがベストだとは思っていません。
紙の方が便利なこと、紙の方が早いこともありますしね。
でもその感覚は、今や「大人たち」と「子どもたち」では大きく隔たりがあるように思います。
私の勤務校の生徒たちも、メモは全部スマホ、シェアはエアドロ(Air Drop:iPhoneのシェア機能)です。
「先生!Teams(Microsoftのサービス:学校で使用)にログインできないんでエアドロで提出してもいいですか?」
なんていう発言が授業中に出てくるくらい。
職員室の先生たちは..Teamsを用いた課題提出のやり方を使いこなしているのも半分くらいのような。エアドロって知っているのかな?という感覚
ちなみにさっきの例は、評価に関わるような提出物の場合は認めていません。Teamsを用いることの意味は、提出時間がはっきりするし、「出した・出していない・いつ出した」というこれまでは教師サイドが管理する情報をデジタル化することに大きく意味があるからです。
わたしはすでに、プリントの印刷は辞めました。紙の無駄だからです。SDGsの観点からも望ましくない。
必要な生徒は自宅で印刷してきますし、多くの生徒はPDFで共有した資料に直接デバイスで書き込んでいます。
「先生、失くしたのでもう一枚ください」
「先生、その日休んでてもらってません」
このやりとりがなくなったのは、精神的にも大きいです。プリントをストック(結局は最後捨てる)しておく必要がないのもありがたいですね。
もちろん、例えば印刷したいけど印刷環境がない、などの場合には応じています。負担軽減と「手を抜く」は別だからです。
また、問題演習などの時はもちろん印刷します。まだ入試は紙で行われていますしね。
授業中はスライドを事前に共有し、投影しながら授業です。
授業のまとめやコメントは共同編集を使用。もちろん従来の挙手での発言も受け付けます。
でもわたしもそうでしたけど、授業中手を上げるのってめっちゃ勇気いりません?
あと先生の漢字の間違えとか言ってあげた方がいいのかな?とか悩むし。そういうの拾えるので、結構いいです。
授業の理解度と振り返りは、毎時間formsを活用。出席もこれで管理しています。
もちろん目視もしますよ。いない生徒いたら大変だし、安全管理上。
でもデータ化しておけば確実ですよね。成績出す時とか。
おかげで授業の質はどんどん良くなっているのを実感します。
ちょっとした工夫で楽にもなるので、DX進めればもっともっと子どもにかけられる時間増えるんですけどね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
