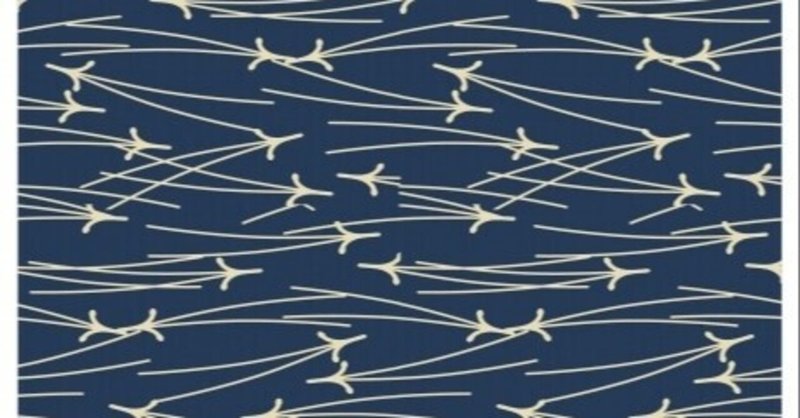
藍染め一年目を振り返る
昨年(2020年)を振り返り、漢字一文字で表すと「染」でした。
藍染めは微生物の発酵の力を使っていることをご存知でしたか。
蓼藍の葉を加工した藍染料である「すくも」を購入しました。
すくもになるまでの工程は「藍師」と呼ばれる技術者によって作られます。蓼藍は春に種が蒔かれ、夏に刈り取ります。刈り取った藍をその夜のうちに、細かく裁断して、翌朝、藍をむしろに並べます。水分が多い葉は、雑菌(藍発酵建てに不要な菌)が増えることになるのでよく乾燥させます。
茎には藍の成分が入っていないので葉と茎を選別します。乾燥させた藍をたたき、茎から葉を分離させる「藍粉成し」の作業をします。選別した葉は「葉藍」と呼ばれる原材料となります。葉藍はずきんと呼ばれる専用の袋に保存されます。
9月になると保存しておいた葉藍を寝床と呼ばれるすくもの製造場所に入れます。寝床の床は、砂利、砂、もみがら、粘土を重ねてつくられています。
その上に葉藍を山積みにして水をかけ、まんべんなくかき混ぜます。これを「寝かせ込み」と言います。葉藍が熱を発しながら発酵し始めます。発酵を促し、大量の葉藍を均一に発酵させるため、約1週間ごとに山を切り崩してまた水を打つ「切り返し」を行います。発酵が進むと黒くなり堆肥状になります。葉藍が発酵するときに発する70度もの熱と猛烈なアンモニアの匂い、もうもうと立ち込める湯気にまみれて、目も開けられないほどの過酷な作業を90日から100日間かけて仕上げます。今では原料である蓼藍もすくもも作り手が減少し、3か月間かけてつくられたすくもは大変貴重なものになっています。
藍師の作ったすくもから藍染めのできる染色液をつくる工程を「藍建て」と言います。
通常、染料は水に溶けますが、藍の染料成分インジゴは水に溶けません。まずそれを水溶性にする必要があります。そのために甕の中にすくもと木灰汁、貝灰、小麦ふすまを入れて微生物の力で発酵させていきます。
最初の液面は茶色で、染色してもまだ色は出ませんが、徐々に発酵が進んでくると液面に赤紫の膜が出始め、液中も黄色みを帯びてきます。これが藍色が出始める兆しとなります。
微生物の働きが藍の色の出具合を左右するため、温度、PH、栄養源など藍液の入った甕をのぞき込んで液面の状態を見ながら世話をしなければならない作業です。
すくもに眠っている微生物を起こし、活性化させて染め液をつくる過程は甕の置かれた環境によっても違うので、10日間くらいで色が出る場合もあれば、私の初回は数か月かかりました。
ある条件が整ったときに、微生物はピカーというイメージで発光して、発色をはじめます。
藍染液の中で還元されたインジゴは、その水に溶け繊維に吸着した後、空気や水に触れさせ酸化されると再び水に溶けないインジゴに変わり繊維は緑色から徐々に青色に変わっていきます。この作業を繰り返すことで、少しずつ青の色が濃くなっていきます。
最後によく水洗いして、布を広げ天日干しすれば完成です。
この本建て正藍染のやり方は藍染の過程での化学変化として、甕の中では決して空気を入れず微生物の嫌気性菌が働き、甕から引き上げたところで酸化を微生物の力だけで行っているところが特徴です。
すくもを作るところで発酵させているので、藍建てで二度目の発酵をするところが藍染めにエネルギーが入っていると感じます。
植物は自らブドウ糖を作り出せますが、必要な時にブドウ糖を使うために、色々な物質とグルコースが配糖体(糖が物質に配位している)として結合で存在しています。藍の生葉の中には水に溶けやすい配糖体の状態で入っています。葉を細かく切ることで酵素の力が働き、生葉に含まれる水溶性のインジカンが溶け出します。グルコースとインジゴに別れるので、この水溶液を染め液として染めます。
生葉染めは蓼藍の葉がある夏に、ほんの短い時間しか染めることができないので、藍は昔から発酵させてすくもにして流通していました。
藍布の衣類は古く戦国時代の頃から健康保持、疾病予防、解毒の作用が知られていて、他の染め物と異なり、積極的に医療目的でも広く使用されていました。
藍染めの下着は保湿に優れ、体臭を外へ出さない。さらに殺菌力に優れていて皮膚病の伝染を阻止する作用があり、江戸時代の城下町ではその衛生上の効果が注目されて、城の近くに紺屋町(藍染め屋の町)を置いているところが多かったのです。
また藍染めの衣類には止血効果があるために、その殺菌力と相俟って矢傷に対する有効性が着目され、鎧の下には藍布の衣類を着用するのが常でありました。さらに防虫作用や毒蛇の攻撃を避ける効果もあるために野宿にもうってつけでした。野良着、蚊帳、手ぬぐい、産着、おむつなどにも使用されていました。また、藍染めの布は箪笥に入れておくと虫よけになると言われています。
戦時中にある部隊では、藍染の手ぬぐいで水をろ過するように配られて、その人たちはひどい下痢にならずに生きて帰ってきたという話を先生から聞きました。
青くて美しいだけでなくその効能も伝承されていたのですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
