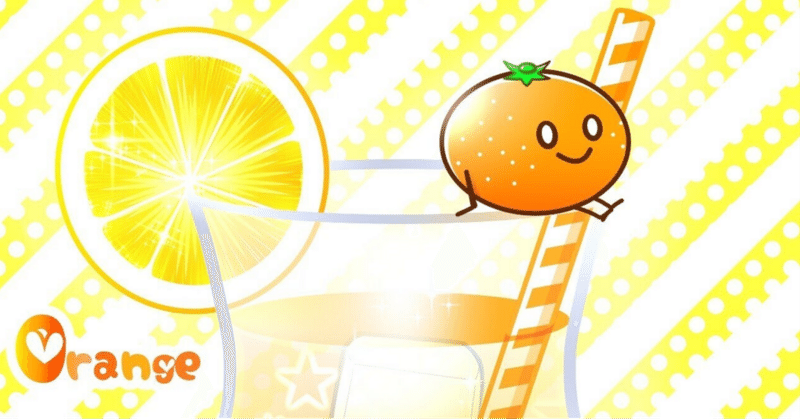
短編 『 橙 』
(約1,800字)
「クリスマスって誰のためにあるんですかね」
ジンちゃんに夕食をオーダーした私は、カウンターのピカピカに光る一枚板のテーブルの手入れの良さに見惚れながら、頬杖をついていた。
今まで目の中に入っていたのか、喫茶店の隅々まで行き届く清潔さと、小物やインテリアの観葉植物に、マスターのセンスが心地よくて人が集まる場所としての意味を持つことを改めて感じていた。
ジンちゃんは私に真顔で数秒、視線を合わせた後に、フワッとした笑顔を作ってみせた。
「クリスマスは、誰のものでもないよ」
そう話すとジンちゃんは、木製の器が二重になったビーフシチューを慎重に私の目の前に運んだ。
オーブンから出したばかりで、ぐつぐつと熱を保って、付け合わせのグリルした野菜も艶々した輝きを放っていた。
「商売人が売りたいモノを売るために、イベントを利用してるの。意味なんか、思いたい人が思うようにくっ付ければいいでしょ」
そうして、クリスマスカラーのシャツの胸の辺りを両手で引っ張って楽しげに笑う。
「きっと親子連れや、二人連れの恋人には別のこと、言うんでしょう」
ー私はすかさず、茶々を入れる。ジンちゃんは大きな右手を口元に当てて、ククッと笑う。
温かい食べ物が冷める前にと、胸の前で手を合わせてから、軽く会釈してスプーンを取り上げた。
「美味しいです。デミグラスソースもしっかりコクがあるのに、濃すぎないっていうか、ご飯がなくてもいい感じ‥‥ほろほろ崩れるお肉もなんて形容したらいいんだろう、とにかく何度も食べたくなる気持ち、分かります」
初めて会ったときのエイトのイタズラっ子のような笑顔を思い出していた。
「あぁ、今日はアイツ、来れないんだよ。取っておいてくれって、電話があったんだ。
ひどいよな、皆んな注文したがるメニューなの分かってるくせして、絶対絶対食べたいんだ〜って譲らないの。子供かよって言ってやった」
ジンちゃんと私は年齢がそう離れていないのだろうが、エイトはジンちゃんをどう思うのだろう。
ー料理を作るお兄さん代わりかなー
フッと心の内側に締め付けられる痛みが走った。
そのとき、入り口の扉のカランという心地よい鈴の音が響いた。
「あ、みどりさん、こんばんは」
茶色の紙袋を両手で抱えたエイトが、驚く私の表情をニコニコしながら見ていた。
「ハチ、シチューは明日じゃなかったのか。
仕事、終わったのか?
さては又、抜け出してきたな」
ジンちゃんは、満更でもない口調だ。
ーこれ、お客さんにもらっちゃってー
そう言うエイトは紙袋からオレンジを取り出して、私の前に2つ置いた。
そして、大量のオレンジが入った紙袋は、ジンちゃんに掛け声をかけて渡された。
私は思い出して、ジンちゃんにパプリカの瓶詰めのお礼に用意したチョコレートをテーブルの上に置く。
「酸味が丁度よくて、3回でいただきました。蜂蜜はフルーツの香りがしていました。ありがとうございました」
「ほらね、みどりさんはハチと違って、感想まで言ってくれる人だよ。これだから、差し上げ甲斐がある人は、有り難いんだよ」
エイトは、ほっぺたを膨らませて、お返しの瓶詰めの中からリンツのチョコレートを一つつまんで、素早く銀紙を外してチョコを頬張った。
「あっ、コイツ。おれの、一個減らしたなぁ」
ジンちゃんは、エイトの頭を肩の両側から押さえて拳の人差し指をグリグリしてふざけていた。
「あの、ハチくんのは、これ‥‥」
会社のバッグの底に忍ばせておいたチョコレートのアソートパックを、エイトの胸のあたりに近づけた。
「やったあ、みどりさん、ありがと!」
エイトはそう言うと腕時計を確認し、軽く手を上げてから口角をぐっとあげて、
「じゃあ、また来るよ」
と入り口へ向かって行った。
風のように去ってしまった。
「ビーフシチュー、よかったんですか」
ジンちゃんは、カウンターにもたれかかって、腕組みして話した。
「仕事、まだ終わってなかったんだよ。これだけ渡しに来たんだ。明日も来るよ。
ま、他にも用があったかもな」
ジンちゃんは意味ありげにウインクした。
私の手元に届いた二つのオレンジは、一枚板のテーブルの輝きと同じく、キラキラといつまでも光っているようだった。
続く
※フィクションです
↓次回のお話です
↓前回のお話です
あと5回ほどで、小説は終了の予定です。
一話が、長めの内容になるかもしれません。ご了承ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
