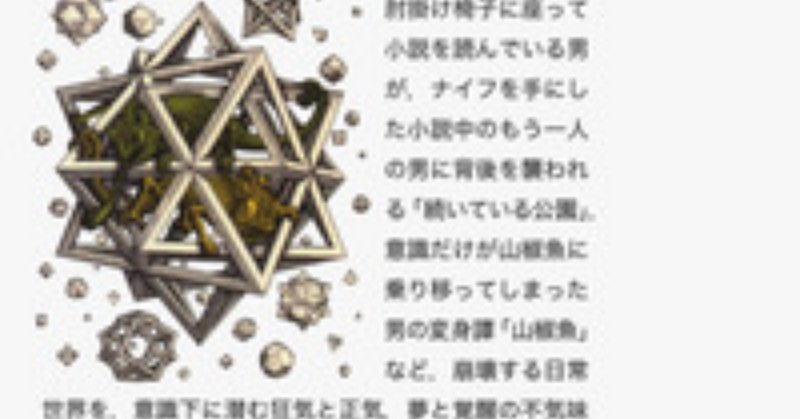
【期間限定無料】「視点」は「語り」ではない──フリオ・コルタサル「続いている公園」(2)
前回に引き続き、「続いている公園」のお話。
農場経営者は作中世界(および作中作の世界)の情報のソース(視点人物)
さて、前回書いたように、僕ら「続いている公園」の読者は、作中世界の情報を、農場経営者である〈彼〉の視点で入手しています。

当然、作中作である〈小説〉の世界の情報も、作中でその〈小説〉を読んでいる農場経営者である〈彼〉の視点で入手しています。
僕ら読者は作中に出てくる〈小説〉の本文を直接読むことはできず、あくまで農場経営者の読書行為の報告の形でのみ、つまり間接的に作中世界にアクセスすることができるのです。
「続いている公園」のような短い小説では、これを固定することは比較的容易です。この作品のばあいは単独の視点人物の視点に固定されている、とひとまず言うことができます。
(この説明に違和感を抱いたあなた、なかなか鋭いですね。その違和感についてはまたのちほど書きます)
「視点」は「語り」ではない
この〈視点〉という用語はなにかと便利だけど厄介な語で、学問的ではない場面では「語り」とごっちゃにされることが多いんですね。ごっちゃにしている例がこれ。
ある晩、友人の引っ越し祝いに集まった数人の男女。彼らがその日経験した小さな出会い、せつない思い。5つの視点で描かれた小さな惑星の小さな物語。書下ろし「きょうのできごとの、つづきのできごと」収録。 〔https://www.amazon.co.jp/dp/4309407110〕
これは柴崎友香さんの、僕の大好きな小説『きょうのできごと』の河出文庫版旧版(2004。最初に出た単行本[2000]よりは増補されているけど、さらにその後出た増補新版[2018]よりはコンテンツが少ない)の、表4(裏表紙)の惹句です。

柴崎さんのこの小説で起こっていることは、作中のパートによってたんに視点人物が変わるというのではなく、語り手(いわゆる「一人称」の)がバトンタッチされていくという事態です。
もちろん、その語り手たちはすべて『きょうのできごと』の作中人物ですから、当然「視点」もバトンタッチされていくわけで、だから惹句は必ずしも間違いではないのです。
でも僕は、文学理論で一般になされているように、「語り」と「視点」というふたつの語を、区別して使いたいと思います。
視点と語りの違い
小説で起こっている事態を冷静に記述するためには、
・いわゆる「三人称」小説における視点人物
・いわゆる「一人称」「三人称」を問わず、小説における語り手
のふたつを区別する必要があるのです。いわゆる「三人称」小説は語り手とはべつに視点人物を設けることができる
僕ら読者は、いわゆる「三人称」小説の作中世界の情報を、その語り手から直接得ることもあれば、作中の視点人物を経由して得ることもあります。
作品によっては、全篇の情報源が固定されていることもあります。新聞記事は一般に、発信者(語り手)である記者あるいはデスクが直接情報源となります。
「視点人物」を作りにくいジャンル、作りやすいジャンル
同じく新聞記事でも、「社会面」の記事になると、記事の一部を構成するいくつかの文については、発信者(語り手)ができごとの当事者の視点を採用して書くことがあります。
同じ犯罪や選挙や災害の記事でも、一面の記事では記者・デスクが「外から、客観的に」語るのにたいして、これが社会面の記事だと、被害者や目撃者、立候補者や有権者個人、被災者などできごとの当事者の視点を代弁したりするのです。
一般に、新聞記事(とくに一面の記事)よりは社会面の記事、あるいはいわゆる「ルポルタージュ」「ノンフィクション」と言われるジャンルのコンテツのほうが、語り手(発信者)とはべつの視点人物を採用する傾向があります。
またこれもあくまで印象ですが、ノンフィクションよりもフィクション、短いテクストよりは長いテクストのほうが、語り手(発信者)とはべつの視点人物を採用する傾向があります。
多くの小説では場面や文によって「語り手から直接」→「視点人物A経由で」→ふたたび「語り手から直接」……と切り替わることがわりとふつうにおこなわれています。「語り手から直接」→「視点人物A経由で」→「視点人物B経由で」……というふうに、複数の視点人物を採用することもよくあります。
語り手はディレクター、視点人物は1台のカメラ
語り(手)と視点(人物)との違いを説明するために、『読まず嫌い。』(角川書店)という本のなかで、物語世界をF1レースのサーキットに喩えたことがあります。

登場人物は1台1台のマシン、そして物語行為はそのTV中継ということになります。
語り手は、全体を俯瞰する視点をもって、サーキットを上から撮影するカメラのようなものです。どのマシンがどのマシンを追い抜いて、抜かれたマシンの車体の色はなにか、俯瞰カメラは伝えることができます。
いっぽう視点人物のひとり「ジャン・アレジ」(『読まず嫌い。』刊行時、すでにF1からは身を引いていたけれど)の視点からは、ハンドルの向こうの前方の風景しか見えません。
他の登場人物「佐藤琢磨」(この人も、『読まず嫌い。』連載中にF1からは去っていましたが)が考えていること──他のマシンのドライヴァー佐藤琢磨のハンドルの動き──は直接見ることができません。
それどころか、自分のマシンの屋根がいまどんな色に見えているかすら見えない。
河野多惠子の『小説の秘密をめぐる十二章』(2002、のち文春文庫)によれば、丹羽文雄は〈自分の頸筋は、自分では見得ず、描くことが出来ない〉という意味のことを言ったそうです。

要するに、オンボードカメラ(視点人物の知覚)は自分のマシンの屋根(自分の首筋)を写すことができないわけです。
「続いている公園」という掌篇小説では、「語り」は作中世界を語っている「語り手」(作中世界において人格を持たない)が担っています。
いっぽう作中で小説を読んでいる農場経営者は「私」ではなく〈彼〉という三人称で指示されているので、視点人物ではあっても語り手ではありません。
「続いている公園」の話は、このあとも続きます。
(↓こちらへつづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

