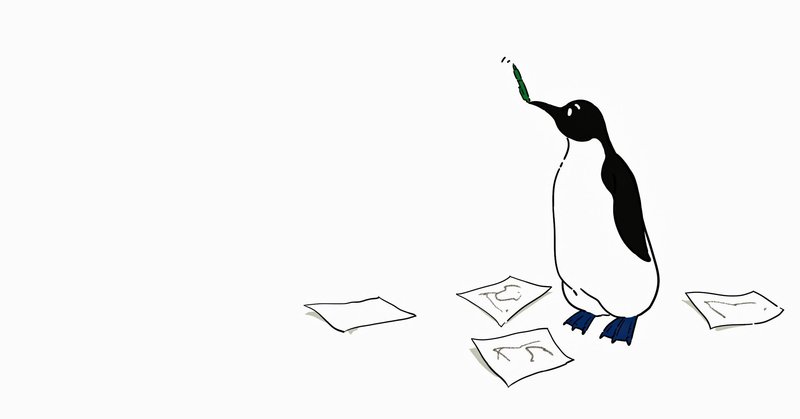
カードゲーマーから見た『Inscryption』のヤバさとその興奮について
以下の有料部分は『Inscryption』のネタバレが100%含まれています。未プレイの方は必ずエンドロールを見てから読むことをおすすめします。
注)2023/03/31 諸事情(無職化)により全文無料公開としました
逆に言えば未プレイならば何を言っているか全くわからないので読む必要がなく、この記事を購入する必要もまったくありません。原作未プレイでこの記事を購入しても後悔するだけなので絶対にやめましょう。
noteのサービスが続く限りこの記事は残すし、仮にnoteがうさんくさい経営になって爆発四散しても別のサービスに記事を移管します。この記事は逃げません。しかるべき時にその扉を開くことを強くおすすめします。
今月中『inscryption』と「やばい」だけの二語で会話するのもやぶさかではない。やばい。俺が朝4時から八時間ぶっ続けで配信するくらいやばい。クリアしたらブログは書くだろうけど、『inscryption』「やばい」の二語で表現すると思う。少しでもカードゲームを触ったことのある人間全員におすすめする
— chomosh / ちょもす (@chomosh) October 26, 2021
**以下有料部分だった場所
カードゲーム
『Inscrypiton』とはなんだったのか。デュエルディスクだ。デュエルディスクであり、おっさんの開封動画であり、ゲームボーイのカードゲームであり、マンティスゴッドだ。何を言いたいのかと言えば、『Inscryption』は謎解きゲームではない。れっきとしたカードゲームだということだ。
謎解きホラーゲーム、あるいはARGにカードゲームのフレーバーを載せているのだという見方もあるが、僕の解釈は違う。
おもむろに謎のおっさんが開封動画を始め、小学生が考えたような壊れたカードを作れば「This card is OP(OverPowered=壊れカードのこと)!」と興奮し、しょっぱなの生贄召喚でもしやと思えばやはり最後にはデュエルディスクで戦う。フロッピーに手作りのシールを貼って自分の好きなようにパラメータを割り振るのは小学生のときにノートの隅に書いたオリジナルカードそのものだし、そこかしこに散らばるカードゲーマーにとって見覚えのあるもの一つ一つを拾っていけば、『Inscryption』はカードゲーマーが最も楽しめるゲームであることは疑う余地がない。それはどんな形であろうと、カードゲームだ。
僕はこのゲームを遊んでいて自分がカードゲーマーであることを誇らしくすら思った。なぜならこの作品を十二分に楽しめるのは、カードゲーマー以外ありえないからだ。カードゲーマーだからこそ、突然の開封動画を見て興奮できたのだ。
ルールと謎解き
このゲームは説明不足だ。『Inscryption』はカードゲームとしてまったく説明が足りていない。
例えばAct1。マスの内容は踏んでみるまでわからない。横にあるルールブックを読んですら攻撃力のわからないモンスターも存在すれば、手に入れたアイテムも使ってみなければ挙動がよくわからない。Act2もルールのわからない謎解きは実戦形式で学ぶしかないし、Act3の獣化については「やればわかるさ」ときた。
はなから説明する気がないのだ。全部を実戦から学ぶしかない。戦う前に理解することはできず、戦って理解するしかない。僕なりの言い方をすればこのカードゲームは全編「正体をあらわす」構文でできている。
フレーバーとしての「死亡時:正体をあらわす」を僕は愛していたけれど、全編そんな調子のカードゲームが受け入れられるわけがない。まして外部に物語を持ったりゅうおうもゾーマもいないなら、それは誰にも理解できない意味不明なゲームだ。
でも『Inscryption』はそれを成立させている。これは謎解きゲームですという建前を使って。
とんでもないことだと思う。ただのカードゲームとして出せば『Inscryption』は不親切極まりない、Steamのレビューが「賛否両論」になることまったなしのゲームだ。優しめの難易度のおかげで気にならないものの、こんなに不親切なゲームはない。特にAct2開始時なんか、デッキを組んだことがない人間が容易に詰みうる設計だ。
でもその時だけ、ゲームのルールを理解するその時だけはこのゲームは謎解きゲームなのだ。自身のカードゲーム体験を問うて答えを出すこともあるだろうし、レシーとの対戦中にカーダーがなんと言っていたか思い出すこともあるだろう。そう、カーダーは「いつだってマンティスゴッドを選べ」と確かに言っていた。マンティスゴッドは200ドルするレアカードなんだと言っていた。これは謎解きなのだ。Act2におけるマンティスゴッドが極めて強力な事実は、カードゲームの素養がなくとも謎とき要素から十分推測できる。だからエネルギーに関するろくな説明がなくとも、意味不明のマジシャンデッキを渡されても、成立するのだ。何故ならクリアできないのはカードゲームが理解できないからではなく、謎が解けていないから。ルールの理解とは、ゲームの攻略とは、本質的に謎解きなのだ。
『Inscryption』はルールが複雑になりがちなカードゲームに一つの答えを出したように思う。ルールそのものを謎ときにしてしまえばいい。「謎解きだから仕方ない」とプレイヤーに思わせる。説明が難しい謎があるなら、それをどうしても知りたい謎にすれば良い。そうして適切なヒントを随所に散りばめれば、人々は勝手に謎を解き、ルールを理解してくれる。
ゲームに新たなルールを追加するとしてそれをどう伝えるのが良いか。所謂生贄召喚のシステムからマナが毎ターン増えていくお馴染みのルールに変えるとして、どうしたらそれを遊んでもらうことができるのか。必要なのは100ページからなる正確なルールブックでも、正しく説明できるチューターの存在でもない。まずなんでもいいからプレイさせること。そしてそれを魅力的な謎にすることだったのだ。
古の興奮と情熱
『Inscryption』はそういったゲーム開発の視点から知見をもたらすゲームでありながら、確かな興奮と情熱をもたらすゲームでもある。リスを出すとリスを手札に一枚加えられるようになったときに例外なくカードゲーマーは興奮する。壊れカードが好きだし、ましてや自分がそれを発見した時の感動は何者にも代えがたい。
『Inscryption』は「発見」を強く意識して作られている。ラスボスの月に攻撃力デバフを入れれば無効化できることや、即死攻撃一発で倒せること、必ず先行がもらえるのでまあまあ先行1ターンキルができること。他にもたくさんあるがその何かしらはプレイヤーが発見できるようになっており、あたかも自分だけが最強の攻略法を見つけたように錯覚する。
原初のカードゲームの楽しみの一つに「発見」があった。友人との対戦中に思わぬコンボを発見してしまったとき。マハーヴァイロに執念の剣をたくさん装備したら強いだろうと妄想したとき。まだ普及していなかったインターネットからヤタロックを発見してしまったとき。発見が喜びを産み、そしてその喜びが更なる探求心を産む。
ネットの普及によってカードゲームの遊び方はまったく変わった。最強のデッキは必ずネットの誰もが見れる場所に公開されており、もっぱら話題の中心になるのはプレイングとカードのバランスだ。多くの人がカードゲームで「発見する」ことを諦めており、最強のデッキで刹那の勝利を求めることがスタンダードな遊び方になった。
『Inscryption』はそんな現代カードゲームを痛烈に風刺しているようにも見える。ラスボスすら容易に蹂躙してしまう、自分だけの最強デッキを作れた時こそがカードゲームの喜びなのだと言い、限られた資産の中からカードパックを開けてデッキを強化していくその工程こそがカードゲームの面白さだと説く。しまいには自分が考えた最強のオリジナルカードをネット上の誰かに使わせる。その何もかもが今のカードゲーマーに失われつつある興奮だ。
そしてこれはおそらく狙って、意味深なストーリーを被せることで「攻略法を共有させること」に歯止めをかけている。Act1もAct2もAct3も、多くの人は理想のプレイングを検索せずに五里霧中を探索するだろう。そしてその中にこそ発見があり、私こそが真にうまくこのゲームを攻略したのだと、プレイした誰もが思う構造になっている。
カードゲームの根源的面白さと今のインターネットは相性が悪い。そのことに気づいていた人達はそれなりにいたが、ここまでの表現力と発想を持って作品にしたものは今まで見たことがなかった。だから『Inscryption』はすごいのだ。誰もが解答を持ちえなかった問題を、謎解きゲームの皮を被せることでいっぺんに解決してしまったのだから。
Inscryption、ヤバい
— chomosh / ちょもす (@chomosh) October 26, 2021
僕が感じた『Inscryption』の「ヤバさ」の一部を文字にしただけでこの有様だ。オタクが好きなメタ構造を内包した物語的ヤバさももちろんあれば、『Her Story』を思わせる演出的ヤバさもあり、もはや常人には理解させる気のないイースターエッグのヤバさもある。そしてそれをネタバレなしにはまったく表現できない。ヤバいのだ。『Inscryption』。
このゲームは圧倒的に、ヤバい。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
