
中国社会はどこへ行くか:中国人社会学者の発言(園田茂人)
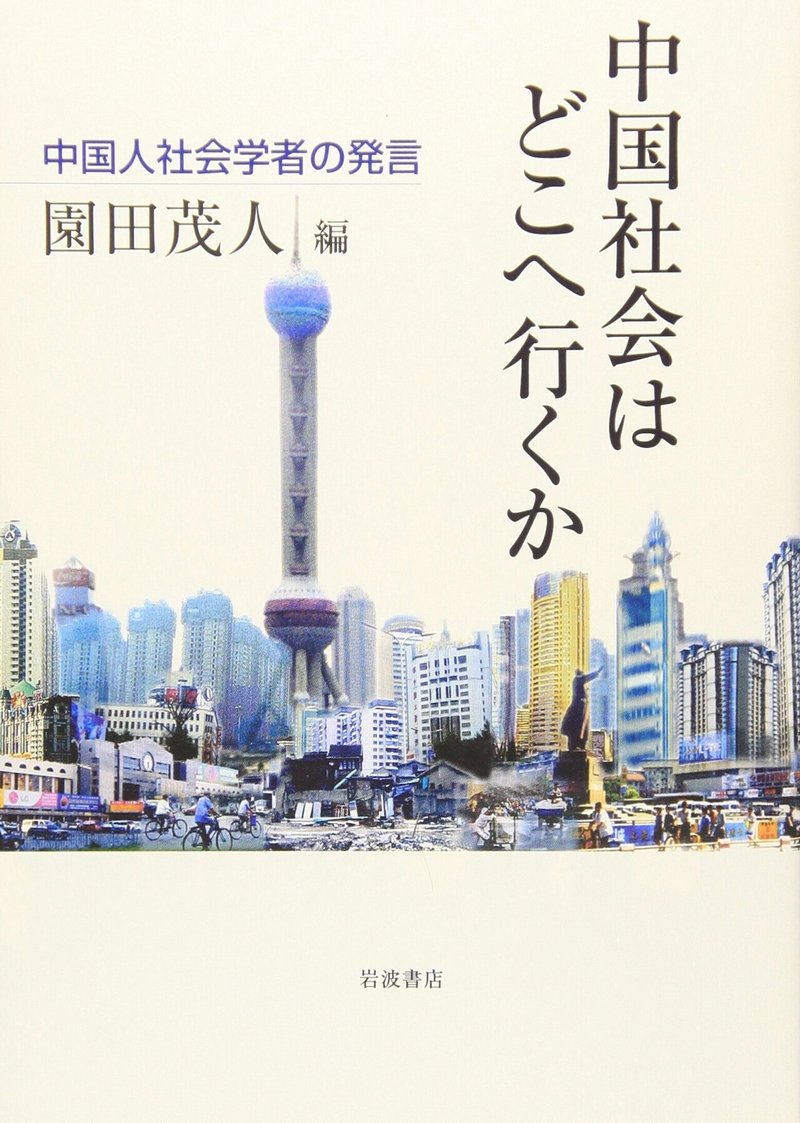
園田茂人 編
岩波書店2008
たとえば、今誰かがぼくに、「2022年12月の中国がどうなっているのだろうか。社会に大きな変化が起きるのだろうか」と訊いたとする。おそらくぼくは、「今とさして変わらない」と答えるだろう。なんの根拠もなく、また何の意味もない答えだが、これこそがもっとも間違いのない答えだと思う。なぜなら、「今」をどう捉えるかは人それぞれであり、今の中国が素晴らしいと考える人は、ぼくの答えから1年後の中国は変わらず素晴らしいと考えるだろう。逆に、今の中国が病膏肓に入るを思う人なら、1年後はさらに満身創痍になると思うだろう。どのような立場にしても、彼らはぼくの答えによって自分の考えが補強されたと思い、満足するのだ。実際、これまでぼくと中国の未来について語り合った日本人は、例外なく最後は自己満足して帰っていった。
こうなるのは、彼らの中国理解が間違っているためではない。相反する二つの中国観があるのなら、どちらかが正しい、少なくとも実情により近いはずだが、実際はどちらも十分自説を補強する根拠を見つけることができ、そのために「今とさして変わらない」ことに満足できるのだ。それだけ、中国があまりにも複雑多様で、誰の目にも氷山の一角しか見えていないのである。にもかかわらず、一角から全貌を推し量ろうとする愚を犯す人の、なんと多いことか。
そうした愚を避けたい方にとって、この本はうってつけだ。13年前の本とはいえ、内容は全く古びていない。現代中国社会を専門とする編者の園田茂人教授は、2006〜2007年に自分のつてを使い中国社会科学院や中国各大学の研究者と対談し、現代中国が直面する課題について各人の意見をまとめた。「中国人社会学者の発言」とは、彼らの論文や研究ではなく、対談の内容のことであり、したがって論文と比べ大変わかりやすい。しかも園田氏はほぼ聞き役に徹し、自分の意見をあくまで相手の話を引き出すために使うため、自説を相手の説に紛れ込ませることなく、対談相手の中国社会に対する見解の大枠を描き出すことに成功している。
対談相手には中国の社会学の重鎮や新進気鋭の学者がずらりと並び、社会学を専門としないぼくでも一度は聞いたことのある名前が多い。対談のテーマとして、各人の専攻であり、且つ現代中国を理解する上で重要な社会問題が選ばれた。格差、農民工、社会保障、企業経営者の位置付け、ネットユーザーの言論、共産主義理想の失墜に伴う儒教伝統の回帰などだ。こうしたテーマに対し、園田氏は学者らが本音を語らないことを懸念したが、「中国人研究者は予想以上に協力的」で、「中国が開放的になり、社会学者たちが今まで以上に自由に意見を表明できるようになっている」という背景から、対談がスムーズに進み、李培林のような政権のブレーンとして政策制定に深く関わる人物とも対談することに成功した。そうした姿勢のおかげで、本書から現代中国の様子だけでなく、中国が今後どのような政策を取りうるのかをある程度予想することができる。しかも、問題の大半は今なお継続しており、2021年現在を中国を理解するのにも、研究者の見解は十分傾聴に値する。
そうして、園田氏と中国の研究者らは現代中国を様々な角度から語り、思考することで、本書のタイトルのように「中国社会はどこへ行くか」を考えるのだが、この本の最後に収録された加藤千洋氏との対談のタイトルにあるように、中国の社会学者の言葉にあらわれているのは、「緊張感を失わない楽観論」であった。「緊張感」は問題だらけの中国社会に由来し、「楽観論」は「それでも必ず解決できるだろう。いい方に向かうだろう」という自信から来る。たとえばある対談者は、「4年前までは悲観していたが、今は楽観的に変わった」と話し、その理由として政府が社会の調和を重要視し、富の再分配を促す政策を打ち出したことを挙げる。調査記者歴があり、中国社会を隅々まで見た別の対談者は、社会保障制度について「改善のための試みがなされている」と評価する。さらに日中関係については、2005年に大規模な反日デモがあったにもかかわらず、対談者の誰もが必ずよくなると話し、政策ブレーンの李培林にいたっては、「きわめて楽観視している」とまで言った。
これらの学者のように中国社会を調査したことがないため、ぼくには統計データから彼らに反論することができない。しかし、上記の対談のテーマにかんしていえば、格差は拡大する一方。農民工は未だ都市戸籍を獲得できず、都市で下等市民に甘んじるか、農村で苦しい生活に逆戻りするかしかない。社会保障は大きなセーフティネットこそできたが、実情は穴だらけで、しかもすでに年金保険の持続不可能が見えてきた。企業経営者は何の悪びれもなく「死ぬほど働いて当たり前」と従業員を搾取する一方で、権力者との癒着をさらに強める。ネットユーザーの言論は十数年前よりはるかに苛烈な抑圧にさらされ、上記の現象を批判しようものなら、即座に内容削除かアカウント凍結になる、中国語で言論を発表しなくなったぼくのような人間も一人や二人ではない。そして、共産主義理想は、危うくウイルスの変異株の名称にされそうになったあのお方の個人崇拝ぶりを見れば、奈落の底まで堕ちたことが誰にもわかる。つまり、どのテーマにしても、十数年後の今の答え合わせとしては、「全く良くなっていない。それどころか悪くなっていることのほうが多い」ということになるだろう。
それなら、なぜ高名な学者らは、揃いも揃って楽観論に浸ることができたのか。対談が行われた時期を考えると、北京五輪を控えて国全体がドーピングしたかのごとく興奮していたため、その雰囲気に飲まれた可能性があるが、憶測に過ぎない。ここはやはり、彼らの言葉からそのヒントを探るしかない。
そこで手がかりとなるのが、関信平の見解である。社会保障を中心に話した彼は、中国の貧困地域での社会保障を長続きさせるために、「農村が長く経済成長を続けないことには難しい」と主張し、「経済成長を続ける限り、貧しい人たちは就業機会を見つけることができますし、福祉サービスの市場化の可能性も生まれてきます」と自説を述べた。この見解を園田氏は、「日本ではともすれば社会保障はパイの分け方の議論になり、経済成長からはあまり議論されない」と評し、「意外」と言ったのである。だが、ぼくからすれば、園田氏の反応の方こそ意外である。「いろんな問題があるけど、経済成長を続けているから、いずれ解決できる」という感覚は、政権が積極的にその論理を使って宣伝したこともあり、1990年代後半から中国を覆い尽くすものとなった。この本に登場する対談者も、農村出身で農民工問題を研究する王春光以外は全員がどこか経済成長の万能性を確信している節があり、その感覚は多くの都市住民にも共有されている。これこそが、楽観論の源泉である。
さらに、経済成長への確信は、中国独特の強力な政府の権力と結びつき、政府への過度な期待という副産物をも生み出した。園田氏が2008年に天津市民を対象に7つの社会問題を提示し、「それぞれの問題を解決すべきは個人か、政府か」と聞いたところ、「個人・家族の繁栄」以外は「政府」と答えた比率が5割を超え、しかもほとんどが85%以上となった。つまり、経済成長によって国が豊かになったからには、政府が責任をもって社会問題を解決すべきであると大半の中国人が考えており、政府への行き過ぎた依存と信頼が見て取れる。だからこそ、政府が「調和の取れた社会」(胡錦濤政権)、「共同富裕」(習近平政権)などと打ち出すと、今までなにも実現されていないにも関わらず、国民はほかに依存すべき対象がないために信用するしかなく、学者らも同様である。
しかし、経済成長と政府への依存から生まれた楽観論は、日本の知識人ーー少なくとも園田氏と巻末の対談の加藤千洋氏ーーには、別の状況として受け取られてしまったようである。両者は「インターネットが中国を変える」とし、ある種の「自由な言論空間」が形成されたと考え、いわゆる近代的市民が成熟しつつある可能性を見ようとした。そして中国の将来を左右するのは豊かになった中間層ではなく、まだ低所得な農民工や都市部のローワーミドルにあるとした。いずれも当時の状況を観察したものとしては間違いではないが、観察の背後に見え隠れするのは、市民の成長と民意の変化により、中国はよくなるだろうとする無意識のうちの思い込みである。つまり、中国人は「政府が責任を持って社会をよくしてくれる」と盲信しているからこそ楽観的なのに、日本はその楽観だけを受け取り、「市民の意見が社会を変えるだろう」と誤解しているのである。
この誤解は、民主国家に生きる人間には、独裁国家がいかにして効果的な言論統制を行い、いかにして経済力をつけてきた低所得者層を飼いならせるのかが、見通せないことを示している。一言で言えば、日本人は自身の経験からあまりにも市民の力を過信しすぎており、中国において政府がどれほど強いのか、考慮できていないのである。戦時中の歴史を知識として知っているだけでは不十分であり、中国に渡ったとしても、外国人として丁重に扱われる日本人は、いわば防護服を全身に纏った状態であり、到底中国の雰囲気を肌で感じることができないのである。
もちろん、このことによって本書や園田氏の研究の価値を否定しようとするのではない。本書の各研究者の主張は、可能であればぜひ多くの日本人に一読してほしいものであり、園田氏の中国史における教育と不平等の関係を論じた著書も大変興味深い。しかし、どちらの場合も忘れてならないのは、いかに優れた学者といえど、どこかで自分の価値観を再確認し自己満足に陥ってしまうおそれがあるということである。たとえそれが民主主義という名だとしても、である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
