
税金と国民に関する三冊
(2019年2月執筆の旧稿、一部加筆修正)

諸富徹
新潮社
2013
妻は税務関連の仕事をしており、この本は彼女が数年前購入したものだ。当時の私は、自分の専攻のことで頭が一杯で、この本の存在を気にもとめなかったが、昨年から個人事業主として再出発することになり、否が応でも税金のことを考えなければいけなくなった。それなら、単に実務だけでなく、もう少し税金を理論的に理解したいということで、本棚からこの本を漁ってきたわけだ。
サブタイトルが「租税の経済思想史」であるように、この本は税制度がどのように誕生し、展開してきたのかを眺めるだけでなく、その背後にある社会情勢や、個々の経済学者・政策立案者の思想にまで踏み込んで、税金をめぐる理解の変遷をたどっている。とはいっても、先史時代から書いていたらキリがないので、著者は国民国家が形成され始めた時代、すなわち17世紀中頃から初めている。その時代のイギリスとドイツが、異なる国家理念から異なる租税制度を形成させたのを紹介したのち、アメリカでどのように近代の税制度が大成されたのかを概観している。最後に、EUでの国民国家を超えた課税権力の展開という最新の動きを眺めて、本書を締めくくっている。
興味深いことに、著者はアダム・スミスのようないわゆる「経済学者」から筆を進めるのではなく、ホッブス、ロック、ヘーゲルなどの哲学者が、「国家」というものをどのように思考したのかを冒頭に持ってきた。本書の帯の言葉にあるように、「国家」と「経済」と「私たち」の関係がメインテーマであり、そのためにまず国家を理解しなくてはならないということであろう。
著者によれば、哲学者たちが考えた国家と国民の関係は大別して二種類ある。イギリスのように個人が集まって国家を形成し、国家は個人を妨げないことを前提に、安全保障など最低限の保護を提供する形と、ドイツのように絶対権力としての国家があり、そのもとでのみ個人が生活を享受できる形だ。それにより、税金を徴収することの正当性や対象範囲が異なってくる。このあたりの議論は要点のみを簡潔を抑えており、何のために税金を納めているのかがわかりにくい現代人にとって、非常に有益な議論だ。とはいえ、やはり制度史と経済思想が中心であり、税金から個人と国家の関係を考えるには、まだ材料不足な感がある。そこで、次の本の登場だ。

三木義一
岩波書店
2015
『私達はなぜ~』が思想史中心で、理論の記述がメインなのに対し、三木義一の『日本の納税者』はどこまでも現実に即している。書名が「納税者」に焦点を当てているように、本書は近代国家において納税者=主権者と定義し、その上で日本の納税者が主権者として行動できるのか、できなければ問題点はどこにあるのかを論じている。
この本の立場は、100%言ってもいいくらいに納税者側にある。著者は納税者に関する統計や、過去の税務紛争の判決文や判例、自身が取り扱った裁判の経過などを挙げ、くどいほどに納税者が主権者としての権利を行使できていないことを論証し、日本の現状を批判する。なかでも第一章から第三章までのタイトルは、「取り残された納税者」「取り締まられる納税者」「頼れるものがない納税者」となっており、著者の論点を端的に示している。すなわち、日本の税制度のもとでは、納税者が主権者意識を持つことができず、税制度の意思決定に参加できていないという意味で「取り残され」、かつ複雑な税制度で、故意ではないのに不利益を被むる(=取り締まられる)可能性が往々にしてある。それを覆そうにも、十分な専門知識を持つプロの支援に容易にアクセスできず、政治家も税のことがよくわからないから現状を変えられないという意味で、「頼れるものがない」のだ。
それなら、どうすればよいのか。終章の「納税者の権利と民主主義」で、著者は政治主導で「納税者権利憲章」のようなものを制定し、それにより納税者の主権者意識を呼び覚ますことを期待しているようである。実際民主党政権下で検討段階に入っていたという。しかし、国民からの強い訴えがなければ、政治が積極的に対応するはずもなく、結局は立ち消えとなった。こうして、主権者意識を呼び覚ますために、まず「国民からの強い訴え」という主権者意識を求められてしまい、にっちもさっちもいかない状況に陥っているのだ。(余談だが、著者は民主党政権で試みられた税制改革を高く評価しているようだが、私からすればそれば単なる自民党政権に対するアンチテーゼであり、彼らが本当に税を理解し実行しているとは思えない)
それでも可能性があるとすれば、「第三の黒船」だと著者は言う。幕末と戦後に海外からの強権の介入で日本が一気に変わったように、税制度ももしかしたら海外の力に頼るしかない。アジア金融危機のときの韓国や、今のギリシャが経験したように、国家財政の危機によって破綻し、そこにIMFが介入することで制度を一変させるのだという。日本で暮らす私としては、なんとしても回避してほしいシナリオであり、著者もこんな劇薬を望んでいるわけではない。彼は学問の仲間と「民間税制調査会」なる団体を結成し、草の根から納税者の意識変革を目指している。この本もその一環だ。その努力には大いに敬意を払いたい。
しかし、著者の活動、そして本書の前提に、私は払拭することのできない引っかかりを感じている。「日本の納税者」というが、その範囲はどこまでだろうか、在日外国人を含むのだろうか。私は日本で暮らし、収入を得て、日本人と同じように国税と地方税を納めている。しかし、私には初めから参政権が与えられおらず、主権者意識を持ったとしても、なにもできないのだ。本書で言う「納税者=主権者」という構図は、すくなくとも日本では日本国籍を持つ人にしか適用されない。それならば、私のような長期滞在している外国人はいったいなぜ納税しなければいけないのだろうかーーそんなことを考えながら、なにかヒントを得られないかと、次の本を手に取った。
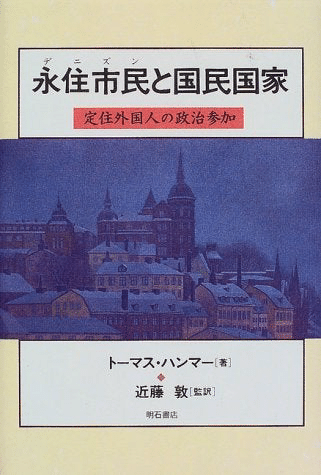
トーマス・ハンマー 著
近藤敦 監訳
明石書店
1999
この本は、外国人参政を語る上で外せない名著である。外国人問題を考える際、得てして「国民」と「外国人」の二分法に陥りがちだが、トーマス・ハンマーはそこに「永住市民」(デニズン)という概念を導入し、現代社会に広く存在する、異国で長期滞在し、生活基盤を異国に置く人たちの存在を見事に描き出した。今の日本で言えば、急増している外国人旅行客は「外国人」だが、永住権を取得した者は「永住市民」だということになる。なお、私のようにまだ永住権がないけれど、長期滞在が可能なビザで日本に在留している外国人をどう捉えればよいのかについては、本書に言明がなく、やや不満が残るが、本書の価値に影響はない。個人的には就労ビザなら、十分「永住市民」と呼べると考えている。
さて、私がこの本を手にとったのは、「外国人として納税をしていながら、選挙権を獲得できないのはおかしくないか」という疑問を抱いたからだ。残念ながら、この本には納税のことが殆ど書かれていないため、ドンピシャの答えが得られなかった。しかし、ヒントになる論述は随所にあった。
まず、私は「納税=国民の権利の獲得」と考えており、国民の権利の一部として選挙権があると考えていたが、トーマス・ハンマーは市民権研究の大家T・H・マーシャルの議論を踏襲し、国民の権利を三つに分けた。すなわち、市民的権利、政治的権利、社会的権利である。市民的権利は言論、結社の自由、財産権など、政治的権利は選挙権、社会的権利は福祉等の社会保障だ。簡単にいえば、市民的権利は民主国家の憲法で「生まれながらにして享有~」などと規定されるような権利であり、政治的と社会的権利はなんらかの条件を満たした上で得られるものだ。この議論と私の疑問を突き合わせてみると、私は日本国において、納税をしなくても市民的権利は保障されると言える。それに対し、社会的権利を十全に保証されるためには、日本の法律を守り納税をしなければならない。政治的権利となると、現時点では外国人のままでは不可能であり、帰化をしなければならない。しかも、帰化申請には厳しい条件があり、社会的権利よりも獲得が難しい。つまり、「納税=国民の権利の一部の獲得」でしかなく、ほかの権利は納税ではなく、当該国が定めるほかの手続きを踏んで獲得しなければならないのだ。
なぜこのように権利の種類によって獲得の難易度が異なるのか。本書に明確な説明はないが、国民国家の誕生の歴史に関する記述を読む限り、「市民と国民の概念の形成の順序がそうさせた」と考えことができる。すなわち、先に国民国家ができあがって、その後内部に暮らす人達に市民的権利を付与したのではなく、人々が市民という自覚を持ち始めたがゆえに、国民国家ができたのである。したがって、市民的権利は国民国家の前提であり、国家が存続する限り、無条件に保障されるものだ。それに対し、政治的権利と社会的権利は、確かに国家の誕生に付随するものではなく、国家の枠組み内での議論を経てから定着したものだ。たとえば100年前の日本なら、市民的権利があっても、選挙権があるのは国民のほんの一部に過ぎず、権利を獲得するために市民たちは長年に渡り戦わなければならなかった。したがって、私が外国人として選挙権を獲得したければ、やはり同様に戦わねばいけないだろう。
だが、それは困難を極めることだ。なんたって私は、外国人だからだ。私は「在留」しているだけであり、日本政府が追い出そうと思えば、いつでも私を国外退去にでき、しかもその法的根拠に私は抗議することすらできない。ある意味、100年前の選挙権のない日本人よりも、私は戦えない状況にある。『日本の納税者』の著者は、納税を義務だけで捉えずに、権利を行使している自覚を持ってほしいと力説したが、そのことは少なくとも私のような外国人にはあてはまらない。この点からいえば、上の二冊はともに国民国家の枠組みのなかで税金を論じているだけであり、グローバルな課題を見落としているのだというべきかもしれない。そして、その見落としは、国民国家という怪物が、そろそろ見直される時期に来ていることを、暗示しているのではないだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
