
幕間狂言(1、国旗班)
国旗班
冷や汗で背中が湿るのを感じながら、ぼくは覚悟を決め、仲間に向かって言った。
「いいか、今日ははじめてだから、慎重にやるんだぞ。ゆっくりでいいから、時間をかけてもいいから、絶対にヘマするなよ!」
「おう!」
「ドゥンガも、国旗をセットするときはゆっくりだぞ!」
「任せろ!」
「よし!出発!」
「おっしゃあ!」
そういって、ぼくを含む同じクラスの男子6人が、遠目には揃っているが、よく見ると揃っていない服装で、校庭横の物置小屋から出ていく。2人1列の計3列で並び、最前列はぼくとドゥンガくん、後ろの2列は日本語クラスのフェイ、ジャン、英語クラスのウィリアムとヨハンだ(英語クラスの学生はみんな英語名を付けてもらっている)。全員白い手袋をし、後ろの4人は国旗の四隅をそれぞれ持ち上げている。そして、ぼくの「イッチ、ニ、イッチ、ニ」の号令に合わせて、6人は校庭にある朝礼台に向かって前進を始めた。そう、今からぼくたち6人は、全校生徒の前で、国旗掲揚を行おうというのである。悪夢のようだが、本当の話である。

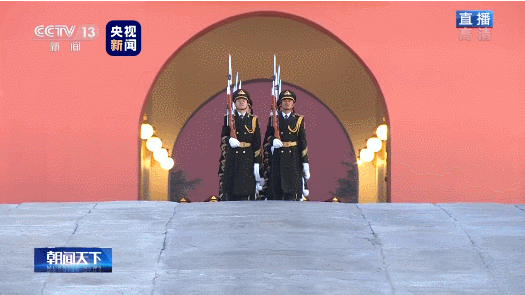


国旗掲揚と聞けば、大抵の中国人はまず、北京の天安門広場で毎朝行われるコレを想起する。日の出の時刻に合わせて、通称「国旗班」の国旗掲揚専門の兵士数人が国旗を携え、詰所からポールまで行進し、国歌に合わせてゆっくりと国旗をあげていく。イデオロギー云々を抜きにするば、とにかく所作の一つ一つが、実にかっこいいのである。それと似たものは、各学校でも定例的に行われ、国旗が掲げられると、校長先生の催眠ボイスが流れ、全校生徒はその声のなかで仮眠を取り、1時間目に備えたものだ。
ぼくが通っていた鄭州外国語中学校でも、月に1度国旗掲揚式が行われた。それがぼくの担当になってしまったのは、自分が1組の学級委員長をしていたからである。担任曰く、「国旗掲揚は1組がやるのが習わし、そしてきみは委員長で成績もいい。なのできみが国旗班を担当することになった」という。さしもの国旗も、成績がすべての場所では何の権威もないと見える。しかし、成績と委員長は、いったい国旗掲揚と何の関係があるのか。猫背で短足で丸顔のぼくに、こんな容姿が物を言う大役を任せていいのか。そもそも、一人でできるものではない、ほかのメンバーはどうするのか、いろいろな疑問を一気にぶつけると、担任は「ほかのメンバーも、もう決まったから、きみと同じくらいの背格好の男子を、うちのクラスから5人選んどいたから、よろしく」と言った。なるほど、ぼくの知らないところで、とっくに話がついていたんだな。
早速、わけのわからない6人が、後にぼくたちの詰所となる校庭横の物置に呼ばれた。そこに担当の先生が入ってきて、「今から30分、練習します。来週月曜日から、早速キミたちの担当になるわ。練習は30分だけだから、真剣にやってね。あと制服はないから、自分たちで揃いの服を用意してね」と、鼻歌でも歌っていそうな軽い口調で説明した。
反対する以前に、まだ状況がよく飲み込めていない6人は、わずか30分の練習を終え、詰所に戻った。先生は「じゃね〜」とどこかに消えてしまっている。残った6人はてんやわんやの大騒ぎだ。「おい、どうするよ?」「オレはいやだ!」「だったらさっき言えよ!」「練習すりゃあなんとかなる!」「練習時間がないんだよ、ボケが!」「ドジ踏んだらどうする?国旗だぞ!」「ていうか3年間ずっとオレたちか?」……
こういうときに頼りになるのがドゥンガくんである。サッカーチームのキャプテンである彼は、みんなが騒ぐなか、冷静にポツリと一言を発した。
「とにかく、やるしかないんだろ?だったらまず、なにを着るか決めようぜ。なあ、班長」
たしかに、そのとおりである。天安門のアレのような軍服は持っていないし、持っていたところでそれを学校に来てくるわけにはいかない。成績だけで国旗班の班長に指名されてしまったぼくは、ドゥンガに仕切らせたくて仕方なかったが、話を振ってきた彼は目を合わさぬようにそっぽを向いてしまった。仕方なく「ドゥンガの言うとおりだ。おまえら、ワイシャツに黒いスラックスは持ってるか?」と、みんなに聞いた。ぼくの頭の中にあったのは、日本の制服スタイルだった。
「ある」「ない」「探せばあるかな」「借りてこれるかも」……頼りない答えがところどころ入り交じるが、賭けてみるしかない。「じゃ、とりあえず白シャツに黒ズボンで決まりだな。靴は黒の革靴で。用意できなさそうだったら日曜にぼくに電話してくれ」と念を押し、不安と興奮となかで月曜日を迎えた。
いちおう、服はみんな用意してきた。しかし、説明が悪かったのか、白シャツはいいとして、黒ズボンはぼくが想定していたものと全く違っていた。スラックスを持ってきたのはぼくを入れてわずか2名、あとはチノパン、コーデュロイ、そしてジーンズさえあった。「どうすんのこれ?」詰所で頭を抱えるぼく、「おまえとドゥンガが前列になるから、とりあえずおまえら2人揃えばいい!」と誰かがやけくその提案をし、ドゥンガは自分のチノパンをウィリアムのスラックスと交換し、筋肉質の太ももで破けそうになるのを気にしながら、前述の通り、朝礼台へと向かっていった。
「イッチ、ニ、イッチ、ニ」、ぼくの号令は続く。だが、わざわざ首を横に向けなくても、隣のドゥンガのリズムがぼくと微妙に合っていないのがわかる。おそらく後ろの4人もそうだろう。まるで「ギクッ、シャクッ」と音が聞こえそうな動きで行進する6人、その動きと素材とりどりのズボンを見て、最前列にいる生徒が「グフッ」と噴き出す。くそ、人の苦労も知らないで。そう罵りながら朝礼台に上がると、国旗はドゥンガくんに手渡された。彼が国旗をポールの旗立てにはめ込んでから、ぼくが国歌に合わせて手動で旗を引き上げる最重要作業が残されている。天安門広場のアレは電動だが、うちの学校は手動だ、しかも滑車が錆びついている。先週練習したときも途中で一回止まってしまった。先生は「アブラ差しとくから」と言ったが、はたして…
不思議なことに、人間もう後に引けないとわかると、緊張しなくなるものである。朝礼台に上がるまで吐きそうだったぼくは、ドゥンガが旗をはめ終えた頃、手足の震えが止まったのを感じた。背中から朝礼の司会者の「国旗掲揚、国歌斉唱!」の声が響く。手に力を込め、引き上げる準備をするぼく。さあどんとこい!そして、国歌が流れ始めた。
何度聞いても、いい曲だ。そう思いながら、ゆっくりとロープを引っ張り、国旗が少しずつ上がるのを見つめる。確かに先週の練習時よりはずいぶんスムーズだ、本当にアブラ差してくれたんだな。これならそんなに力を込めなくていいと、やや力を緩めたが、少しすると、後ろからフェイの焦りが混じった囁きが聞こえた。
「おい、張、遅れてるぞ、これじゃ国歌が終わるまでに頂上まで上がらん!」
「そうだよ。もっと早くしないと、半旗になっちまうぞ!」ドゥンガも焦り始める。ポールの真下にいるぼくは、国旗と頂上の距離感がうまくつかめず、仲間を信頼するしかないと、強くロープを引き始めた。まるで競馬の最終コーナーを過ぎてから追い込む馬のように急速に上がり始める国旗。よし、間に合うぞと安心したその瞬間、上の方で旗立てがポールに「ガン!」と勢いよくぶつかり、その衝撃で、国旗が落ちそうになったのである。
慌てて引く速さを落とすぼく。フェイの息を飲む様子が手にとるようにわかり、ドゥンガも一気に青ざめる。ウィリアムが「おまえ、ちゃんとセットしたか?」と聞くと、「安全ピン止め忘れたかも…」とドゥンガ。だが、こんなところで文句を言っても仕方がない。もう国旗は2/3まで上がった。まさか下ろしてやり直しはありえない。幸い今日は風が強くない、あとは無事に上がり切るのを祈るのみ。
そう覚悟を決めた瞬間、音楽が止まった。そう、ぼくがどうしようかと迷っている間に、国歌斉唱が終わってしまったのである。しかし、国旗はまだ上がりきっていない。音楽がなくても、ロープを引くしかないーー
今思えば、あれはシュールな光景だったに違いない。全校生徒が集まった雲ひとつない晴天のなか、国旗はまずノロノロ、そしていきなり猛ダッシュで上がったかと思うと、なぜか一瞬止まってから、音楽が止まった静寂のなかで、残り1/3を上り続けるのである。国歌斉唱時はかき消されていた滑車の「ギーゴ、ギーゴ」だけが鳴り響き、その度に国旗が揺れて落ちそうになる。青ざめる国旗班一同と、なにかすごいことが起きそうと固唾を呑んで見守る生徒。国旗が頂上に着くまでの数秒間が一生のように長く感じられ、遂にロープが動かくなった瞬間、ぼくは腰が抜けそうになるのを必死で耐えた。
ドゥンガはロープをポールに止め、それまでの一部始終を同じく青ざめて見守っていた司会の先生は「よし、解散!」と即時閉会を宣言。全員背中がビショビショになった国旗班の6人も詰所に戻り、極度の緊張からの放心状態でだらけていた。そこに担当の先生が入ってきた。ああ、なんと言われるのかな……
「よかったね!合格!服もかっこよかったよ!30分の練習でここまでやるなんてすごいわ!」
先生、あんたなにを見てたんだ?服がかっこいい?ジャンなんてドレスシャツにジーンズだぞ?言いたいことは山ほどあるが、とりあえず全部飲み込んで、いちばん大事なことを聞いた。
「国旗どうするんですか?風吹いたら落ちそうですけど。」
「今から下ろしてもう一回上げなおせばいいわ。大丈夫、もう授業始まってるから、誰も見てないって」
なんとも中国人らしい解決案だが、たしかにそれ以外に方法はない。早速先生の言う通りにするぼくたち。そんなドジな少年たちを見守りながら、先生は言った。
「キミたちの前の国旗班なんて、一回目のときは朝礼台で転んだからね。キミたちは上出来だよ。あと、同じ服だとつまらないから、来月は服を変えてみてね。よろしく〜」
唖然とするぼくたちを残し、先生は颯爽と去っていった。そしてぼくたちは、以降2年半に渡って、この大役をこなすことになった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
