
中国社会の超安定システムーー「大一統」のメカニズム(金觀濤・劉青峰)
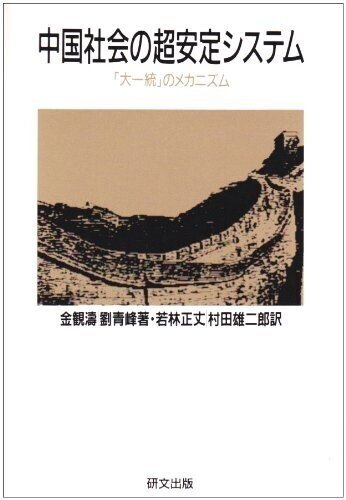
金觀濤・劉青峰 著
若林正丈・村田雄二郎 訳
研文出版1987
ぼくは1980年代前半に生まれ、中国では「80後」と呼ばれる世代に属する。1980年代はぼくの乳幼児から小学校低学年時代であり、そんな乳臭さが抜けきっていない子供が当時の社会の雰囲気を語ることは不可能だ。だからぼくが知る1980年代は、ごく限られた実体験と、書物や大人たちの述懐などの伝聞からなる偏ったイメージになる。特に伝聞は、往々にして語り手の主観によって美化されがちである。だが、そうした偏りをマイナスとばかり捉えるべきではない。偏りがあるからこそ、1980年代に中国の人々が何を嫌い、何を強く望んだのかが見えてくるからだ。
その視点でぼくの聞いたことを振り返れば、今まで接した大人が皆揃いも揃ってあの時代を「活気あふれた」「制限はあったが自由に思考しようとする空気があった」と述懐していたのは、実に興味深いことである。1980年代の国家の統制が2021年現在の今よりも緩かったというのは事実ではない。経済的には当時のほうがはるかに制限だらけであり、思想的には本書のまえがきからわかるように、マルクス主義から外れたものを書くこと自体が困難だった。それでも大人たちがそう振り返るのはーーぼくが接した大人に知識人が多いのも関係しているがーー1980年代に実際に数多くの新風が吹き込んできたからだと考えることができる。1960年代から70年代まで続いた文化大革命への反省として、1980年代の中国では、国家がこれからどこへ向かうべきかについて全員が思考した。その結果、数多くの問いが提起され、それらに答えるための学説や理論が外国から導入され、また国内から誕生したのである。
その活気のなかで登場した問いの一つが、本書が扱う「なぜ中国の封建時代が数千年も続いたのか」というものだ。より正確に言えば、この問は20世紀初頭に一度登場しており、解決を見ないまま戦争に突入してしまったがゆえに、ズルズルと数十年引きずられてきた。その間「封建」という用語の意味が変わってしまい、1980年代の文脈に限って言えば、封建は中国の王朝時代の価値観とライフスタイル全体に加え、「古い」と目される現代の言行をも含む。たとえば老人が「まだ結婚していない男女がイチャイチャするなんてけしからん!」なんて言えば、「あの人は封建的だね〜」と揶揄されたものだ。さらに、文化大革命の一因としても「封建主義の残滓」が指弾されている。端的にいえば、1980年代の中国において、「封建」はなんとしても克服しなければならないネガティブな過去の代名詞だったのである。
こうしたイメージを持つ「封建」を扱うが故、本書は単なる客観的な研究によって歴史の真相を究明を目指すのではなく、「中国を数千年の長きに渡って封建時代に閉じ込めた原因を究明し、そこから前進する手立てを得る」ことを目論む。過去を総括し、得失を分析した上で新たな時代突き進むという非常に野心的で強い現実志向を持った労作なのである。本書の結論はその野心同様に大きなスケールを持ち、ここで説明していては紙幅が足りなくなるため割愛するが、表題に「システム」「メカニズム」などの文言が踊っていることからも見て取れるように、著者たちは中国史の一つ一の細かい事象を扱うのではなく、中国史全体に通底する構造を見つけ出し、構造を組成する各要素の連動関係から中国史の変遷を説明しようとした。その学説は訳者あとがきが評する通り「斬新にして大胆」であり、しかも確かにかなりの程度において説得力を持つため、前進するための拠り所を渇望していた若者に熱烈に歓迎され、学術書であるにもかかわらず数十万部も売り上げた。同様に、中国をどう理解すればよいのか迷っていたであろう日本の学者にも注目され、原書の出版からわずか3年で日本語版が刊行されるに至った。
もちろん、複雑な事象を完全無欠に説明する理論はありえない。ましてや本書のように、時代の問いに答えようと前のめりになっている場合、往々にして結論を急ぐあまり、答えを揃えるために恣意的な史料選択に陥ってしまいがちだ。本書の個々の時代についての考察には首肯しかねるところが多く、異民族文化による影響の軽視、仏教・道教の価値観の浸透の過小評価なども現在の視点からすればいただけない。そうした理由からか、2010年に中国大陸でこの本が再版されたときはさほど注目を集められず、「あまりにも古すぎる、再版の価値なし」という酷評さえされるようになっていた。
だが、それをもって本書の賞味期限がすでに切れたと断じるのは早計だ。「なぜ中国の封建時代が数千年も続いたのか」という問題は、今なお明快な回答が得られていないからだ。20世紀の初頭にこの問いが存亡の機によって覆い隠されてしまったのだとすれば、20世紀末の中国では、成長を謳歌する雰囲気のなかでこの問いが完全に忘れ去られてしまった。1980年代にたしかにあった過去の毒素(それを「封建」と呼べるかはさておき)を一掃する心意気は、2008年の北京五輪の成功と世界的な金融危機を乗り越えたことによって、過去を反省する必要性をかなぐり捨てた、歴史を誇るべき財産として評価し直す尊大さに取って代わられた。自分たちの手で新しい時代を切り拓く意欲さに至っては、ただ国家に付き従っていけばよいという惰性に様変わりしているように見える。
こんなことでいいだろうか。少なくともぼくははっきりと「ノー」と言いたい。ぼくには過去を全否定する気はなく、ネガティブなものを簡単に取り去れると思うほど楽天的でもない。それでも、過去を反省しなければ、いずれこの本が描写したような惨劇が繰り返されるのは間違いない。だから今、時宜にかなっていないと承知しながらも、1980年代に提起された諸々の問を再び動かすべきだと考えている。
ただし、事情はこの数十年間で大きく変わった。本書は随所で中国の古代を西欧や日本のそれと比較し、中国といわゆる西洋の封建時代の違いをくどいほどに説明したが、なぜ「中国」という特殊な存在が前提として措定されているのかについては一言も説明がなかった。それは前回の許紀霖、前々回の汪暉なども同じであり、「中国」という枠組みを彼らは無条件に受け入れているのである。しかし、今はグローバルな時代である。反動する力がどれだけ強くても、グローバル化が逆戻りできない水準にまで進行したのは揺るぎない事実である。もはや中国を中国だけで完結する一個の実体として捉えるのは不可能であり、種々な他者とのつながりのなかで「中国」を再定義するところから始めなければ、どのような問いも回答も意味を持たない。その過程において、様々な中国観が出てくることが予想される。次回は、真正面からこの問に挑んだ著作を扱う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
