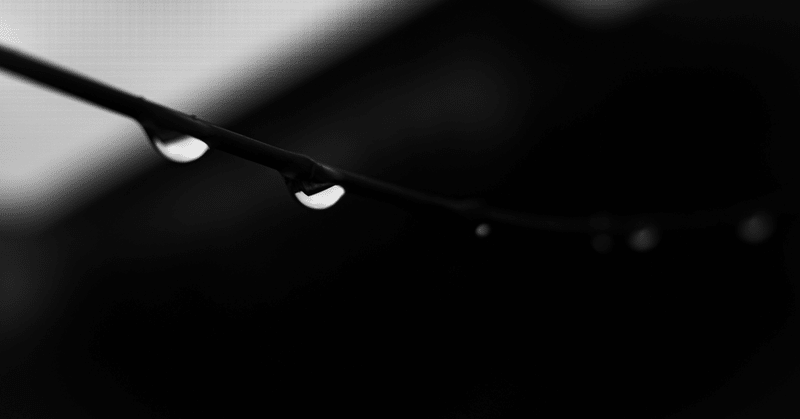
影響力の横展開、という危険な行為
私が日々生産しているのは文章ではあるけれど、むしろ作っているのは、そのへんに出来上がっていく「ムード」のほうだな、と思うことがある。もしくは、自分のあたり一帯に漂う空気というか……。
それが時代の追い風を受けて高く舞い上がれば、時流やトレンドと呼ばれるようになったりするし、深く根付けば文化と呼ばれたりもするんだろう。けど、べつにそこまでの大事にならなずとも、きっと私は死ぬまで半径数メートルの空気をせっせとこしらえていくんだろうと思う。その手段がYouTubeになったりもするし、もっとよくわからない何かを選ぶこともあるかもしれないけれど、空気屋さんであることはたぶん変わらない。
けれども、空気屋さんには免許も国家資格も不要であるのに、ときに態度がデカくなり、同時に影響を及ぼす範囲もデカくなる。ここがなかなか厄介なのだ。
──
私はアートや、クリエイティブの界隈での十数年の草の根活動を経て、ある程度の発言権を得た。つまり、いっぱしの空気屋になり、時と場合によってはそれなりに態度がデカい。他人様の作品を審査したり、個人的に気に入らないクリエイションをズタボロに批判したりしているなかなかおっかない人間である。
いや、まぁそういったことは昔からやっていたんだけど、単純に影響力が増したので、「あの人にそう言われてみれば、そうだなぁ」と賛同したり、耳を傾けてくれる方が増えてきた。
ただ、そうした主義主張に至るまでの内訳は、私の直感や経験則といったかなりあやふやなものである。私は科学的な根拠や経済的な保証を軸に動いている人間じゃない。
というか、そうした不明瞭であやふやなものを自信満々で礼賛することが出来るという特異性が、私が芸術に惹かれる所以なんだと思う。芸術は無責任だ。無責任だから魅力的なのだ。前例も勝算もない曖昧な世界に、真っ裸で飛び込んでいくことが許される。私が美しいと思ったものは美しい。なんともエゴイスティックな独裁小国家だ。
──
けれども、疫病、震災、公害、戦争……様々な問題が乱発して、社会全体が迷子状態になってしまったときには、我々はとりいそぎ、役に立たない。なのにいつもの癖で「さぁ、無責任って最高!真っ裸で飛び込まん!」と扇動してしまっては、最悪の事態になりかねない。感性豊かでお喋りな自分には一旦お暇願うとして、ここで必要になってくるのは空気屋さんではなく、過去の歴史や今日の科学技術から学び、リスクの少ない方に舵を切れる専門家である。
けれども何故か世の中は、有事の際にも我々のような「空気屋さん」に意見を求めることが多い。ワイドショーのコメンテーターとして。SNSの中でのオピニオンリーダーとして。専門家の意見よりも、慣れ親しんだ空気屋さんの意見はずっと心に刺さりやすい。そして、たちまちひとつのムードを醸成していく。それが祭りになり、大きなムーブメントになっていく。そして情報は怒りや悲しみと共に曲解され、それがまた拡散し、いよいよ何が何だかわからなくなっていく──。
──
太平洋戦争で少尉としてフィリピンの戦地で戦い、命からがら帰国した山本七平氏は、そこに流れた空気を知る帰還者の一人として、こう語っている。
(前略)人間とは「空気」に支配されてはならない存在であっても「いまの空気では仕方がない」と言ってよい存在ではなかったはずである。ところが昭和期に入るとともに「空気」の拘束力はしだいに強くなり、いつしか「その場の空気」「あの時代の空気」を、一種の不可抗力的拘束と考えるようになり、同時にそれに拘束されたことの証明が、個人の責任を免除するとさえ考えられるに至った。
"空気に拘束されたことの証明が、個人の責任を免除する。"
あぁ、いろんな点で心当たりがある。そこに流れる空気に賛同することで、コミュニティの中で波風立てずに生存する場所を得て、人はホッとしてしまう。個性を捨て、空気の一部として混ざり合うことによって、安心感を得てしまう。そうなってしまうことの危険性を、先人たちがさんざん警鐘を鳴らしていても。
──
もちろん、社会に向けて語り続けていくことは、誰にだって許された権利だ。けれども自分が空気屋なのであれば、「自分の影響力がどの土壌から生まれたものなのか」については自覚的にらなきゃいけない。
自分の土壌から飛び出て発言をするときは、もちろん日頃のデカい態度は通用しない。専門家の意見を学び、セカンドオピニオンも得て、慎重に支持すべき言説を決めてから発信する……といった謙虚な姿勢が必須だ。けれども「慕われること」「意見を支持されること」にすっかり慣れてしまった空気屋さんは、ときに無知な分野でも持論を繰り広げて、あらたな空気を生成しようとしてしまう。
そうした影響力の横展開には、慎重になり過ぎるくらいがちょうどいい。自分が築いた地位や持論が、まったく役立たない世界があるということに自覚的でいたいのだ。
──
戦争がはじまり、1ヶ月と1週間が経過した今。いっときは「戦争反対」ばかりに染まった日本語圏のタイムラインは、戦地の現状とは裏腹に、今や平常を取り戻し初めている。感情の共鳴から生まれる空気は、それくらい刹那的だ。そうした刹那的な空気をときに「扇動出来てしまう」側として、自戒をここに残しておきたい。
ここから先は
新刊『小さな声の向こうに』を文藝春秋から4月9日に上梓します。noteには載せていない書き下ろしも沢山ありますので、ご興味があれば読んでいただけると、とても嬉しいです。

