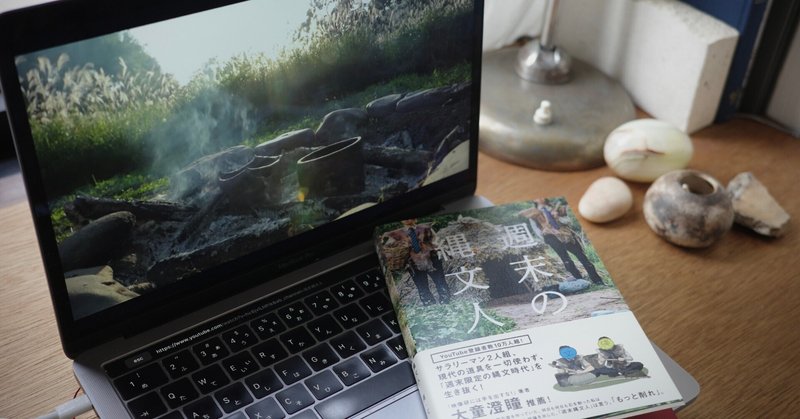
私の好きな、漫画、音声、動画、ドラマ……の話。
文字ばかり書いている身で言うのもなんですが、ときに文字って読むのしんどいですよね。
いや、「しんどいですよね」と共感前提で書いてしまったけれど、世の中には活字中毒の人もいれば、文字情報がさっぱり頭に入って来ないという人もいる。文字に感じる抵抗の度合いは人によってまるで違うしらしいし、平均値がどのへんかはよくわからんけど、私はときどきしんどい。
ここ最近、マットレスの上に転がっている時間があまりにも長かった。激痛や高熱が続く訳じゃあないけれど、家事や仕事をするのはキツいし、横になって読書……もしんどい。映画も重すぎるし、SNSも見たくない。
……というときであれ、助けてくれる作品というのはある。本の紹介はnoteでも時々してきたけれど、今日は本以外で、気持ちを明るくしてくれている作品のことをいくつか。
違国日記

音楽や美術を始めとして、主人公がなにかしらの文化的なことに取り組んでいる漫画は数あれど、どうしても芸術[※だが攻め方はスポ根]となるものが多い。全国大会で優勝を目指すとか、有名芸術大学へ挑戦するとか、欧米でのサクセスストーリーまでを描くとか……。そうした物語はもちろん続きが気になるし刺激的ではあるのだけれど、でも本来の文化というものは生活の内側にも入り込んでいたり、祈りのような形で存在していたりもする。
この物語は、両親を事故で亡くした中学生の少女と、彼女を引き取った小説家の叔母を中心に展開していく。その姪は良い歌声を持っているのだけれど、だからといってシンガーソングライターとしてデビューを目指す訳でもなければ、叔母が姪との生活を体験して世間を揺るがす名作を発表する、という訳でもない。
この物語に明確な目的地はなくて、ただそこに流れているように日々が過ぎていく。誰かの存在によって誰かの言葉が、作品が、表現が、少しずつ変化して、それが当たり前に呼応していく。美しい絵と共に、その時間の中に潜るのがなんとも心地良い。
登場人物はそれなりに沢山出てくるのだけれど、彼ら彼女らの持つ感情の一つくらいは、自分と重なるところがあるかもしれない。私は、朝(姪)に対して槙生(小説家の叔母)が語る以下の部分、あぁー… と思うところがあった。
槙生:…書くことと読んでもらうことと そのぶん嫌われることは全部別で…
──本当はただ 書いてさえいられたらいいはずなのに欲が出て
その上嫌われたくないなんて……とてもかっこわるいんだけど
いちいち傷ついていたら身が持たないから意識的に鈍麻して
朝:どんま
槙生:えー…鈍く麻痺する
…そしたら そのうち本当に心が鈍くなった
いいことにも悪いことにも心があまり動かない
ミモリラジオ

家事が出来るぞ、というところまで具合が良くなってくると、とっ散らかった家の中を片付けたり、溜まった洗濯物を洗って干したり。家でそうした単純なしごとをする時間は嫌いじゃないのだけれど、耳がさみしい。そんなときに最近好んで再生しているのがミモリラジオ。
北海道在住の友人( @ma_chi_co )に教えてもらったのだけれど、北海道で自然ガイドをしている20代男子2人組が「音で届ける自然ガイド」としてお喋りしている番組で、これがかなり面白い。自然が切り口ではあるのだけど、文化や産業、政治の話まで、話はポンポン弾んでいく。
たとえば竹の花が咲くのは120年(?)に1度……とされているらしいのだけど、その花が咲いてしまうと最後、地下茎で繋がった竹が一斉に枯れてしまい、村が滅ぶほどの大事になるのだとか。そして高度経済成長の折にそうした開花が各地で起きて、竹材が不足して、そこに入れ替わるようにプラスチック産業が台頭してきた……という興味深いエピソードもここで知った。そのとき花が咲かなければ、日本はここまでのプラスチック大国になっていなかったのかしら、だなんて考えてしまう。
彼ら二人は特定分野の専門家という訳でははないのだけど、沢山の書籍を読み、専門家に話を聞き、さらには現地での取材を重ねて番組の準備をしている。さらにテーマが「鮭」になればあらゆる鮭を食べすぎて塩分過多になるほど、全身全霊で予習している様子には、いち伝え手としても頭が下がる。
しかしそこまでしても、どうしても正確な情報発信ってむずかしい。特に自然科学の分野は用語の定義が日常のそれとは異なったり、諸説あったり、新しい説が出ているのにまだ周知されていなかったり……と、「多岐にわたり正しい情報」を伝えるのはあまりにも大変。しかもトーク番組って細かい校閲が出来ないし。
だからきっと専門家が聞くと気になる部分もあるのだろうけれど、いちリスナーとしては、楽しく知識に出会うきっかけとして捉えつつ、気になることは自分であらためて調べる……というのが最適解かなぁ、とも思う。彼らも「大切なのは、聞く側が信じすぎないこと…」とも言っていた。もちろん「世の中の言説は間違っており、私こそが真実」と言ったほうが儲かるんですけどね。
雑談回などを聴いていると、若い彼らは野心に満ち溢れているのがよくわかる。ただそれは「自然を利用して自論を展開し、儲けたいぞ」みたいな方向の野心ではなくて、もっとまっすぐなものだなぁ、と。そういえば、壮大な夢や目標について友人と語り合うというのを、私は久しくやっていないな……とも気付かされるのだよ。
らんまん

NHKの朝ドラは毎回観ている訳じゃあないけど、今回は気になり最初から観ていた『らんまん』。平日毎朝これがあるお陰で、私は会社員時代ぶりに目覚ましをかける暮らしを取り戻した(リアタイしたいという強い意志)。そして長年の朝ドラフォーマット、1回15分なのがちょうどいい。1時間の物語を観続けるのは、それなりに体力いるよね。
ここから先は
新刊『小さな声の向こうに』を文藝春秋から4月9日に上梓します。noteには載せていない書き下ろしも沢山ありますので、ご興味があれば読んでいただけると、とても嬉しいです。

