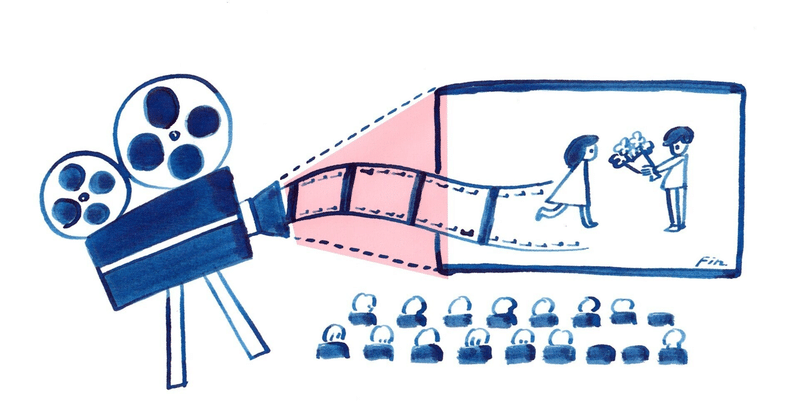
会ったことのない祖父に思いを巡らす〜映画「モリコーネ 映画が恋した音楽家」
私の祖父は、映写技師をしていたそうだ。
ちなみに祖父は父が高校生くらいのころに亡くなっているので、写真でしか見たことがない。父もだが、祖母も祖父について話さないので、どんな人だったかもほとんど知らない。
祖母も父もあまり感情を表に出さない人で、泣き言を言うのも聞いたことがないが、大黒柱を欠いた一家の生活は決して楽ではなかったはずだ。そんな雰囲気なので、自分から祖父について尋ねることはなかった。
「映画音楽の作曲家といえば」のモリコーネのドキュメンタリー映画を先日やっと観てきた。
私は映画経験値がかなり低くて、観るとしても そのジャンルがかなり限られる(演技と分かっていても、痛そうなシーンが苦手なのです)。音楽をモリコーネが手がけた作品を通して観たことすら、おそらく一度もない。
ただ、モリコーネの代表曲はいくつか知っているし、名曲だと思う。そんな「現代を生きたメロディメーカー」がどんな人だったか知りたいというのが、この映画に興味をもった理由。ちょっと変わった動機だとは自覚してます。
2時間半を超える大作で、観に行くのにはそれなりに気合いが必要だった。でも、いざ観はじめると飽きることなくエンディングへ。
いちばん心を掴まれたのは「ガブリエルのオーボエ」からの
フルオーケストラの演奏シーンにつながるところ。
「これ『第9』やん」と思った。
西洋音楽、民族音楽、音楽の根底にある人の声(=合唱)など、いろんな音楽の要素が詰まった「人間賛歌」だなぁと。
ベートーヴェンの「第9」を1楽章から順に聴いていって、いざあの合唱に入った瞬間の開けた感じ。紆余曲折を経て、じわじわと揺さぶられた感情が一気にあふれ出るような、そんな心の動き方も共通していた。
音楽で「情景描写」する例は多いけど、音楽でここまで繊細に、かつ的確に「心理描写」できる作曲家・・・思いつかない。
喜・怒・哀・楽というシンプルな感情だけでなく、感情の移ろいまでも音楽で表現する。そこまで表現しているからこそ、多くの人の心を掴むことができるのだろう。
モリコーネの曲には、宗教曲や はたまた実験的な現代音楽の活動が下敷きになっていることなど、初めて知ることも満載だったし、いろんな思いが掻き立てられるドキュメンタリーだった。
何より、映画がもっと観たくなった。この作品で取り上げられていて、曲が好みだったものから観てみたい。
祖父はどんなきっかけで映写に携わるようになったんだろう。どんなことを思い、どんな映画を映していたんだろう。
コロナ禍もあり、ずいぶん帰省がかなっていないが、次に帰省するときには祖父のことを尋ねてみようと思う。
近いうち、お茶会のような雰囲気のコンサートを企画したいと思っています。もしサポートいただけたら、その運営費用に充てさせていただきます。
