
ノートに書かれた言葉は消えない。
雨が降っている。窓の外の空は色を失ったように、白とも灰色ともつかぬ曖昧さでのっぺりとしている。私がフランスに来てから三年と一か月が過ぎた。早いものだ。時は振り返らず進む。街ではハロウィンとクリスマスが、毛糸玉を追いかける子猫たちのようにじゃれながら追いかけっこしている。
先ほど、ゴミを出すついでに競技場まで散歩しに行った。遠くの空がほんのすこし青く、しかし小雨がシャワーのように降り出したので、あわてて帰ってきた。道中、無料で本を提供してくれる小さなコーナー(何と呼べばいいのだろう)に立ち寄り、メリー・ヒギンズ・クラークの『追跡のクリスマスイヴ』(原題"Silent Night")を失敬した。特にこの作家が好きだというわけではない。たまたまその本がそこにあり、読みやすそうだったから、そしてクリスマスシーズンのミステリー小説だったからという理由である(私はミステリーに目がない)。小さな子どもが書斎からこっそり本を抜き取って文字を覚えるように、私もこうしてフランス語に慣れていくしかないのだ。
先日、小説を書き終わって以来、すこし放心している。作家になりたいと幼いころから望んでいたのに、その想いに二十年近くも蓋をし続けてきた。大学生のころ、ちょろっと短編を書いたりはしたが(文学史という授業をとっていたのだ)、社会人になってからはモノを書く気も本を読む気もぱったり起こらなくなってしまった。当時、一般職のOLと比べたら勤務時間も給料もうんと少なかったのに、私は一日に四十時間も働いているような気がしていた。おまけに移動の多い仕事だったので、新宿の次は銀座へ、続いてさいたま県の川口市へ、という具合にしょっちゅう電車に乗っていた。いつもいつも疲れていて、帰ってくるとへとへとで、機嫌が悪かった。「魂の不在に労災は下りない」などと格好つけて日記に書いたのを覚えている。
そのような日々を十年近く送っているうちに、夢、などという白々しい言葉は色褪せていった。ちょうど電車の車窓から見えた夕焼けがどんどん遠ざかってゆくように。桃色と黄金色の混じり合う美しい時間帯に、私は資料に目を通しながら満員電車に揺られて勤務地を目指す。輝く太陽は死に向かって全力で走っている。私は顔を上げ、一瞬だけそれを見る。だがまぶしい光に目を射抜かれぬよう、顔を伏せ、また資料に目を戻す。
そしてある日ふとこう思う。「ああ、そういえば昔は作家になりたいなんて馬鹿なことを言ってたっけ」と。その夢は腐った落ち葉の匂いのする森の奥に深く、ふかく埋められる。そして子どもっぽいノスタルジーを墓前に置き、私はそこを去る。薄紫色のサフランで飾られたその墓も、やがて朽ちていくだろう。お前に書く資格などない、才能などありはしないのだと、誰かに言われるのが怖かったのかもしれない。そうなる前に私は自分の夢を殺したのだ。

父は常々、私にこう言ったものだ。「いやしくも文筆業のプロを目指すなら、お金をいただいてまで文章を書くのはなぜなのか、考えなければならない。それは私情の吐き出しであってはならないし(そんなもの反吐が出る)、ましてや言葉を使って真実を伝えられるなどと考えてはならない。いや、むしろ言葉を重ねれば重ねるほど、真理から遠ざかってしまうのだ。それはクスクスの箱を積み上げた階段を踏みしめて月に行くのと同じくらい、絶望的な試みだ。作家の仕事というのは、言葉という枠に収まった、美しい嘘を提供することでしかないのではないか」と。
そうかもしれない、と私は思う。きっと父の言う通りだろう。父は賢いひとだったし、いつも正しいことを言った。それに世の中には美しい物語も、目をみはるほど上手な文章を書く人も、掃いて捨てるほどいる。そして若かった私は、自分の物語というものを持ち合わせていなかった。どこかで読んだ小説の断章、古本屋で見つけたボードレールの詩集、そして安っぽい少女漫画の名残などが、私の唯一のインスピレーションだった。そういうものを落ち葉拾いのおばあさんみたいにかき集めて、なんとか形になるようにいじくりまわして、大学の授業の締め切りに間に合うように書く、それが私にできるすべてだった。でも、当時は私なりに一生懸命だったのだろうと思う。

二〇一八年、私は九年間勤務した語学学校を辞め、フランスへ旅立った。最初の二年間は語学学校に通ってフランス語を学びなおし、空いた時間で日本語を教えるという生活をしていた。忙しかったが、充実していた。プライベートで入り組んだ問題が発生してはいたものの、それに目をつぶって虚勢を張るくらいの元気はまだ残っていた。フランスに到着したばかりで、まだ気持ちが高ぶっていたのだろう。大概のことは勢いで乗り切れると思っていた(もちろんそういう具合に人生は根性論だけで乗り切れるものではないけれど)。
ある日、語学学校の最終試験課題として「小説の執筆」が言い渡された。筆記試験のテーマとしては、ずいぶん変わっていると思う。「各国のコロナ政策についてどう思うか、二千字以内で述べよ」とか「母国の学校教育とフランスの教育を比較せよ」とか、そのような課題が出るものとばかり思っていたのだ。その年の担当教師はふたりとも女性で、しかもどちらの先生も文学をこよなく愛しており、生徒たちの独創性を伸ばすことを重視しようという考えの持ち主だった。そこで生徒たちは長ったらしい議論を紙の上に吐き出すという退屈な作業から解放され、もっと自由な作文をするように求められたというわけだった。
小説のテーマは「移民の子ども」。もし、自国の子どもがフランスへ亡命せざるを得ない状況になったら、どのようなことが想定されるかを書け、というものだった。当時、私たちはクラスでアズーズ・ベガグ著の「シャーバの子ども」(Le Gone du Chaâba)という本を読んでいた。それはアルジェリアからフランスにやってきた移民一家のことを描いた話で、著者の自伝的小説だとのことだった。フランスでの移民問題は方々で口にされるが、そのことを、湿っぽく、苦々しい、嫌な問題としてではなく、ユーモアをもって明るく描いた小説だった。先生方の狙いとしては、古き良き時代の美しいフランスではなく、今現在、実際に目の前で起こっているリアルな問題を、文学を通して生徒たちに考えさせようというものだったのだと思う。
自分の国の子どもたちが、彼らと同じ状況に置かれたら、と私たち生徒は頭をひねって考えた。しかし、日本という国は幸いにして経済面や安全性の面で安定しており、フランスに援助を仰ぐために移民が発生するとは、正直に言って今の情勢からは考えにくいことだった。そこで私が考えたのは、近未来において第三次世界大戦が起こったら、ということだった。
こうして私はそのお題に沿って小説を書き始めた。もちろん、へたくそなフランス語なので、とてもではないが読めた代物ではなかっただろうと思う。表現の技法どころか文法ごと間違えている箇所もたくさんあっただろう。それでも、とにかく無我夢中で書いた。締め切りに間に合わせなければならなかったので(そしてそれがそのまま成績に反映されるので)、とにかく急いで書き上げた。成績は悪くなかったように記憶している。けれど成績の評価以上に嬉しかったのは、担当教師の女性が、もっと書くように、そしてコンクールにも応募するようにと励ましてくださったことである。月並みな表現になってしまうけれど、なんだか涙が出るほど嬉しかった。
語学学校が終わり、一年ほど過ぎた。私はビザを取得するために大学に入学し、リヨンからタラールという街に引っ越しをした。小説の続きを書いたら添削してくださいとお願いしていた元担当教師の女性は、新しい勤務先が決まり、遠くコスタリカへと旅立っていった。それでも、私は小説を仕上げたいとどこかで思っていた。友人に相談してみたところ、「フランス語じゃなく、日本語で書いてみたら?何と言っても君の母国語なんだから」と言う。それもそうだな、と私は思った。フランス語で文章を書くと、当然のことながら「文法的に正しいか、正しくないか」ということに神経の90%くらいを集中させることになり、とてもではないが「のびのびと文学的思索の羽をはばたかせる」なんてところまでいかない。せいぜいよちよち歩きのあひるが、があ、とかげえ、とか唸るくらいのものだ。もちろん、日本語で書けば白鳥のように美しい文章が書けるわけではない。だが、仮にもそれは私の母国語なので、フランス語で書くより少しはましだろうと思ったのだ。
そんなわけで、なんだかものすごく遠回りをして、再び「モノを書く」という作業に戻ってきたのだった。まるで誰かが何かの目的で、わざと道をややこしくしているのではないかと思うほど、長く入り組んだ道筋だった。
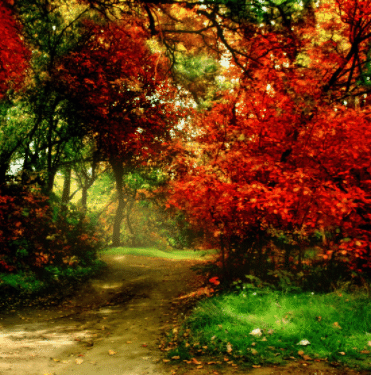
私はある雨の日、あの日生き埋めにした「夢」に会いに行った。湿った黒い土を踏み、あちこちに散らばっている犬の落とし物をよけながら。墓石をどけ、腐ってどろどろになったサフランの花を払い、私はそれを掘り起こした。それはいくらか色褪せて精気を失い、ぐったりしているようだった。
「元気?」と私は尋ねた。
「元気というか、なんというか。お互い、年を取ったな」とそれは言った。
「そうね」と私は言った。「あんたなんて、もう死んでるかと思ってた」
「すべての物体の質量とエネルギーは等価である。従って、エネルギーの変化はありえるが、エネルギー自体はなくならない。よって、厳密な意味での『死』は存在しない」とそれは言った。
「なんだかよくわかんないわ」と私は言った。
「そうかね。では説明しよう。こういうことだ。つまり、落ち葉は土になり、土は水やその他の微生物やらに分解される。もぐらや虫たちがその微生物を食べる。土は肥沃になり、人間が林檎の樹を植える。すると林檎の樹から実がなる。実を鴉が食べる。林檎の実は鴉の体内で吸収され、栄養となり、躰の一部となる。鴉はまた小鴉を産む。親鴉は死ぬ。その躰が土に還る。土は豊かになり、新たな林檎の樹を実らせる。こうして延々と続く。君の夢も」とそれは言った。
「ノートに書き殴られた詩の一節だろうと、夜中に聴く音楽の中に隠れた囁き声だろうと、みな、同じことを語っている。それは君から出て、君に還る、同じエネルギーだ。それは決してなくならない。君の死後でさえも。たとえ、誰からも見つけられなかったとしても。ノートに書かれた言葉は消えない。もしかしたら、雲を突き抜けて別の惑星の誰かのもとに届くかもしれない。君が隠せば隠すほど、そのエネルギーは全宇宙に向かって響き渡るだろう。私は書きたいんだという声が。だから私を生き埋めにしようなどと、愚かな考えは捨てなさい」と言って、それは笑った。
腐った落ち葉の放つ甘い匂いにうずもれて、笑い声は低く、くぐもって聞こえた。私は黒い土をひとかたまり手に取り、悔し紛れにそれにかけた。けれどそれは埋葬の儀式としてではなかった。小雨が降り出した。傘もささず、私は歩き始めた。ダッフルコートのポケットに手を突っ込んで。先ほどより1㎝くらい背筋を伸ばして。私はまたきっとここに来るだろうと思った。
この記事がいいなと思っていただけたら、サポートをお願い致します。 いただいたサポート費はクリエーターとしての活動費に使わせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします!
