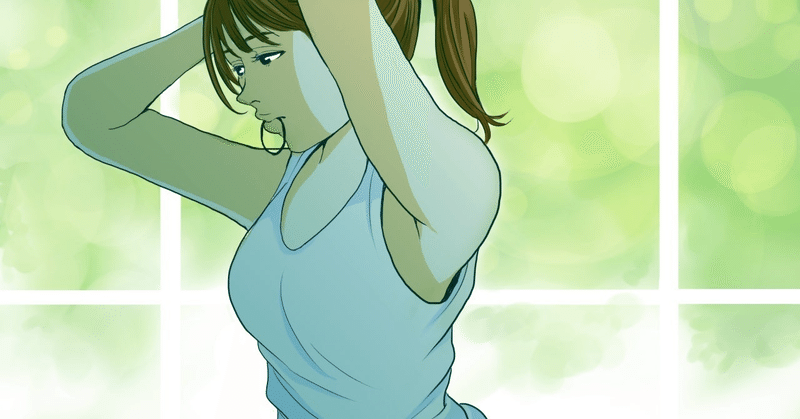
自己とは(ニーチェ編)
君はおのれを「我」と呼んで、この言葉を誇りとする。
しかしより偉大なものは、君が信じようとしないもの――すなわち君の肉体と、その肉体のもつ大いなる理性なのだ。
それは「我」を唱えはしない。「我」を行うのである。
ではこの肉体とは何か
肉体は一つの大きい理性である。
一つの意味をもった多様体、戦争であり、平和であり、畜群であり、牧人である。
ひとまずは、さまざまな差異や闘争あるいは調和といった乱雑なものを内部に含みつつも、全体としてまとまっている活動体、という風に考えておこう。
では、ツァラトゥストラがばかにする「我(Ich)」についてさらに見ていこう。
感覚と認識は、道具であり、玩具なのだ。
それらの背後になお「本来のおのれ(das Selbst)」がある。
〔略〕それは支配する、そして「我」の支配者でもある。
「我」は感覚と認識で構成されていると考えられている。そして普段は、それが本当の「自分」だとされている。しかしニーチェはそういう意識的で自覚的な「自分(この場合は「我」)」の背後に、無意識的・身体的な生(本来のおのれ)を想定する。だから、「肉体(大きな理性)」≒「本来のおのれ」と言っていいだろう。
この「本来のおのれ」は、しかし「本当の自分」というような固定的な主体、実体と理解されてはならないだろう。むしろ「自我(自分)」という観念を生み出している一つの運動と言える。
とはいえ感覚と認識は、それがなければ何も始まらないものなのだから、それを単に道具とみなすのは流石に拙速な気もする。ニーチェは「本来のおのれ」という生成が根源だと言いたいのだろうけど。
むしろそれは、さまざまな心理的・身体的状態が次々と去来し変転していく運動そのものを指している。
要するに、「本来のおのれ」とは、語られる以前に遂行されるもの、つまり名詞ではなく、動詞として理解されるべきものなのであり、~、非人称的な生成なのである。
考えてみれば、私たちの身体だっていまこの瞬間も細胞が死んでは新しく作られている。つまり不断の生成変化や消滅が行われている。
脳神経科学者のベンジャミン・リベットは、「ひとが意識のレベルで自分の行動を決心するよりも先に、脳においてその行動を引き起こす神経活動が始まっている」という実験結果を提示した(山口尚『人が人を罰するということ』p.117)。詳しい話は省くが、これも「自我」というものがそれ以前のものの影響を受けている例と言えるだろう。
あるいは、この「本来のおのれ」は、「自我」という存在者を作り上げている存在と言えるかもしれない。また、フロイト的に言えば「エス(無意識)」(と、もしかしたら「超自我」を組み合わせたもの)ということになるだろう。
いずれにしてもこの「本来のおのれ」は、「自我」の背後ではたらく身体的・無意識的な生であり、その内部では多様な力がせめぎあっている。そうした生の遂行のことをニーチェは「大きい理性」と呼んだ。だからこれは「理性」とついているけれどもいわゆる合理的・言語的なものではなく、むしろロゴス化されていないカオスに近いものである。ちなみに私はいま、この「大きな理性」を、中心をもたない運動として台風に例えることを思いついた。もっと乱雑なイメージの方が適しているかもしれないが、、、。
そしてこれはデカルト批判でもある。「思う」という意識の活動があるからにはその主体としての「我」がなくてはならないとデカルトは言うからだ。とはいえデカルトは、「思うたび、意識するごとに「私」は存在する」と言っていたはずなので、即デカルト却下~とはならないだろう。しかしそれでも、ニーチェの主体破壊が大きな転換点なのは間違いないと思われる。
このニーチェの発想には本人の病気、つまり分裂症的な気質も関係していた可能性が高いだろう。
重いテーマなのでほんのさわりしか書けていないが、ひとまずここまで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
