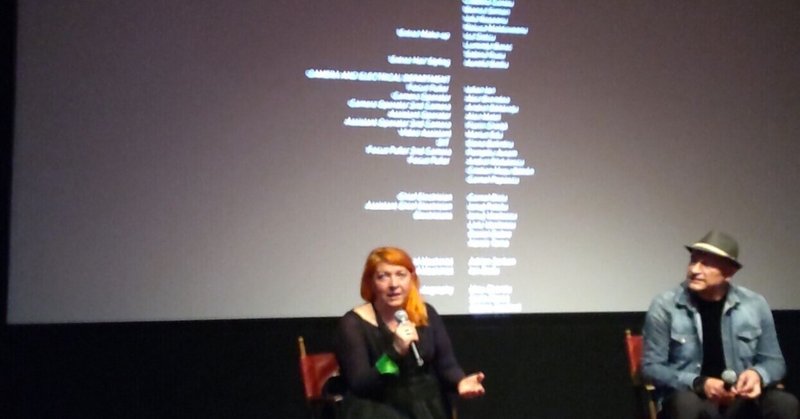
(58) ルーマニアの女性映画人たち
今年で18回目となるルーマニア映画祭(Making Waves)が、ニューヨーク市マンハッタンの3ヶ所の映画館で開催され、8本の旧作や新作が紹介された。ルーマニア映画ではないが国境を接するウクライナの作家ミハイル・コチュビンスキ原作、今年生誕100周年となるジョージア(グルージア)生まれのアルメニア人監督セルゲイ・パラジャノフが映画化した『忘れられた祖先の影』(1964)も上映された。
革命時の混乱

『自由(Libertate)』(2023、ルーマニア=ハンガリー合作)のトュドル・ジウルジウ監督は本コラム(7)の『カタツムリと人間と』(2012)や(23)の『なぜ自分が?』(2015)などの作品がある。ルーマニアで長く続いたニコラエ・チャウシェスクの独裁政権が1989年12月に市民によって倒された革命の30周年の映画を作りたいと、製作者で監督の妻オアナ・ブジゴイ・ジウルジウ(本コラム(23)の『アリア・ダダ』(2015)の監督でもある)が企画した映画である。
革命はセルビア(当時はユーゴスラヴィア)との国境近くの街ティミショアラから始まり、ブカレスト、シビウ、、、と都市に広がっていった。今まで語られず、ルーマニア人にもほとんど知られていないシビウで起きた特異な事件を、本作は取り上げている。
独裁への不満が高まり市民が通りを覆い尽くし、政治犯の釈放を求めて秘密警察署前に押しかける。軍は市民に向けて銃を向けないと発表するが、緊張が高まった中で起こった発砲を機に、一気に市民が建物になだれ込み武器を奪う。警官たちは外へ逃れるがあちらこちらから発せられる銃弾に阻まれ、流血騒ぎとなる。警察、秘密警察、軍隊、市民の間での対立が続く。
映画は秘密警察官ヴィオレル(アレックス・カランジウ)、タクシー運転手で秘密警察の密告者であった疑いがあるレアフ(カタリン・ヘルロ)、軍の将校ドラゴマン(イウリアン・ポステルニク、本コラム(52)にある『行動する人々』の主役をしていた)を中心に展開する。混乱の中で制圧者となった軍は、次々と容疑者を「テロリスト」「帝国主義者」として連行して水の張っていないプールに集めて銃を向けて監禁する。ヴィオレルやレアフも連行されて、他の多くの男たちと共に恐怖の中で過ごす時間が描かれる。

混乱の中で反革命勢力が水道に毒を入れたという噂が流れ、煮沸したり化学成分で濾過した水以外は飲まないようにという通告が出されるのを見ると、関東大震災直後の日本でも朝鮮人が井戸に毒を入れたという流言があっという間に広まったことを思い起こされた。
本作は冒頭から手持ちカメラで揺れる画面が連続する。同胞同士が生命を奪い合う中で敵味方もどう転ぶかわからない。生死の決定権を握られた人間の不安や焦燥感が、リアルに描かれていた。
上映後の質疑応答で製作者のジウルジウは、本作で描かれている知られざる事実を最近軍隊も認めてこの映画の撮影にも協力してくれたと述べた。ウクライナ国境近くの街でロケ撮影をしていた最後の日の2022年2月24日にウクライナ戦争が勃発し、まだ撮影が残っていたが軍隊が緊急事態でいなくなってしまったと、生々しい撮影現場の状況を語った。
歴史の陰で
『時々のスパイ(Occasional Spies』(2021)は、第二次世界大戦中にドイツ軍に撃ち落とされたり不時着した連合軍側の爆撃機のパイロットを救う作戦に貢献した東欧出身のユダヤ人たちについての作品である。
ハンガリー、ルーマニア、スロヴァキアなどから第二次世界大戦前にパレスチナに移住していた彼らは、ナチス・ドイツの支配下にあるそれらの国々の言語が話せ、地理や文化にも精通しているため、英国軍によりスパイの訓練を受けてドイツ軍に捕えられているパイロットたちの救出に向かった。上記作品の製作者であるオアナ・ブジゴイ・ジウルジウの監督2作目作品である。急遽スパイになった彼らについての当時の記録から、各人に似ている俳優を見つけて配役をし、モノクロ写真4000枚を編集してナレーションを被せ、その歴史的なストーリーを語っている。
彼らは暗号名与えられ、東欧現地のレジスタンス運動やシオニズム運動に携わる者たちと協力して危険な任務に就く。目的を執行できた者も、その前にドイツ支配下にあった現地の警察やドイツ軍に逮捕されて処刑されてしまった者もいる。

身分を隠して大胆にもナチスの高官アドルフ・アイヒマンに会見し、賄賂を渡して収容所へ送られるはずのユダヤ人を中立国スイスに逃す計画や、船でユダヤ人をパレスチナに送る作戦に参加した者もいる。こうして知られざる秘話が次々と紹介されるのだが、同胞を救うためにスパイになった若者たちが直面した危険に満ちた任務は、見ていてハラハラする連続であった。
本作も『自由』と同様、知られざる歴史の一コマを再現するものであったが、ステイル写真で構成するユニークなスタイルが独特の世界を構築していた。モノクロ写真を見ていて、最初は俳優が当時を再現するイメージであると気が付かず、その物語に引き込まれていたのである。
監督との拮抗


イギリスを拠点とするイリンカ・カルガレアヌ監督の『警告(A Cautionary Tale)』(2023、ルーマニア=イギリス共作)は、ドキュメンタリーの題材となる人物と監督との緊張に満ちた関係の展開を見せる。25年暮らしたトルコから2018年にルーマニアに帰国したコンスタンティン・レリウは、無効になっていた身分証明書を更新しようとして、自分が死亡宣言を受けていることを知り驚愕する。彼の身分証明書は更新されないので、日常生活で不便を強いられているが、国外追放になったトルコにも戻れない。
その事件のニュースを聞いた監督がレリウに映画製作を申し入れ、レリウを追う日々の記録が始まる。糖尿病を患う60代のレリウは病院の診察を拒否され、市役所に行ってもらちがあかない。役所をたらい回しにされ、疲れ果てて公園のベンチに座り込むレリウを見ていると可哀想になる。レリウは連絡した妻や娘からも話をすることを拒否され、孤独に苛まれて深夜になると監督に電話をして監督に話を聞いてもらっている。
しかし監督がレリウの家族に会って事情を聞き始めると、レリウが被害者であるという単純な話ではないことが次第に分かってくる。レリウと一緒に老母の家へ行くと、彼が居なくなってから一度も家族に連絡しなかったことが明かされ、母親も久しぶりに会ったレリウと親しく交わろうとはしない。彼と連絡が取れないことが10年以上続いた家族はやむを得ず、彼の死亡宣言の書類を提出したのだった。
監督がレリウになぜルーマニアを去ったのか聞くと、ある日突然プッツリと蒸発したくなったと答える。家族と一切連絡を取らなかった理由も、答えがない。
そのうちこの件を聞いた若い弁護士が、裁判所とかけ合って彼の死亡宣言書を取り消す手続きをしてくれることになる。その裁判に再婚した妻も召喚されていることを知ったレリウは怒りに満ちて監督にナイフを見せ、妻を裁判所で殺すと宣言する。
こうなると見ている私は、映画製作中に元上官を殺しに行くと監督に打ち明けた第二次世界大戦の帰還兵・奥崎謙三と原一男監督の関係を思い出すのだが、その作品『ゆきゆきて、神軍』(1987年)でも奥崎氏は原監督を振り回しながら映画の製作をある意味仕切っていた。もう協力しないと監督を脅すことは一度ではなく、それでいて監督に頼ってきたりするこのレリウも一筋縄ではいかない題材である。
幸いレリウの妻は裁判所に現れなかったので大事には至らなかった。しかし、レリウを援助する彼の親友夫妻にレリウ抜きで会いに行った監督の撮影の途中に、レリウが鉄棒を手に乱入してカメラを叩き壊す。身の危険を感じた監督と録音技師はこっそりルーマニアを後にする。
上映中に観客たちはしばしば笑っていたが、レリウの巻き込まれるお役所仕事があまりに不条理で苦笑することから始まり、次第に説明不可能なレリウの行動にも笑うほかなかったのだろう。
上映後の監督との討論に観客からの質問は途切れることなく続き、見る者を刺激する作品であった。監督はこの作品はレリウの人生についてと、映画製作の過程についての2つの題材があると述べ、レリウの持っている父権主義的思想が若い女性監督と衝突したと分析した。しかし、必ずしも自分が好意的に描かれていない本作を見たレリウは、本作を否定しなかったそうだ。矛盾を抱えながら、どこかで理性が残っていたのだろう。
Photo credit for
LIBERTATE, OCCASIONAL SPIES and A CAUTIONARY STORY: Making Waves
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
