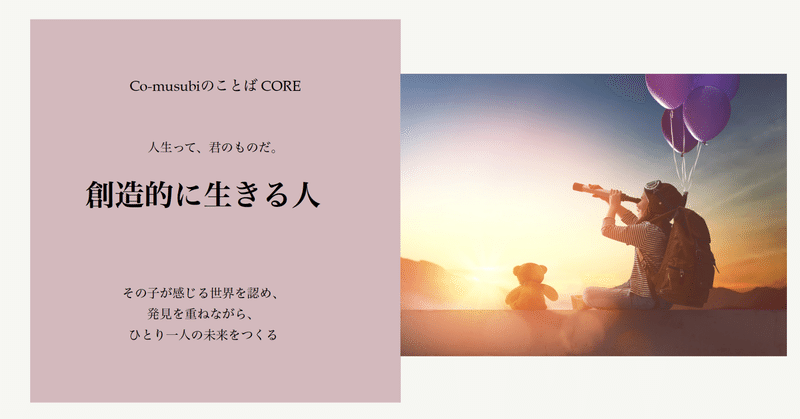
Co-musubiのことば CORE / 創造的に生きる人
人生って、君のものだ。
創造的に生きる人
その子が感じる世界を認め、発見を重ねながら、ひとり一人の未来をつくる

複雑化する世の中で、子どもが幸せになれるような教育をしていきたい。
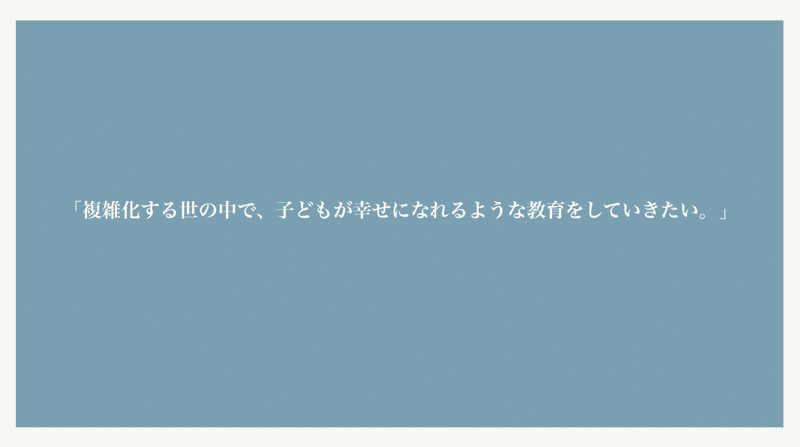
▼そんなとき
急激な社会の変化により、教科的教育だけではカバーしきれないことも必要となってきており、このままでは今の子どもたちが新しい学びをしていく機会を逃してしまいます。
教育は検証に時間がかかるため、大規模であればあるほど動きは慎重になりがちです。
また、今後に向けてどんな学びが必要かについては様々な見解がありますが、公的教育は全員を対象としていく必要があるため、当面は各家庭で考えていくこととなりそうです。
しかし、親世代は自分たちが受けてきた教育のイメージを強く持っていたり、仕事等で忙しく教育について十分に考える時間がとれなかったりして、問題を感じつつも、なんとなく受動的な姿勢となってしまいがちです。
また、実際に家庭で学びを組み立てようとしても、教育に関する深い知識や関心を持っていなければ、なかなかうまくはいかないものです。
▼そこで
Co-musubiは、その子自身の生きる力を引き出し、自分で人生を創造しながら歩んでいけることをゴールとして、ひとり一人に今必要なサポートを考えながら、親とともにその子の日々に寄り添い続ける円環的な教育システムをつくりました。
Co-musubiは、子どもが《創造的に生きる人》として育つよう、学ぶ環境とコンテンツを複合的にデザインしています。複数家庭の親子がオンラインで集うコミュニティという形を取り、プログラム作成者が細かに日々の学びを観察しながら家庭とつながることで、テーマ設定やファシリテーション、個別コミュニケーションを通じて、ひとり一人の《個別の導き》をつくります。また、子どもが学んだことを家庭に伝え、日常と学びのシームレスな連携を生むことで、親同士による《大人の学びほぐし》が生まれ、子どもが《ありのままに育つ場所》としてのより良い環境に整えていきます。
学びのプログラムは、学校教育とは違うアプローチによって並行し、オフラインの日常全体を学びの機会とすることで、複雑な世界を教科を超え《球体で捉える》ことを目指します。
子どもが感じたことを《自分の言葉》で話し、正解のない問いについて《他者の視界》を知る環境づくりを徹底することで、子どもたちは多様性を尊重しながら、自己を発信できる子に育ちます。そのような、すべての意見が認められる中で《創造のワクワク》が得られるプログラムを経験し、学びを通じた自己肯定が積み重なり、《意欲の循環》が上手く回るようにしていきます。
そして、それをエンジンとしながら、子ども自身が少し高めのハードルを乗り越えていくと、最終的には《人生のオーナーシップ》を持てるようになるのです。
創造的で自己肯定的な学びを通じて生きる力を育む、このシステムを鮮度高く維持できるよう、Co-musubiは日々の運営だけではなく、プログラム作成者自身が常に時代を先取りした《創造的な学び手の視界》を獲得する経験を積むことを意識し、そこで得た新しい知見を加えながら《多次元での学びのデザイン》によってプログラムを開発し、子どもたちの間で共創が自然と生まれるような、未来を生きる彼らに最適な学びの機会を提供し続けられるよう力を注いでいます。
▼その結果(すると)
多様性を認める風土が確固なものとして築かれ、かつ気心の知れている環境の中で育つことで、親も子も安心して自分の創造性を発揮することができます。
そのような創造的に生きている子どもたちと、その学びをサポートする大人たちがともにネットワークをもつことで、新しい学びへの気付きが飛び交い、新たなアクションが生まれていきます。
日常や自分と結びついた様々な学びを経験することで、子どもたちは安心して自分が信じる道を選択し、何があっても、自分で何とかしながら歩いていける人に育つのです。
そのように、その時々での化学反応を起こしながら成長・進化を遂げていく生命体的な学びのエコシステムをみんなで創っていくことが、社会における新しい教育のひとつの在り方のモデルになっていきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
