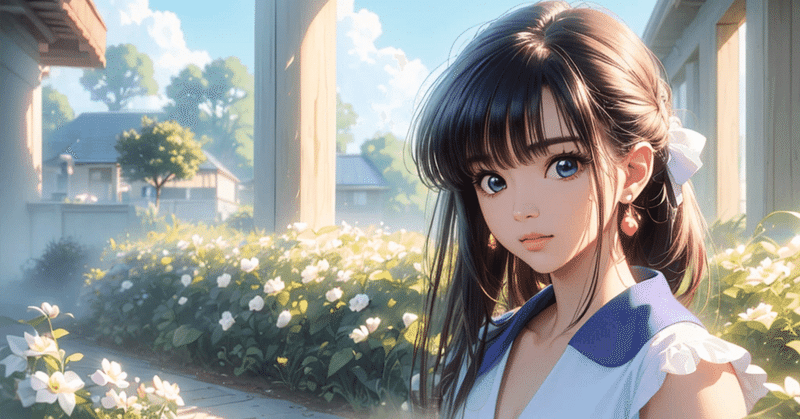
経済学から見た会社と従業員の過去と今
こんにちは、皆さん。
皆さんは会社と従業員の関係について考えたことはありますか?
日常生活の中で、我々はさまざまな関係に身を置きますが、会社と従業員の関係もまた重要なものです。
普段は節約記事をちまちまと書いておりますが、今日は視点を変えて会社と従業員の関係を探求してみましょう。(視点を変えるのは節約ネタが切れたからでは決してありません!汗)
現代社会の企業と従業員の状況
バブル崩壊後の失われた30年と呼ばれる時期を経て、過去の家族経営的な形態は鳴りを潜めてしまいました。
企業は経営が厳しくなったため、安い人件費を求めて派遣労働者を雇ったり、外国人を受け入れたり、賃金カットをしたりと様々な施策を行って既存の従業員を切り捨てていきました。
また、企業は経団連というギルドの元、政治に一定の影響力を及ぼし企業の利益を増やすのに奔走しています。
その結果、企業の利益は上がっているにもかかわらず、年々法人税の収入は下がる一方です。
企業が着々と人件費をカットし政治に口を出して利益を増やす傍ら、その被害を人知れず被っているのが国民です。
ここ30年企業の成長に対して可処分所得が上がらないどころかむしろ下がっております。
また、年々上がる消費税は企業に口を出せなくなり、法人税が減ってしまった分の穴埋めによるものです。
何をやっても黙っている国民から搾取して解決することを政治家は選択し続けています。(日本の国民は選挙に行かないから何しても大丈夫!また有力者に力を借りれば当選確実や!!選挙行かないやる気のないやつのことなんて知らん!)
スマホやSNSで情報共有が容易になった昨今、次々とこういったことが明るみになり、企業や政治に対する不信感は年々増すばかりです。(令和日本 乗っ取れますよ ナポレオン!! by CosMo)
その結果、従業員は従業員で自分の身を守るために仕事は適当にやり過ごし、自己投資による転職や副業に時間を費やすことに注力するようになりました。
かつての信頼関係が嘘のように企業と従業員の関係が加速度的に希薄になっている。それが、現代社会の日本の状況です。
この状況を囚人のジレンマという経済学の考え方を用いて見ていきましょう。
囚人のジレンマとは
まずは囚人のジレンマという概念をご紹介します。
これは、ゲーム理論の一つで、協力することが最良の結果をもたらすが、自己利益追求のために協力しないことが個々の利益になる場合、困難な状況に陥るというものです。
具体的な例を挙げると、二人の囚人がお互いに自白しないことで最も良い結果が得られますが、一方が自白した場合、もう一方は自白した囚人よりも良い取引を受けることができます。
全体を考えると最も良い選択はお互いに自白しないとなります。
しかし、個人で考えた場合は自白した方が良い結果を得られます。
こうして二人とも自分にとって最良の選択をした結果、二人とも自白するという最悪の結果を得ることになってしまいました。
これが囚人のジレンマです。
会社と従業員の関係
これを会社と従業員の関係に当てはめてみましょう。
会社と従業員は共に成功するために協力する必要があります。
会社は従業員に安定した収入や福利厚生を提供し、従業員は会社に貢献し、業績向上に寄与します。
しかし、時には従業員は自らの利益を最優先に考え、会社に忠実であることが難しくなることがあります。
終身雇用は経済学的に理にかなっている
過去の日本では終身雇用という制度が一般的でした。
この制度では、会社が従業員に安定した雇用を提供し、従業員は会社に長期間忠実に働くことが期待されました。
企業には長期で働く従業員が次世代にノウハウを伝えることで、ノウハウが蓄積され企業価値が高まり利益を上げやすくなる。
従業員も安定した雇用の下で仕事に集中し、会社をより良くするために忠実に働くことで業績向上に寄与する。
そんな、好循環は囚人のジレンマでいうと最良の結果をもたらしていました。
しかし、時代が変化し、現代では失われた30年と呼ばれる戦犯になっている大失政に伴い、企業が次々と限界を迎え保身に走る中で終身雇用が希少になっていきます。
こうして企業が自分の利益を優先し安定した提供を従業員にしなくなると、従業員も企業に貢献することは二の次となります。
その結果起こっていることが今まさに皆さんが日々経験している状況です。
終身雇用は時代遅れだという意見もありますが、囚人のジレンマから考えると、実は日本はむしろ強固な信頼関係の下、経済学的に非常に理にかなった行動を企業と従業員がお互いにとっていた非常に進んだ国だったのです。(なお、今は今で経済学的に理にかなった行動をお互い取っています。)
まとめ
今回紹介した終身雇用における企業と従業員の関係は囚人のジレンマの一例と言えるでしょう。
だからといって従業員が今さら企業を信頼して行動してもカモられるだけなので、この流れは変わることはないでしょう。
信頼関係は一夜で崩れるが、築くのは容易ではないということですね。(でも、信頼関係を築くには自分から信頼するしかない。)
(頭に流れる恐怖の声は無視し、たとえ何度も裏切られ心が無残に引き裂かれたとしても無条件に信頼し続けた先にきっとなにかがあるのでしょう。恐怖から自分を解放できるのは自分だけ。分かっていても想像しただけで恐怖という煩悩に支配されてしまう。というか今この記事を書きながらめちゃくちゃ恐怖に襲われている笑)
このように、会社と従業員の関係に限らず、囚人のジレンマに当てはまる状況は日常生活の様々な場面で直面します。
お互いに信頼し合い、協力することで、より良い未来を築くことができるので、少なくとも日本の政治や企業のように自ら信頼関係をぶち壊すような行動は避けるように注意しましょう。(おい!この記事を書いているお前はどうなんだ?信頼関係なんて意識して行動してなくなくなくない?)
この記事を読んで、経済学に少しでも興味を持った方は「アメリカの高校生が学ぶ経済学」やミネルヴァ書房の「MINERVAスタートアップ経済」シリーズもぜひ読んでみてください。
それでは、今日も皆さんがより良い関係を築けるよう、応援しています。お元気で!
〜Who am I ?〜
【参考図書】
よろしければサポートお願いします。
