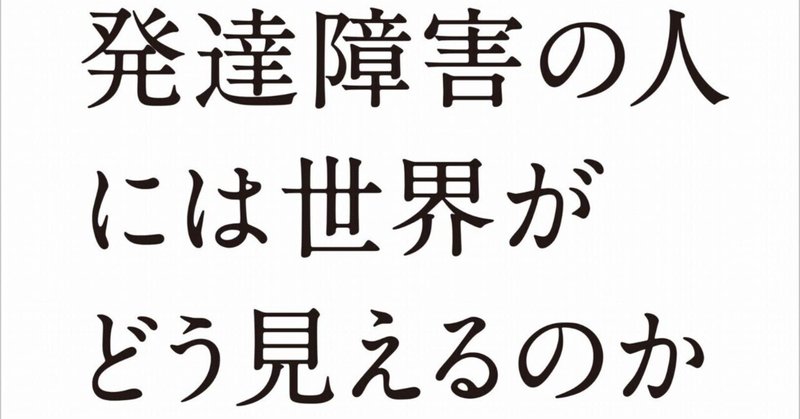
読書感想:発達障害の人には、世界がどう見えるのか
私もASDと診断された身として、自分のことをもっとよく知りたい!
ということで、この本を手に取りました。
確かにそうだわ!と思う部分と、同じASD者でも私と違う感覚の持ち主が沢山いるんだなという理解が深まりました。
この著者の井手さんは、認知神経科学者として、主にASDの知覚(嗅覚、触覚、嗅覚等)について研究されているらしいです。
発達障害とは
まず、発達障害とは先天性の機能障害で乳幼児期から発達の遅れが生じるもの。
そして、発達障害者特有の振る舞いが、脳の特性ではなく、本人の人間性や性格など、出来るのにやらないという問題で認識されてしまうため、周囲の理解を得られない。苦しいですよね。
なお、アメリカ精神医学会が作成している精神疾患の診断マニュアルというものが存在するらしく(最新版が2013年版)、ASDの判断基準は大きく2つあるらしい。
①社会的コミュニケーションからくる困難性
②個人の限定された反復する興味、行動、活動様式
そして、2013年の改定で新たに加わったのが、感覚入力に対する反応特性(感覚過敏・感覚鈍麻)とのこと。
つまり、五感が定型発達の人と比べて、鈍いのもあれば、鋭いのもあるみたいな。そして、この過敏な感覚と鈍麻な感覚は、一人の人間に共存しているということ。
ASD者は感覚が違う
感覚が違うと言われると確かにそう感じます。私の場合、寒い時期には友人から「そんな寒いか?」って突っ込まれるほど、ガタガタ震えています 笑
これは、本当に感覚が敏感だったんだなと納得しました。また、運動も動きが鈍いから、あまり得意ではない、、。
他の例だと、太陽の光に敏感すぎて暗闇を好むとか、嗅覚が強すぎて強い匂いを避ける人もいるんだとか。
鈍い人は、血を流すケガでも気づいていなかったり、寒い日でも平気で短パンを着ていたりする。
そう言われれば、いますよね。寒い日でもすごく薄着で平気な人。
木を見て森をみずになりがち
ASD者は、部分的な情報処理能力はすごいが、それらが組み合わさる全体的な情報処理は苦手とのこと。
これは、個人的にも良くわかります。一点集中しすぎて、全体が見えないし、部分と全体の意識のスイッチングが難しい。
これは、定型発達の人の脳が、効率性重視で処理する傾向があるのに対し、ASD者の脳は効率性をあまり重視しないからなんですって。ですから、1つの感覚を知覚するのに脳がパワーを使いすぎて、複数の対象を知覚するほど効率よくパワーを使えない。
なるほど、だから、一つの知覚にとらわれたら、なかなか抜け出せないわけだ。
コミュニケーションのとりずらさ
私は、集団で話を進めているときに、自分の意見を言うのは得意ではないです。
なぜかというと、複数の人たちの中で飛び交う会話の流れを見失うことがしばしばあって、的を得た発言ができるかな?と不安になるからです。
これは、ASDが自分中心で世界を見ているからだそう。定型発達の人は、他社中心で全体として世界をみれる。だから、ASD者は、あくまでも自分対個人の関係で状況を把握する傾向が強いため、全体で他人と他人が話す会話とかをトラックするのが難しく感じる。
これは、私も現在も訓練中ですが、全体を把握するって難しい!

ASD者の良い面
感覚の違いで問題も生じますが、素晴らしい面もある!
特に、画家、音楽家等にASD者も多く見られ、その繊細な感覚のおかげで、この世界を美しく表現できる。
特に、面白かったのが共感覚という概念。
例えば、①文字や数字に色がついて見える ②音に色を感じる ③味から形を想像する等
これは、ある特定の脳の領域の結びつきが強いために、定型発達の人にとっては、別々に感じられる感覚が、ASD者にとっては、くっついて感じとることができるために起こるらしい。
私にはない世界観ですので、なんか、うらやましい。
終わりに
もう、感覚が違うのだから、他人と違うのはしかたがないねって思います。感覚が鈍い強いで、世界の見え方が全然違うのだし、本に書いてある通り、隣人がみている世界は、本当に別世界である。
それを前提に、人と関わっていきたいなと思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
