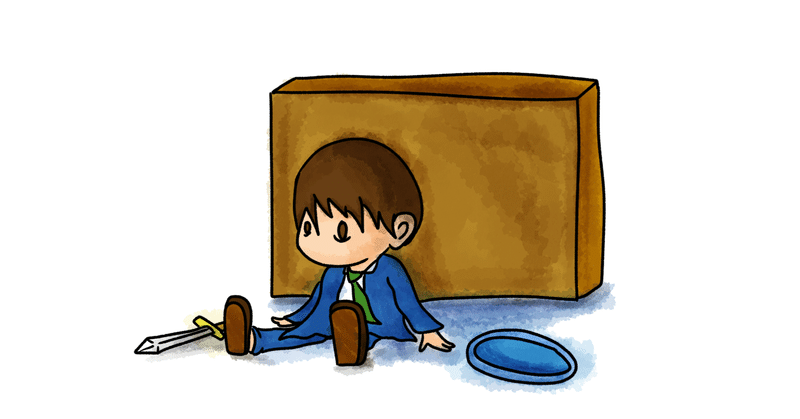
ゥツになった人への対応を学ぼう
ウツの人が増えてます。
まだまだ人ごとだと思うかもしれませんが、
家族や友人、職場の同僚など自分の身近な人が急にウツになる、ということもこれからしばらくは増えそうな感じです(理由はいろいろあります)。
ということで、
今日は普段なかなか声を大にして言えないことを、
思い切って書いてみようと思います。
身近な人がウツになったとき、あなたはどうしますか?
精神科かメンタルクリニックに行って
お薬を処方してもらうことをすすめますか?
ちょっと待ってください。
抗うつ剤は、ある種の覚醒剤であり、
うつを治療するものではないというのを知ってますか?
要は、ウツ(低活性)からラリった状態(過活性)に移行するだけという。
躁状態になってるのを、「おお、調子よさそう」などと間違っても勘違いしてはいけません。
そして、抗うつ剤の依存性は強力なのです。
覚醒剤なので当たり前ですが。
いったん飲み始めると、依存から抜け出せない無限地獄サイクルに入ることが非常に多いみたいです。
7年前にクライアントだった32歳の女の子は抗精神薬乱用依存になり、ピークどきは一日になんと100錠飲んでました(7軒のメンタルクリニックハシゴと、闇販売からも入手)。
3年ぶりぐらいに「助けて」とSOSの連絡があり、家まで行ってみたらゴミ屋敷と化した部屋に薬の包装が散乱してました。
そこまでいってしまうと、
「ヒャッハー」と「死にたい」のループで、理性がなくなりもう家族もセラピストも手の施しようがなく、、
彼女の両親と話し合って、うちで面倒見ることにしようとなって本人にも説得していたのですが、
薬漬けと共依存の彼氏とのコンフォートゾーンから脱出することを彼女は選びませんでした、、、
彼女いわく、
周りにも同じように抗不安剤や睡眠薬を乱用して無限ループにハマっている友だちはたくさんいるとのこと。
表には出てないだけで、
そういうケースは氷山の一角なのかもしれません。
向精神薬の依存や乱用により、人格が変わって攻撃性が増えたり、後遺症で認知障害になったり、自死することも少なくないという警告をしている治療家は少なくはないです。
抗うつ剤や睡眠薬は自殺のトリガーになる、ということも、実際にレポートされています。
しかし、そんな声は簡単にかき消されてしまう世の中です。
わたしは、そういった薬物中毒の実態も見てますし、薬物療法を始めてから、自死念慮に悩まされるようになった人を何人も知ってます。
実態を目の当たりにして、「これはやばいな、、、」と本当に感じています。
「ウツは、薬で治すもの」という思い込みがあったら、
一度そこに疑問を持ってみてください。
そして、ウツの本当の原因、特徴的な症状、解決策について学びましょう。
鬱を理解するのに、
心理学的な観点やスピリチュアルな観点などいろんな視点があることはあるのですが、
わたしが一番ウツに対する認識を深められたのは、「ポリヴェーガル理論」という自律神経の新しい理論です。
ポリヴェーガル理論によると
ウツは病気ではなく、自律神経の生命維持のための自然な防衛反応なのだと。
ストレスのある状況にあると、
自律神経が「危機的状況にある」と判断し、生命を守る原始的な反応として、
神経が
◯興奮→闘争•逃走モードになるか、
◯動かない、フリーズモードになるかします。
いのちを守る自然な身体の調整反応といっても、
実際はそこまでの危機的状況ではない時に、神経系がそのように判断して誤作動が起きてしまうのです。
それが一時的ではなく、
この誤作動(フリーズ)がずっと続いている状態がウツです。
興奮とフリーズを行ったり来たりするのが躁鬱病です。
これを解き放つ唯一の薬は、「安心感」と「絆(ぬくもり)」、この2つです。
子どものときに
この2つをインストールできなかった人が、健全に自律神経の調整機能を発達させることができずに、誤作動を起こしてしまうのです。
それで、ウツの改善にはトラウマセラピーが有効になるというわけですが、
たとえ専門的なセラピーを使わなくても、
家族や周りの人が、その人に「安心感」と「絆(ぬくもり)」を与え続けていけば、自律神経のフリーズは解けていきます(本人の神経トレーニングや腸活も必要です)。
ウツ状態の人を目の前にすると、どうしようかとオロオロしたり、
口にする「死にたい」という言葉に動揺したりするのが普通だと思いますが、
「安心感」と「絆(ぬくもり)」で、回復するということがわかっていれば、自然と対応が変わってくると思います。
誰でもできて、ものすごく効果があるのが、
背中や手を優しくさすって、「大丈夫だよ〜」と声をかけてあげることです。
手を当てるだけでもいいです。
身体が硬直して、顔色が土色で、表情が全くない人でも、しばらくそうしてると、筋肉が弛緩し血行がよくなり、表情も変わります。
ウツだけでなく、
「私たちが不安やストレスを抱えることによって、自分の意思とは関係なく働いてしまう自律神経のクセ」
は、いろんなパターンで私たちを困らせます。
たとえば、
◯身体が重たく、やる気が起こらない
◯引きこもり
◯無表情
◯キレる
◯テンションが高すぎる
◯眠れない
◯肩こりや頭痛が酷い
◯対人関係で疲れてしまう
◯すぐに緊張する
◯パニックになる
◯マシンガントーク
◯イライラ
◯落ち着かない
◯あらゆる発達障害の特徴
こういうことは,大なり小なり誰にでもみられることと思いますが、
すべて自律神経の調整不全ということになります。
自律神経ということは、オートマチックな働き。
自律神経のなすがまま、なので、本人の意図を超えてます。
そこがわからずにいると、
そういう人がそばにいたとき、
確実に対応間違えます。
なので、家族や仲間や友人、生徒、部下などのため、そして何よりも自分のためにそのような神経のしくみを学んでおくことは、これから誰にとってももっともっと必要なことになってくると、心から思います。
セラピスト、カウンセラーさんは必須です。
ポリヴェーガル理論の第一人者、浅井咲子さんの本2冊がとりあえずおすすめです。
「今ここ」神経系エクササイズ
「いごこち」神経系アプローチ
わたしがレクチャーしているポリヴェーガル理論のオンライン講座のアーカイブもあるので、ぜひこちらでも学んでみてみてください。
上の2冊の内容をベースに、これまでの臨床経験や独自の見解を2時間弱にまとめてお伝えしています。
本は、ある程度心のしくみやセラピーなどになじみのある人向けに書かれているので、それをもっともっとわかりやすくお伝えするように心がけています。
かなり濃厚な内容なので、おすすめです。
ここから先は
¥ 2,500
よろしければサポートお願いいたします。 いただいたサポートは、日本の空き田んぼの復興、農業シェアハウスコミュニティの発展のために使わせていただきます。
