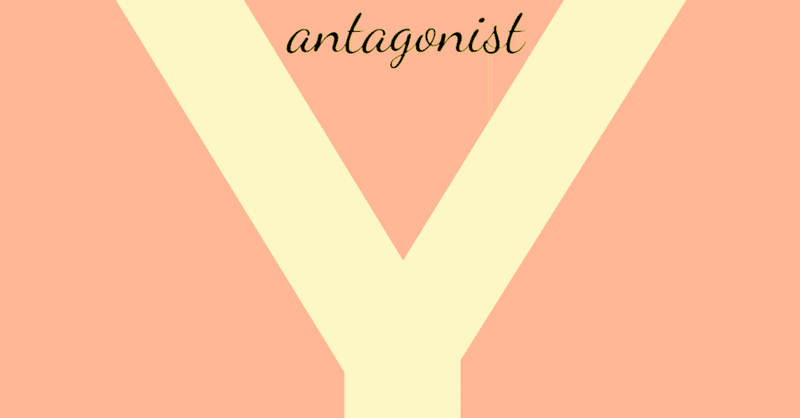
どこよりも楽に覚える抗うつ薬
このまとめ記事を読めば、抗うつ薬の理解はバッチリです。薬学生向け。
part単位で少しずつ読み進めてみてください。
※part1のみ無料で公開しています
<<part①三環系>>
抗うつ薬の基本方針は、モノアミン仮説を実践することです。
モノアミン仮説:
中枢において、手前の神経細胞から次の神経細胞へ向けて分泌されるモノアミン(セロトニン5-HT・ノルアドレナリンNAd)。それによって、神経細胞間の繋ぎ目「シナプス間隙」に滞留することになるモノアミンの量がうつの程度に関係する、とされている。
→シナプス間隙に滞留するモノアミン量が増えると鬱が改善される(はず)
この仮説を実践できる薬物、つまり、シナプス間隙に滞留するモノアミン量を増やすことのできる薬物が「抗うつ薬」として用いられています。
「抗うつ薬」には複数の種類がありますが、いずれも最終目的は同じです。やり方は違えど、結果としてシナプス間隙のモノアミン量を増やすのです。
この記事では、抗うつ薬のうち古いものから順にpartを分けて紹介していきます。
三環系抗うつ薬
抗うつ薬の中でも最も古い部類の三環系抗うつ薬ですが、シナプス間隙のモノアミン量をどうやって増やすのでしょうか?
その答えは…
モノアミンの「再取り込み」を阻害する
です。
初見ではピンと来ない文章だと思いますので、まずは「再取り込み」という言葉を理解しましょう。
「再取り込み」とは…
一度シナプス間隙へ分泌された物質(今回の場合はモノアミン)を、分泌した神経細胞自身がトランスポーターと呼ばれる窓口を使って回収する行為。
一言で言えば、「やっぱ分泌やーめた」です。
三環系抗うつ薬がモノアミンの「再取り込み」を阻害すると…
→「やっぱ分泌やーめた」ができない
→シナプス間隙に滞留するモノアミン量が増加
→うつ改善
という流れになります。
即ち、三環系抗うつ薬の作用機序は「モノアミン(5-HTとNAd)トランスポーター」の阻害。
その阻害作用は強力ですが、余分な骨格パーツが多いせいで、様々な受容体遮断作用がオマケでついてきてしまうのが三環系のデメリットです。
具体的には…
・ヒスタミンH1遮断作用 →眠気など
・自律神経系(NAd、アセチルコリン受容体)遮断作用 →血圧や脈の変動、口渇など
三環系抗うつ薬の名前の特徴は、
・〜プラミン(pull+amine) →シナプス間隙にアミン(amine)を引っ張り出す(pull)
・トリプチリン トリは「三」環系を意味する
※余談ですが、この三環系抗うつ薬の副作用であるヒスタミンH1遮断作用を主作用として流用しているのが、花粉症などに使われる抗H1薬です。そのため、抗H1薬の副作用には「抗コリン作用」が名残として残っているのです。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
