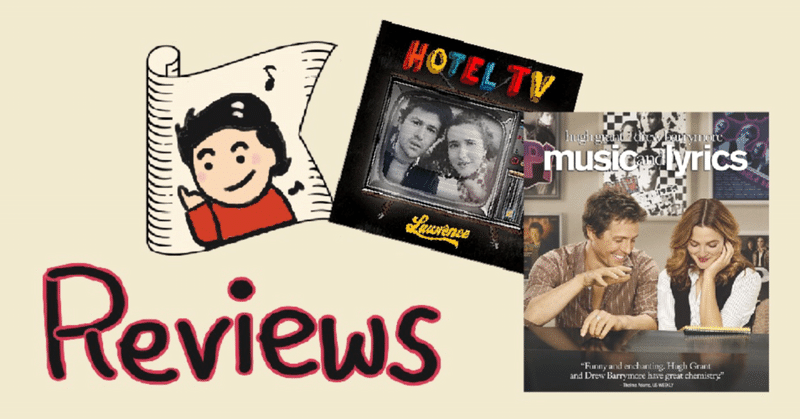
『ラブソングができるまで』〜続・ローレンス〜
マーク・ローレンスとLawrence、ときどきシュレシンジャー
【前回までのあらすじ】
で。ですね。
ローレンス兄妹がいわゆる“ええとこの子”だということは、デビュー当時からよく知られている。
でね。
で。
(続く)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(やっと前回の続き)
前回は、先月ニュー・アルバム『HOTEL TV』をリリースしたバンド“Lawrence” のアルバムがどんなに素晴らしいかについてレヴューした。
バンドの中心メンバーである、クライド&グレースのローレンス兄妹はニューヨーク生まれ。マンハッタンの超高級住宅エリア、ドラマ『ゴシップ・ガール』の舞台でも知られるアッパー・イーストサイドに育ち、3歳半違いの兄妹はともに全米屈指の名門私立高ダルトン・スクールを卒業、アイヴィーリーグの名門ブラウン大学に進学している。
父親は有名な映画製作者で、ふたりは幼い頃から文化的で裕福な家庭環境に恵まれて音楽の才能をのびのび開花させてきた…みたいなプロフィールを、デビュー以来あちこちの記事で読んだ。
つまり、“ええとこの子”である。
まさにリアル“ゴシップ・ガール”といって過言ではない。
もし彼らがもうちょっと早く生まれていたら、イヴァンカ・トランプ夫妻やジェシカ・スプリングスティーンのようにドラマの主人公たちの友人役としてカメオ出演していたに違いない。
この、彼らの“ええとこの子”感は心地よい。好きだ。決してイヤミでも皮肉でもなく、魅力的だ。
いわゆる「うちのパパは金持ちなんだぜ。えへん」みたいなスネ夫ポジションとは違う。“ええとこ”の“ええ”とは、必ずしもあからさまにマネーを指しているわけではない。もっと芸術的な意味でのアドバンテージというか。マニアックだけど無邪気で明るくておおらかなところとか、決して超・超・王道というわけではないマニアック路線なのに、自分たちが面白ければいいじゃん…というブレのなさ。ポップ・ミュージックの作り手としてはひとつの課題となりうる、いい意味での“ハングリー精神の欠如”(笑)に生まれつき恵まれている感というか(ほめてますよ)。
もうひとつ、総じて“ええとこの子”は意外とオトナ受けがいい。ワルガキぶってても、なにげにオトナとのつきあいに慣れていたり。敬語もなめらかにつかえたり。ローレンスがインディーロックなのにわりと中高年ウケがいいのも、そういうキャラが反映されている気がする。いい意味で。
あくまで“いい意味で”の“ええとこの子”というのは、自分で言っておきながらよくわからないけど、つまり日本でいえば安達哲のマンガ『バカ姉弟』みたいな反骨精神イメージかしらん。
まぁ、姉と弟が兄と妹にひっくり返ってるバージョンだけど。
と、しばらく前からそんなことを思っていたものの。彼らの細かい家庭事情などはググることもなく、現在に至っていた。
ところが先日初めてWikipediaにて兄妹のプロフィールを確認してみてびっくり。
《著名な映画製作者を父に持つ》の《著名な映画製作者》って、マーク・ローレンスだったのか!
びっっっっっくら!
ていうか、これ、知らなかったのワタシだけなんですか? もし「そんなの常識だぜ、みんなとっくの昔に知っていたよ」ということでしたら、以下、今ごろビックリしている微笑ましい人の談話として、しばし優しく見守ってください。
ローレンス兄妹の父こと、まさかのマーク・ローレンス。
マーク・ローレンス(1959〜)は、ブルックリン生まれの映画プロデューサー/監督/脚本家。
マイケル・J・フォックスの出世作である、80年代の大人気シット・コム『ファミリー・タイズ』のスタッフ・ライターで注目を集めたのをきっかけに、映画/テレビの世界で幅広く活躍。『デンジャラス・ビューティー』(2000年、製作総指揮・脚本)や『噂のモーガン夫妻』(2009年、監督・脚本)などの大ヒット映画も手掛けている。なぜかヒュー・グラントとの仕事がものすごく多い人みたいで、特に監督や脚本手がけた映画に関しては大半がグラント絡みだ。
そして。
我々のような音楽ファンにとってマーク・ローレンスといえば、なんといってもヒュー・グラント&ドリュー・バリモア主演のラブ・コメディ『ラブソングができるまで』(2007年/原題:Music and Lyrics)の監督・脚本家として有名。

●現在、Netflix、U-NEXTなどでも見られます!(※2021年8月現在)
すでにご覧になっている方も多いかもしれないけど。
この映画は、80’s ポップ好きだったら物語の本筋とは関係なく涙なくしては観られない…というか、ポップスを愛するすべての音楽ファンにとってマストな1作。ほんとに、まじでマストです。
↓英語版予告。
物語は、80年代に大ヒットを飛ばした人気ポップ・グループのヴォーカリストだったアレックス(ヒュー・グラント)が、姉の経営するダイエット・ショップで働いているけれど実は作詞家としてものすごい潜在能力を秘めているソフィー(ドリュー・バリモア)と偶然に出会い、ひょんなことからソングライティング・コンビを組むことになり、しかし最初は相性サイアクで、それでもいろいろあってやがてふたりの心は……という、もう、水戸黄門ばりにお約束あるあるの王道ドタバタ胸キュン♡ラブコメ。
しかも、主人公の設定が作曲家と作詞家(正確には、作詞の才能を秘めたタマゴ)ということで、まさに原題どおり“Music and Lyrics(曲と歌詞)”が出会い、結びつき、溶け合って名曲になってゆく過程が、だんだんと恋に落ちてゆくふたりのストーリーと重ね合わせて描かれているのだ。どうよ。
音楽ファン、特にキング=ゴフィンやマン=ワイルなど実際に“恋に落ちたソングライターコンビ”を愛するティン・パン・アレイ系ポップス好きにはたまらないラブストーリーだ。
バート・バカラックもキャロル・キングも、いつの時代にもすぐれたソングライターたちは名曲の誕生を恋愛や結婚にたとえる。
本当に、そういうことなんだと思う。
ならば、恋が育ってゆく過程をソングライティングと同時進行にしたら……というアイディア。音楽を愛していなければ思いつかない。そりゃ、子供たちも音楽まみれの環境で育つわけだ。
で、この映画の見どころは、とにかく題材が題材だけに音楽ネタ。
(以下、軽いネタバレですがいろいろバレます。そもそも、曲を紹介するだけでネタバレる映画なので。まぁ、バレてもバレなくても面白さは変わらないと思いますが、未見でネタバレ苦手な方はNetflixなどでも見られるので今すぐぜひ!)
そもそもアレックスが「オレは過去に生きているんだ」と公言してはばからない俺様キャラの懐メロ・スターなだけあって、80’sポップのマニアックで細かすぎるネタが全編にみっちり。同時に、公開当時の00年代ポップ・シーンの雰囲気とか、まだまだお元気wだったVH1やMTVの懐メロ番組っぽい映像の再現とか…現代のショービズ模様も随所に登場する。
会話にも小ネタ満載。第二のブリトニー・スピアーズとして全米に旋風を巻き起こしている歌姫がアレックスにヒット曲を書いてくれと熱望する場面では、ショービズ界の頂点を極めつつある彼女が「シャキーラが下から迫ってるのよっ!」と半泣きで本音を口走ったり。アレックスが久々にテレビ出演依頼されるも、懐かしの80年代スターたちを悪ノリでいじるリアリティ・ショウ企画だったとか。もう、どれもこれもいかにもありそうで爆笑。
▲アレックスは、80年代に一世を風靡したポップ・バンド”PoP!”のヴォーカリストという設定。デュランデュランとカジャグーグーを足して、さらにお調子者にしたようなバンド?? バンド名も、いかにもありそう。
ちゃんとPVも完璧に作られている!
80年代は大真面目に作っていたはずだけど、今になってみたらおバカ映像でしかないテイスト。これなんか、もう、完全にローレンスの大好物じゃないですか。
この曲はPoP!最大のヒット曲である、1984年発表の「PoP Goes My Heart」(←あくまで劇中設定)。
サビの♪Po—P!のところで、アレックスがセクシーにお尻をぷりっとさせる決めポーズが有名だった…という設定で、おじさんになった今でもお尻をぷりっとさせては当時ファンだったお嬢さんたちを熱狂させているのも笑える。
ちなみに、アレックスはPoP!解散後に唯一のソロ作を出すのだけれど…それがパッとしなくてねぇ。まぁ、劇中ではそれほど詳しく「パッとしない」様子は語られないのだが。レコード屋でひっそりとホコリをかぶっている、そのソロ・アルバムのジャケのダサさを見れば一目瞭然。しかも、なんつーか、ジャケをチラ見せするだけで、そのソロが「あんまり乗り気じゃなかったんだよね」的なものだったことを匂わせちゃう。うまい。
このあたりの容赦ない80’sダサ文化の使い方、ひょっとしたらジョン・メイヤーもこの映画を見てニュー・アルバム『SOB ROCK』のアイディアを得たのではと思ってしまうくらいの見事。
そして、第三の主役。そんなアレックスに曲を依頼する当代随一のスーパー・ディーヴァ、コーラちゃんのキャラがまた最高。東洋のスピリチュアルに傾倒しているらしくて、PVもこんなありさまに。スーパーディーヴァだけに止めてくれる人もなく、この後、マディソン・スクエア・ガーデンでのステージはさらに激しくおかしなことになっている。
Buddha’s Delight
コーラちゃんを演じたヘイリー・ベネットは、いちおこの作品が出世作ということになっている模様。
それにしてもこんな歌手いたっけ?と思ってしまうほどの見事なディーヴァっぷり。歌もうまいし。他にも何曲か歌っているのも全部いい感じ。が、もともと歌手ではなく女優だそうで、やっぱアメリカは奥深いな。その後は順調にキャリアを重ねて、最近ではNetflixの話題作『ヒルビリー・エレジー』などでも好演している。
ま、何度も書いているように、ストーリー自体は昔ながらのオーソドックスな王道ラブコメ。だけど、それをとりまくマニアック・ネタの膨大さがハンパない。チラッと映るテレビ画面やポスターひとつとっても面白いので、何度見ても飽きない。
物語の土台はスタンダードでシンプルながら、それをとりまく設定やら小ギャグの連発やら、マニアを唸らせるくすぐりネタやらで飽きさせない……という作風、公開当時は「ああ、さすがシットコム出身の監督だな」と感心しておりました。
が。今では「ああ、さすがローレンス兄妹の父ちゃんだな」ですよ。
もう、この芸風、親ゆずり……というか、親子で一緒じゃねーか(萌)。
それにしても、ですよ。
こういう“名曲”が主役の映画でいちばん難しいのは音楽ですよね。
美女という設定の役者が美女に見えるよう演じられなかったら話にならないように、“名曲”という設定の曲が名曲じゃなかったら物語全体のリアリティがなくなってしまう。
そんなわけで、実に単純な定番ラブコメと言いつつも、この作品は絶対に“名曲ありき”でなければ成立しないというハードルの高さを最初からわかって作っているわけですよ。ローレンスの父ちゃんは。
そして実際、この映画はとにかく何よりも音楽が素晴らしい。
そこが最大の魅力。
で、この映画の音楽担当は、誰あろう、アダム・シュレジンジャー。
そうなんです。
悲しいことに昨年4月1日、COVID-19の合併症により51歳の若さで亡くなった名ソングライターにしてベーシスト、ファウンテンズ・オブ・ウェインの故アダム・シュレシンジャーだ。
そりゃ素晴らしいに決まっている。
シュレシンジャーは1997年、トム・ハンクス初監督作品『すべてをあなたに』の主題歌である「That Thing You Do!」で一躍その名が知れ渡った。架空のバンド“ザ・ワンダーズ”を主役にした青春恋愛音楽映画で、バンドはデイヴ・クラーク・ファイブを原型にしていると思われる(根拠: ドラム音のデカさw)。
この曲がもう、名曲すぎた。
ある意味、この曲そのものが映画の“主役”といってもよい作品。この曲があまりに素晴らしかったことの功罪ゆえバンドが“ワン・ヒット・ワンダー(一発屋)”として消えていった…という映画のストーリーは、すべてはこの曲があったからこそ成立したのだと思わせる。それくらいの超名曲。
そして、『すべてをあなたに』と同じように“名曲”が陰の主役となっている『ラブソングができるまで』でも、シュレシンジャーは主題歌の「Way Back Into Love」という奇跡の名曲を生み出したのだった。
↓コーラのために書いたこの曲を、彼女のマディソン・スクエア・ガーデン公演でアレックスがゲストとして登場して一緒に歌うクライマックス・シーン。
個人的にはジェイソン・ドノヴァン&カイリー・ミノーグの「Especially for You」(1993年)を連想してしまった。
最高の甘酢っぱヤングアダルト・バラッド。
でも、実はこの完成ヴァージョンよりも、ようやく曲が完成した場面でアレックスとソフィアが自宅でデモテープを録音する場面でのシンプルなデモ・ヴァージョンが最高なんです。何度見ても涙してしまうー。この場面もYou Tubeにクリップあったのですが、ここだけは絶対に本編で見るのを激しく推奨したいです。と言いながら、音だけでも…↓
ソングライティングという作業を通じて、ガンコなふたりの心がだんだんと近づいていって恋が育まれてゆく…という図を、音と映像を通じてこんなにもロマンティックに端的に描いた恋愛&音楽映画は見たことがない。
で、フツウに考えたら曲が書きあがったところで恋が成就…となるはずなのだけど、“ほぼ完成したけど、まだデモ段階だよ”っていうのもひとつのメタファーになっていて。デモverと完成verを比較すると、この2ヴァージョンが「恋は、芽生えた時とゴールインした時とではどっちが盛り上がるでしょうか」的なテーマも提示しているような気がしてくる。
いやぁ、うまいなー。
余談ですが、アレックスの仕事場にキンクスのポスターが貼ってあるんですよ。ナルシストのアレックスのリヴィングにはPoP!時代のポスターとかゴールドディスクばかり飾られているのに、仕事部屋にそっとキンクス。そこに気づいた時、キュンとしました。そして、そういえばシュレシンジャーのファウンテンズ・オブ・ウエインっていうのもよく「キンクスっぽい」と言われてきた。そんなことも思い出して、さらにキュンとする。
こんな素敵なメロディをいつもたくさん頭の中で育てていたシュレシンジャーがもういないなんて。あらためて寂しさがこみあげてくる。
シュレシンジャー作品としては、アレックスがピアノの弾き語りで歌うバラード「Don’t Write Me Off」も最高。
ちなみにサントラは全曲を彼が手がけているわけではなく、周辺人脈を中心とした複数のソングライターによって書かれている。が、いずれもよく練られた佳作揃い。PoP!のヒット曲を手がけているのは(笑)『アリー/スター誕生』でレディ・ガガが歌った「Shallow」の共作でグラミー&アカデミー受賞したアンドリュー・ワイアットだし。
ワイアットはマーク・ロンソン系の人脈でもありますが、シュレシンジャーやロンソンやこのあたりの人たちはみんな“真摯なナンチャッテ”の天才ですね。ナンチャッテと言うのはちょっと言葉がよくないけれど。自分が生まれるより前の時代、あるいはオトナになるより前に世を賑わせた音楽に心惹かれてしまうタイプの音楽ファンが頭の中に作る、イマジナリー・フレンド的な意味での(ものすごくいい意味で)まちがっている60年代とか80年代とかの音楽シーン…みたいな世界観をポップにカッコよく構築する名人が多い。そんな印象。
↓オリジナル・サウンドトラック(Spotify)。こんなアルバムまでサブスクにあるなんて、現代社会に感謝。
で。
ですね。
主題歌「Way Back Into Love」は別格として、それ以外で私がいちばん好きな劇中曲は「Dance with Me Tonight」という曲なんです。
アレックスが遊園地でおばちゃんファンに囲まれて歌うわびしい(というか、せつない)営業ライヴで歌われる曲なのだが、物語としてはちょっといい展開になる大事な場面。なので、この場面で使われる楽曲ということは、おそらく脚本段階から「大ヒット曲ではなかったけれどコアなファンには支持されていた、知る人ぞ知る隠れ名曲」みたいなキャラ設定がされていたんじゃないかと推測される。
軽くノスタルジックな雰囲気の三連バラードで、だけど本格的なオールディーズ調というほどではなくて絶妙にゆるい。そのさじ加減がめっちゃ素敵です。
80年代、それこそジェイソン・ドノヴァンとかリック・アストリーとかがアルバムの最後に入れそうな曲…といえば、おわかりいただけるだろうか(笑)。
おまけに、日本人には妙にフレンドリーに響くムーディなイントロ。まさに“歌謡”なエモさ。思えばワム!の「ケアレス・ウィスパー」を筆頭に、たしかに日本でも洋楽が大人気だった80年代にはこういう歌謡フレンドリーな洋楽がいっぱいあったなー。なんてことを思い出させてくれたり。そういう時代感を含めての名曲、芸が細かい。
で、私は長いこと、これは絶対アダム・シュレシンジャーの曲だと勝手に思いこんでいた。しかーし、今回あらためてサントラのクレジットを見て驚いた。
本当に驚いた。
ある意味、ローレンス兄妹の父がマーク・ローレンスだと知った時以上に驚いた。
この曲を書いたのは、クライド・ローレンス。
そう、ローレンス兄なのです!
まさか、こんなところですでに出会っていたとはねー。
それにしても、ちょっと待てよ。
兄は1994年生まれということになっているから、単純計算しても2007年の公開時には13歳。
13歳にして、40歳のオタクがにやにやしながら作っちゃいそうなレトロ・ポップスを書いてたのか⁉︎
ある日「社長の✗✗でございます」と名刺を出してきたスーツ姿の立派な青年が、昔、先代であるお父さんに連れられて遊びに来たことのあるやんちゃな幼稚園児だったと気づいた時の衝撃(実話)に勝るとも劣らぬ衝撃だ。
この父にして、あの兄妹あり。
そりゃローレンスがおませなわけですよ。
つまり私はローレンスというバンドが世に出る前からローレンスのファンだったんだな。
そういうことか。
ソフィア・コッポラも、子供の頃に父親との共同名義で短編映画の脚本を書いたり、衣装を担当したりしていた。彼女にとっては夏休みの自由研究くらいの無邪気なものだったのかもしれないけど、これが本当に素晴らしくて。個人的にはソフィアの関わった映画の中でいちばん好きかもしれないくらいの作品だったりする。
だからローレンス家の場合も、子供の頃から曲を書いたり俳優をやったりするのも決して親バカえこひいきというのではなく、クリエイターである親が子供の才能をちゃんと見抜いて、それをどう伸ばすかを考えてあげていたのかな。
“ええとこの子”の世界は深いな!
さて。これを書いていたらまた『ラブソングができるまで』が見たくなってきた。
しかし、この日本タイトルもいいですよね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
