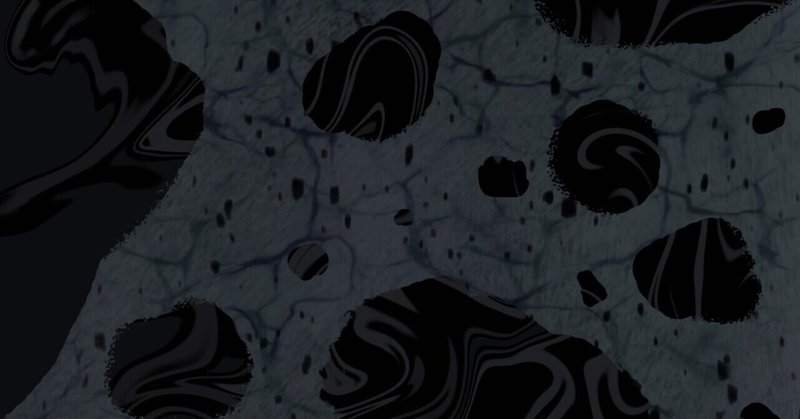
短編小説『鬼が嗤う』
日暮里駅で常磐線に乗り換え、南千住駅で下車。十八時。大学の友人と落ち合う。飲み屋へ向かう道中、まいばすけっとの前で煙草をふかしながらワンカップを飲んでいる中年の日雇い労働者たちが視界に入る。彼らはわれわれの存在に気づくや否や、会話を中断し、頭のてっぺんから足の先までじっとりと湿った目で眺め、薄ら笑いを浮かべた。そのうちの、ガードレールに凭れ掛かり泥酔している一人が、何か呻きながらわたしの足を触ろうとしたが、呂律が回っておらず、何を言っているのか聞き取れなかった。
飲み屋に入り友人は生ビール、わたしは黒ホッピーを頼む。周囲の人間からホッピーが好きだと思われているらしく、しばしば「この店、ホッピーあるよ」と注文する前に先手を打たれるのだが、べつに好き好んで飲んでいるわけでは無い。願わくは上等の日本酒を飲みたいものであるが、吝嗇な心の持ち主なので、その値段相応に酔わなければと意識し過ぎるあまり、かえって気が張りどうにも落ち着かないのだ。そういう意味では確かに、好き好んでホッピーを飲んでいるということになるかも知れない。ああ、これでちゃんと酔っ払えると思うと安心する。何より分相応の味がする。二人の間に沈黙が訪れるたび、脳味噌の奥底まで届くよう、深く深く酒を飲む。
今回友人を誘った際、「話したいことがあるから丁度良かった」と言われた。彼女は在学中から交際している人が居るから、もしかしたら結婚の報告かも知れないと思い、その場合こちらから訊ねるべきなのだろうが、まだ「それで、話したいことって?」と砕けた笑いとともに水を向けられるほど、思考の針が抜けていない。彼女のことはとても好きだが、会うのが数ヶ月ぶりなので少しく緊張する。数ヶ月ぶりと書いたが、正直に打ち明ければたった二ヶ月ぶりだ。二ヶ月を数ヶ月と書いて虚勢を張った。醜く愚かである。とにかくどうにかこの場を、彼女にとって楽しいものにしたい、無駄な時間だったとか、退屈だとか感じさせたくない。しかしどんな話をすれば楽しんでくれるのか、面白がってくれるのかが分からない。分かる為には早く“正気”にならなくては、と四杯目のナカを頼む頃、友人自ら「話したいことがあるって言ったの覚えてる?」と切り出して来た。まだ待ってくれ、いや、待つ必要は無いのだけど。おめでとう、結婚してもわたしとこうしてたまに遊んでね。祝儀袋には三億円包みます。──こんな具合か?ああ、完璧だ。早速「勿論覚えてるよ。何があったの?」と訊く。すると友人は笑いを噛み殺したような表情で「最近見てやばかったグロ動画の話なんだけど」と思いがけない方向から話し始めたのだった。曰く、とあるイベントで御神籤のようなものを引き、USBメモリが当たった。帰宅し、彼氏とデータを確認したところ、「※グロ注意」というファイル名の動画と、その内容に関する注意書きの記されたファイルが入っていた。さすがに怖かったので、先に彼氏に動画を視聴してもらい感想を訊くと、注意書きの通りの内容だったと言う。勇気を振り絞り、再生ボタンを押し、急いでPCから離れる……知らない男が笑いながら嘔吐し始め、撮影者が男にコップを差し出すと、そのコップに嘔吐し、それを飲み干し、また嘔吐する……。婉曲表現を一切用いない友人の口振りに一頻り笑った後、思い切って「話したいことってそれだけ?結婚とかじゃなく?」と言うと、「うん。だってこういう話出来る人、他に居ないから」と友人はわたしの目を真っ直ぐに見た。丸くて大きな黒い虹彩。虹彩は何故こんなにも丸いのだろう。それも、みんながみんな。どういう状況であろうとも、数少ない大切な友人が、わたしが不在の場でわたしのことを思い出してくれたというのは、かけがえのないことだと思った。幸いなるかな。もしかしたら、少しだけ許されたのかも知れないとすら思った──誰に?誰でもいい。そして、たとえこれがアルコールの回った脳味噌が齎す馬鹿げた妄想だとしても、きっと重要なサインの一つに違いないのだ……。
その後も、烏龍茶を飲む友人を横目にナカを頼み続け、頭の中が気持ち良く、なにも憂うことは無い、目を瞑ればそこには青く澄んだ地球があって、一人残らずすべての人間を知覚し、愛することさえ出来ると思った。何より、実際に出来ていた。ジョッキの中にゆらゆらと、個と全とがまろやかに混ざり合い、懐かしい歌を歌っているのが見える。この歌が聞こえているうちは、まだ大丈夫。世界中の人の手に触れる。誰もここから居なくなることは無い。何もかもが永遠によい感じである。このまったき真実を、無言のうちに友人と相互に確認し合い、合意に至り調印、店を後にする。「もう秋だね」と友人が言うが、それが何を指すのかさっぱりわからない。分からないけれども「そうだね」と返す。何故なら、彼女はいつでも正しく、わたしはいつでも間違っているからだ。
駅で別れると、発車案内板に「遅れ三十分」とあった。電車が遅れているのだ。三十分。折角だし少し、例の秋とやらの中を散歩したいような気持ちになり、高架下を歩く。まだ歌が聞こえる。失くしたと思ったものもここにあり、今あるものもずっと変わらずここにある。いつまでもずっと。強い衝撃。後頭部を何か、硬い、重くて硬い、金属か何かで以って殴打される。前のめりになる。振り返る前に、すぐさま同じ辺りを再び殴られ、転倒する。あまりの激痛に吐き気がする。血が出ているような気がする。何が痛くて何が痛くないのか、これは果たして痛いのか、どこまでが自分の体なのか、何も判別出来ない。悲鳴を上げたのかどうかも不明である。更に数回殴られたのち、スカートの中に乾いた手が入ってくる気配があり、反射的に脚を蹴り上げる。靴の先が何かに当たり、ギャッという男の悲鳴が響く。暗いからなのか、それとも意識が混濁しているのか、男の顔はまったく見えず、ぼんやりとした黒い影が緩慢に揺れている。「クソ女が!」という声の後、顔面を強かに蹴られる。鼻の下から頬へと液体が伝う。この前生まれて初めて鼻血を出したが、こんなすぐにまた出すとは思わなかった。わたしの兄はよく鼻血を出す子供だった。鼻からぼたぼたと血を流し、口の辺りに受け皿のように手を差し出す姿に憧れ、幼い頃、鼻の穴に針を刺して母親に怒られたことがあった。などと思い出していると、ぬるま湯のようなものを顔にかけられた。匂いから察するに尿だった。その間も男は痛々しげにアーだのワーだの呻いていた。排尿を終えると、「クソ、ド腐れきちがい女、ぶっ殺してやる、このブス」とかなんとか悪態をつきながら何故か去って行った。しばらくぼうっとしたのち、立ち上がり駅に戻った。トイレで顔を洗い、再び発車案内板を見遣る。電車はもう行ってしまった。ベンチに倒れ込み、真っ暗な空を見上げる。またあの歌が始まる。
無職を救って下さい。
