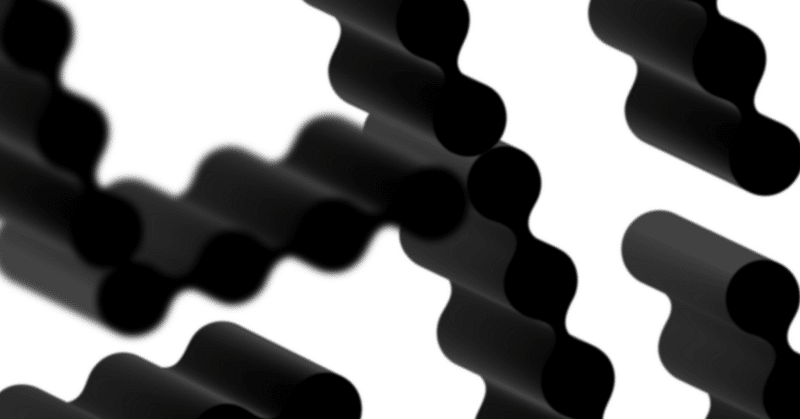
短編小説『悲劇の名称』
知らない友人の家へ遊びに行く。茶色く色褪せたコーデュロイのソファに座り、体と体の間に世界地図を広げ、この国に行くにはどれくらい時間が掛かるのだろうかというような話をする。トルコは十二時間くらい掛かると思うと友人が言う。わたしは同意して頷く。金色の包み紙に入った、手のひらにすっぽり収まるくらいの、丸い、硬貨のようなチョコレートを一枚ずつ食べる。包み紙の裏に、彼女は自分の名前を書きつけてわたしに見せる。インクが薄くて判読出来ない。よく見えるように顔を近づける。チョコレートの甘い香りがする。字はやはり読めない。私のそんな表情を見て、彼女は笑いながら包み紙を小さく丸める。そしてそれを、服のポケットにしまってしまう。細い腕を、蛇のように首に巻きつけられ、抱き締められるような格好になる。ゲッカコウとシクンシ、旧世界の砂で出来た赤い花。下品なネクタイを締めた老人の、色欲にまみれたほほえみ……。
友人はわたしを抱き締めたまま、ソファから立ち上がる。首にまわっていた腕は、それぞれ肩と腰の辺りに回され、二人並んで歩くのがやっとの狭い廊下に連れ出される。廊下の照明は消されているが、小さな丸窓があり、冬の空にあがる煙突の煙のような曖昧な光が、わたしたちの周りをぼんやりと漂っている。
左手に階段がある。この階段が上の階に続くのか、それとも下の階に続くのかが分からない。まったく見当もつかない。友人の体温を感じながらふと、先ほどの部屋に、家の鍵や祖母の形見の指輪のような、何か大切なものを忘れたような気がしてくる。あるいは十五歳のあの夕方のこと、誰にも言っていない秘密が、知らず知らずのうちにどこかで露見してしまっているような気がしてくる。しかし友人は、そのようなわたしの心配には気付いていない様子で、あるいは単純に気付きながらも無視をして、埃っぽいシルクのカーテンを片手で開き、中に連れ込まれていく。その手で、壁にある螺子のような摘みを右に捻ると、蝋燭の形を模したガラス製の照明が灯り、少しだけそこの様子が明らかになる。部屋の中はあまり広くなく、いくつかの円形や四角形のテーブルが、ほとんど隙間無く押し込まれている。その上に、人形遊びに使う、小ぶりな陶器の食器や猫の置物、用途不明の大小さまざまな真鍮の計器類といったものが様々に、無造作に──それでも無意味では無く──配置されている。
友人が机の下にもぐる。わたしの体に回されていた腕が消失する。音楽の裂け目から出て来た幽霊が、耳の穴に入ってくるようだ。誤って人を殺してしまい、慌てて死体を埋めて逃走する。場所は鮮明に記憶しているのに、もう何度探そうとも、もうふたたびその死体が見つかることは無い気がする。眠っている間に悪魔に全身を縛られ、遠い国の雪深い山奥に棄てられる気がする。古い日記の最も醜悪な一文が、火をつけても燃えること無く、永遠に残り続ける気がする。部屋に飾ってあるすべての花たちが、萎れて粉々に散り、それを吸ったがために肺の病気で死んでしまう気がする……。わたしは彼らの無理解を感じ、ただ視線を落とし続けた。その視線の先、友人が居なくなった辺りとは異なるテーブルの下に、金色の包み紙を見つける。わたしはそれを拾う。包みを開き、そこに書かれた文字を見つめる。先程と変わらないのに、今度は一文字一文字正確に読み取ることが出来る。わたしは、今知ったばかりの友人の名前を口にする。それがこの世に齎される、最後の悲劇を示す名称であるとは知らないまま。
無職を救って下さい。
