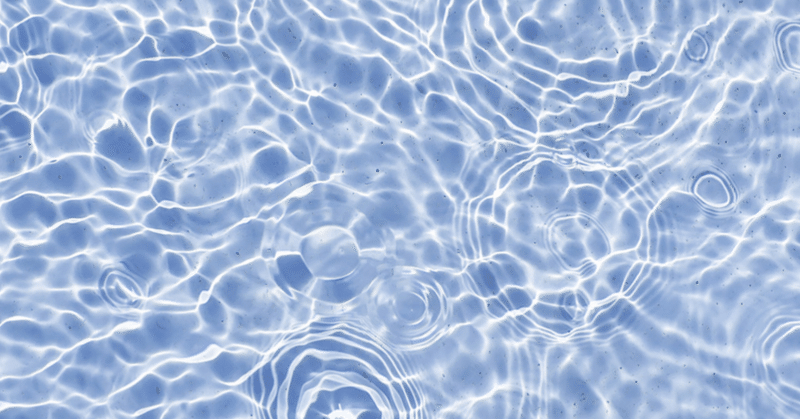
短編小説『オーロラの泡』
起床する。バッハの平均律クラヴィーア曲集が聴こえる。足音を立てないよう寒い廊下を歩き、ダイニングに向かう。ドアを開ける。母が気怠そうにトーストを囓りながら、朝刊を読んでいる。トースターにパンを挿れる。母の斜向かいの席に着く。少し離れたところにあるソファに凭れ、ウイスキーを飲みながら、アメリカの戦争映画を観る父の後ろ姿が目に入る。灰皿の上には、煙草の吸殻が山となり積まれている。幼少期の朝の風景。トーストが焼き上がる。りんごのジャムを塗る。ふと母が顔を上げ「あなたのお父さん、ゆうべまた事故に遭ったんだって」と言う。父はいつも泥酔して車を運転し、交通事故を起こす。誰も轢いたことが無いのは奇跡だ。そして彼もまた、必ず無傷で帰って来る。車だけが大破している。たまにいい具合に酒に酔うと、彼は直近の事故の様子をわたしに話して聞かせた。結びの段階に入ると、決まって「ドイツ車は馬力が違う」とうっとり夢見るような口調で言う。スピード狂のアル中。彼の見る戦争映画がいつも同じものだったのか、それとも毎回違うものだったのか、今となっては判然としない。性格から推し量るに同じものを観ていたんだろうが、父親の性格なんてほとんど知らないに等しい。
わたしは飲み込むようにして朝食を平らげ、母に「お兄ちゃんの分は?」と訊く。「もう持って行った」と新聞に視線を戻し、母。兄はいつからか自分の部屋でしか食事を摂らなくなった。母かわたしのどちらかが、彼の部屋に食事を届ける。大抵母が持って行くが、たまに忘れることがある。だから念のため確認しておく。牛乳を飲み、何とも無しに窓の外を見る。結露したガラス越しに曇った白い光が見える。冬の光。ご馳走様を言い、食器をシンクに移し、自室に戻る。祖母に買い与えられたフランス人形の山。ガラスの目玉が怖くすべて後ろ向きにしているが、かえってそれが恐ろしいような気もする。おもちゃ箱の上に置かれたマリア像。黒く光るロザリオ。ベッドに飛び込みテディベアに抱きつく。仰向けになると、電球の辺りに人間の手がぼんやりと見える。エアコンから男のぼそぼそ話す声が聞こえる。毛並みのいいテディベアを何度も何度も撫でる。
ドアが突然開く。父が部屋に入り、真っ直ぐにこちらへ歩いて来る。無表情でわたしを見下ろす。父の身長は百九十センチ近くあり、当時は怪獣みたいだと思っていた。アルコールくさい息を吐きながら「行くぞ」とだけ言うと、わたしの腕を無理矢理掴む。ベッドから引き摺り下ろされる。手首から先と足首から先とが、風船のようにどんどん膨張していく。指に込めていた力が抜け、抱き締めていたテディベアが地面に落ちる。父に体を持ち上げられ、外に連れ出される。灰色の新車──またドイツ車だ──の後部座席に放り投げられる。猛スピードで車が発進する。後ろを振り返ると、母が茫然と立ち尽くしている姿が見えた。新車にも拘らず車内は既にヤニのにおいが充満していた。車体は何度も壁を擦り、電柱があるごとにしたたかにぶつかる音がする。目を閉じる。ピンク色の水が出て来る泉のことを想像する。甘い匂い。周りにはひなぎくが咲いていて、わたしの部屋にいるすべてのぬいぐるみと人形たちが気持ち良さそうに眠っている。なにに触れても柔らかくあたたかい。カーステレオからは、やはりバッハの平均律が流れている。開け放たれた窓から、冷たい空気が頻りに吹き込んでくる。膨張していた体が、しだいに小さくなっていく。車が揺れるたび、牛乳瓶ほどの大きさになった体が上下左右に投げ飛ばされる。
車が急停止する。静かにドアが開く。目を開ける。眼球の表面に白い膜が張っている。優しい声色で父はわたしの名前を呼び、大きな手を差し伸べる。その手を掴み外に出る。どこか知らない海。生まれて初めて父と手を繋いだ。靴を履いていなかったので、裸足のまま砂浜を歩いた。海は静かで誰も居なかった。遠くに一艘の船が見えた。しばらくそのまま無言で歩き続けていたが、父が少しずつ海のほうへ向かい、革靴を履いたまま海水の中に入って行った。手を引かれ、導かれるままわたしも海に入って行く。脹脛、膝、腰、胸……父は背が高いからまだ腰の辺りまでしか浸かっていない。足がつかない深さまで辿り着き、父の首にしがみつく。父はわたしの頭を掴み、一緒に水中へと潜っていく。足に重りがついているかのように、真っ直ぐに沈んでいく。オーロラの泡。暗く深いところへと、真っ直ぐに沈んでいく。
無職を救って下さい。
