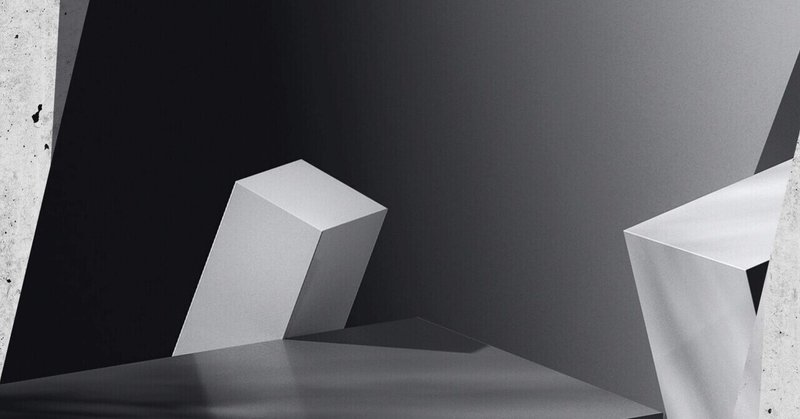
短編小説『エル』
確かその時スプーンを落としたんだったと思う。夏に父方の祖父母の家に行くと、決まって青い容器に入ったあまり甘くないバニラ味のアイスクリームが出て来た。偏食だったからなのか飽きたからなのかは定かで無いが、好んで食べた記憶が無い。
私の対面にはいつも祖父が座っていた。祖父の後ろに大きな窓があり、逆光のせいで記憶の中の彼の顔はいつも翳っている。祖父は若い時分、仕立て屋だったそうだが、きちんと働いていたような面影は少しも残されておらず、アルコールとニコチンと睡眠薬の中毒に蝕まれた、骸骨のような老人だった(彼の死後、初めてウィリアム・バロウズの写真を見た時、顔や表情が少し似ていると思った)。私が小学校低学年頃までは、祖父の趣味は狩猟だった。祖父母の家は、彼が撃ち殺した鳥、鹿、猪などの剥製と、祖母が蒐集していたフランス人形とで埋め尽くされていた。父は男だけの3人兄弟で、私の家庭もまず兄が生まれ、ようやく生まれた女児が私だったので、フランス人形をよく買い与えられたが、幼心に不気味で仕方無く、すべて壁向きにして顔を見ないで済むようにしていた。
祖父母の家には、狩猟の景品で得たというダルメシアンの老犬が居た。エルという名前だった──実際はもっと長い名前だったが、略してエルと呼ばれていた。とても物静かな犬で、いつも両足に顎を載せて寝転がり、上目遣いにこちらを見るばかりで、吠えるどころか一度も鳴き声を耳にしたことが無かった。エルは18歳で、老衰により亡くなった。父が泣いたのをこの時初めて見た。
私がスプーンを落とした音に反応し、勝手口でいつものように寝ていたエルが、ほんの少し顔を上げる気配がした。数テンポ遅れて目の前に佇む老人の陥ち窪んだ暗い双眼が、分厚い眼鏡の奥でこちらを捉えた。彼は喫んでいたハイライトを煙草盆に置き、落ち着いた仕草で部屋を出た。2階に続く階段を上る音が微かに聞こえた。
その日両親はおらず、代わりに伯父が居た。伯父は、祖父と私から少し離れた場所にあるソファに座っていた。彼の娘──つまり私の従姉妹にあたる歳下の少女は、2階の子供部屋で人形遊びか何かしていたのだろうか──その場には居なかった。私は一人黙って、床に落ちたスプーンを拾い上げた。洗ってまで食べるのが面倒で、元通りに椅子に座り直し、青い容器を見つめながら、綿菓子のように消えて無くなればいいのに──と思った。
音も無く戻ってきた祖父の腕に、剥き出しの猟銃が抱えられていた。それは彼のベッド脇に立て掛けてある代物だった。何度か祖父母の寝室に忍び込んだ事があるのですぐに分かった。その姿と共に、百合の花の香りを思い出す。噎せ返るような鮮烈な香り。まだ幼かったので、花の匂いだとは分からなかった筈だ──だからどこに百合が生けてあったのかは最早与り知らぬところだが、俄かに強い薫香が仄暗い室内を満たした。鼻腔を通り脳味噌にまで沁み渡る。頭が痺れて茫然とする。何を思えばいいのか分からない。祖父の顔はやはりよく見えず、硬く冷たい鉄の筒が首を擡げこちらを真っ直ぐに見つめている。
その次の記憶では、伯父と従姉妹と共に2階の子供部屋で遊んでいた。私はシンデレラの格好をして、従姉妹は白雪姫の格好をしていた。歌を歌ったり踊ったり絵を描いたりして遊んだ。あのアイスクリームは溶けて消えて無くなった。私は今でもそう信じている。
無職を救って下さい。
