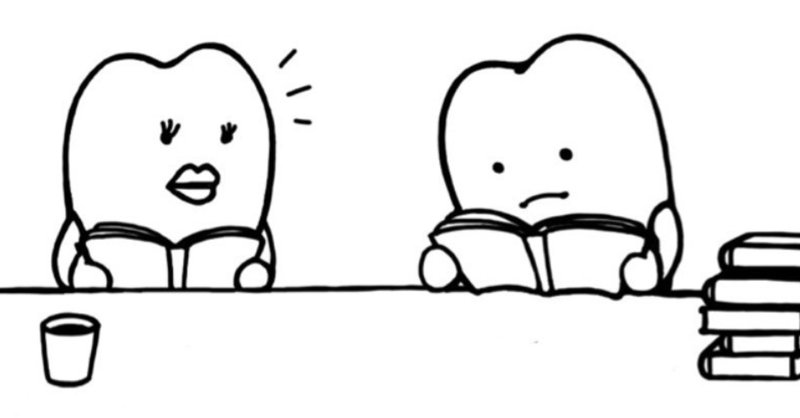
斉藤的、脱力じょーずな世界
初めまして、”緊張と脱力”というテーマにどっぷり浸かっている歯科医師の斉藤です。それも免許をいただくちょっと前からなので、もしかしたら少し変わったタイプかもしれません。
変わった経歴ならではの、学んできたこと、見てきたことを惜しみなく書きまくっていきたいと思っています。
ただ、初回だけは私のモチベーションについて書かせてくださいね。
なぜ”緊張と脱力”がテーマに?
出会いは父の友人が顎関節症のエキスパートだったことから、国試を終えて暇な時、見学に行った時でした。当時(2009年ごろ)は顎関節症の現場は変革の時期にありました。誰もが思っていた
「噛み合わせが悪いとなる・・だから、噛み合わせを治しましょう」
「マウスピースで治しましょう!」
というのが定説だった時に、必要のない時に歯を当てている癖(TCH)が大きな原因であると判明してきたのです。当然ながら、最も変わったのは治療法で、癖の治し方の指導とセルフリハビリトレーニングの指導が大半を占めるようになりました。
「え!じゃあ今まで何で歯を削られてきたんだ?」
と思ってしまいますよね?
指導という会話が中心の診療に励む日々。他所で色々とやって治らなかった患者さんたちが並ぶ大学治療部の待合室。
病態は違えど同じ指導を淡々と繰り返していました。
そんな中、TCHを克服し、軽快していく患者さんたちにはある変化があることに気づいたのです。
脱力できるってすごい。
時には裁判になるほどの、積年の悩みを抱えている患者さんとの1対1指導は新人にとってはなかなか恐ろしく、緊張感のあるものでした。
しかし、幾度となく治療を重ねるうちに表情が優しくなってきたものです。もちろん、慣れもあったはずです。しかし、そこには表情筋の弛緩から見て取れる”脱力”の為す変化が見て取れたのです。
そんなことを繰り返すうちに
過緊張⇆脱力のバランスは人によって違うことがわかってきました。人によってだけでなく「朝と夜」「夏と冬」「暇と多忙」「食前と食後」などでもバランスは変化。その中でもTCHがある人、ひいては顎関節症がある人には脱力が弱く、過緊張に偏っている傾向を感じていました。
新宿駅南口、1分間に30人はTCHみつかる。
ここまでくると、顔の表情でも過緊張がわかります。新宿の南口で待ち合わせでもしようものならTCH!TCHTCHTCHTCH!!!実際に30人見つけられるかはともかく、見えてくるのは誰もが緊張している自覚なく、過緊張している現実。
「そうか、病院に行く人なんてのはほんの一握り」
多少症状があっても「ストレス?」「年のせい?」とか曖昧な自己解釈で放置してるんじゃないの?歯を食いしばって頑張れば立派である?それはあまり理にかなっていない気がするぞ。
そして、より広いターゲットにアプローチできるTCHコントロールを模索するようになったのです。
脱力をシステマティックに育てる方法を
そして、2016年より自分にとってはスキルとコンテンツの向上、受講者は脱力力向上を目指し、講座「脱力教室」をスタート。内容をアップグレードしながら、現在に至っています。
本音を言うと
儲け、好き勝手治療した挙句に患者を諦めたドクター。一方で、残された患者さんは一筋縄でいかないことが多く、その寛解に費やした日々は悔しかったと思う。
だけれども、その時間に得た経験は、今までの教科書には載っていないもの。次世代の教科書に常識として載せていきたい。
それがモチベーションである。
(イラスト はみがき先生)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
