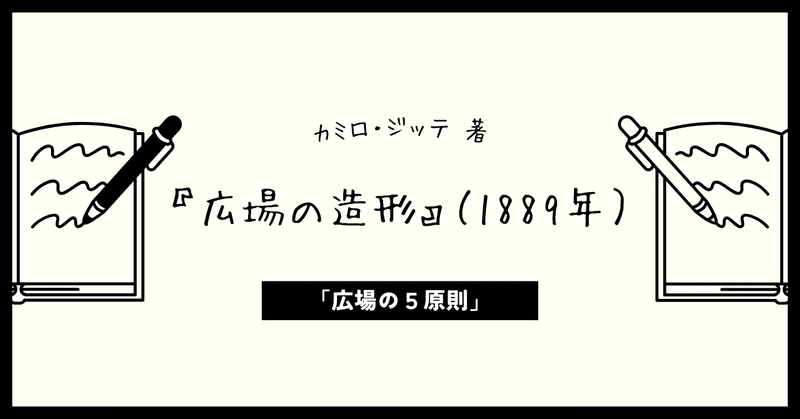
カミロ・ジッテ 著『広場の造形』(1889年)による「広場の5原則」
執筆日:2023年12月08日(金)
更新日:2023年12月08日(金)
オフィシャルサイト(ポートフォリオサイト)
今から約1世紀以上前の1889年に刊行された『広場の造形』は、広場論の大御所である19世紀オーストリアの都市計画家・建築家・画家カミロ・ジッテの著書である。本著では、イタリアを中心とする中世ヨーロッパの広場について分析し、自然発生的な都市空間の構成を再評価している。その評価軸は、スケール感や空間感覚の重要性を主張すると同時に、パブリックスペースの「にぎわいの場」を空間的な構造として分析したものともいえる。1889年といえば、フランスではナポレオン三世の帝政下でオースマンのパリ改造が完了した頃であり、本著は、オースマン的な都市改造のあり方に異議を唱えた形で出版されたといえる。ジッテは、パリのオペラ座をして、都市軸のアイストップとして交差点に突き立てるより、これを主景観として囲い込まれた歩行者広場を構築すべきと訴えたのである。いま改めて現代の眼で『広場の造形』を俯瞰すると、技術革新を間近に控え、近代化に移行しつつある都市にすでに見えつつあった画一的な単調さと芸術性への無関心に警鐘を鳴らし、アノニマスな不規則性がもたらす多様性やヴァナキュラーな空間的力動性(ダイナミズム)こそ、人が生きる場としての資質であるという価値観が見てとれる。
ジッテは、広場の条件として、①広場の中央を自由にする、②閉ざされた空間としての広場、③広場の大きさと形、④広場の不規則な形、⑤広場を群で構成する、5つの原則を提示している。
西欧広場の原点は、古代ローマのアゴラやフォルム(フォーラム)であり、いずれも列柱回廊に囲まれた矩形の中庭型広場空間である。商取引の市場、あるいは裁判・政治など公的な集会場として用いられる目的で建設された。後に、初代キリスト教の教会建築で用いられる。この時代のモニュメントは、広場の端に置かれ、広場中央はオープンにされていた。その後、中世後期であるゴシック期に入ると、欧州各地で異民族の襲来に対抗して城郭都市が形成され市民自治されるようになる。不規則な街路を持ったアノニマスな都市構造の中で、広場も整形を離れ不規則で有機的な形状で造形された。その中でもやはり、市場広場、教会広場としての機能性から中央ににぎわいを受容する構造として内部を自由なオープンスペースとし、モニュメントや噴水を交通の死角に配置するという方法論が取られた。

1-2 領域性
パブリックスペース設計ではしばしば、あるいはほとんど常に、“にぎわい”を創りだすことが求められる。少なくとも、にぎわいの場として機能することが。
広場や公園のような面的な場所に限らず、街路や水辺のようなリニアなオープンスペースにしてもそれは同様のことだ。
パブリックスペースのデザインを語る以上、「にぎわいの場」という空間構造について考えることは避けられない。そして、その際の重要な概念の一つが領域性territoryである。
にぎわいを創り出すには、相当規模の空地がただあれば済むというものではない。
オーストリアの都市計画家カミロ・ジッテが1889年に著した『広場の造形』は、イタリアを中心とする中世の広場を中心に、広場の視覚的効果という観点からその芸術性と建築的造形原理について論じたものだ。だが、その評価軸は、現代のわれわれから見ると “にぎわいの空間構造”としても読み取ることが可能なものとなっている。
それを示す上でも、この著作が出版された時代背景について少々触れておく。
1889年といえば、フランスではナポレオン三世の帝政下でオースマンのパリ改造が完了した頃であり、産業革命前夜といっていい時代だ。いわば近代文明の黎明期に差し掛かったその時代、急速に変貌しつつある都市景観のただなかでジッテはこれを書いた。
ジッテが賛美した広場の多くは、中世後期(ゴシック期)からルネサンス、そしてバロックのものだ。出版当時は大変な反響で、出版したその年に重版され、3年内に第3版が出された。中世の空間造形の価値について再評価を与えた功績が評価された形である。
だが、その時代に中世への関心が高まっていたかというと決してそういうことはなく、むしろ全く逆のベクトルだった。
この書は、オースマン的な都市改造のあり方に異議を唱えた形で出版されたといっていい。実際にジッテは、パリのオペラ座をして、都市軸のアイストップとして交差点に突き立てるより、これを主景観として囲い込まれた歩行者広場を構築すべきと訴えた。
それが実践されることがなかったのはいうまでもない。
ザルツブルクの国立工芸学校の元校長で実践的な都市計画家として知られていたジッテがその後、実際に中世的な都市設計を実現する機会に恵まれたかというと、そのようなこともまたなかった。実際にチェコやポーランドといった東欧の一部都市でいくつかの街路など部分的な成果を上げたにすぎない。
しかし、いま改めて現代の眼で『広場の造形』を俯瞰すると、技術革新を間近に控え、近代化に移行しつつある都市にすでに見えつつあった画一的な単調さと芸術性への無関心に警鐘を鳴らし、アノニマスな不規則性がもたらす多様性やヴァナキュラーな空間的力動性(ダイナミズム)こそ、人が生きる場としての資質であるという価値観が見てとれる。
人が自ら生きることの意義や意味を見いだせる場こそが価値であり、空間芸術の眼目であるという、そのことだ。
その普遍的価値観があればこそ、120年の時を超えてこの著書は読みつながれている。
だからこそジッテの広場論は、「にぎわい」のデザイン方法論としても読めるのだ。
前置きが長くなったが、著書の中でジッテは、数多くの事例を引き出しながら、優れた広場の条件として、おもに5つの原則を提示している。すなわち、
①広場の中央を(アクティビティのために)自由にしておくこと
②閉ざされた(領域性の優れた)空間であること
③(主景に対し適切な)広場の大きさと形
④不規則な形態
⑤広場を群で構成すること
である。(括弧内筆者)
ジッテの掲げるこの原則を“にぎわい”の空間構造に読み替えることの是非のために、本来はまず西欧的な概念における「広場」なるものについて概覧しなければならないところだ。
しかし、本稿ではとてもその余裕はない。広場という概念については、「2-5 にぎわいを造形する」や「3-3 日本的広場試論(門司港駅前広場、日向市駅前広場、道後温泉広場)」でも改めて触れるつもりだ。
ここでは、ひとまず、ジッテの構成原理をそのまま解読してみる。
①はいうまでもない。中央にオープンな空間を用意しなければにぎわいは生まれづらいという、当たり前のような事実をいっている。じつは近代都市計画以降の広場では、それが当り前ではなくなり、モニュメンタリティが優先された交通広場のような様相の空間が台頭し始める。それはともかくとして、①についてさらにジッテは、
「広場の端にモニュメントをおくという古典古代の原則に続いて、モニュメント特に市場広場の噴水を交通の死角に配置するという生粋の中世的、さらに北方的原則」
のことだと付け加えている。(『広場の造形』鹿島出版会,P.34-35)
少し解説すると、「古典古代」とはアゴラやフォルム(フォーラム)が現れたギリシャやローマ帝国期を指す。いずれも列柱回廊に囲まれた矩形の中庭型広場空間だが、これが西欧広場の原点であることをいっている。商取引の市場、あるいは裁判・政治など公的な集会場として用いられる目的で建設されたこの広場において、外周の列柱廊はストアと呼ばれそこに店舗が並んだことが後に用語になった。
古典古代のこの時代、モニュメントは広場の端に置かれ、広場中央はオープンにされていた。
その後、中世後期であるゴシック期に入ると、欧州各地で異民族の襲来に対抗して城郭都市が形成され市民自治されるようになる。不規則な街路を持ったアノニマスな都市構造の中で、広場も整形を離れ不規則で有機的な形状で造形された。
その中でもやはり、市場広場、教会広場としての機能性から中央ににぎわいを受容する構造として内部を自由なオープンスペースとし、モニュメントや噴水を交通の死角に配置するという方法論が取られた。ジッテはそのことをいっている。
ついでに、「北方的原則」というのは、ゴシックという様式性を指す。
美術史家が中世期を前期と後期に分けたのは15世紀以降のことだ。前期をロマネスクとし、後者をゴシックとして分けた。それまでは5世紀ごろから約一千年近くの永き時代をひとくくりに中世と呼んでいた。
ロマネスクとは字義通り「ローマ風」を意味する。後期の名称となったゴシックは、当時ローマ帝国に支配されていた北方のフランスやドイツの人々を指すゴート族の文化「ゴート風」、ゴーティックからきている。ゴシックとは、ローマ的でないという否定語である一方で、北方の理知的で精緻な概念を指し示す。この時代に北方民族の思考が建築構造や空間造形を大いに発展させた。これが、現代に至るも西欧という空間文化の基盤として継続されている。
余談が過ぎた。
続いて②こそが、領域性の重要性についての言及だ。今回はこれを解説する。
③の(主景に対し適切な)広場の大きさと形については、次項の「1-3 スケール、サイズ」で解説する。
④の不規則な形態と⑤広場群とは、バロック期以降に発展した近代都市計画において広場が幾何学的形態で都市構成に組み込まれ、中世期の空間的ダイナミズムを失うようになった状況を知らないと分かりづらい。
オースマンのパリ改造に代表される近代都市計画以降、都市は、整形の広場中央にオベリスクを立てる荘厳な景観的レトリックを獲得したが、その一方で、原初的でヴァナキュラーなにぎわいをもった中世独特の動的構成や空間的ダイナミズムを喪失した。
不規則な平面形態。そのことは、いわゆる“にぎわい”の構造に直接関連するものではない。とはいえ、確かに整形の敷地は動きに乏しく、空間的に単調で活力を与えにくいというのは設計者なら誰もが肯定することだろう。むしろ不規則な平面を生かし、空間的なダイナミズムを獲得するところにこそ、にぎわいの空間構造の契機がある。そのことは、また次項「1-3 スケール、サイズ」で述べる。
また、中世の不規則な平面形態は、しばしばその結果として、教会の外周に複数の広場群を創出し、それらが呼応して都市に活力を与えてきた。近代以降、そういうフラクタルな図像を都市は否定し始めた。⑤でジッテが強調したかったのはそのことだ。
領域性の話をする。
ここでいう領域性とは、ケヴィン・リンチが『都市のイメージ』で語るところの、都市空間の構成要素(ノード、パス、エッジ、ランドマーク、ディストリクト)におけるディストリクトとは異なる。むしろterritoryというべきものだ。
ジッテの第2原則「閉ざされた(領域性の優れた)空間であること」とは、いうまでもなく、優れた広場が空間的に「はっきりと限定され、閉ざされている(『広場の造形』P.45)」ということだ。
そのためには接続する街路の数を抑え、かつ接続の向きを変えることで、視軸的な抜けをつくらずに領域的なまとまりが形成できるということを指摘し、優れた広場の空間構成がそのようにできていることを示した。この発見は、けだし慧眼である。
シエナのカンポ広場は市庁舎ブップリコ宮を中心に、その対辺で円弧状に建物が取り囲む。市庁舎の量塊的な主要部は、周囲の建物とほぼ高さを揃え、よく見れば自らもファサードの一部をゆるく折って、取り囲む広場空間の一翼として造形されている。その主要部から聳え立つマンジャの塔こそ、この広場の図像的中心である。
広場は、全体にゆるく傾斜し、塔に向かって収斂している。
そこから見る広場は空間的に緊密に閉ざされている。いくつかの街路が接続していても、斜めに入り込んで空間を閉ざしていたり、あるいはT字路ですぐ奥に建物が立ち上がって視線が抜けることがない。ほぼ完璧な構成といっていい。
日本の都市空間では、なかなかこのような構成は形成しえない。
いわゆる道路の延長では「交差点広場」は形成できても、歩行者空間のまとまりがなかなか確保できない。ほとんどの場合歩行者のオープンスペースに接して車道が回りこんでくる。
領域性が形成できない広場は、広場とはいえない。
文字通り気の抜けた空き地に過ぎない。にぎわいが焦点を結ばずに拡散してしまう。
それを防ぐには、何らかの形で人為的に領域性を構築する以外にない。
建築を配置して空間をクローズするのが最も効果が高い。それができない場合、並木など列柱的要素で領域性を創出するという方法が考えられる。森や丘陵などで囲むということも有効だろう。
物理的に囲めなければ? あるいは、物理的に囲う以外に手はないのか?
そこが、本項のポイントでもある。
実は、日本的空間において領域性を形成する概念的手法は、このような物理的なものばかりではない。
「結界」
というものがある。
“結界をはる”という方法。それは日本の空間文化独特の手法的概念である。
前述した日向市駅前の「ひむかの杜」緑地広場では、イベントステージ(「木もれ日ステージ」)や並木、鉄道軌道高架で領域性を整えてある。とはいえ、とてもカンポ広場のような景観的統一性を持った領域性ではない。
むしろ周辺街区へにぎわいを展開する意図もあるので、「閉じつつ、開く」というニュアンスが重要だった。空間的には閉じたい。しかし、視界的には開きたい。
結界、という手法がそれを可能にする。
強い構造物で閉じるのではなく、並木や築山やせせらぎなどで、薄く柔らかく数層で包み込んだ。結界とは、いわば「間=イマジナリー・スペース」で閉じる手法のことなのだ。(『日本デザイン論』伊藤ていじ、鹿島出版会P.112、あるいは『日本の都市空間』都市デザイン研究体、彰国社P.42)
「結界」とは、シンボルによって場の領域性を形成する操作であり、その境界は物理的な障壁というよりは、心象風景として捉えられる。
心象風景とは何か。
西欧的な「広場」という都市文化を日本は歴史的に持っていないということはすでに述べたが、公共性の高い拠点的な施設があり、その周りに人間活動(アクティビティ)が収斂する舞台的な場を「広場」というなら、日本の空間文化でそれに相当するのは大路(つまり広幅員の街路)や寺社の境内、あるいは名所と呼ばれる景勝地や河川敷(河原)、橋詰などであったろう。
しかし、それにしたところで、寺社の境内は都市に開いておらず、「かわらもの」が集う河川敷は、賑わいの中心だったかもしれないが、ハレとケガレが背反的に共存する都市外縁部の異界だった。「広場」とは相当にニュアンスが異なる。
西欧広場には主景がある。あまりにも当然過ぎて、ジッテやポール・ズッカーですらも「原則」に上げていないほどの大原則である。
西欧広場は、教会や市庁舎といった精神的中核、政治経済の中核に寄り添う形で、またそのにぎわいを受容する装置として構築された。
同じように、日本の伝統空間のにぎわいの場でも、主景とよぶべきものはあった。
だが、それは必ずしも寺社や宮殿といった建築に限らず、山や森、あるいは海や河川、湖沼といった、自然景観の場合が少なくなかった。また、さらに近景とは限らず、遠景であったり、場合によってはイメージの場合ですらあった。
なぜ、そういうことが可能になるのか。
主景の存在と領域性こそ、にぎわいの場としての最低限の条件だ。そこまでは西欧も日本も変わりはない。
日本のにぎわい空間の主景は、しばしば遠望する山岳景(「山アテ」)や、海や川といった水景(「汐見」など)であった。
街路の領域性はまず家並みであり壁面がそのままエッジになる。境内の場合は、寺社建築や鎮守杜が領域性を囲い込む。そして、それと同列で遠望景や水域などが領域性に加担するというのが西欧広場にはないところだ。
建築で物理的に囲い込むのとは異なるのは、日本の空間文化が象徴的なシンボルに取り囲まれた、「間」の概念で組み立てられているところに起因するものと思われる。
「間」とは、心象に投影された空間的ヴォリュームである。伊藤ていじはそれをイマジナリー・スペースと呼んだ。象徴的シンボルに囲まれて形成されるイマジナリー・スペースでは、空間の調和やバランスの概念も、絶対座標軸を持ったユークリッド幾何学的世界観では説明しえない。
西欧的概念の調和でいうハーモニーharmonyとは、要素が抽象化され元素化した上で組織的に組み合わされるバランス状態である。クラシック音楽などの洋楽をイメージしてもらいたい。空間および時間は唯一つの視点(総括的展望)によって眺められる。いわば静的バランスといっていい。
これに対して、動的バランスによる調和概念をヘテロフォニーheterophonyと呼ぶ。雅楽やアジアの民族音楽でこの用語は使われている。各音は抽象化というより象徴化であり、元素化されないまま何らかの濁りを保持した音で、さらに演者が任意で別々に動いたり、リズムやテンポを微妙にずらしたりすることで生じる「間」が、偶発性や瞬発性のある複雑な音色を重ね合わせる。洋楽でも、ジャズやそれから派生したボサノヴァ、あるいはポルトガルのファドやスペインのフラメンコなどといった民俗音楽はこれに近い。共通するのは、総括的展望は希薄で、継起的連鎖が重視される点だ。
見る者、聞く者は、対象にある音の濁りやリズム的な「間」に心象を投影する。音や物を通して、実はモノとモノの間に象徴化された意味を心象投影的に見出しながら体験しているのである。
能面のわずかな動きに喜怒哀楽を見るのも、歌舞伎の見得に気分を乗せるのも同じ根だといっていい。
庭園でいえば、定点という総括的展望を持つ西欧式幾何学庭園に対し、日本庭園は見る者が動き、あるいは刻々と変化する時間の中で心象風景と重ね合わせつつ体験する空間ということができる。ヴェルサイユ宮殿やヴォー・ル・ヴィコント宮に見られる、ル・ノートル的なパースペクティヴ空間と日本の回遊式庭園を比べればその違いは瞭然としている。回遊式でなくとも、たとえば枯山水の傑作・竜安寺石庭は、見る主体が動かなければどこに座っても決してすべての石を視野に入れることができない。各要素は海岸景観に見立てられたり、生き物の姿だといわれたりする象徴的造形である。これもまた動的バランスの中にある。石の大きさや形が、心象的な均衡としてバランスよく配置されたものなのである。
象徴、間、継起的展開……。
ヘテロフォニーでは、全体構造は常に共時的(シンクロニスティック)に存在し、相対的な関係である。それらは原因と結果という継時的連鎖によって把握されない。
ここに日本の空間文化の傾向がある。
「傾向」といったのは、上記のことは絶対的な特徴ではないからだ。西欧文化がすべて抽象的で静的というようなものではなく、日本の伝統文化がすべて「間」だけで語られるものではない。
だが、少なくともそのことから導き出される日本的な領域性の概念は、傾向としてであっても、必ずしも建築的に取り囲まれた物理的空間に限らないということを指し示す。
宮崎県日南市にある油津・堀川運河。
その中核に位置する水際のオープンスペース「夢ひろば」は、遠望する山と森、そして堀川運河という水面によって囲まれている。堀川運河は、領域を形成するエッジであると同時に、広場の主景でもある。
そう、イマジナリー・スペースの中では、主景は必ずしも建築のように立ち上らなくとも成立すると筆者は考えている。海や山といった、象徴性の高い自然のランドマークを心象的に位置付けることでも成立すると。
参考文献:教会建築家の推薦書籍
「励ましのお言葉」から「お仕事のご相談」まで、ポジティブかつ幅広い声をお待ちしております。
共著『日本の最も美しい教会』の新装版『日本の美しい教会』が、2023年11月末に刊行されました。
都内の教会を自著『東京の名教会さんぽ』でご紹介しています。
【東京・銀座編】教会めぐり:カトリック築地教会、聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂、日本基督教団銀座教会を紹介
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
