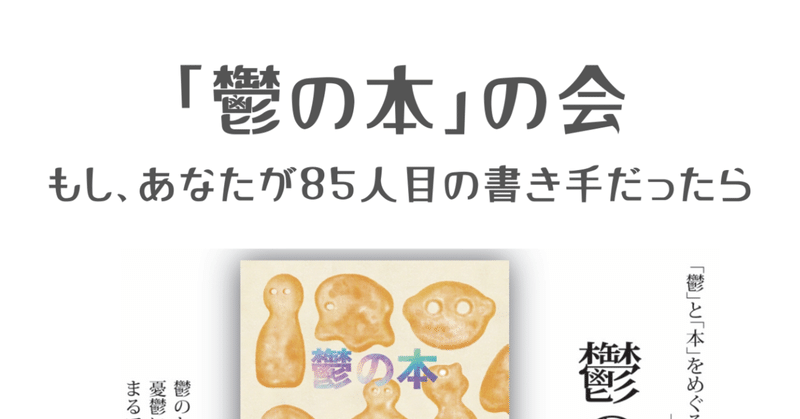
【実施レポート】5/18「鬱の本の会」
5月18日(土)に「鬱の本の会」を実施しました。
まず始めに、この会に鬱の本を出版された点滅社代表の屋良さんにお越しいただきました。文フリの前日にも関わらず、埼玉県まで本当にありがとうございました。
今回、実施レポートという形で記載しますが、参加者の方がお話した具体的な内容には触れません。私がこの会を開いて、そして参加して感じたことを中心にまとめます。
まず印象的だったこと。
文字にするとすごく当たり前の事のように見えてしまうのですが、「みんな生きるのが辛い(しんどい)と感じた経験がある」ということです。
私は基本弱い人間なので「自分だけではない」と思えるだけで、少し心が軽くなったりします。
そして「その辛さをどのように乗り越えてきたのか」、という点がすごく興味深かったです。
自分で何か創作することで吐き出している方が、何名かいらっしゃいました。自己治癒能力と表現してよいのか、私にはない感覚で新鮮でした。
誰かの何気ない一言で救われるという話もありました。これは私も経験があります。生きるうえでは基本的に誰かと関わることになるので、そこから救いが得られるというのはとても重要なことだなと感じます。
ただし、おそらく誰かの何気ない一言で傷つく経験の方が多いかもしれません。。
人だけでなく本の表現によって救われる、という話もありました。
今回は、皆さんがこの会で思い浮かべた本を紹介してくださいました。
話は少し変わりますが、私が大学でキャリア支援の仕事をしている時の話です。学生が自己分析するときにやってもらう「自分史」の作成ですが、学生にそこに喜怒哀楽それぞれで一番だった出来事を書き加えてもらっていました。自分の感情が大きく動いた時を突き詰めて捉えてみると、自分自身の事がわかるのではないか、という考えからです。
辛い時や落ち込んでいる時に読んで救われた本というのは、やはり大きく感情が動くことで余計印象に残るのかもしれません。
会の中では「生きるうえでのお守り」があるか、という話題になりました。
私は「過去の自分」という、超絶クサいイタい回答をしました。今振り返るとほんとに恥ずかしいです。皆さんにとってのお守りは何かもぜひお店で教えてください。
鬱の本の会では、参加された方がおそらく話しにくかったであろう話題も話してくださいました。家族でも近しい友人でもない第三者だからこそ話せることもある、というコンセプトではありますが、とはいえ勇気を出してお話してくださった皆さんには本当に感謝です。
元々、2024年2月に「メメント・モリとわたし」というイベントを開催しました。
誰しもが必ずいつか経験する「死」というものですが、日常ではなかなか話題にしにくいし、気軽に話せるようなテーマではありません。なんとなくこの話をするのがタブーであるかのような空気感もあります。この話題に真正面からぶつかってみることが、でこぼこ書店の存在意義のひとつだ!と感じて開催したイベントでしたが、実際にやってみて本当に良かったという感触がありました。
このような企画を継続的に実施したいということで、今回は「鬱の本の会」を開催したわけですが、改めてやって良かったと感じています。
普段、話題としてあげにくいテーマに向き合っていく企画は継続的に実施していく予定です。もしご都合のつく方は、ぜひ参加検討してください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
