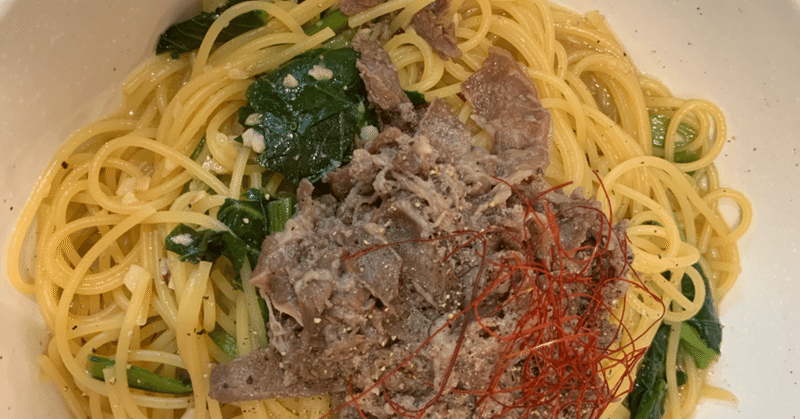
一億総ツッコミ社会
大阪で出会って5年目の友人が言う。
「一億総ツッコミ社会だ」と。
情報発信のツールは21世紀になって以降、ますます充実した。「掲示板(BBS)」にはじまり、mixiやfacebook。数年前から「Yahoo!ニュース」においては、2007年からコメントをつけられるようになり、今では14万件を超えるコメントが寄せられるようになった。匿名、実名問わずに以前に増して意見「ツッコミ」を入れられる機会は増えてきた。
ポジティブな自己発信であらば歓迎されるべきことだ。しかし、日本の場合のツッコミはネガティブな声が多いような気がしてならない。
2018年3月30日に「学校教育法施行規則の一部改正と高等学校学習指導要領」の改訂が行われ、学習指導要領が2022年から年次進行で実施されることになる。それに伴い、教育現場では、【講義型(受動的)授業】から【参加型(能動的)授業】に変わろうとしており、生徒の「主体性」が求められる。
自ら課題発見・解決といったスキルの習得し、「自己発信」を行えるような教育プログラムの策定が急がれる。(僕の同窓会における、在校生サポートの取り組みも形を変えていきたいとの申し入れが先生方からあった。)
その背景には、社会における人間の役割の変化がある。
これからの職場(会社)においては、「機械的処理」や「単純作業」はコンピューターが行えるようになる。更には、規則性(アルゴリズム)のある判断は、人工知能(AI)でも行えるようになる。
結果、人間は新しい価値を生むことを念頭においた「創造的な仕事」や、他者と「共創する仕事」に専念することが求められるようになる。教育現場における大きな転換点であり、先生方もこれ迄の「教育」のあり方を見直す時期にきている。
話を戻して、今回の「主体性」や「自己発信」が一億総ツッコミ社会のネガティブな側面を増長するきっかけになる可能性も孕んでいるように思う。そうであっては、今回の文科省の取り組みは本末転倒だ。
文科省の「総合的な探求の時間」の解説書の学習指導要領の「改訂経緯」に記載の通り、「多様性を原動力」として、「新たな価値を生み出していく」ための取り組みとならなければならない。
急激な少子高齢化が進む中で成熟社会を迎え た我が国にあっては,一人一人が持続可能な社会の担い手として,その多様性を原動力とし,質的な豊かさを伴った個人と社会の成長につながる新たな価値を生み出していくことが期待される。(文部科学省発行:「学習指導要領解説」の「総合的な探求の時間編」より)
多様な考えを発信するためのプラットフォームとして、このnoteは非常に面白い。勝手なるままに、つらつらと書く。自分の頭の中の整理のために。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
