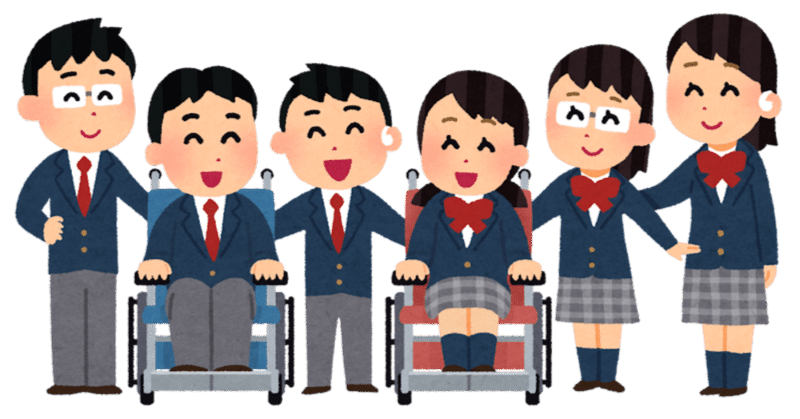
医療的ケア児の親、障がいについて真面目に考えてみた。
我が子は、生まれてすぐに医療的ケア児となりました。(詳細が気になる方は、ぜひ他の記事もご覧になってみてくださいね。)
ここでは、改めて「障がいって何だろう?」と考えてみましたので、その内容をご紹介します。
「障がい」とは何か
まず、心身に関する「障がい」を辞書で確認してみます。
個人的な原因や、社会的な環境により、心や身体上の機能が十分に働かず、活動に制限があること。
シンプルで分かりやすいですが、深く考えるには少し言葉足らずのようにも感じます。
そこで少しだけ付け加えて、私は「障がい」を次のように捉えたいと思うのです。
①個人的な原因(生得的または獲得的なもの)と、②自然・社会環境との関係に基づき、③生活に何らかの支障があり、④それが治療や支援等の対象となる要素のこと。
先の定義より随分と長ったらしくなってしまいましたので、①〜④についてそれぞれ補足させてください。
①生得的または獲得的な原因について
個人的な原因には、それがいつ獲得されたかによって、生得的/獲得的の大きく二つに分けられます。
前者には、生まれつき目が見えない、歩くことがままならないなどの場合が想定されます。
一方後者には、事故にあったため歩けなくなってしまった場合などです。
両者をごちゃ混ぜに捉えてしまうと、個々人に対する支援策を見誤ってします可能性があります。
例えば、目が見えないという同じ障がいを持つ人がいたとして、それが生得的か獲得的かで意味は大きく異なります。獲得的な人の場合、一度は世界を目視している訳ですから、その後のフォローの仕方が異なるのは当然です。
ただし両者について、理念的に区別しているものの、実際には不可分なケースも多々考えられます。
例えば医療技術の向上に伴い出生時に命が救われたものの、生きていくためには継続して医療的ケアが必要となった我が子のような医療的ケア児です。彼らにとってみれば「勝手に医ケア児として産み落とされた」わけですから生得的原因とも言えます。一方それは、人類としての医療的技術の発展によって獲得した要素とも言えるのです。
デザイナーズベイビーなど、今後そうした例は増えていくのではないでしょうか。
②自然・社会環境との関係、及び③生活への支障について
先にあげた辞書の定義では、社会的環境のみ挙げられていました。しかし、障がいのすべてを社会に還元することはできないでしょう。というより、そもそも自然環境と社会環境は相互依存的かつ不可分なものです。
例えばもし、大気を持たない自然環境であれば、社会的に別の方法で必要なエネルギーを摂取しているはずですから、呼吸器に不具合があろうとも生活に支障はありませんので、それは障がいと認識されていないはずだからです。
そういった意味で、障がいを「社会制度が悪いんだ」と極端に捉えてしまうのは適切でないように思います。(もちろん、社会制度によって乗り越えていく必要はあります。)
④治療や支援の対象となる点について
そもそも、わざわざ「障がい」の有無で人々を分けるのは何故でしょうか。
それは、医療的治療や行政支援など、様々なフォローを行う“根拠”となるからではないでしょうか。根拠がなければ、それらは人権侵害や不当利得とみなされてしまいます。
(この点は、次節にも大きく関係するものです。)
また支援等の対象となるかどうかは、常に揺れ動きます。それは社会情勢の影響であったり、医療的技術の向上であったりするでしょう。
なお参考までに、障がいとみなされない点(人種やジェンダーなど)について区分することは「差別」といえます。
障がいの子を育てる際の留意点
以上のように障がいをとらえることで、自分の子が障がいを持つ際に、考えられることが2つあります。
苦悩は尽きない、前向きに生きよう。
まず、競争社会が激化するに伴い、障がいを持つことに対する苦悩は尽きないということ。良くも悪くも、資本主義の世の中である限り、これは避けようがないでしょう。
この点、障がいという事実について悩むことは何の解決にもなりません。そもそも①〜③までの定義に従っていえば、誰しもが何らかの個人的な障がいを持つということができます。
例えば、私は思春期にくせ毛であることがコンプレックスでした。ストレートヘアがカッコいいとされる環境にあれば、それは生得的原因に基づく、個人的な障がいといえます。
「そんなの障がいじゃない」と思われる方もいるでしょう。しかしここで言いたいことは、どんな種類の障がいであっても、それを所与のものとして生きていくしかない!ということです。
加えて、これは超個人的な考えですが、親の“獲得的”要素(例えばお金)によって、子の障がいをフォローしてあげたいと思うわけです。
「多様性」にはご注意を。
次に、昨今の社会ではそこら中で、多様性の尊重が謳われています。もちろん、そのことは悪いことではありません。
しかし、それが文字面だけの多様性の尊重になってしまうと、④であげた支援の対象が狭まることに繋がりかねないのです。
「だって歩けないのはその人の個性でしょ?私のくせ毛と何も違わない。だったら公的支援なんて不要だ。」といった主張が出ないとも限りません。
前節で述べた通り、障がいの区分は治療や支援の対象を決めるものです。
そのため、多様性という言葉はもっと丁寧に浸透していって欲しいな、と願うのです。
以上、取り止めもないですが、現時点での障がいに対する私見とさせていただきます。
(参考)
浅野慎一『人間的自然と社会環境』2005、大学教育出版、第8章
ヨシタケシンスケほか『みえるとかみえないとか』2018、アリス館
2023.11.15更新
