
『ハウス・オブ・グッチ』は「関係性」で演じる。
『ハウス・オブ・グッチ』最高でしたねー。
やはりリッチな人々の世界を描写させたら、リドリー・スコット監督に勝る者無し。彼くらいになると、よくあるリッチな料理や調度品をアップで次々と見せたり「ほらほらリッチな生活ですよ〜」みたいな撮影は一切しないんです。
リドリーはリッチな物体をただ映してるんじゃなくて、その豪華さに普通に反応している富裕層たちの自然込みで映している・・・つまりリッチな「関係性」を映してるんですよ。家にでっかいクリムトが飾ってあってすご〜い!じゃなくて「ああ、これ?いいでしょ」って好きな映画のポスターでも見せるみたいな軽さで紹介するっていう(笑)、ちょっとムカつく関係性でリッチを表現します。
だから観客の我々もなんだか富裕層の家に招かれてどう振舞っていいかわからないみたいな気分にさせられるんですよねー。あれ?無造作に飾ってるけどあのデカい絵、クリムトじゃない?え?本物?みたいな(笑)、まさにパトリツィアの心境ですよね。
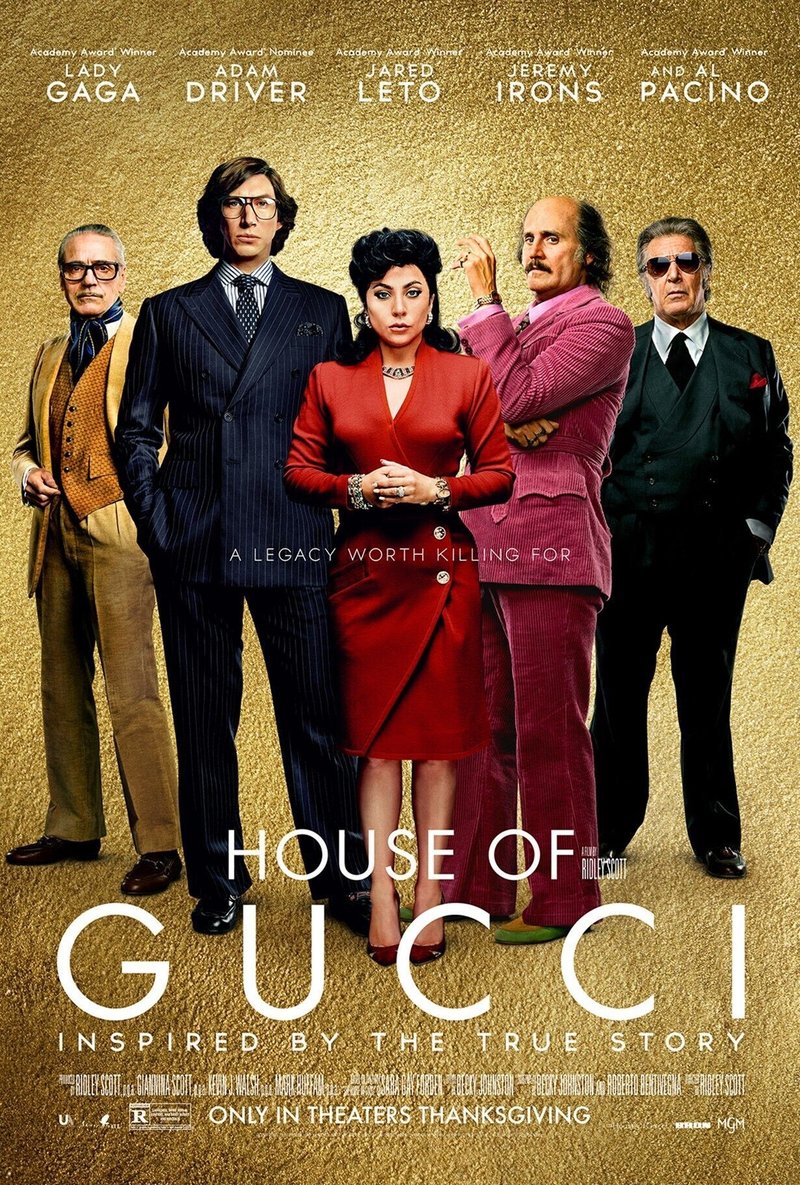
上質なブラックコメディ。
この映画『ハウス・オブ・グッチ』ってブラックコメディだと思うんですけど、上質なブラックコメディって前回紹介した『ドント・ルック・アップ』なんかもそうでしたけど、どんなに笑えるシーンでも人物描写・社会描写がリアルなんですよね。だからブラックコメディなんです。
コメディ作品むけの演技って古くは「感情をデフォルメ」したり「キャラ性をデフォルメ」したりしたものですが、さすが『ハウス・オブ・グッチ』の現代の名優たちは今やもうそんな安い芝居はやってませんでしたね。先日紹介した『ドント・ルック・アップ』なんかもそうでしたが、デフォルメされているのは「感情」でも「キャラ」でもありません。「関係性」です。
それはアル・パチーノが演じたアルド・グッチの芝居とかを見ているとわかりやすいですよね。 『ゴッドファーザー』『スカーフェイス』などでの若きアル・パチーノの演技と比較してみましょう。
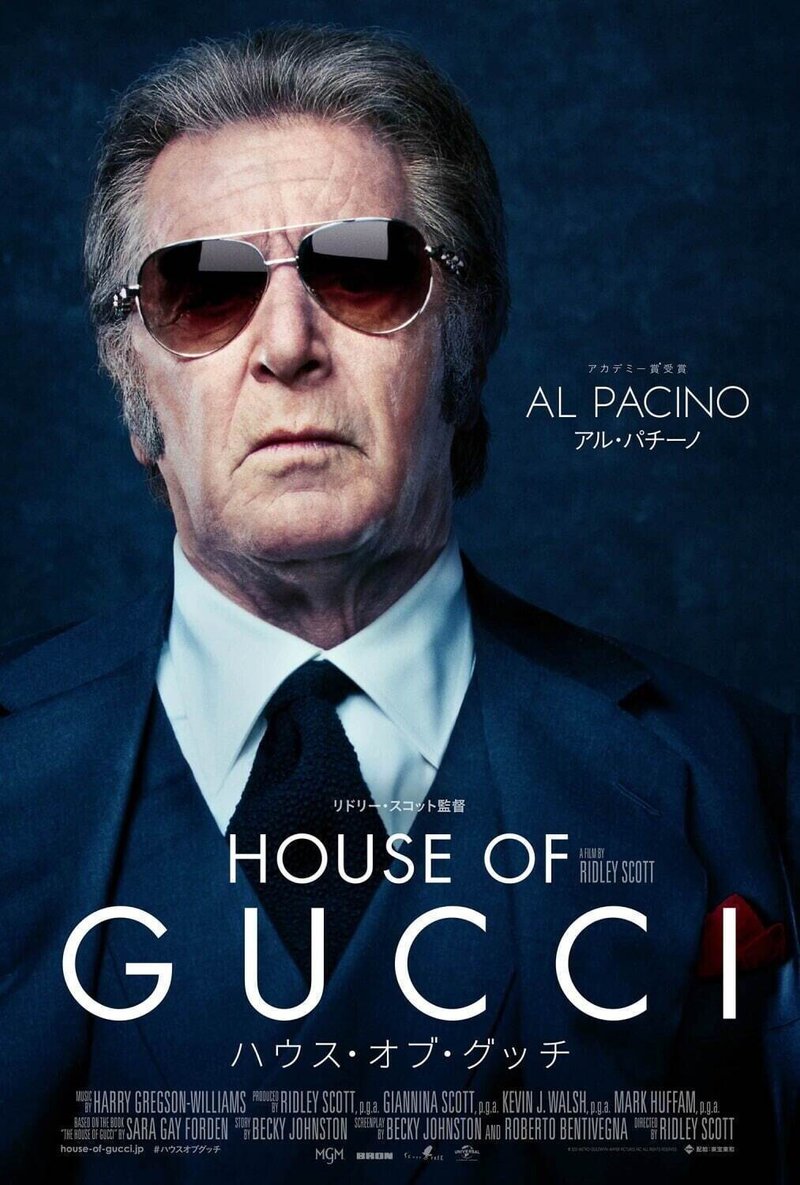

アル・パチーノの演技法の歴史
アル・パチーノ演じるアルド・グッチがどんなに陽気なふるまいをしていても、彼が日々孤独を感じながら生活していることは画面から伝わってきます。そこが今回のアル・パチーノの芝居の素晴らしさです。
『ハウス・オブ・グッチ』にはアルドが孤独であることを表現するシーンやショットが特にあるわけではないし、そういう芝居やセリフも無い。だけど観客にそれがひしひしと伝わってくるのは、彼がマウリツィオ(アダム・ドライバー)やパトリツィア(レディー・ガガ)やパオロ(ジャレッド・レト)と会話している時のふるまいの中に、過剰な反応というか喜びというか、孤独をこじらせた人間独特のテンションの上がり方の気配があるからです。ココがデフォルメされています。
アル・パチーノは陽気なコミュニケーションの芝居の中で、孤独な老人独特の気配を演じているんです。これを名演と呼ばずになんと呼びましょう。
孤独な大組織のボスを演じるという点では『ゴッドファーザー』や『スカーフェイス』などと同じなんですが、それらの脚本には孤独を表現するシーンや台詞があったし、アル・パチーノの演技法というか芝居の切り取り方、強調する部分もそれぞれ全く違っているんですよね。
ちょっとマニアックな演技の話をしますね。
『ゴッドファーザー』『狼たちの午後』などの70年代のパチーノは「内面の葛藤」に突き動かされて動きます。自分の内面に集中して演じているので、外から見てちょっとわかりにくい芝居になっています。メソード期・内面期です。
それが『スカーフェイス』あたりからの80〜90年代のパチーノは、「キャラクターの性質」に突き動かされて動きます。そして人物をどう見せるか、どう歌舞いて見せるかに集中して演じているので、外から見てキャラがハッキリ分かりやすいのがこの時期のパチーノの芝居の特徴です。
よくアル・パチーノはメソード俳優だと言われますが、それは70年代の話。いま彼は『ゴッドファーザー』や『狼たちの午後』時代みたいな演技をやっていません。デ・ニーロなんかも全然変わりましたよね。そう、真に才能ある俳優である彼らは時代の変化と共にさらにさらに進化し続けているんです。


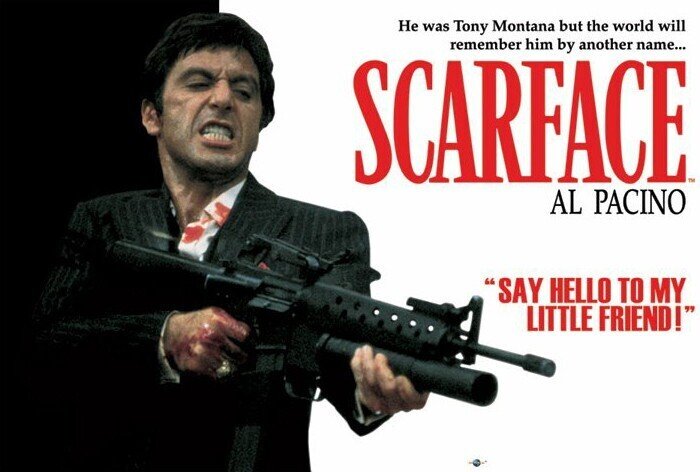


『ハウス・オブ・グッチ』でのアル・パチーノの芝居。
では最新作『ハウス・オブ・グッチ』のパチーノの演技はどうなのか・・・アルド・グッチを演じるパチーノを突き動かしているのは、もはや「内面の葛藤」でも「キャラクター」でもなく、「目の前の相手」・・・そう「関係性」が彼を突き動かすのです。
アルドを動かしているのは目の前のマウリツィオの人生観であり、パトリツィアの人生観であり、パオロの人生観、それらに触れるとアルドは強烈に何かをしたくなる。そして居ても立ってもいられなくなって行動してしまう。つい世話してあげちゃうとか、つい株を譲渡しちゃうとか、契約書にグチャグチャグチャ!ってサインしちゃうとかw。あのシーンは本当に素晴らしかった。
『ハウス・オブ・グッチ』と『ゴッドファーザー』でのアル・パチーノの演技の大きな違いとは・・・それは『ゴッドファーザー』での彼の芝居は、彼ひとりの内的衝動によってスタンドアローンで演じられているのですが、『ハウス・オブ・グッチ』では周囲の人物たちや環境との「関係性」、外的刺激によって演じられている点です。
例の契約書のシーンで、アルド・グッチが両手で顔を覆いますよね。あれって『ゴッドファーザーPARTIII』のクライマックスのアレだと思うんですが、あそこから孤独な絶叫に行くのかと思わせておいて・・・グチャグチャグチャ!ってサインします(笑)。不本意な契約書との関係性・・・あの契約書が彼にああさせたんですね。そしてアルドはパオロと一緒に去って行きます。彼は『ゴッドファーザー』の時みたいに1人の世界に入ってゆかない。なぜならアルドは誰かと一緒にいても充分に孤独だからです。



レディー・ガガ様の動物メソッド。
そして女優レディー・ガガ。スターの輝きを爆発させてましたよね。アル・パチーノみたいな本物の名優と並んでもまったく引けを取らない。
彼女は完璧主義なので、演技でも有能なトレーナーをつけていたのかな、「関係性で人物を演じる」とはまさにこーゆーことだ!という最新かつハイレベルな演技でパトリツィアを演じていました。
パトリツィアは相手との関係性の変化と共に、猫の目みたいに態度やふるまいが変わってゆく。実際目の輝きが変わるんですよね、モードが切り替わると。あれは対象に完璧に集中できていて、しかも自らが完璧にリラックスできている証拠で、さすがガガ様。女優の経験が少なくてもパフォーマーとしての肉体と感覚のコントロールは超一流、そして超楽しんでパトリツィアを演じてますよね。
彼女の役作りはパトリツィアという実在の人物のリサーチも徹底していたんですが、さらに役作りのために3種類の動物の動きを研究したらしいですね。これがまた素晴らしい。ガガ様はインタビューでこう語ってます。
「身体的な特徴で演技するように心がけました。役作りのために3種類の動物をイメージしました。若い頃のパトリツィアは家ネコのように、中盤ではキツネのように遊び心がある狩りの方法から学びました。そして終盤ではヒョウ。ヒョウの動画をたくさん見て学んだんですけど、狩りの仕方が魅惑的で、相手を惹きつけておいてから襲いかかるの。こうして役の身体性を見いだしていったの。」
いや正直、役作りに動物の動きを使うとか、古臭い演技メソッドだなあと思って話を聞いていたんですが、途中でそうではないことに気づきました。ガガ様のこれってそれを「関係性」のものとして捉え直しているんですね。単純に自分の動作を動物に寄せるのではなく、その動物の狩りの戦略と獲物との「関係性の結び方」を肉体化して自分の芝居に取り入れているということなんですよ。
で、実際パトリツィアの芝居はそう見えますよね。20代家猫、30代キツネ、40代ヒョウみたいな方法で相手に近づいていって、狩る。まさに。そこでその身体性の豊かなディテールがパトリツィアのクセの強い印象を作っていったんでしょう。お見事。
だって実際ネコやキツネやヒョウみたいな態度で近寄ってくる女性っていますからねw。魅力的なんだけど危険信号が出るやつです(笑)。いや〜ガガ様、リアルな「貪欲さ」の芝居でした。




さて話は尽きないですが、そろそろ〆ましょうか。
『ハウスオブグッチ』を見ていて驚いた点が一つありまして。
それはこの映画で次々と消されてゆくグッチ家の人達ってみんな人のいい連中だっていうことです。全然悪い人じゃない。じゃあなんで消されるのかっていうとそれは「時代に合わないから」「老害だから」・・・今ですよねー。まさに2020年代現在の世界で起きている世代間・コミュニティ間で起きている殺し合いをリアルに描いている。
だって経営陣はグッチ家の人たちを無能だ無能だって言うけど、そもそもその「GUCCI」をクリエイトしたのは彼らグッチ家の人たちですからね。ぜんぜん無能じゃないわけですよ。それをマーケティングの観点から無能だと判断して追い出すという・・・アルドやマウリツィオが追い出されるシーンを見てボクは、ルーカス・フィルムから追い出されたジョージ・ルーカスや、アップルから追い出されたスティーブ・ジョブズのことを思い出してました。
怖いですよねー。昔だったら映画の登場人物でも何の罪もない誰かを「やり方が古い」だけで全て奪って野垂れ死にさせるなんてこと、観客が納得しなかった。でもいまの観客はすんなり受け入れちゃうんですよね。「あ、それはそうなるよねー」と納得しちゃう・・・だって我々はそういう世界に生きてるから。「映画は時代を映す鏡だ」とはよく言ったものですよね。
リドリー・スコットに「映画もマーケティングばかりで、真のクリエイティブに対して敬意を払わない時代になっちゃったねー。」と言われた気がしました。
小林でび <でびノート☆彡>
【関連記事】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
